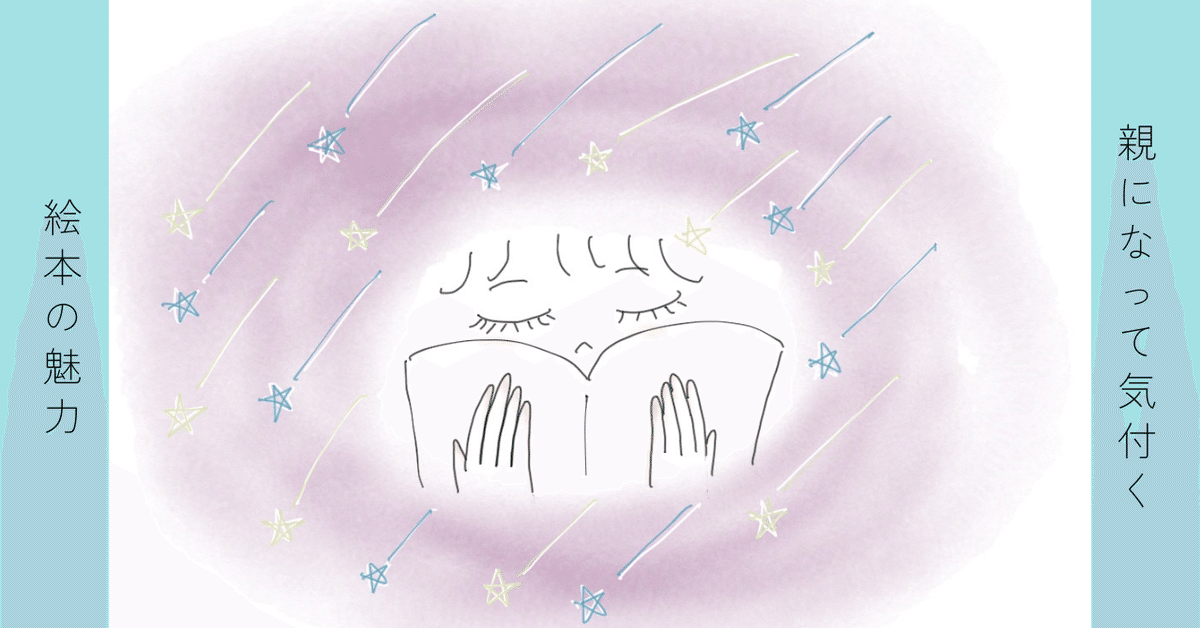
絵本はすばらしい
はじめまして
わたしは1人の子を持つ親です。
今年子どもは6年生になります。信じられないくらいあっという間でした。部屋には読みきかせをしてきた絵本や児童書が陳列されたまま。
きっともう開かない絵本もあるかもしれないと思うと、寂しいものです。
さて、このnoteでわたしがしたいのは今までこどもと一緒に楽しんできた
絵本と児童書を記録することです。
わたしにとっての子育ては「読みきかせ」といっても過言ではないかもしれません。
はじめは寝かせるという目的で読み始めた絵本ですが、
子どもを思うおとなの優しさがたっぷり詰まった絵本の魅了に引き込まれ、
読みきかせという時間が、かけがえのない大切な時間となったのです。
ここで記録する絵本は、初版から何十年という定番の絵本も多く新鮮ではないかもしれませんが、これから絵本を選ぼうとしている方にとって、参考になるかもしれません。
わたしには子どもは1人しかいませんが、親になって初めて知ることが何と多かったことか(そして今もその驚きは継続中です)。
0歳から保育園に子どもを預けていたこともあり、ママ友という情報網もなく、親も頼らずで今思えば独学で子育てをしていたように思います。
まさに暗中模索、遠回りしていたり間違えていることも多かったです。
絵本選びも自分の好みで選んでいました。
記載されている「推奨年齢」を無視して、「こんな絵本を読んで育った子は個性的に育つはず!」「美的センスを身につけて欲しいからデザイン性の高い海外の絵本にしよう」とか。
本屋さんにある赤ちゃん向けの絵本はわかりやすい絵に、簡単な言葉(というか音)がバーン!みたいなものが多く、わたしは心の中で「こんな幼稚なもの、我が子には読まんわい」と排除していました。
ところが、こどもが1歳のときの保育園での出来事です。
ベテランの保育士さんが「もこもこもこ」という絵本を子どもたちに読んでいました。
これは大きめのサイズの絵本で、単純なカタチがページをめくるたびに変化していき、言葉も擬音ばかり。
感情を乗せなければ30秒で読めてしまうようなものです。
これを保育士さんは抑揚たっぷりに読み、15人くらいの子どもたちが食いつくように見入っている。ページをめくるタイミングと「もこ」「ばちん!」などの音に子どもたちが目を輝かせて大喜びをしている。
「しーん」という箇所では子どもたちも息をひそめて様子を伺っている。
まさに絵本、読む人、読まれる人が一体化した光景でした。
この光景を目にして、保育士さんの技量に圧倒されたと共に、絵本の力を思い知らされたのです。
絵本って子どものために作られている特別なものなんだ。将来こんなふうに育って欲しいからこれを読ませようとか、そんな意図をもって選んでも子どもが楽しまなければ意味がないんだ。
推奨年齢には意味があって、その時期だからこそ育まれる感性に添って作られているんだ。(これは2歳の時に買っても読んでくれなかった絵本を4歳くらいで楽しんでいる子どもを見て実感しました)
それからは絵本を選ぶときは自分の好みだけに偏らずに、子どもの喜ぶ顔を想像することにしたのです。
子どもは今年で12歳になります。今は戦国武将の本や漫画ばかりになりましたが、たまに好きな絵本を読み返していることがあります。
その時は絵本を読んでいたときの嬉しい気分が蘇っているようです。今はあまり読まなくても、幸せな思い出として心のどこかに残ってくれたらと思います。
次回からは具体的な絵本の紹介をします。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
