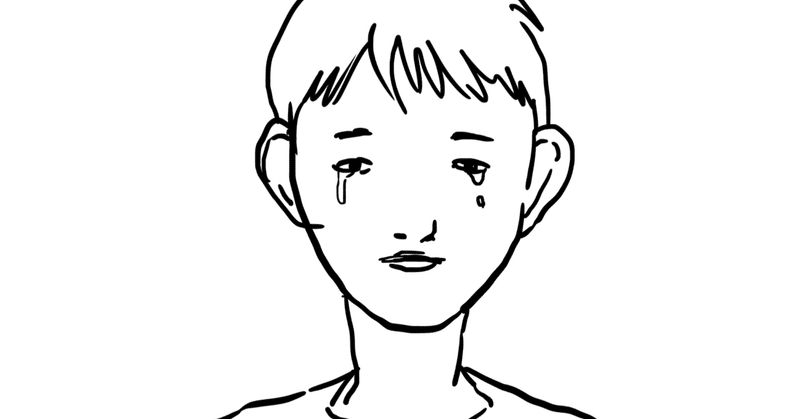
そういうところ、似なくてもいいよ。
先日、小学1年生の息子が放課後に通っている児童会館から妻に連絡があった。
「息子さん、おしっこを漏らしてしまいまして…とりあえず、こちらに置いてあった予備のパンツを履いてもらっているのですが…」
【注意】本文中には一部、もしくは全部、下品な
表現が含まれます。苦手な方、食事中の方は「戻る」で戻っていただくのが賢明かと思います。
あいつ、やりやがったな。うちの子供たちは総じてゆるふわ下半身を持って生まれてくる。児童会館の先生は笑いをこらえながら、続けた。
「予備のパンツが赤ちゃん用しかなくて…あ…あ…赤ちゃん用のパンツを履いてもらって…います…あと、ズボンがなくて、今はとりあえず着てきたジャージの上を腰に巻いてもらっているんですが…」
このあたりで、僕に状況を伝える妻の声も震えてくる。
「とりあえず本人は下半身が開放的になってテンションが上がってますので、このままでも大丈夫かとは思いますが…」
赤ちゃん用のパンツを履いて、腰にジャージの上を巻き付けたテンションの高い男児。本人が気にしてないならいいか、とも思ったが、その状態で同級生にでも会うことがあればトラウマになりかねない。本人だけでなく、お互いに。
妻からそんな怪情報を受け取った僕は、仕事を抜け出して家に帰り、息子の着替えを持って児童会館に駆けつけた。息子は確かに落ち込む様子もなく、下半身をアディダスで包んで元気に走り回っていた。ジャージの隙間から時折覗くピッチピチの赤ちゃん用パンツが、見る人に混乱と戸惑いを与えた。
そんな中、僕は胸のざわつきを覚えた。頭の片隅で、思い出したくない記憶の蓋が開きかけていることに気が付いたのだ。
小さいパンツ…
(ざわ…ざわ…)
トラウマ…
(ざわ…ざわ…)
ゆるふわ下半身…
いくつかのキーワードが頭の中を駆け巡り、少しずつ核心に近づいていく。忌まわしき記憶を魔封波(マフーバ)した電子ジャーのお札は剥がれかけている。なんで本番のときに新しい電子ジャーを買わなかったん、天津飯…そんなことを今更後悔しても遅い。
あれは5年ほど前のことだった。
僕は妻と、長女と生まれたばかりの長男を連れて、母親の実家にお邪魔していた。昔からお盆の時期には母方の墓参りで毎年のように遊びに行っていた親戚の家だ。妻はそこをとても気に入っており、今年も帰省するのかと僕の母親に確認し、休みを合せて訪問することが多かった。
札幌から車で5時間の田舎である。酪農を営んでいるその家は広い敷地内にクマを捕まえる罠が仕掛けられており、車を走らせればシカに激突し、道を歩けば黒板五郎に出会うようなところだ。
外灯はほとんどないに等しく、日が落ちて、家の照明が消されれば都市部とは比べものにならないような漆黒の闇があたりを包む。
昼過ぎに到着した我々は、ひと通り牛を見たあと家の中で過ごした。夕食が振る舞われ、同じ町内に暮らす親戚の方々も集まり、賑やかな夜となった。買い置きされていたビールと我々が買ってきたビールと親戚が持ち寄ったビールで、まるで日本昔ばなしに出てくる鬼やネズミやスズメが主催を務める宴会のようであった。残念ながら現代ではクマもシカも参加せず、黒板五郎も「食べる前に飲む」と登場することもなかった。そして、当然のように僕はべろべろに酔っ払った。
覚えているのは「僕は妻を愛している」と声高に叫んでいるシーンである。
親戚一同(母含む)の前で、牧師さんに求められているわけでもなく直接的に愛を宣言するなど、夏目漱石が聞いたら卒倒しているに違いない。僕だって、思い出すたびに叫び出したくなる。マインドアサシンが僕の前に現れることを祈っているがナチスドイツによって生み出された超能力者がおいそれと北海道の片田舎に顔を出すわけがないことを僕は知っている。
そうして恥ずかしい夜は更けていき、一人、また一人と床に入る者や帰宅する者が現れはじめ、僕も愛妻に「そろそろ寝るか」と言って客間へ戻った。布団が四組ほど敷かれたその部屋は、北側に出入りする扉があり、西側に納戸へ出入りする扉があった。僕は南側に頭を向けるような格好で布団に入り、酒でグルングルンする視界にまぶたで蓋をして早々に眠りに落ちた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
どの程度の時間眠っていただろうか。近くに時計もなく、まだ酒の抜けていない頭では近くにあるであろう携帯電話を探し出すこともできなかった。
ただ、布団に潜り込んだ時と変わらない闇が部屋中を支配していて、まだ夜が明けていないのだろうことは明白だった。隣の布団では、妻と二人の子供が寝息をたてて眠っている気配だけがした。
どうして気配しかしなかったのかといえば、完全なる暗闇だったからだ。札幌であればどんなに夜中に目を覚ましたとしても、外から外灯の明かりや走る車のヘッドライト、遅くまで起きているアパートの明かりなどが部屋に滑り込み、完全な暗闇などはあり得なかった。
だが、ここは違う。ただ一つの明かりである月や星の光はカーテンによって遮られ、あとは完全に真っ暗。黒以外の色はなく、目を空けているのか閉じているのかわからないほどだった。
僕は部屋の見取り図を頭に描いた。僕は一番西側の布団で、南に頭をむけて眠っている。出入口は北。
僕は猛烈な便意で目を覚ましたのだった。しかも、これは酒を飲み過ぎた日に起きる軟便の気配である。タイムリミットはすぐそこだ。酔っ払ってはいても、かろうじて立って歩くことはできる。だが、もうグルングルン目が回っている。
この暗闇の中、まさに文字どおり闇雲に出入り口を目指すことは危険だ。最短距離は部屋を対角線上にショートカットすることだが、まっすぐ歩くことができなければ最愛の妻と子供たちの上で今の自分が持つ最強の武器をぶっ放すことになりかねない。家族の命を自らの尊厳と同時に絶ってしまう恐れがある。安全に行こう。僕は左手を壁につけた。壁に沿って歩けば出入口のドアがある。そのドアを出てすぐの下り階段を降りてしまえば、トイレまでの道のりは遠くない。焦らなければ幼稚園児でもクリアできる簡単なミッションだ。壁に触れながら歩を進める。角に当たる。進路を変えて進む。少し歩くとドアのノブが手に触れた。ビンゴ。僕はほくそ笑んだ。これが大人の危機対応能力だ。
ノブを回し、ドアを開ける。しかし、ドアの先も真っ暗闇には変わりない。出入口のすぐそこは下り階段である。踏み外せば命はない。そっと足を出す。一歩、二歩、三歩…おかしい。もう階段があってもおかしくないが床はまだ先に続いている。慎重になり過ぎているのだろう、と考えた。
今思えば、この時に引き返すべきだったのである。
しかし、爆弾を腹に抱えた僕にそのような冷静さはなかった。さらに歩を進める。すると、ヒザの高さほどの障害物に触れる。何だ、これは…。わからぬまま足を上げて障害物を乗り越える。大腸が動いてグルグルと音がなる。僕にはまるで異形の化物が笑っているようにも聞こえた。化物の足音がひたひたと背後に迫っているのを感じて、僕は歩を早めた。今度は頭に何かが当たる。おかしい…しかし、僕は階段だけを目指しているのだ。腰をかがめて障害物をくぐる。目指すものが明確な時、人は得てして落とし穴にハマりやすいものなのだ。
そうして僕は目に見えぬ何かに足を取られ、進路を阻まれ、身動きが取れなくなった。
戻る道もわからない。化け物の笑い声がどんどん大きくなる。
がんばれ、頑張ってくれ僕の括約筋…!
もはや僕にできることは括約筋を応援することだけであった。しかし、キルアが三の門を簡単に開けてしまったように、異形の化物は簡単に肛の門を開けることができる。応援など無意味だ。
こうして、ついにモンスターが放たれてしまった。「待ってました」と言わんばかりに大量のモンスターがあちらの世界からこちらの世界にやってきた。もう、この世の終わりである。終わりの始まりである。数時間前の僕の無邪気な「妻を愛している」発言が前フリにしか見えない。どうしようもなくなって僕は、
「たすけて」
と言った。誰かには聞こえる程度に、みんなには聞こえない程度の声量で。
どこかでゴソゴソと音が聞こえる。「…どうした?」
恐怖と驚きと戸惑いが入り混じった妻の声である。そして「くっさ!」と言ったのも聞こえた。妻が電気をつけると、僕がいるのは納戸であった。
そう、暗闇の中で触れたあのノブは、北側にある出入口のドアではなく、西側にある納戸のドアだったのである。そんなことも知らず、僕はビンゴだの大人の危機管理能力がどうのこうのとのたまっていたのだ。とんだピエロである。足元にはガラスケースに入った人形や額縁などが置かれていた。僕は妻に救出された。
すべてを察知した妻は、そのあとも何度か「くっさ!」と言いながら僕を階段へと誘導した。一階に降りてトイレに座った僕は何度も妻に「ねぇ、これって夢?」と尋ねたが、返答はすべて「現実だ」という嘘のない愛情のこもった一言だった。
汚染した下着をビニール袋にしまった後、妻に手をひかれ、風呂に向かった。ある意味、アンジャッシュ渡部よりも汚れた下半身をシャワーで洗い流しながら「これって夢じゃないかなぁ?」と考えていた。
すると、今度は後方から「何やってるの」という緊迫した声がした。母であった。
妻は「あ」しか言えなかった。当然だ。この状況で正解など存在しない。沈黙。それこそが唯一の答えだ。
「馬鹿じゃないだろうか」と言いながら、汚れた下着の入ったビニール袋をひとまず鞄にしまう母親の背中を見て、僕は「これって夢かなぁ?」と考えていた。そして妻は残酷な事実を僕に告げた。
「もう、あなたの替えの下着はない」
もし僕がキムタクだったら「ちょ、待てよ」と言っているシーンであるが、キムタクはおそらく便失禁はしない。僕は下半身が冷えていくのを感じながらぼんやりと立ちすくんでいたが、やがて妻が「これしかない」と鞄から何かを取り出した。
妻のパンツであった。
帯に短しタスキに長し。痛しかゆし。適切な慣用句が見当たらないが、先人も想定外の出来事が、今ここで繰り広げられている。神龍に「ギャルのパンティをおくれ」と頼んだわけでもないのに、僕の手には妻のパンツが乗せられている。決して華美なパンツではないが、もちろん女性用のパンツである。
そっと足を通す。今までにないフィット感と共に、僕の中で「自尊心」という氷山の一角が崩れ落ちたのを感じた。僕たち夫婦は、言葉少なに二階に戻った。母はいつの間にか消えていた。
目を覚ます。二日酔いのせいか、頭が痛むが体調は悪くなかった。階下では人の気配がしており、朝食の用意が進んでいるようであった。
「おはようございます」
僕は階段を降り、伯母に挨拶をする。「おはよう」と笑顔を返して伯母は朝食の用意に戻った。親族がちらほらと居間に集まり、一言二言挨拶を交わす。僕は水道に立って水をコップ一杯飲んだ。二日酔いじゃないのか、と声をかけられ大丈夫ですと答えた。歯を磨いてトイレに入った。ズボンを下ろすと、妻のパンツが「おはよう」と言った。夢じゃなかったか…。
母が朝食のテーブルに座り、顔を合わせたが昨夜のことは忘れているかのように露ほども態度には表さなかった。
僕の妻に「決して美人ではない」と言ったり、太っている人が通りかかると「どうやったらあんなに太れるんだろ」と口に出すほど、デリカシーというものと縁遠いあの母親が、である。
そのことは、逆に僕の心をえぐったが、だからといって自ら「いやあ、昨日は参りましたわ」と言えるほどの図太さも持ち合わせていなかった。
このエピソードに何一つとして教訓などない。言えることがあるとすれば「もらすな」の四文字である。ちなみに、妻はこのエピソードを人間関係の潤滑油として活用している。新しい職場、ママ友など、あと一歩お近づきになろうという場面でよく披露している。打率はかなり良いらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
