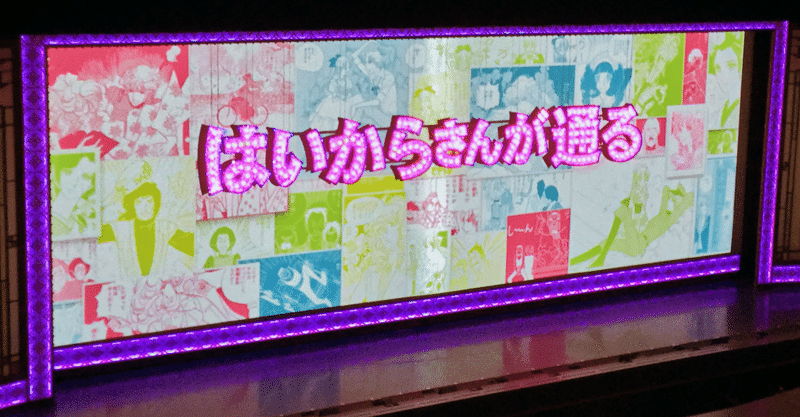
【観劇メモ】宝塚歌劇花組公演『はいからさんが通る』
【観劇日】
2020年7月28日(火曜日)宝塚大劇場
※敬称は略しましたが、生徒のみなさまへの尊敬はこめたつもりです。
『はいからさんが通る』。
最初の1巻を小学校の図書室で読んだけれど続きを読む機会は逸したままだったので、こんな波瀾万丈の物語だったのかと驚いた。と同時に、この作品を宝塚歌劇が上演したことの意味がよくわかった。女性が自立する姿や一途に尽くす姿など、前近代的なものと近代的なものの様々な女性観がひとつの物語の中に混在している。さらに軍国賛美にならないぎりぎりのところで抑制しつつも、華族や士族といった階級社会への懐古趣味、家を守り仲間を支える保守的な協調性の強調、矢絣の袴とブーツの女学生スタイルやドレスや軍服などの記号的な「ユニフォーム」の嗜好、ドイツロシア寄りの貴族社会へのファッション的な憧れも全面展開している。とっちらかっているが、この価値観の多様性が物語の世界を華やかにしているのだろうと考えた。観客の見たいものをさまざまに見せる。だからこそ宝塚歌劇において、さまざまな個性を持つ生徒たちに演じさせがいがあるのだろうし、再演する意味は大きいのだろうと思った。
柚香光の花組トップお披露目公演である。初見の新鮮みを大事にしたかったので、あえて前回の公演の放送も見ないようにして今回の舞台を見た。プロローグで柚香光が出てきたときは舞台に光り輝くような気がした。美しい。その美しさは、長身や足の長さや頭身のバランスの良さ、まっすぐにのびた鼻筋と射るようなまなざしから来ているのかもしれないが、なにより柚香光の魅力は真摯さを感じられるところにあるんだろうと思う。それを生み出しているのは柚香光の声だと思う。
柚香光の声はざらりと耳に残る。そのざらりとした感触が、たどたどしさやもどかしさ、不器用さや無骨さを感じさせるのだ。鋭く美しい顔立ちと、ざらりとした声のギャップに心がひきよせられる。つい柚香光がなにを考えているか、なにを思っているのか知りたくなる。完全無比の完璧な美しさだけではひとの心はつかめない。ひとの魅力とはふしぎなものだと思う。
ひとは矛盾に満ちていて、間違いもすれば過ちもおかす。そのような等身大の人間を柚香光は実直に、実にまっとうに生きている。その実直さ真摯さはまるごと柚香光そのものであるかのような錯覚もおぼえる。わたしは『金色の砂漠』でテオドロスを演じた柚香光が好きなのだが、いよいよ負けがわかるとさっさと逃げていくところがとてもリアルでとても好きだ。器の小ささもじつに人間らしい。『ポーの一族』でのアランも見事だった。柚香光が演じた人物は、悪人・善人と単純にくくることのできない、人間らしい人間だと思う。そのような演技をみるのはとても心地よい。
『はいからさんが通る』で、柚香光演じる伊集院忍(少尉)は漫画から抜け出したようだと評される。百聞は一見にしかずで、なるほどそのとおりだと思った。けれどもそれはビジュアルだけではないだろう。物語における少尉の行動はわたしからみるとよくわからないところが多い。なぜだか紅緒を翻弄しているのかと思ったら、少尉の方が紅緒への想いが強いところもあり、第2幕以降の記憶喪失云々の展開でも筋の通し方がずれている気がした。でも柚香光が演じると、矛盾に満ちた少尉の行動や気持ちが、自然にうけとめられた。とんちんかんなところもあるひとだけど愛すべきひとになったのだ。それは柚香光が持つ不器用さ、無骨さが大いに寄与しているのだと思う。柚香光の少尉は不完全だからこそすばらしかった。
花村紅緒を演じるのはトップ娘役の華優希。わたしにとっては『ポーの一族』のメリーベル役が彼女を知った最初の作品である。消滅してしまう場面で恐怖に怯え叫び続ける場面で、むしろ彼女のきらめく生命力や瞬発力や情熱を持続させるエネルギーに感じ入った。『A Fairy Tale ~青い薔薇の精~』のシャーロット役もよかった。お芝居が上手いと思う。とりわけ、シャーロットの送ってきた半生の艱難辛苦が時に洗われて、ひとつの悟りとして自らの生きてきた人生を語る彼女の姿には、悟りのなかにも悔恨や切なさがかすかに漂い、ひとが生きることの喜びとかなしみを感じて涙が出た。9月に宝塚大劇場で観たあと、東京宝塚大劇場の千秋楽中継をライブビューイングを観た時は彼女の表情をこまかく観ることができたこともあり、彼女のお芝居が深化していることを実感できた。
そこで今回の花村紅緒である。中途半端に演じると浮いたキャラクターになりかねない役であると内心危惧していたが、それは杞憂だった。紅緒が自転車を乗り回したり、少尉につっかかったり、車夫にけんかを売られて買ったり、軍人に啖呵を切ったり、そんな紅緒の行動は常に誰かを想ってのことである。彼女なりに筋を通していると感じられて、その一貫性にすがすがしさを覚えた。好きになった。
華優希は紅緒という人物をよく理解して、彼女の生き方を心から愛しているように感じた。「花村紅緒」は観客のみんなが愛するにふさわしいキャラクターとして舞台の上で輝いていた。
少尉とのソファのシーンはコミカルでありつつ、柚香光の美しさに魅了される心の揺れを感じさせる良い芝居だった。2人の徹底した役作りがこの作品の成功につながっていると思う。柚香光の少尉のすばらしさと共に、華優希の紅緒もまたすばらしかった。
瀬戸かずや演じる青江冬星は面白いキャラクターとして舞台に息づいている。話の筋、展開上での彼は若干いいひとすぎて気の毒ではある。それをさておいても、瀬戸かずやの芝居を観られるから十分満ち足りるのである。わたしは舞台に瀬戸かずや(あきら)が出てくるだけで安心する。瀬戸かずやは今自分がこの舞台の上でどのように振る舞えばこの舞台の空間をもっと大きく広げることができるか、そのために自分の身体と声でなにをすればいいのかをよくわかっている俳優だと思う。あきらがいればだいじょうぶ。そう思わせる職人技の安定感がある。冬星としてその巻き髪をなびかせるタイミングもよく心得ていて、髪をさわるだけでも会場に笑いが起きる。髪だけで芝居ができるし、彼が次になにをするのかを観客のみんなで心待ちにする。生の舞台の醍醐味は、俳優が台本通りに演じるのを見るだけでなく、次になにをするか、どんな表情をみせてくれるのか、俳優のいきいきとした芝居を期待する空気に全身を浸せることにある。瀬戸かずやは生の舞台の観客の期待を一身に背負い、その期待にみごとにこたえてくれるすぐれた俳優だと思う。
宝塚歌劇の舞台の魅力は、花組なら花組の組子全体で作品を作り上げるところにある。名前もない役ながら、いわゆる繋ぎの場面であっても、その場面に完璧に生き命を燃やす俳優がいる。それを見るのが心地よい。細かな人物造型や賑やかな関係性を示す小芝居を仕込んでいる。「一所懸命」という言葉は自分の領地を命がけで守る武士の本分を表す言葉だが、まさに自分の役と自分の居場所を輝かせるべく命をかけて生きている宝塚歌劇団の生徒たちの一所懸命な姿はとても美しく、心打たれる。
実をいうと、柚香光が舞台の中央に現れた時には涙が出た。
明日海りおのさよなら公演のときに背中をおされていたひとが、今こうしてトップになったことに感慨を覚えた。生きて続けていたからこその光り輝く舞台にいま立っている。その背景を知るとなおさら感慨も深まる。宝塚はこうした虚と実の多層構造が醍醐味である。柚香光と水美舞斗の同期ふたりが、伊集院と鬼島の熱い友情関係を演じるのも多層的な嬉しさを感じさせてくれるのだ。
水美舞斗は開襟の姿がうつくしいと聞いていたので、わたしも注視した。たしかにうつくしい。でも水美のうつくしさは、あんなに切れ味のよいダンスをし、すぐれた筋肉をもちながら、俳優としては非常に謙虚で控えめなところにあると思う。もうすこし前に出てもいいように思うのだが、水美はいわゆる「受ける芝居」が得意なのだと気づいた。相手の出方を注意深くみてうけとめる優しさがあると思う。そんな水美舞斗の優しさは、『CASANOVA』という作品を慈愛にみちたものにしてくれていたと思う。
今回の『はいからさんが通る』でもその優しさはいかんなく発揮されていて、紅緒と少尉のふたりを、役柄としても舞台人としてもよく支えてくれていると思う。
また雪組から組替えになった永久輝せあと朝月希和が和装なのも、「日本物の雪組」から来たという経歴・彼らが過ごした時間・かれらが身につけた個性、全てそのまま受け継いでこれから飛躍させるというスタンスを前面に示すことで、雪組時代から応援しているファンを安心させてくれるし、初めてみる客や花組ファンへの良い紹介にもなっているのだ。ふたりとものびのびと細部まで丁寧で良い芝居をしてくれていて嬉しかった。特に芸者役を演じる朝月希和は、心を寄せる少尉の一挙手一投足、ひとつひとつの言葉にヴィヴィッドに反応してみせる。それは決してオーバーリアクションではなく、さりげない目の動きや首の角度でそっと表現される。そうすることで少尉への想いを表すと共に、彼女の生き方のつつましさも表れていてとても切なかった。それだけ確かな演技力があるということを物語っている。映像には残らないかもしれないのでその場面の朝月希和を凝視していた。よかったよひらめちゃん。
永久輝せあが登場してきた時の拍手の大きさに観客の期待と愛情を感じた。フィナーレでもそうなのだが、限られた登場時間に届けるように拍手のピッチが速く、客席の雰囲気も前のめりになって迎える感じだった。小説家を演じた永久輝せあも、カメラに映らないようなときも細かいお芝居をしていて、その姿をオペラグラスで追ってたのはわたしだけではないと思う。細かいお芝居に客席もウケて笑っていたから、その反応は舞台の上にの永久輝せあにも伝わっていると思う。少ない出番ながらも、関係性をきちんと演じて、物語と観客をうまくつなぐ役割を果たしていた。とにかく輝くように美しくて、存在感は抜群で、客席との交流は熱く、永久輝せあは観客のこころをつかんでいた。よかったと思って目が潤んだ。
演出に話をかえる。場面それぞれの舞台装置が美しかった。柱と壁をうまく使って邸宅の雰囲気の差異をわかりやすく示す工夫が感じられた。装飾は大正ロマン風で統一され、七宝飾りをアレンジしたものなど、配色も綺麗で、飾りにも細部までこだわりを感じ、エレガントで気品があった。
舞台の背景にデスクトップ壁紙のような写真を映し出し、その前で生徒が芝居をする演出も、この作品が漫画を原作にしていることをふまえた演出だろう。まるで漫画の一コマのようで新鮮で面白かった。場面転換も見事で、少尉が紅緒を探しに行く場面で、キャストを盆の上に載せて回したのは人間劇のカルーセルのようでとてもよかった。盆の上に載っていたひとたちを映像でじっくり観る楽しみも期待できそうである。
終盤の関東大震災の場面は一瞬身体がこわばる。心がすくんだが、開演の事前に「この建物は耐震基準をクリアしているので大丈夫」という旨のアナウンスがあったのを思い出して、落ち着きを取り戻せた。あのアナウンスはこの場面の伏線であり配慮だったのかと合点がいった。宝塚歌劇はどこまでも親切である。
最後は復興への希望を語ってのエンディングとなる。思わず涙ぐむほどに、この物語は話の筋と気持ちの流れがよく工夫されて気持ちよく心を運んでくれる。
フィナーレがあるのが宝塚歌劇のよいところである。
観客は徹頭徹尾とにかくとてつもなく優しい。パレードからずっと拍手していた観客が、柚香光が大羽根を背負って現われた瞬間、さらに大きな拍手で出迎えたのを音と振動で感じた。もう手が痛くなっているはずなのに、さらに2倍の力で拍手を送っていると思う。それくらい会場全体の拍手のボリュームと振動は大きかった。
涙がこみあげてきてしょうがなかった。こんなにもみんなで愛を送っている。誰かが指揮したわけでもなく、心をあわせて、拍手のタイミングの息をあわせて、拍手のボリュームをあげている。わたしは命令されてやらされる類の集団行動がとても苦手なのだけれど、このようにおのずと息を合わせられる瞬間に身をゆだねられることを奇跡のような時間として尊んでいる。舞台にいるひとたちへの賛辞を贈りたいという気持ちでつながるこの宝石のように輝かしい空間と時間が愛おしかった。
幕がおりる瞬間まで、舞台にいる花組の生徒たちは手を振りながらきらきらの笑顔で1階から2階をずっと見つめていた。いつ休演になってもおかしくない状況で、今日が最後になるかもしれないという覚悟でも、きらきらの笑顔で、客席の様子を目に灼き付けているんだと気付いて涙が出た。
こちらも必死で拍手した。
われわれ観客の贈る拍手が聞こえているのだろう、喜んでいるように見えるし、今日が最後の舞台になるかもしれないという覚悟で、もう二度と会えないかもしれないような切迫感といとおしさと、今日無事に終えた安堵感とが入り混じった笑顔のように見えた。次の公演はないかもしれないという想いで双方が拍手と笑顔を交換していた。また涙が出た。
さよならみなさまを聴きながら嗚咽してしまった。
ありがとう花組。ありがとう宝塚歌劇。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
