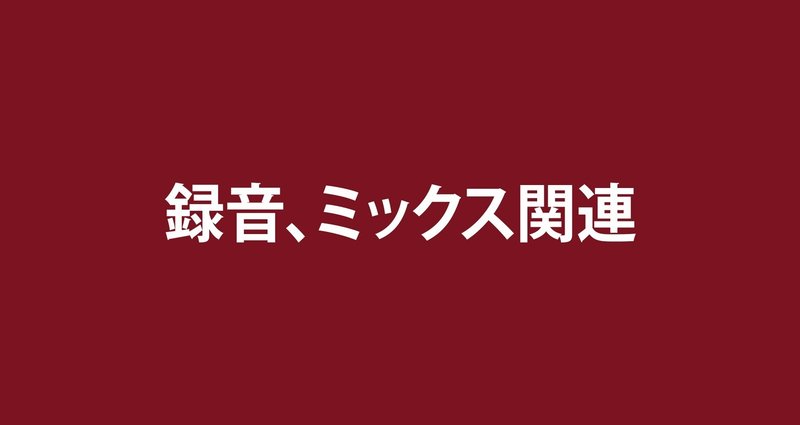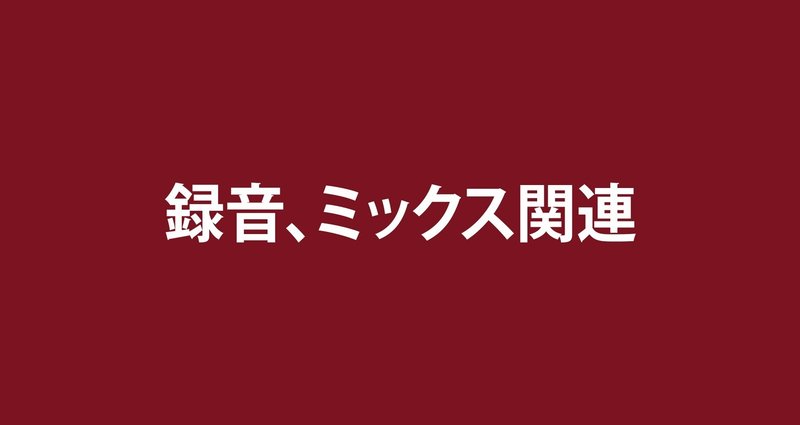アンプシミュレーター初心者でも出音を手っ取り早く良い感じにするためのポイント
レコーディングスタジオで100Wのチューブアンプにマイクを立てて録音した所謂プロの現場の音を簡単に出すノウハウは一朝一夕で身につくものではありませんが、その音に何となく近い音を手っ取り早く楽しむ方法は無くはありません。
この記事ではシミュレーターに触り始めたばかりの人、久しぶりに触る人、たまにしか触らない人が100点満点中70点の音を目指す時のチェックポイントをいくつか紹介します。概要は目次をご覧ください。人によっては当たり前のことかもしれませんし、見落としていることかもし