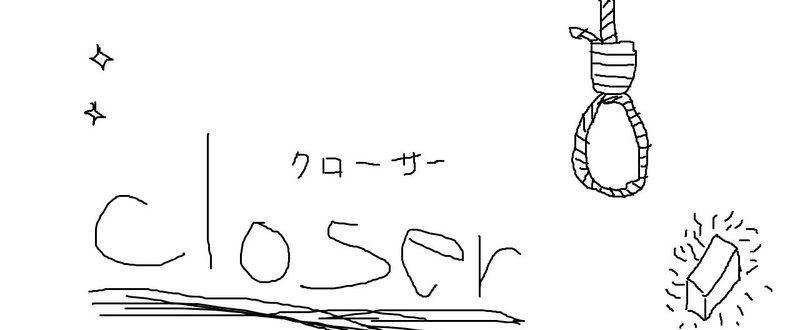
クローサー (2)
『前章 クローサー(1)』
「ポストパンクは終わった。いや分かってた!だが遂に今日破滅した。終わりなんだ!もう、この音楽は何の役にも、何の助けにもならない!」 マスターは激高し叫ぶ。 正直よくある事だが、今日は一段と様子がおかしい。「いやいやいや!」「落ち着いて下さいよー」「終わりなんだ!!!」 マスターは大声で吠え、カウンターのグラスを勢いよくスライドさせ、床に落として割った。
先週来た時もそうだったが、この割れたグラスは俺が掃除してやる事になるだろう。
「うははははー!」
蔓押は荒れているマスターを見ながら平然と笑い、グラスに残っていたジンをクッと飲み干す。
「マスターさぁー、考えすぎだって。変なジジィが糞詰めただけじゃん。ほら、さ、飲もう。ヘンドリックス無い?」
「そんなジミヘンみたいな名前の酒はうちに無い!」
「じゃータンカレーもう一杯。マスターも飲もう飲もう!」
そう言いながら蔓押は、バーカウンターの中に勝手に入り込み、勝手に棚からタンカレーの瓶を取り、自分のグラスとマスターのグラスにジンを注ぐ。
マスターはそこへオレンジジュースを加えてチビチビと飲み始めた。
マスターは酒に弱い。
というか、このバーを始めるまで、まともに酒を飲んだ事すら無かった。
酒に弱いのに何故バーをやっているのか?
マスター曰く、バンド活動以外にポストパンクで飯を食うとしたら、ポストパンク愛好家のバーを開けばよい。
そう考え、親の財産を使ってこの店をオープンさせたらしい。
約半年ほど前の事だ。
「……俺は、ポストパンクが……最高にクールで、無敵な音楽だと信じてきた……」
マスターはそう愚痴りながら、ジュースで割ったジンを飲む。
「うんうん、俺は今だってそう思うよ。ギャング・オブ・フォー、再結成した来日行けばよかった」
蔓押はストレートで飲みながら相槌を打つ。
「俺は行ったよ。確かにすごいライブだった。だがなぁ……俺はもうわかったよ……わかったよ……」
「……マスター、大丈夫ですか?」
俺はマスターの情緒不安定さを憂慮した。
この男も蔓押同様、救いようのない愚かな人間ではあるが、俺はどうしても捨て置けなかった。
俺と同様、通常の社会や人間関係に馴染めない、音楽好きの孤独な人だからだ。
「……ムニエル君ならわかるだろ。音楽には、もう無いんだよ。 バリヤーが」
「??……バリヤー…………ですか?」
「そう。凄い音楽を聴いている時に出るバリヤー。例えばディス・ヒートを聴いてる時には強烈にバリヤーが出る。このバリヤーで、俺は生き延びてきた!世の中のクソみたいな奴らや、クソみたいな社会に、バリヤーで対抗する!音楽、特にパンクよりもかっこいいポストパンクからは、ヒリヒリとしたエネルギーが湧き出てきて、バリヤーが俺を包む……!」
マスターは目を血走らせて叫び、ジンを口に運ぶ。
「はい……まあ、その気持ちはわかります」
バリヤーの事はよくわからないが、ロックを聴いている時のあの高揚感を指しているのだろう。
「そうだろ?……そしてバリヤーで無敵になった俺はあらゆる人間や、あらゆる社会の決まり事を超越した!学校、就職、ちゃんとしろとか言う奴ら、空気を読めとか言ってくる奴ら、全員死ね!全部死ね!俺は強く、俺が強い事を知らない奴らの事はどうでもいいし、かなり強い俺は偉い。強い!強いので偉く、正しさがある!」
マスターは早口で怒鳴り続け、ジンをグっと飲み干す。
すかさず蔓押が空になったグラスにジンを注ぎ、マスターに今度はストレートで飲ませる。
「強さが偉い!強くて偉い!俺は強くて偉い!1番強くて1番偉い!俺が1番偉いんだ!!1番すごい!正しさが!ここにある!俺の心の中に!!」
そう怒鳴るとマスターは、飲んでいたジンのグラスを壁に向かってぶん投げて叩き割った。
「あはははは!」
この状況でも相変わらず蔓押は笑ってばかりいる。
相当酔いが進んでおり、今日何杯飲んだか本人もわかっていないだろう。
「わかりました。とりあえず落ち着きましょう」
マスターの顔は赤く、さっき2杯飲んだだけだが、かなり酔っ払っている様に見える。
俺は立ち上がり、冷静になるようマスターの両肩を撫でた。
「……ポストパンクの名盤から生まれるバリヤーは強力で、社会のカスどもからの攻撃を防ぐだけでなく、バリヤーに触れた奴らにダメージを与える必殺の武器でもある。エヴァンゲリオンのATフィールド知ってるでしょ?アレをイメージしよう!無論、実際にバリヤーでムカつく奴らをバリッ!とやってしまえる訳ではなくて、結局俺の妄想だよ。でも、俺は長年、音楽のバリヤーで常にいろんな奴を攻撃してたし、社会と戦ってきた!バリヤーがあったから、辛い時でも無敵でいられたんだ……」
マスターはそう言いながら、新たなグラスにジンを注ぎ、炭酸水で割って飲んだ。
「……その、バリヤーが、もう無いンスかー?」
蔓押が壁にへばり付きながらそう尋ねた。
「そうだ!1ヶ月前からどのアルバムを聴いてもテンションが上がらなくなった!ずっと最高の音楽だと思っていた作品に、何のエネルギーも感じなくなった」
「それは単に聴きすぎて飽きたのでは?」
「いや、長年ずっと聴いてきたけど、こんな風に何も感じなくなったのは初めてだ。こないだ観てきた若い子がやってるポストパンクっぽい、割といいバンドのライブを観た時もそう。何にも感じない。もっと前に観た時は良かったのに」
「……そうですか」
それは多分、この店には客がほとんど来ないから、マスターが精神的に不安になっているからではなかろうか?
30までは何をしてもいい、金も出す。
引きこもっていた彼は、そう親に言われ、散々散財したあげく意を決してこの店を開いた。
だがそんなマスターも今や34だ。
そしてマスターは稼ぎを得るためにこの店を開いた訳じゃない。
友達を作るためだ。
自分の好きな音楽を流すバーを作れば、自分と趣向・性格が似た人間が寄ってきてくれるに違いない。
そう思ってこの店を始めたらしい。
……なんて贅沢な男だよ。
では、親とトラブルが起きて悩んでいるのか?
友達が俺以外、一向にできないから悩んでいるのか?
そんな事を言おうとしたが、俺は口をつぐんだ。
「おかしいとは思っていた。ひょっとしたらポストパンクは死んでしまったのかと。そんなはずはない、そんなはずはないと自分に言い聞かせてきたけど、あのパンクしたポストを見て今日確信した。ポストパンクは死んだ。終わりだ。俺も死ぬ」
そう言うとマスターは冷凍庫から大きな氷のブロックを取り出し、床に置いてその上に乗った。
この店の天井からは4本の首吊り紐がぶら下がっており、そのうちの1本にマスターは首を掛けた。
乗っている氷が溶けていくとやがてマスターは宙吊りになり首が絞まって死ぬ。
ジョイ・ディヴィジョンのフロントマン、イアン・カーティスは傑作アルバム『クローサー』の録音を終え、妻と離婚調停をした後に、自宅でこの様な氷を使った首吊り自殺を行なった。
マスターのこの奇行はそれを真似たものであり、何か困った事がある度に俺の前で氷を置き、自殺未遂を見せつけてくる。
マスターがロープに首を掛けたまま、相手にせずそのまま店を出た時もあった。
だが案の定、氷が溶ける前にマスターは首を抜いてのうのうと生きており、もう馬鹿な真似は止めろと次の日俺は説教した。
「ははは、はははは!」
蔓押がふざけて足元の氷をどかそうとするのを止めさせる。
「マスター、止めてください。滑ると本当に首が絞まりますよ」
「絞まればいい。首が絞まって死ねばいい。ポストパンクが死んだ世界にこれ以上いる必要がな……」
そう言い終える前に俺が言い放つ。
「パンクロックのパンクと、タイヤなどのパンクとでは英語のスペルが違ったと思いますが」
「パンクはパンクだ。あのポストがメッセージだ……」
「………………フーーッ……」
俺はため息をついた。
マスターはもう駄目だ。
おそらく今日も結局自殺したりはしないだろうが、このままではこの人は一生自分勝手な理屈に閉じ籠っているだけだろう。
何か、どうにかして、この人をもう少しまともに……というか前向きに生きさせる事はできないだろうか?
俺はしばらく沈黙した。
マスターは意を決した様な表情でロープに首を掛けたまま動かない。
蔓押は壁に頭を預け、床に寝転びながらウィスキーを呷っている。
……やがて俺は、酒の勢いで思いついたとてつもなくくだらない提案を言う事にした。
「マスター、そのままでいいんで聞いてください」
「……何?」
俺は鞄から、今日焼いた手作りのマリファナ入りバナナブレッドと、抹茶とマリファナのグリーンパウンドケーキを取り出した。
これらは今夜蔓押に味見させた後、マリファナ・スイーツの材料になるクサと交換する予定だった。
「おおー!?」
蔓押が目を爛々とさせる。
「これはただのケーキに見えますが、パンです。だが実はパンではない。パンを超えたパン、即ちポストパンです」
「??」
「??」
我ながら無理のある思いつきだ。
「ピストルズのジョニー・ロットンは、ロックは死んだと言ってジョン・ライドンになり、PILでポストパンクりました。あとワイヤーの……誰かが、ロック以外ならなんでも良いと言ってポストパンクしました」
俺は早口で熱弁を振るう。
「一般的には知られてませんが、実はパンも既に死んでおり、人間が今食べているパンは死んだパンです。古い価値観の食料だ。そしてパンの次に来るのが、このポストパンです。俺はこのポストパンで一旗上げようと日々ポストパン作りに精を出しています」
「……うん、で、それで?」
マスターは興味なさげに尋ねた。
「クローサーにこのポストパンを置いてくださいよ。酒のアテになるよう多少改良しますから!病みつきになる美味さですよ。これを目当てにしてお客さんも必ず増えますよ。元気出してください!」
「パン目当ての客が増えたからってどうなるんだ!そいつらはアンノウン・プレジャーズも聴いた事がないろくでもないクソ人間だ!」
「まあ聞いてください、ポストパンクのバーでポストパンを出す。これだけでもなかなか粋ってモンですが、さらにもう一工夫かけます。このポストパンをそこらの首吊り縄の代わりに天井に吊るして、パン食い競走をするんです!ポストパン食い競争!パン食い競走が大人になってもやれるなんて滅多にない機会ですし、これは流行りますよー。しかもそのパンが美味い」
「ポストパン食い競争……」
ここでマスターの目の色が少し変わった。
「ふ、なんだよそれー」
蔓押は呆れ気味に笑う。
「いきなりポストパンクが好きな人間だけ呼ぼうだなんて無理がありすぎますよ。まずいろいろ目を惹く客寄せをやって、そこから音楽好き、パンク好き、ポストパンク好き……ポストロック好きお前は用がない、とふるいをかけていくんですよ」
俺は熱くなり、熱弁を続ける。
「とにかくパン食い競争をやるバー……前衛的ですよ。ポストパンクというかニューウェーヴっぽいパフォーマンスですが、ともかくサブカルなロック感があります」
俺は語り終え、腕を組んで下を向くマスターの返事を待った。
「…………うん……そうね…………それは、いいかもしれないね」
しどろもどろに、マスターはそう答えた。
「おー!?」
蔓押が声をあげる。
「店に誰も来なくて……来てもロックも何も知らないただのうるさい若者だったりでさ…………俺は辛かったよ」
「うんうん!」
蔓押が相槌を打つ。
「うう……本当に辛い……きつかった…………でもそんな中、ムニエル君と出会えてほんとによかった……」
マスターは嗚咽をあげ、涙を流しながら語る。
「もう店を辞めて、また家にひきこもろうかな……そう思ってたけど、もう少し続けるよ。これ以外……俺は方法がわからないし……」
「うん。わかった……マスターがんばろう。わからない事、出来ないことがあっても別にそれでいい」
俺はカウンターの中に入り、マスターの背中を撫でて首に掛かった縄を外させ、氷の上から降ろさせた。
「……給料は別にほとんどいらないし、俺が店の手伝いしていいか?」
「……お願いできる?」
俺はマスターの目を見ながら、深く頷いた。
「パン食い競争!やるやるー!」
蔓押がはしゃぎ、黒緑に色づく新たな食料概念、ポストパンに手をつける。
それをちぎって一口食すと、酒で流し込む。
「うん、美味いねこれー。モチモチしてる。効いてくんのはもうちょい後かな」
「こないだ頂いたブルーベリーを使ってる」
「おおー!あれはいいよー。いつものハイドロじゃなくて、頑張って土で育てたやつだからね」
ブルーベリーとは果物のそれではなく、大麻の一種だ。
俺達はバーの天井の首吊り紐に、クリップで無理やりポストパン……もといマリファナ入りのマフィンとブレッドをくっつけて、必死にジャンプや体当たりを掛け合って獲り合った。
そのうち、これはバーの中ではなく外でやった方がよいという結論に至り、俺達3人は店を出て近所の公園へと繰り出した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
