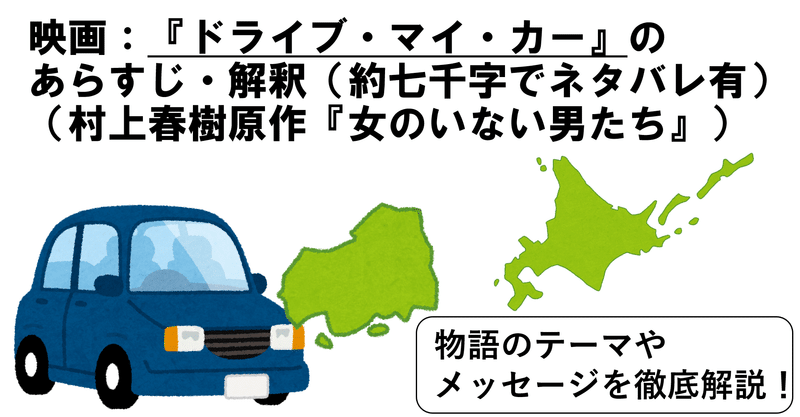
映画:「ドライブ・マイ・カー」を徹底的に解説!(約7000字)
先日、ドライブマイカーと言う映画を映画館(吉祥寺オデオン)で観た。
村上春樹の『女のいない男たち』という小説が原作らしい。
180分という長い時間だったが、思っていたよりも面白く、色々考えさせられたので、感想を書いてみることにする。
なお、以下の内容はネタバレ満載なのでご注意を。
7000字近い長文だが、画像が10枚以上あるので、ざっとスクロールするだけでも、筆者の言いたいことは伝わると思う。
(「あらすじ編」と「感想編」が以下にある。「あらすじ編」も地味に長いので、大まかな振り返りでいいなら画像をざっとみればいいかも。むしろ、「感想編」が本題。)
あらすじ編:
語のあらすじをざっくりと振り返ることにしよう。
=====================
●起:愛し合う夫婦、その妻の死
・劇団を主宰する男(夫)と、脚本家の妻の夫婦がいて愛し合っている
・妻はセックス中に物語を語る(無意識的に物語は語られ、それを覚えておいて伝えるのが男の役目である)
・妻は男に隠れて浮気。男は気づきつつも見て見ぬふり
・ある日、妻は男に「帰宅したら話したいことがある」と話す
・男がその夜、帰宅すると妻は家で倒れていた。妻は亡くなる

●承:広島での公演のための準備期間
・男は劇団での活動を続ける。新たに、広島で行う劇の演目として、『ワーニャ伯父さん』を選ぶ。
・劇の公開前の練習や準備のために、広島で過ごす男。生活する場所から、広島への移動に、車の運転手をつけることに。当初は、自分で運転したいと嫌がる男だったが、万が一運転する人が事故を起こすと大問題だからと言われて渋々了承する
・男の運転手となったのは、若い女性。最初は不安だったたが、試しに運転を任せると想像以上に運転技術が高く、居心地の良い相手だったため、運転手に認める
・男と運転手の女の子は、最低限のコミュニケーションしかとらない。「これが私の役目ですから、お気になさらず」ということを、女の子はぶっきらぼうに言うようなことが多い状態だった。
・広島では、『ワーニャ伯父さん』の舞台の役者探しから始める。
・男は自分の妻と浮気をしていたらしい男(※以下、色男とする)が、色男のような役を希望してきたのにもかかわらず、主人公のワーニャ伯父さん役に充てる。
・また、喋ることのできない女性も、その舞台に志望する。手話を取り入れた演技ができるということだった
・劇の練習は、当初脚本読みのようなことばかりに終始する。それも、できるだけ感情を殺したような読み方で、こんな練習に何の意味があるのだろう、みたいなことをよく言われている。脚本読みの練習が終わって、緊張がほぐれたタイミングになると、劇のメンバーは急に緊張がほぐれたようになって、あれこれと話すようになったりもする

●転:妻と浮気をしていた色男との対峙・その逮捕
・色男は、俳優として自分がワーニャ伯父さんに向いていないと悩んでいる。また、色男は俳優として名が売れているために、写真の盗撮も頻発しており、怒って相手を怒鳴りつける短気な所もあった。また、劇のメンバーの中国人の女性とすぐに体の関係を持ったりもしていた。さらには劇団員でトラブル御法度なのに、自分が運転する車で事故を起こしたりもしていた。
・色男は、男の亡き妻に惚れ込んでいた。それをほのめかすようなことも度々言う。そして、あんな素敵な女性と結婚した男をうらやんでいるかのような発言もする。
・あるとき、男と男の運転手の女性と色男の三人で車の中で話をする。
その中で、男は亡き妻の昔についての話をする。亡き妻は、セックス中に無意識的に物語を作っていたが、その物語は完結しなかったことを。また、亡き妻は明らかに浮気をしていて、その場面に遭遇したことすらあることを。
・色男は、「実は、奥さんの物語にはまだ続きがあります」と言って語る。つまり、実質的に浮気をしていたのは自分だと認めている
・そして、色男は「奥さんはいろいろな人と付き合いつつも、それでもやはりあなたのことを愛していたとは考えることはできませんか?自分の気持ちに見て見ぬふりをしていて本当にいいんですか?!自分の心と向き合うべきです!」という旨のことを話す。そして、生意気言ってすみませんでした、ということを言って別れる。
・運転手の女の子は、「あの人の言っていることは本当のことだと思います」という旨のことを言う。
・だが、色男はこの車での会話の直前に、自分を盗撮しようとしていた人を殴り殺してしまっていたのだった。劇団の練習をしている場所に、警察がやって来て、色男は連行されていく

●結:北海道へのドライブ・ドライバーの過去の告白。舞台本番・そして…
・色男が舞台の主人公ではなくなった後、主人公は誰にしようかという話になる。そして、「主催者自身が主人公を演じるか、それとも公演自体を中止にするか」という決断を迫られる。
・男はしばらく考えて、時間をくださいと伝えたのち、一番考え事ができる場所、車の中でしばらくドライブをすることに決める。運転手の女の子に車を運転してもらうのだ。
・ドライブで、運転手の女の子の故郷の北海道に向かってもらうことにする。その土地に向かう道中で、女の子はさまざまな話をする。故郷では母親と同居していたこと。母親から厳しく運転技術を叩きこまれたこと。眠る母親を起こさないようにするために、どんな荒れた道でもスムーズに運転することができるようになったこと。厳しい母との生活が苦しかったこと。時折、母親が幼女のような別人格となってコミュニケーションしてくるときだけが、不思議と癒される時間だったこと。雪崩が起きて、家を押しつぶした時、なかば見殺しのようなことをしてしまって、母親を救い出すことができなかったこと。
・互いの苦しみを話し合った二人は、北海道の地で抱きしめ合うのだった
・場面転換して、劇の舞台が映し出される。そこでは、男が、主人公のワーニャ伯父さんを演じている。男は、ワーニャ伯父さんを演じつつも、舞台の影で非常に苦しそうにしている。(男の人生の苦しみとワーニャ伯父さんの苦しみがリンクしていると思われる節があるため、そのことも影響しているのだろうか)
・「なんて人生は苦しいのだ」という旨のことを、舞台上でワーニャ伯父さんは言う。それに対して、少女は「いずれ死ぬ時が来たら、さっぱりと亡くなりましょう。それから、神様の前に行って、私たちはこんなに苦しみましたよって語りましょう。そして天国で幸せな素敵な暮らしをしましょうね」みたいなことを言う。そして閉幕する。拍手喝さいの仲、劇のカーテンが下りていく。
・劇場から舞台が変わって、韓国に移る。そこでは、運転手の女性が例の男の車を運転して、買い物などをしている。また、車に犬も数匹いて、可愛がっているようである。
(つまり、男と運転手の女の子は何らかの濃い関係性を続けていることを暗示させつつも、映画は終わる)
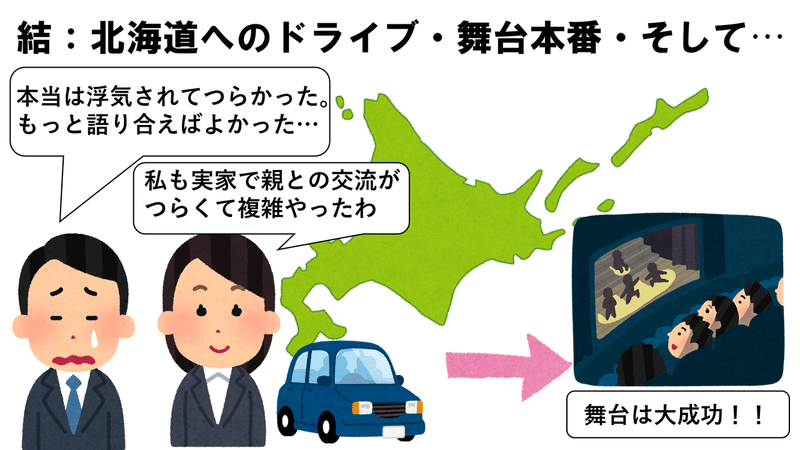
あらすじは以上!大まかな記憶で書いているので、忘れている内容もあるだろうけど、大筋は間違いないはずだ。
====================
感想編:
さて、肝心の物語の感想を書いていきたい。
●同じ空間で過ごす=ディスコミュニケーションの苦しみが生まれる
私は、この物語を『ディスコミュニケーションの苦しみから、人はどう逃れうるのか』についての物語と捉えられると思った。
私たちは、目的を持って同じ空間で他人と過ごすことが少なからずある。
例えば、日々を過ごす家庭、劇団内、職場、目的地に向かう車内。
そうした「他人と過ごす場所」で、できれば楽しく上手にコミュニケーションを取って、居心地よくいたいものだが、なかなかそううまくいかないのが現実だ。
他人の気持ちなんて、完全にわかりっこないのだ。そして、気持ちをうまく伝えることはなかなか難しい。関わる相手に、何らかの不満を持って、ストレスを抱える面が必ずあるはずだ。

●円滑な交流のために「役割」が設定される
円滑な交流手段として特に分かりやすいのが、『役割』を設定することだろうと思われる。
例えば、父、妻、母、娘、劇団の主催者、劇団のメンバー、運転手、客、介護者、要介護者、漫才のボケ、ツッコミ…。役割がありさえすれば、混沌とした関係性にも秩序が生まれうる。「このような役割なのだからこのように振る舞おう。そうすれば、相手はこう返してくれるはず」とするようなこと。
やるべきことが決まっているのだから、交流はスムーズだ。スムーズに物事が進行したり、役割のある関係性の中で癒されるようなことだってあるだろう。

しかし、一方で「役割」は人を苦しめる側面を持ちうる。
例えば、「夫」と「妻」という関係。夫は夫としてこのように妻を愛さねばならない、こうして振る舞わねばならない。妻はそれにこう応じなければならない…。社会では『規範』めいたものが流布されていて、それに縛られて、本来の自分らしくあれずに苦しんでいる人もいるだろう。
他にも、「母」と「娘」という関係性。母は娘に対して『こう振る舞いなさい』という規範を教え込むことが多く、かつそれに従いがちな傾向というのは、ある気がする。(あくまでも筆者の感覚的な話だが)それに苦しみ、実家を出て一人で生活して母と距離を取ることで解放された娘は多い気がする。
主人公の男の妻は、複数の男たちと肉体関係を持っていたわけだが。これは、「夫」と「妻」の関係性の「役割」の中で、なんらかの(言語化できる・できないにかかわらず)苦しみを抱えていて、その癒しを「本来の役割(妻が貞淑であること)」を超えたところ(=肉体関係のある不倫)に求めていたところがあるのではないだろうか。
一方、車の運転手の女の子の母親は、時折無垢な幼い少女のような態度を取るときがあった。これは、「母」として「娘」と関わることに何らかの苦しみを抱えていたために、その「役割からの解放」を求めていたのではないだろうか。
ここまでの話をまとめよう。「役割」は、コミュニケーションを円滑にして癒すことがある一方、人を何らかの固定的な在り方に縛り付けてしまうことがある。そのため、その役割からの解放を求めて、役割を超えた行動を時に人はするかもしれないのだ。
●「妻」「母」などの役割を超えさえすれば救われるのか?
しかし、ときに「役割を超えた行動」を取りさえすれば、全て解決できるかというと、そうとも限らない。
それは、誰かを傷つける新たな要因を生み出しうる。
妻の不倫は、主人公の男を大いに傷つけた。運転手の女の子の母親の幼児化も、運転手の女の子の胸を痛めたはずだ。

「役割」のなかで振る舞っていても、「役割を超え」ても、どっちにしても人は傷つくときには傷ついてしまう。人が同じ場所で交流していくとはなんて難しくて、残酷なことなんだ。なんだか、旧エヴァの『まごころを君に』すら思い出してしまうぞ。

では、どこに救いがあるのだろうか。人は、ディスコミュニケーションの苦しみから逃れられないのだろうか。我々はこのつらい社会の中でどう生きていけばよいのだろう。
そのことについてのアンサーが、この物語で示されているように、私には感じられた。
●結論:「物語る」行為によって、救われて次へと踏み出せるかも!
結論を言おう。
我々は色々足掻いても、ディスコミュニケーションの苦しみから逃れられない。しかし、その「苦しみを語る」という行為によって、救われて、苦しみにとらわれ続けることから解放されうる、かもしれないということだ。
どれほど愛し合っている夫婦、親子、恋人同士でも、相手の全てを完璧に受け止めきれるとは限らない。耐えられない側面というのは、99.9%の人にあるだろう。それにもかかわらず、『嫌な面があるけども目をつぶるわ』となっている人は、相当多いと思う。
だが、自分のつらさに目をつぶることで、傷ついている人は間違いなく多いだろう。見ぬふりをしている事実すら、意識的に気づかないようにしている人もいるかもしれない。この物語の主人公の男が特にそうだ。
(もしかすると、相手の嫌な所を見て見ぬ振りせずに伝え合えるようになった時こそが、本当に気持ちを受け止め合えている理想的な関係性なのかもしれない)
主人公の男は、運転手の女に「妻が浮気をしていたことがつらかった。なんでだって、怒りたかった」というように、自分のことを語る。その語る行為で、主人公の苦しみは浄化されている面が間違いなくあるだろう。
また、主人公の男は「妻の話をもっとちゃんと聞いてやろうとすればよかった。でも聞くのがずっと怖かった」ということも吐露する。浮気していた妻も、何かに苦しんでいたかもしれないのだから。その「苦しみ」がなんであるのか、夫婦間で互いに見て見ぬふりをせずに語り合おうとすればよかったのだ。
「コミュニケーションの中での苦しみを伝え合う」のは、生者にしかできない。物語中の「主人公の男の妻の突然の死」は、「語れるときに語っておかないと、人は突然死んでしまうかもしれない」という残酷で重大なメッセージだと感じられた。

社会で生きていく・他人と過ごすことには、まず間違いなく苦しみを伴う。その苦しみから逃れようと、我々は足掻く。だが、その足掻いた結果、別の苦しみが生まれたりする。
しかし、我々はそれぞれの苦しみを語り合える。例えば、自分自身へのやりきれなさとか、他人や社会やらどうしようもない運命への怒りか、そうした類について苦しみを吐露する。
苦しみの物語を他人から伝え聞いたとき、人は相手に労わりの心を持つかもしれない。優しい気持ちで、慰めようとするかもしれない。そうしたことが、人の心を大いに癒して浄化していく。癒された心は、苦しみ続けることをやめて、前を向こうとし始める。
そう考えると、これは希望に満ちた物語だ。

(まあ、ちなみに「苦しみを語る」ことに縛られ続けて動けなくなってしまうタイプの人間もそれなりにいる。もしかすると、その人は満足するまで語り続けるしかないのかもしれない。それほどに強い苦しみがあったのだろうから。それが「創作活動」の動機となる人もきっといるだろうね)
そうそう。映画内の『ワーニャ伯父さん』の舞台で、娘のキャラが言った「いつか死ぬ時が来たら、神様にこんなに苦しかったですよ、つらかったですよって言ってやりましょう。で、それから素晴らしい天国での生活が待ち受けているのよ。そうなると、『信じましょう』よ」みたいな言葉があった。
あのシーンは、ここまで語ってきたような解釈をしてきていた私にはとても心に刺さった。
究極は、死後に神様に対して、「苦しかった物語」をするのだ。そのことによって、心の重荷を下ろすことのできた人は、苦しむことを辞めて楽園での幸福を享受していくのだ。そうなると、『信じる』のだ。
信じるというのは、客観的・合理的な科学的行為ではない。しかし、生きていくうえで起きるつらい出来事は、客観的・合理的に解決できないことばかりなのだ。
だからこそ、つらい心だけでも救うためにも。私たちはときに物語を語る必要があると、筆者は感じた次第である。

ここまで述べてきたようなことを考えながら観ていたので、映画はとても楽しかった。
・その他に思ったこと
ほかにも色々と面白い解釈のできる余地のあるシーンが色々ある。
・途中、感情を殺した読み方での脚本読みがあったが、あれは、「役割だけがそこに存在することの空虚さ」を強調するようだな~と思ったこととか。「役割にどんな感情をこめていくべきかを深く考えるための準備期間として、あえてあのような脚本読み期間をもうけたのではないか?」などと空想したこととか。(もしかすると、本当に劇団で脚本読みの練習をするというのは、ああいうのがセオリーなのかもしれないけど。)
・主人公の奥さんが、無意識的にセックス中に物語をするのがなぜかというと。無意識的にでも物語を語るという行為によって、彼女の抱えている何らかの苦しみを癒そうとしているのではないか?と思った。
(自分の抱える問題に意識的でなくても、物語が語られると、その問題への癒しにつながっていく側面があるのかも?創作活動をする人が書いている物語なんて、本人の意識する・せざるにかかわらず、その創作者本人の抱える問題とリンクする物語を無意識的に書いて感情を癒してそうだよな~なんて。身に覚えがなきにしも)
・この物語のテーマとぶつけるなら、キューブリック監督の『アイズ・ワイド・シャット』が絶対に良いよな~って思ったこととか。
「アイズ・ワイド・シャット(大きく目をつぶって)」妻の不倫を疑う夫の物語。いや~、面白いし、最高のタイトルですよね。
すごく色々と考えさせられた!
そんなこんなで、今回はこの辺で。
