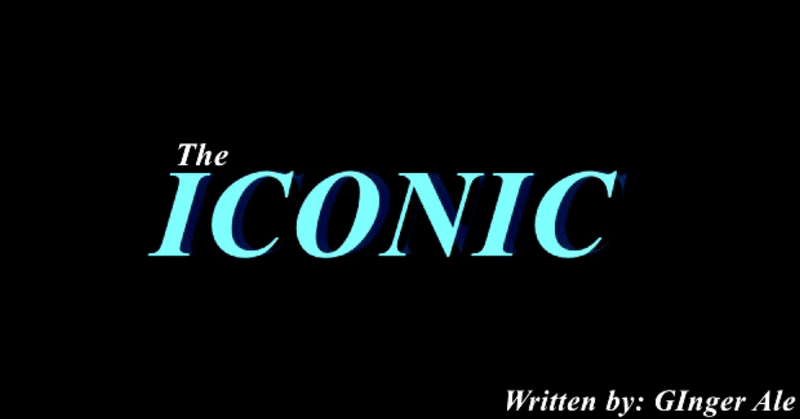
ICONIC / アイコニック ⑮
翌日の夜8時。一部の運動部以外はとっくに帰宅しており、校舎に点いている明かりも片手で数えられるほどになっていた。
「夜8時なんて、優しい時間に召集かけられたもんやな」
秋龍は相変わらず飄々としている。
「なんにせよ怪我人が出ないことを祈るよ」
「まったくだ」
俺と武村は秋龍に誘われるまま学校に残り、図書室を追い出されるまで仲良く仮眠をとっていた。追い出されてからの2時間は退屈極まりなく、最終的に廊下に三角座りをして眠ることになった。
そんなことをして大丈夫か、と聞かれたら俺はこう答えよう。首は痛いし額には跡がつくし、やらない方が良かった、と。
「ここやな」
屋外にあるプールは周りをフェンスで囲われており、入り口には南京錠がかけられていて"通常"は入ることができない。では"非常"なら?非常なんて滅多にならないからこれと言って例は出せないが、少なくとも南京錠が破壊されて床に落ちている状態は非常だろう。
もう秋も暮れにかかっているこの季節、屋外にあるプールはとっくに水が抜かれていた。プールサイドには各辺に2つづつ、計8つのスタンドライトが設置されており、それぞれが水のないプールを照らしていた。
「『2001年 宇宙の旅』の月のモノリスのシーンみたいやな」
「2001年 宇宙の旅?観たことないな」
「映画をあんま観ぃひん人間なら、まだ観ぃひんほうがいいかもしれへんな」
プールサイドには幾らかの人間がおり、どれもガタイのいい生徒ばかりだった。たまに細い生徒も見かけるが、並べてみな身体強化のTHTに体を換装している。
「君たち」
プールサイドを散歩する俺たちの前に立ちはだかったのは、ある女子生徒だった。
「見たところ新入りね。ただ、君は…」
女子生徒が秋龍に近寄る。
「話には聞いてるわ。荒牧ちゃんに喧嘩売ったんでしょ?あと文元にもね。たしか名前は、秋龍くんだっけ?」
秋龍はいつもの微笑を浮かべたままである。
「せやで。キミは2年A組、荒牧とおんなじクラスの生徒やろ?名前は東雲 麗華」
「あら、知ってるの?」
「せや、知ってるで」
「なら話が早いわね。もうちょっと待ってて、あと1時間もすれば始まると思うから」
東雲はそう言うと去っていった。
1時間?ふざけるな。何時間学校で時間を潰さなければならないんだ。
「また寝るか」
なんだと秋龍?俺はごめんだ。
その後俺たちは飛び込み台のあたりに座り込み、雑談をしながら時間を潰した。時間が経つにつれ人数は増えていき、9時10分ごろに荒牧と文元が到着した時にはプールサイドは人で溢れかえっていた。
「ハイハイ、みんな静かに〜!」
プール中央で大声を上げたのは、先ほどの東雲だった。
「急遽この祭りが開催されたのは、他でもない荒牧ちゃんの提案よ。でもまぁ、みんな楽しみにしてたでしょ?」
おぉ〜!と雄叫びが上がった。俺と武村が驚いている一方で、秋龍はノリノリで雄叫びを上げている。
「そしてこの祭りが企画された理由は、他でもないアイツのせい!」
東雲が勢いよく指差した先には、やはり秋龍がいた。
「期待の新人!秋龍 陵時!」
今度はうぉ〜!という雄叫びだ。
「せっかく君のために開催されたから、軽くルール説明をしてあげる!ここでは年に数回、殴り合いパーティが開催されるの。対戦は一対一で行われて、どちらかがギブアップするまで戦いは続くわ。挑戦者が相手を指名して戦うシステムで、指名された側は是が非でも応じないといけない。オーケー?」
秋龍は「オッケー!」と意気揚々と返事をした。
「ここで行われる戦いは大きく分けて二種類、下剋上と制裁よ。スクールカースト下位の生徒が上位の生徒を倒せば、立場は逆転。まさしく下剋上ね。そして制裁というのは−−−」
「上位の者が下位の者を蹂躙する、身の程を弁えさせる試合だ!」
東雲の説明を遮って声を荒げたのは、文元だった。
「今日ここで決着をつけてやる。純粋な殴り合いでな!」
今にも殴りかかろうと叫ぶ文元を、東雲がまぁまぁと宥めた。
「とはいえ、物事には順序ってもんがあるからね。この私、東雲がお手本を見せたげる。そこの君!」
東雲が指差したのは、さながらゴリラのような筋肉の男子生徒だった。
「勝負よ!」
東雲とゴリラ君はそれぞれ向かい合うかたちになった。ゴリラ君は取り巻きにTHTの調整をしてもらい、一方の東雲は二人のこれまた筋肉隆々な生徒が持ってきた正方形の重々しいケースを開けていた。
「あんな細っちいのが勝てんのかよ?」
武村が腕を組み直しながら言った。
「確かにな」
見たところ東雲は身長が160センチ半ば程度の細身で、とてもゴリラ君と渡り合えるような力は無いように思える。
「いや、東雲は相当強い方やで?」
「アレが?」
心外だ。
「せやで?あのケースの中、何か分かるか?」
東雲が鍵を解除しているケースは、少なくともマトモな物が入っているとは思えない。だが何が入っているかも予想がつかない。
「特注の巨大な掌THTや」
その瞬間、その「手」とやらがケースから取り出された。初見の印象は、手というよりかは巨大な岩だったが。
「でも、あんなモンまともに振り回せんのかよ?あんな体でさ?」
武村に賛成だ。
「それができるんや。東雲の両腕・両足はヘルドッグス社のソウルキーパーシリーズ専用THTのスーパーギアグレードでな。型番までは知らんけど」
「でも生身との接続部が千切れたりするだろ?…まさか」
「そのまさかや。アイツはフルメタルボディ、つまり首から下全部がTHTの人間や。ボディはテクノ・カイザー製のモンで、四肢のTHTの正確な制御が可能や」
東雲は両手を取り外し、巨岩こと特注拳に接続しはじめた。
「でもソウルキーパーシリーズって女性型の生産をしてなかった気がするんだけど」
そうなのか?何かと粗探しをして騒ぎ立てる輩のことを懸念しなかったのか?
「まぁな。実際、アイツは元々テクノ・カイザーの非正規クローンでな。いわばプロトタイプっちゅうやつや。アイツの持ち主はテクノ・カイザーの有名研究者で、本来捨てられるはずやったアレを拾って改造したんや。…武村クン、NFAのスペックはある程度知ってるか?」
「うん、まぁ」
「なら、NFAがTHT耐性に関してヘルドッグスのクローンとおんなじ位なのが、テクノ・カイザーのNEXUS Mindsによるものなんも知ってるな?あれの研究の第一人者もアイツの持ち主でな、興味本位でインストールしたんやと。それのおかげで、一流企業のクローンでもODしかねへんスペックのTHTを扱えるっちゅうわけや」
ここで、東雲はTHTの接続が完了したようだった。ゆっくりと立ち上がり、すでに準備が完了していたゴリラ君のほうに向き直った。
「それじゃ、始めよっか」
東雲の振っている手は、遠近法の概念を壊すほどに大きかった。顔より二回り以上大きい手のひらなんて、見たことがない。
なかなか凄いことになってきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
