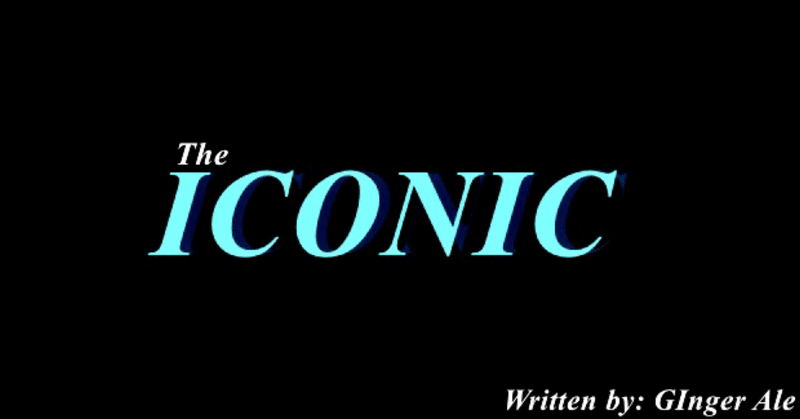
ICONIC / アイコニック ⑬
その後しばらくしても秋龍とレイジがなかなか店の奥から出てこなかったため、俺と武村は様子を見に行った。
鉄製の重々しいドアを開けて中に入ると、薄暗い部屋の中央に診察台のようなものがあり、そこに秋龍は寝そべっていた。レイジはその隣で椅子に腰掛けながら、コンピュータディスプレイに映った情報を眺めている。
「あれ、どうしたんや?」
秋龍がこちらに気付き、声をかけてきた。
「いや、なかなか出てこなかったからさ。なにかあったのかと」
俺はレイジの眺めるディスプレイの方に目を向けながら、秋龍に応えた。
「ちょっとしたケンカや。大したことない」
レイジがディスプレイから目を離し、秋龍の方を振り返った。
「大したことないわけあるか。お前自分が何を言ってるのか分かってんのか?」
秋龍がため息を吐いた。
「あのなぁ、レイジ。俺は大丈夫や、なんとかなる」
「なんとかなるだと?あのTHTは高負担過ぎる代物なんだぞ?いくらお前といえど、そろそろODキメてもおかしくない」
「Meta-BRAINのTDか?」
それまで黙っていた武村が口を開いた。
「よく分かったな」
秋龍が目を丸くして言った。
「まて、TDってなんだ?」
俺は武村に聞いた。THTオタク語を話されても分かるわけがない。
「TD…Time Dominatorの頭文字さ。Time DominatorっていうTHTはMeta-BRAIN社作った製品で、世界最高負担の名を冠してる。三流企業のクローンが使えば、死ぬかイカれるかのどっちかだな…。それで、秋龍の型番は?」
「型番はNF…」
「秘密や」
レイジが型番を答えようとすると、秋龍がそれを遮った。
「…まぁいい。それと、この前の謎のデータチップの解析が終わったぞ」
「お、中身は何やった?」
レイジがカタカタとキーボードを叩くと、コンピュータの画面に新しいウィンドウが表示された。
「げ、神文字じゃないか」
武村が言った。
「ん、よく知ってんな」
レイジが武村の方を振り返った。
「神文字ってなんだ?」
もちろん、この俺がTHT関連の話題についていける訳もない。
「神文字っていうのは、シュイウォズンティス=ムーアノイシュっていう博士の作ったコンピュータ言語のひとつで…」
「シュイ…なんだって?」
「シュイウォズンティス、だ。神文字っていうのはその博士が作った特殊なコンピュータ言語で、一文字の中に膨大な情報を詰め込めるんだ。でも、その神文字を完全に翻訳することは現時点で不可能とされてる」
「不可能?なんでさ?」
「それはな、」
レイジがこちらに体を向けた。
「一つ目、ムーアノイシュ博士が行方知れずになっている。二つ目、一つの文字列に含まれる情報が膨大すぎる。三つ目、言語としてアホほど難解すぎる。そして四つ目、翻訳できる機能があるTHTとコンピュータがこの世にほとんど存在しない。これらの要素のせいだ」
そうそう、と頷きながら、武村も言葉を続けた。
「主として問題視されているのは四つ目、翻訳できるTHTとコンピュータがこの世に少ししかないことだな。神文字は七文字で一行が構成されて、それが四つでワンセットになってる。そのセットを三つまで一気に翻訳できるのはNFAっていうクローンに搭載されていた脳機能拡張THTだけ。博士は神文字を数百セット翻訳できるコンピュータを設計していたんだが、ある日突然姿を消したんだ。その後世界中の学者が設計を続けようとしたんだが、理論もシステムもあまりに難解だったから断念されたんだよ」
ほんじゃぁ、と秋龍が診察台から足を下ろしながら言った。
「NFAが一体居れば話は解決するんやな?」
「いや、そういうことにはならないんだよな」
レイジが言った。
「なんで?」
武村が問いかける。
「データチップに保存されてたのは神文字540セット。神文字はその特性として、連続性のある情報、つまりは前文との繋がりがないと完全に翻訳できない。だからNFAを呼んで3セットずつ地道に翻訳してもらっても、最終的には訳のわからない文字列になっちまう。それにそもそも、生産されたNFA12体のうち10体は破壊されてるし、残った2体は……どこにいるのやら」
そして、そんなわけのわからないデータが保存されたデータチップがここにある、と。
「翻訳はまず無理だろうな。まぁ、お守り程度に持っとくといい」
レイジはケースに入ったデータチップを秋龍に投げて寄越した。
「話戻すけどな、とりあえず来週に俺は『津波』に行って、笠山からTDを貰ってくる。レイジ、インストールは頼んだで?」
レイジは溜息をつくと、はいはいと応えた。
秋龍はそれを聞き笑みを浮かべると、こちらを振り返った。
「ほな、帰ろか」
秋龍の車で俺たちはそれぞれ家まで送ってもらった。武村の家の方が近かったため、途中から車には俺と秋龍だけが乗っている状態になった。
「『津波』、一緒に来るか?」
秋龍が助手席から話しかけてきた。
「料亭だっけ?テックギャングがいっぱい居る」
「せやで」
「…面白そうだし、行ってみようかな」
「面白そう、か。ええな。…武村クンも来るかな?」
「どうだろうな。あいつ確か来週の半ばくらいに『メガルザーク』の脚型THTをインストールする手術を受けるはずだから」
「そうか…」
会話はそこで途切れた。
「ほなまた明日」
「あぁ、また明日な」
秋龍は俺を家の前で降ろし、帰っていった。そういえば、彼の家はどこなのだろうか。犯罪組織の家だから、知らない方がいいかもしれない。知らぬが仏、などと考えながら、俺は家の門を開けた。
薄暗い庭を歩き、ロータリーを直進する。中央の噴水はチロチロと水を流しており、少し波の立っている水面に月が揺れており、その横を枯葉が浮いている。
玄関を開け、家に入る。乱雑に脱ぎ捨てられたヒールは、母親が帰宅していることを示していた。ただいま、と言ってみるも返事は返ってこない。おおよそ、もうとっくに眠ってしまっているのだろう。
俺は真っ暗な廊下を進み、階段を上った。廊下を歩く足音が響く。部屋の扉を開け、明かりをつけると、荷物を床に置いた。
翌朝、いつも通りの時間に目を覚ました俺はせっせと学校の準備をすると家を出た。
昨日の特別な体験により世界が違って見えることなどなく、いつも通りの風景に欠伸が出た。滲み出た涙によって世界が揺らいで見えたが、その程度である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
