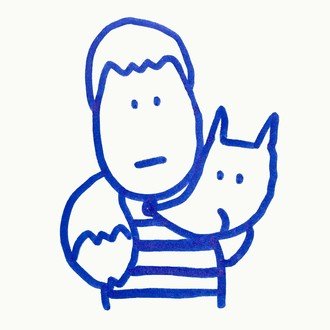2018年6月の記事一覧
簡単に怒りだして、無理難題を言った挙句に、相手への罵倒が止められない人いるけど。アンガーマネジメント無理だと思う。罵倒してる自覚もないはず。きっと怒れば言うことを聞いてもらえるって、学習してしまってるんじゃないかなと思う。
ドキンちゃんみたいなもんだよ、全くタチが悪い。
僕とスピリチュアルはなぜだか切っても切れない関係にある。周りにいる人たちも僕のことをそっちに詳しい人だと思っている。僕は表現こそ文系だが、ロジックやシステム、アルゴリズムでものを見る理系だと思う。だからきっと橋渡しをしないといけないのだ。見えないものと見えるものの橋渡し。
「デザイン教育」を、とにかく誰にでもわかるように、と突き詰めていき、療育、認知科学、発達科学とか、思想哲学、などが、教え方の切り口になっている。教育は、多くの知識よりも、1回の学びをいかにクリティカルなものにできるかが大切なのだと、思う。
障がい福祉や、こどものワークショップに関わり出したときに、準備の配慮とか、いかにこどもたちが汚れないようにするか、飽きないように、気が散らないようにするか工夫したり教えてもらったりしてたら、言葉がけやタイミング、イメージの共有には、認知科学がめっちゃ関係してるやん、と思った。
どんな活動してるかとか、一番なにやりたいのかとか、そんなのは常に探しながら走る。だから、これだと答えられるものがあるなら、自分がやる必要がない。答えられない。
例えば、自分で身につけたのと同じやり方がアドラー本にのってたとして、アドラー心理学ですねと言われるのは、違う。
「回り道」は大切な道だ、と思う。
ひとつ前に書いたように、自分のオリジナルな経験で身につけた事が、本やらなんやらに簡単に載っていると「〇〇の本に影響うけたんですね」と言われてしまい嬉しくはない。でも回り道して身につけたことは、自分の言葉で語れるのだからそれがいいに決まってる。
「あの人は提案ができない」なんて他人を厳しく評価する人がいるけど、たいていその人は、提案がうまれるような質問もできない、提案しても文句しか返さないようなことがある。どうなんそれは。