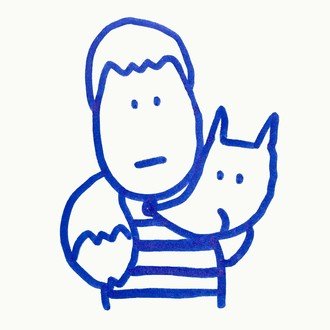2017年5月の記事一覧
4-5歳の小さい頃に、よくこの野草をガムがわりにしがんでいました。それは母に教えてもらったんですが、どの草だったかすっかり忘れてたのが、さっきふいに見つけたので、実に35年ぶりぐらいにしがんでみたら、なかなかえぐみがあって、よくあんなに食べてたなぁとおもった。

「好きなもの図鑑」というデザイン&セラピーワークショップをやっている。
幼少からの自分が「好きなもの」を画像検索で収集して、スクラップブックして、紹介しあうのだけど、たいがいは誰でも何かのオタクなので、その場はなんともマニアックな学び場になるのだ。
無理数(πとか√とか)は「割り切れない」んだけど、自分にとって「もう無理」って思うことも「わりきれない」から、イヤ!と思うんじゃないかな。
明快な答えがでるまで、小数点以下を求め続けるんじゃなくて、それを「π」とか「√」だって捉えたら、判然としなくても次に進むことはできそう。
なんで成功にこだわるのか。
成功したいけどさ、納得が大切だと思うんだ。
話し合いをせずに、どちらが間違いかを決めて、なにか解決した気になる人が多いよ。それこそ放置なのに。
お互いがどこでズレたを知るためじゃなく、どっちが悪いか、を決めるために原因を突き詰めたりする。
話せば悪とみなされるし、黙れば放棄とみなされるし、そういう思考は何をしたいんだ。
こどもも大人も、「ぼーっとする」ということができない人が多いのではないかなと思っている。つまり、何もしないでいいもきに、自分で意味を見出せない。
ぼくはそこに、大切な療育の要素があると考えている。
自分のことを「わかろう」とするのは、自分を「わかっていない」と、自ら決めているからなんだ。
そして、わかっていないことを、認めようとするのではなくて、どこかに封じ込めるために理屈をつくってわかろうとしている。
必要なのは、わかる、わからないじゃなく、ただ直視すること。
人は物事を修正訂正したがるのが性分で、対象や自分を「直したい」と思う気持ちは、そのままそれを「認めない」という思い。
逆に放置できるのは、有り体に見て「訂正したい」なんて事を考えないとき。それが、認めること。
そりゃ言うのは簡単なので、それをできるかどうかはまた別の話。
「社会」というのは、シンプルに考えると、多数決や妥協点であったり、人の集合的意識であったり、そういった本来備わっている欲求と自律が自然にかたちとなったものなのかな、と思う。
「反論」は、考え方の違いを主張するもんであって、話しの流れがズレてるときに、確認したり、違うよって言うのは反論じゃないんだよ。ましてや否定でもなければ、攻撃な訳がない。
齟齬がおきてる事を確認したら「攻撃」と思われるってパターン多くていやだよ。
「言い訳」って。なんでか悪者にされてしまうけど、「事実」なんよ。
それを受け入れてもらえないときに「言い訳=事実」が、「言い訳=言い逃れ」に書き換えられてしまう。
言い訳があれば良いわけではないんだけれど、聞く耳もたず「言い訳するな」は何かが違うように思うよ。