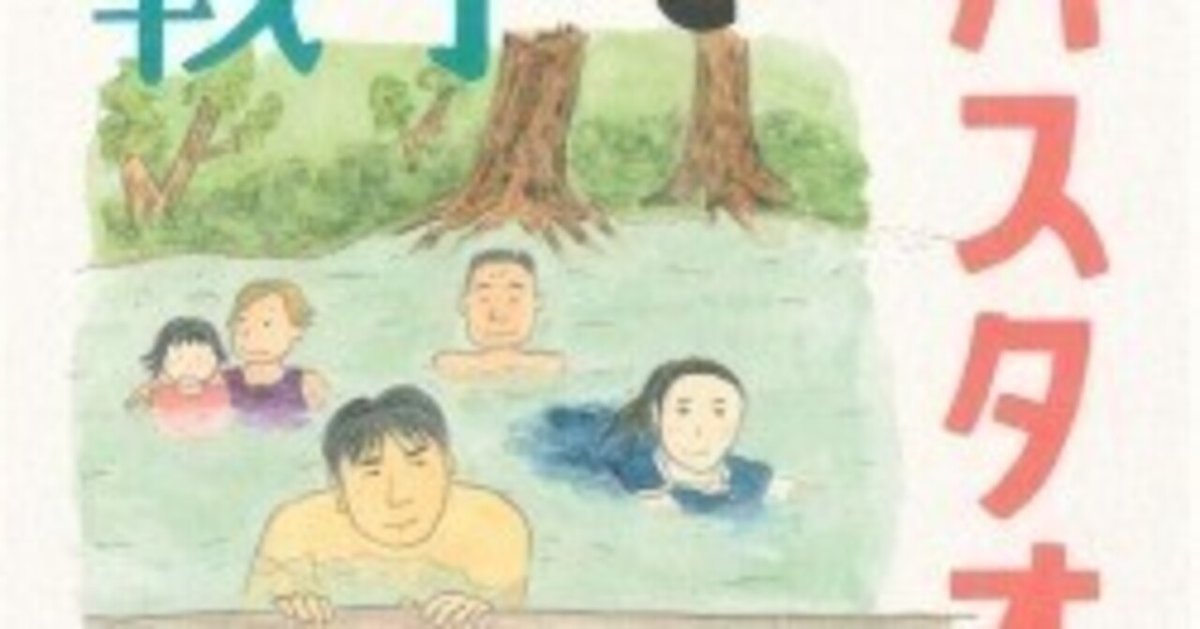
【読書日記】安田浩一・金井真紀『戦争とバスタオル』
安田浩一・金井真紀(2021):『戦争とバスタオル』亜紀書房,373p.,1,700円.
本書は,YouTube番組「NoHateTV」でおなじみのノンフィクションライター安田浩一さんと,難民フェスを主宰し,入管法問題ですっかり話題になったイラストレーターの金井真紀さんによる共著。実は,私自身金井真紀さんを知ったのは本書を通じてだった。デモクラシータイムスのYouTube番組で,「池田香代子の世界を変える100人の働き人」というのがあるが,そこで本書が取り上げられ,著者のお二人がゲストで出演したのだ。
その後,安田さんの本も一冊読み,金井さんの本も一冊読んだ。本書もそのうち読みたいなと思っていたら,なんと近所のブックオフの棚に並んでいたのだ。古書店で購入しても著者にはお金は入らないし,ここに置いてあれば一般の書店とは違った客層の目に触れるかもしれないし,ここで本書のことを知っている私がわざわざ買わなくてもいいような気もしたが,何となく私に連れて帰ってもらいたそうに訴えかけられたので,それほど安くなっていなかったことを意味のない言い訳にして連れて帰ることにした。
はじめに
第1章 ジャングル風呂と旧泰緬鉄道:タイ
第2章 日本最南端の「ユーフルヤー」:沖縄
第3章 沐浴湯とアカスリ,ふたつの国を生きた人:韓国
第4章 引揚者たちの銭湯と秘密の工場:寒川
第5章 「うさぎの島」の毒ガス兵器:大久野島
付録対談:旅の途中で
おわりに
あらかじめ,上記のYouTube動画で内容については知っていたものの,やはり本というのは実際に読むのとはだいぶ印象が違うものです。金井さんはイラストレータといいながらも自分で文章も書く。本書はお二人が一緒に旅をしながら,もちろん男女別々にお風呂に入り,本文は安田パートと金井パートとが交互に入れ替わるといった編成。もちろん,金井さんのイラストも多数掲載され,写真もある。
NoHateTVでも,最近安田さんの鉄道コーナーがあるのだが,本書とよく似ている。安田さんはお風呂も鉄道も好きだということだが,単にお風呂に入りに行ったり,鉄道に乗りに行ったりするわけではない。安田さんは常に国家という大きなものに抑圧された市井の人々の姿を追っているような気がする。そして,彼の仕事をみると,成長する国家が帝国主義・植民地主義へと移行するその過程が論理的に理解できるような気がする。日本という国は19世紀末に向けて軍国主義へと突き進み,日清戦争・日露戦争を経て,台湾・朝鮮半島を植民地とし,第一次世界大戦では連合国側に着くことで,そのおこぼれをもらう(ドイツが占領していた太平洋島々の委任統治)。中国本土へと侵攻し,第二次世界大戦へと突き進む。この半世紀余りの歴史の中で,本土,植民地,侵攻先でのエネルギー,交通,土木を整備することで国力を高めようとする。そうした多くの尽力を必要とする現場では,国内の棄民はもちろんのこと,植民地からも多くの労働力が動員され,過酷な労働を強いてきた。トンネルや空港,鉄道など,最終的には陽の目を見なかった施設も含め,多くの犠牲が出て,遺構が遺された。そうした痕跡を探して安田さんは日々国内外を問わず駆け回っている。本書は,元来のお風呂好きということもあって意気投合したというのはあるとは思うが,行き当たりばったりの取材旅行に,人当たりがよい女性である金井さんが同行することで引き出された人とのつながりも含めて,後半に向けてミステリー小説を読み進むようなスリリングな展開をしている。
とはいえ,本書はそうした埋もれた歴史を掘り起こすようなスクープなわけではない。当然のように,本書に登場する史実のほとんどをわたしは知らないわけだが,本書に出てくる史実や,その語り部のことをネットで検索すると,そこそこ記事が出てくるのだ。しかし,「はじめに」で金井さんが書いているように,なかなかお二人の本は売れないようで,「おもしろくて売れる本を作って,対抗すればいいじゃん。」(p.3)というのが本書刊行の目的。私が入手したこの本は,2021年9月28日に第1刷で,11月12日の第2刷のものである。2か月経たずに増刷とはなかなか売れているのかもしれない。上にも書いたように,私的にはそれぞれ1冊読んだお二人の本以上に本書は面白く,そこそこ厚いのだが,残りページも気にならずに数日で読み終えた。普通に書棚にならんでいたら背表紙の厚さで躊躇してしまうかもしれないが,本文は軽やかで厚さを感じない本なので,是非多くのお宅にお持ち帰りいただきたい。
さて,内容だが,登場する場所を簡単に紹介しよう。第1章はタイの北西部にあるヒンダット温泉という場所。バンコクからそこまでは鉄道を利用する。それが旧泰緬鉄道というもので,第二次世界大戦中に日本兵が侵攻し,現地の人のみならずオーストラリアや英国の連合国軍の捕虜兵を使ってタイとビルマ(現:ミャンマー)とを結ぶ鉄道として日本軍が建設したもの。私の世代は1985年の公開された映画『ビルマの竪琴』を知っている。中井貴一が主演したものだが,改めて観たいと思う。しかし,Wikipediaで調べたら,なんと1956年に市川 崑監督による二部作映画が作られていたとのこと(しかも,1985年版も市川 崑監督とのこと)。さらには,この作品には原作があり,1948年に刊行された児童向け小説とのこと。原作も読んでみたくなった。そして,このヒンダット温泉というのは日本兵たちが自らの心身を癒すために作ったものだという。それが今や現地の人々に癒しを与えているのだから皮肉なものである。決して,日本が植民地や侵攻の地でインフラを整備したことは良いことであるなんて論調には与しないが,そのようにして現在まで残された戦争遺物というのはけっこう多いようだ。日本ではそういう物が語る記憶を消去したい風潮だが,そうした物は戦争の記憶を語り継ぐことにもなり,著者たちの旅はそのような遺物を捜し,そこに関わる人々の語りを集めているのかもしれない。
第2章は沖縄で唯一残るという銭湯に行く。中澤高志(2022)「銭湯的ジェントリフィケーション」(荒又美陽+明治大学地理学教室編『東京の批判地誌学』ナカニシヤ出版)で東京の状況が語られているように,日本全国で銭湯が求められた時期には多くの銭湯があったが,個々の住宅に風呂が設置されることで,その機能的な役割を終え,銭湯は数を減らし,公衆浴場という役割はスーパー銭湯的なものに奪われていった。同じような過程で沖縄の銭湯も消えつつあるのだが,仲村シゲさんが経営する中乃湯が沖縄で唯一残っている銭湯とのこと。1960年から経営を続けているという。沖縄の1960年といえばまだアメリカ占領期であり,そうした時代を,こうした人々が集まる場で過ごしてきた方に話を聞くだけで,さまざまな物語を聞き出すことができる。唯一の銭湯には常連さんがいて,遠方からわざわざ浸かりに来る人がいて,そうした人の話を聞くのも面白い。
第3章は韓国。南部の釜山に近い温泉をいくつか訪ねる。周知のとおり朝鮮半島はかつて日本の植民地であり,日本は植民地時代に,その植民地(朝鮮半島,台湾島,満州)を訪れる観光ツアーを組んでいた。それと関係するかどうかは分からないが,朝鮮半島には温泉地も整備されていたという。安田さんは日本で2000年代に入って激しさを増した在日朝鮮人に対するヘイトスピーチの現場をいくつも取材してきたこともあり,日韓の歴史には詳しい。金井さんも日本に住む外国人とのネットワークを広げるような活動をしており,自ずから日本に住む数の多い韓国人との関係もあると思う。そんな人間関係から韓国へ行き,年配の人に話を聞き,植民地時代の日本の名残について話を聞く。もちろん,第二次大戦のこと,朝鮮戦争のこと,そしてお風呂に入りに来たこともあり,韓国といえばアカスリ,そしてそのアカスリの道具イテリがイタリアにルーツがあるという話など,どんどん話は膨らんでいく。
第4章から,面白い展開になっていく。神奈川県の寒川町にあった「すずらん湯」という銭湯を訪ねるところから始まるのだが,既に廃業していて,跡地には進学学習塾が建っていた。その銭湯は戦後引揚げ者のための住宅が作られたのだが,風呂なしの住宅であったため,住民が町に請願をして町営浴場として1954年に開業したのだという。この二人の取材はともかく現地に足を運び,手当たり次第に話を聞いて広げていくスタイルだが,ここではうまくいかない。そこで,寒川町の図書館を訪ね,文書館という町に関わる歴史資料を集めているところに足を運ぶ。そこからいろんなことが分かってきて,先ほどの引揚げ者用住宅が,もともとは戦時中に作られた相模海軍工廠の従業員寮だったという。そして,その工場では毒ガスが製造されていたというのだ。色々調べていると,その工場で働いていた人物,石垣 肇さんにたどり着く。石垣さんは現在日野市在住ということで,著者のお二人は石垣さんを訪ねて私の住む日野市に来たらしい。石垣さんに一通りお話を聞いた後,本書はこの「毒ガス工場」のテーマに突き進むことになる。
第5章は,日本で最大の毒ガス工場があった瀬戸内海に浮かぶ広島県大久野島を二人は訪れる。無人島に軍の毒ガス工場が作られ,戦時中の地図ではこの島は黒塗りされている。現在は国民休暇村が建てられ,うさぎが多数生息する「うさぎの島」として観光地化もされているという。二人はその休暇村の温泉につかり(そこは律儀に書名のテーマを守ります),取材を始める。当時は隠蔽されていたこの島の歴史を広く伝えようとする「大久野島の平和と環境を考える会」の山内正之さんが案内してくれる。毒ガスの話はまだまだ続く。本誌の内容はウェブ記事として連載されていたようだが,寒川町の回(第4章)で登場した石垣さんの甥だという高畠 修さんが,都内某所で金井さんに声をかけてきたのだという。高畑さんは叔父が寒川の工廠で働いていたということで,日本軍が作っていた毒ガス兵器に関心を持ち,大久野島はもちろんのこと,大久野島で製造された兵器が運ばれたという中国の北坦村も訪れたことがあるという。それから,大久野島で働いていたという藤本安馬さんにも話を聞きに行くことになる。藤本さんは当時95歳で,昨年末に亡くなってしまったらしい。この人の証言がものすごい。そして,彼も北坦村に行き,住民たちに謝罪をしたという。大久野島から運ばれた毒ガス兵器はほとんど使用されることはなかったのだが,終戦後日本軍はその兵器の後処理をせず,そのまま放置してきたのだという。毒ガスであることを知らずにドラム缶等を扱った現地の人が次々と被害にあったという。本当にひどい話だ。ここではかかなかったが,藤本さんは加害者として中国に謝罪に行ったのだが,彼自身もひどい労働環境で14歳から働かされた藤本さんも被害者の一人である。一方で日本政府は,そのように働かせた国民に対しても,当然その後日本国籍を奪った,朝鮮からの徴用工に対してもほとんど責任を取っていない。そして日本軍が製造した兵器によって戦後被害を受けた中国の人に対しても責任は取っていない。本当に戦争に関してはことごとく日本の行ったことは非道なことばかりで,しかもその末裔である私たちはそこから学ぶこともなく,将来的にも戦争被害を生み出すことになることばかりを推し進めている。
ちょうど終戦の夏,そして直接は関係ないが関東大震災から100年目を迎える直前にいろんなことを考えさせられる読書だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
