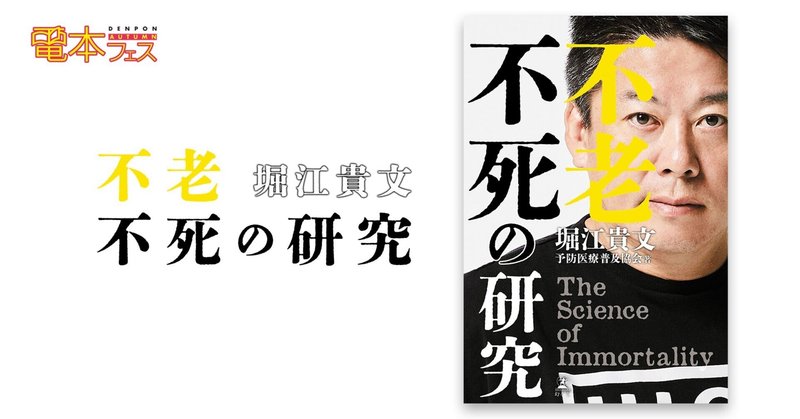
【電本フェスおすすめ本vol.6】金と頭は健康に使え!ホリエモンが世界最先端の研究者から得た知見を公開
この記事では、電本フェス本祭(~9/14)の対象作品の冒頭を試し読みしていただけます。数ある電子書籍の中から、スタッフが厳選ピックアップしたおすすめ作品です。ぜひお楽しみください!
今回は第一線の研究者にインタビューし続けた、ホリエモンこと堀江貴文さんによる唯一無二の健康本を紹介します。まずは、冒頭部分を読んでみてください。
100歳まで健康であるためには「知ること」が最大の武器
『不老不死の研究』堀江貴文・予防医療普及協会
* * *
はじめに
子どものころ、死ぬのが怖くて怖くて仕方なかった。
夜になってから電気を消して布団に潜っても、なかなか寝つけない。ひょっとすると自分は、このまま目覚めることなくあの世に逝ってしまうのではないか。電化製品のヒューズが飛ぶように心臓がいきなり止まったら、人間の魂はどこへ行ってしまうのだろう。そんなことを想像していたら、体がブルブル震えてきた。
大人になってから、ヴィクトル・ユーゴーの『死刑囚最後の日』(岩波文庫)という古典の存在を知った。この作品には、死刑執行を待つ男の様子が日記のように綴られている。〈人はみな不定期の猶予つきで死刑に処せられている〉という一節は衝撃的だ。
なるほど、いつか必ず死ぬことが約束されている人間は、私も含めて全員が死刑囚に等しい。死へのカウントダウンが今この瞬間も続いているかと思うと、ますます死ぬのが怖くなってきた。
死を恐れるのは私だけではない。秦の始皇帝は「不老不死の薬」がどこかにあると信じ、草の根を分けてでも探すよう命じた。日本の昔話『竹取物語』(かぐや姫)にも「不死の薬」が出てくる。
サイエンスとイノベーションによって、いつの日か夢の「不老不死の薬」が開発されないものか。寿命なき世界を永遠に生きられないものか。できることなら、100歳までも120歳までも生きたい。私は切実にそう願ってきたのだ。

従来、「人間の生物学的寿命は120歳が限界だ」と言われてきた。ところがほとんどの人が、80代後半か90代にさしかかるころには亡くなってしまう。生物学的寿命が120歳だとして、なぜ20年も30年も早く人間は死んでしまうのだろう。中には、生物学的寿命の半分も生きられずこの世を去っていく人もいる。
もちろん中には、DNAにエラーがあるせいで生まれつき早逝が約束されてしまっている人もいるだろう。「生老病死」を「四苦」と呼ぶとおり、生きている限りインフルエンザにかかって苦しむこともあれば、思わぬ病気に罹患してしまうこともある。
すべての病気をゼロにできなくとも、病気のリスクを未然に減らし、人為的に健康寿命を延伸させることはできるはずだ。病気の発生因子を知り、自分の体の状態を医学的・科学的に熟知する。早期発見・早期治療に加えて「予防医療」という観点を加味すれば、人間は寿命なき世界に一歩ずつ近づけるはずだ。
すべての人に、1日でも長く健康に長生きし、一度きりしかない人生を謳歌してほしい。健康管理をあと回しにし続けた結果、家族や友人、そしてあなた自身が人生を後悔しないでほしい。
そんな思いから、私は仲間と一緒に一般社団法人「予防医療普及協会」を立ち上げた(2016年9月)。これまで100名以上の医師や専門家にインタビューをお願いし、最新の予防医療の知見をうかがってきた。
本書は、2019年から2022年にかけて予防医療普及協会が企画したインタビューの内容をベースとして、全篇書き下ろした一冊だ。
医学者が読む専門書ではないため、一般向けにできるだけ易しく書きたい。かといって、サイエンスから逸脱した似非科学的な所見が混じってはならない。
そこで本書に登場していただいた23名の医師・専門家に、論文発表で言うところの「査読」(専門家の視点からのクロスチェック)をお願いした。「査読」の過程で、それぞれの項目の最新知見を加筆して盛りこんでいただいたりもした。
予防医療の分野は、今こうして原稿を書いている間も凄まじい進歩を続けている。24時間365日、世界中の研究者がラボで実験や研究を重ね、論文を量産しているのだ。
19世紀に活躍したSF作家ジュール・ヴェルヌ(『海底二万里』『八十日間世界一周』『十五少年漂流記』で有名)は「人間が想像できることは、必ず人間が実現できる」と言った。この言葉どおり、「寿命なき世界」「人間が120歳まで生きられる世界」はすぐそこまで来ていると信じたい。
私がそう確信する理由の一端は、本書にも綴られている。
「人工冬眠」の可能性だ。筑波大学・国際統合睡眠医科学研究機構の櫻井武教授は、2020年に世界で初めて冬眠状態を誘導する新しい神経回路を突き止めた。
カエルやリスやクマなど、生物の中には生まれつき冬眠の機能が組みこまれている種類がいる。体の状態を冬眠モードに切り替え、代謝を100分の1まで抑え、呼吸までも制御して食糧が乏しい冬を生き延びるのだ。
過去に山で遭難した人の中に、20日以上も飲まず食わず、発見当時は心肺停止状態から蘇生した例がある。ひょっとすると哺乳類である人間には、生命の危機を乗り切る冬眠モードのスイッチが、どこかに組みこまれているのかもしれない。

そんなお話をうかがっていたらワクワクしてきた。人工冬眠が技術的に可能になれば、冬眠したまま宇宙船に乗りこみ、100年後とか1000年後に復活することだってできるかもしれないのだ。
サイエンスと医学の知見を勉強するだけでは、大学生や10代の中高生がついてこられなくなってしまう。そこで本書には、人工冬眠のようにSF映画っぽいエンタメの要素、ノンフィクションやミステリーの要素も盛りこんで読みやすくまとめた。
「知ることは力なり」だ。サイエンスと医療技術に関する最新の知見を手に入れることによって、読者の皆さんも予防医療に努めてほしい。
本書で紹介した研究者の知見には、あらゆるビジネスの種が潜んでいる。事実、私もインタビュー中に新しい仕事をいくつも思いついた。30~40代のがっついた若手ビジネスパーソンにも、ぜひ本書を手に取ってほしい
2022年、精神科医の和田秀樹さんが書いた『80歳の壁』(幻冬舎新書)という本が53万部超えの大ベストセラーになった。「80歳の壁」を悠々と乗り越え、願わくは90歳の壁、100歳の壁も突破したい。さらなる強いバイタリティで仕事もプライベートも楽しみ尽くすために、本書を実用書として活用してほしい。
なお、私は現在月刊誌「GOETHE」(ゲーテ)で「金を使うならカラダに使え!」を連載中だ。ウェブサイトでも読める(https://goetheweb.jp/)。
本書の副読本として、こちらの連載にも注目してほしい。
すべての人に、いつまでも健康に人生を満喫してほしい。みんなのQOL(Quality of Life)を一歩ずつ向上させるために、これから私はますます奮闘していく。
300人の「百寿者」調査から見えてきたこと
自分の寿命を1カ月でも1日でも延ばし、この世でやりたい仕事、おもしろい体験を死ぬまで思いきり満喫したい。どうすれば80歳、90歳まで現役で仕事を続け、100歳になっても元気で毎日を過ごせるのか。
私は喉から手が出るほど「百寿の秘訣」を知りたい。
2014年、慶應義塾大学医学部に「百寿総合研究センター」という興味深いネーミングの研究所が設立された。慶應義塾大学医学部では、広瀬信義先生が1992年から「百寿者」(100歳以上の人)に焦点を当てた研究を始めたそうだ。その4代目センター長が、広瀬先生に師事した新井康通・慶應義塾大学看護医療学部教授だ。
内科医として高齢者を診察していた新井教授は「なぜ100歳になっても人は元気でいられるのだろう」と素朴な疑問を抱いたそうだ。もちろん歳を重ねれば体のあちこちにガタが来るし、さまざまな病気にもかかる。そのうえで治療を重ねつつ、平均寿命よりはるかに長く元気に生きる人が実際にいるのだ。
介護保険制度が導入された2000年頃、慶應義塾大学と東京都健康長寿医療センターの研究チームは、東京在住の百寿者300名の健康状態を調査した。
すると次のような結果が出たという。
「高血圧や骨粗鬆症などの病気も含めると、97%の百寿者は何らかの疾患をもっていました。ただし糖尿病が少ないという特徴があります。糖尿病のリスクは年齢とともに上昇し、60~70代のうち15~20%が糖尿病にかかると言われています。ところが300名の百寿者は6%と、糖尿病の有病率が圧倒的に少なかったのです。糖尿病は血管の病気を引き起こす要因となります。動脈硬化の有無を調べたところ、百寿者には動脈硬化が少ないこともわかりました」(新井教授)
糖尿病のリスクが低いことが、どうやら「人生100年時代」を謳歌する一つの重要な要因であることが見えてきた。
60~70代の15~20%が糖尿病にかかるにもかかわらず、なぜ300名の百寿者にはほとんど糖尿病の症状が見られないのだろう。端的に言って、肥満とメタボ体型、暴飲暴食は糖尿病に直結する。新井教授が調査した百寿者には、肥満体型の人が少なかったそうだ。百寿者の若いころの生活習慣を調査した研究では次のような声も得られている。
「中高年のころから体型の維持には気をつけてきた」
「食事は腹八分目を意識している」
つまりはやっぱり自業自得だよねと思われる読者もいるかもしれないので、一つここで補足しておくと、生活習慣に気をつけていても糖尿病を発症する人は少なからず存在する。
糖尿病には1型と2型があり、生活習慣が関係するのは2型だ。
また、2型の糖尿病でも遺伝的素因と環境要因(生活習慣)の相互作用で発症するため、生活習慣が乱れると必然的に発症する、というわけではない。
とはいえ、肥満体型になることが糖尿病のリスクを高めることは間違いない。
そして逆に言えば、生活習慣をあらためて日々の生き方を刷新すれば、60~70代の未来を変えられる。80~90代、100歳になったときの自分の未来を、今この瞬間から変えられるのだ。
健康長寿の人生を脅かす5種類の危険因子
「百寿者」人生を目指すためには、糖尿病や動脈硬化の予防とあわせて「フレイル」の予防が重要だと新井教授は強調する。
聞き慣れない言葉だと感じる読者のために、かいつまんで解説しよう。
2014年、日本老年医学会は「frailty」(虚弱)をあらわす言葉として「フレイル」を導入した。ここから健康雑誌やテレビ番組で、しきりに「フレイル」というカタカナ語が使われるようになる。
アメリカ老年医学会によると、(1)移動能力低下(2)握力低下(3)体重減少(4)疲労感の自覚(5)活動レベルの低下──のうち三つが該当すると「フレイル」(すなわち要介護状態に至る前段階)と認定されるそうだ(ジャパンナレッジ版『情報・知識 imidas』より)。
「身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態」という定義もある(一般社団法人日本老年医学会、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター『フレイル診療ガイド 2018年版』ライフ・サイエンス)。
ひとたび要介護状態になってしまうと、そこから時計の針を逆回しするのは容易ではない。(1)~(5)が複合連鎖し、「フレイル」状態に陥るのを避けるためにはどうすればいいのだろうか。(1)~(5)を予防するために重要なのは「日々の食事と運動です」と新井教授は力説する。
「体を動かさないことは病気のリスクを上昇させます。1日10分でも良いので、余分に体を動かすことが重要です。我々が研究対象としている高齢者の世代は、運動をするためにジムに行くという発想はあまりありません。だからこそ、日常生活の中で動くことを意識するのが大事なのです」(新井教授)
◇ ◇ ◇
👇続きはこちらで👇
不老不死の研究

紙書籍はこちらから
電子書籍はこちらから
幻冬舎の電子書籍が最大70%OFFになる
電本フェス2023秋は9/28(木)まで開催中!

