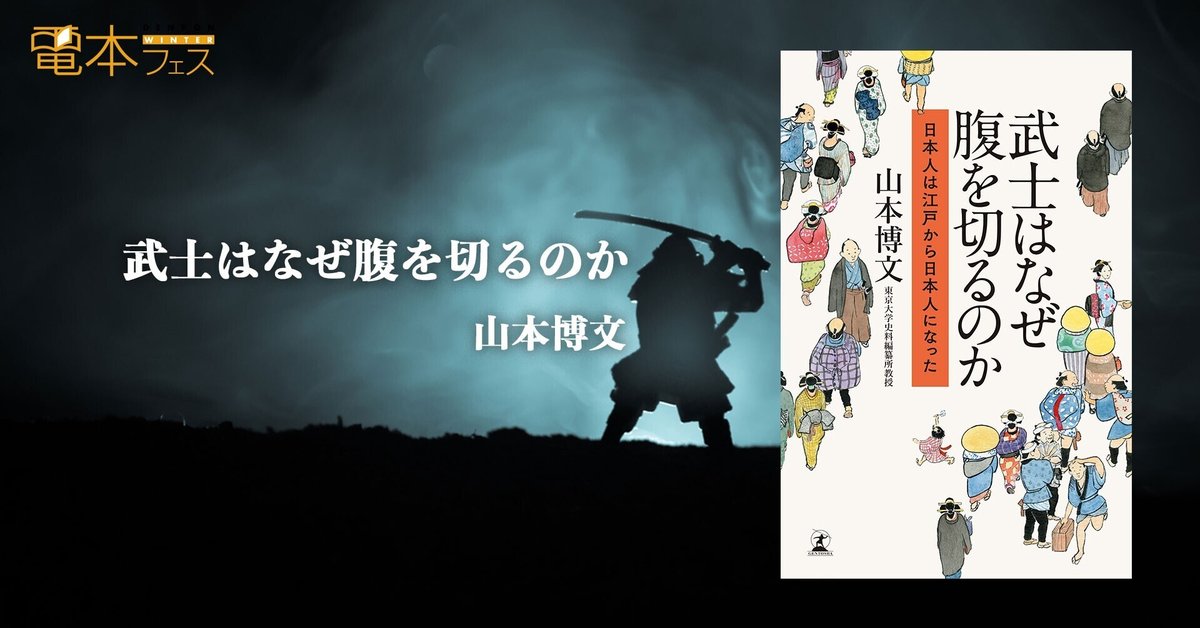
時代劇のアンチヒーロー「悪代官」は本当は存在しなかった? #5 武士はなぜ腹を切るのか
「日本人は、もっと日本人であることに自信をもってよい」。そう語るのは、歴史学者の山本博文先生。江戸時代の専門家である先生は、著書『武士はなぜ腹を切るのか』で、義理固さ、我慢強さ、勤勉さといった日本人ならではの美徳をとり上げながら、当時の武士や庶民の姿をいきいきと描いています。昔の人はカッコよかったんだなあ、と素直に思えるこちらの本。一部を抜粋してご紹介します。
* * *
多くの代官はまじめで有能だった
時代劇では「越後屋」と「代官」は悪者と相場が決まっています。賄賂をとったり、町娘を罠にはめたりして「そちもワルよのぅ」といかにもワルそうな笑いを交わし合う場面は、ステレオタイプといってもいいくらいで、誰でも脳裏に思い浮かべることができるでしょう。

水戸光圀がご隠居さまとなってから全国をお忍びで歩くという設定で人気を博した国民的時代劇「水戸黄門」では、悪代官が悪徳商人と結託して不正を働き、領民をいじめるイメージが浸透しています。
代官とはそもそも、幕府の直轄領を治め、おもに年貢の徴収や訴訟の処理などを行う地方行政官のことです。
けれど彼らは役人、いまでいう公務員なので、賄賂をとっていることや不正などが発覚すればすぐに罷免されてしまいます。つまり、そうそう悪いことはできないわけです。
現実には代官は、悪代官どころか、相当まじめで非常に有能な者が多かったともいわれています。自分が支配する地域の民を思い、いかにその地域の生活がよくなるかということを考えて行動する。幕府直轄領の年貢は各藩に比べて軽く、暮らしやすかったという話もあるくらいです。
代官は江戸時代、日本全国に四十名ほどいました。
支配する直轄領は、石高でいうと約四百万石。ひとり頭に直すと十万石で、これは中程度の大名と同じくらいの規模になります。
彼らの仕事は、年貢の徴収のほかに新田開発や治水事業、村々の人別帳(戸籍)の管理、紛争の調停、罪人の処罰など、多岐にわたっていました。
水害から民を救った田中丘隅
名代官として知られている者に、たとえば田中丘隅とその娘婿・蓑笠之助がいます。丘隅は、大岡越前守忠相によって、相模国(現・神奈川県)の代官に登用されました。丘隅と笠之助の功績は、富士山の宝永大噴火により荒廃した酒匂川流域の復興事業を行ったことで知られています。

その頃酒匂川は、宝永四年(一七〇七)の富士山噴火による降灰のために流れがせき止められ、洪水をくり返していました。洪水の被害を食い止め、最小限に抑えることは、相模国の領民による悲願だったのです。
丘隅は、治水のための堤を築く方法を自ら考案し、酒匂川沿岸の村々を水害から救いました。丘隅が築いた堤は文明堤と呼ばれ、現在も残されています。
また、武田信玄の娘・松姫が、家康の目を逃れて八王子に隠れ住んだのを最後まで庇護した代官・下嶋与政、遊女を更生させて東北開拓の農民と結ばせた寺西封元なども、時代的に弱者であった女性の味方で、悪代官のイメージとはほど遠いようです。
そのほか、岡上景能なども、下総の堀田家領地の農民に対し、二割の増税はひどすぎるから無視せよ、と書き送るなど、四角四面な役人ではありませんでした。このように、民に優しい代官もいたようです。
幕府の直轄領だったところ、たとえば駿河(現・静岡県)や陸奥(現・青森県)などにも、いまでも語り継がれている名代官がいます。
それがなぜ、ステレオタイプといわれるほどに、悪代官のイメージで定着したのでしょう。ひとつには、家康の「百姓は、殺さぬよう、生かさぬよう」に代表される、搾取される側、つまり、農民からのイメージにあるのでしょう。つまり、代官というのは、搾取階級の代表であり、急先鋒であるわけです。
実際、江戸時代の初期は、戦国時代からその土地を支配してきた土豪が代官に登用されるケースが多く、そういう土豪的な代官のなかには不正を行っていた者も少なくありませんでした。「水戸黄門」が全国をまわっていたとされていたのはこの時代ですから、そういったイメージが定着しやすかったのかもしれません。
◇ ◇ ◇
連載一覧はこちら↓
武士はなぜ腹を切るのか?

