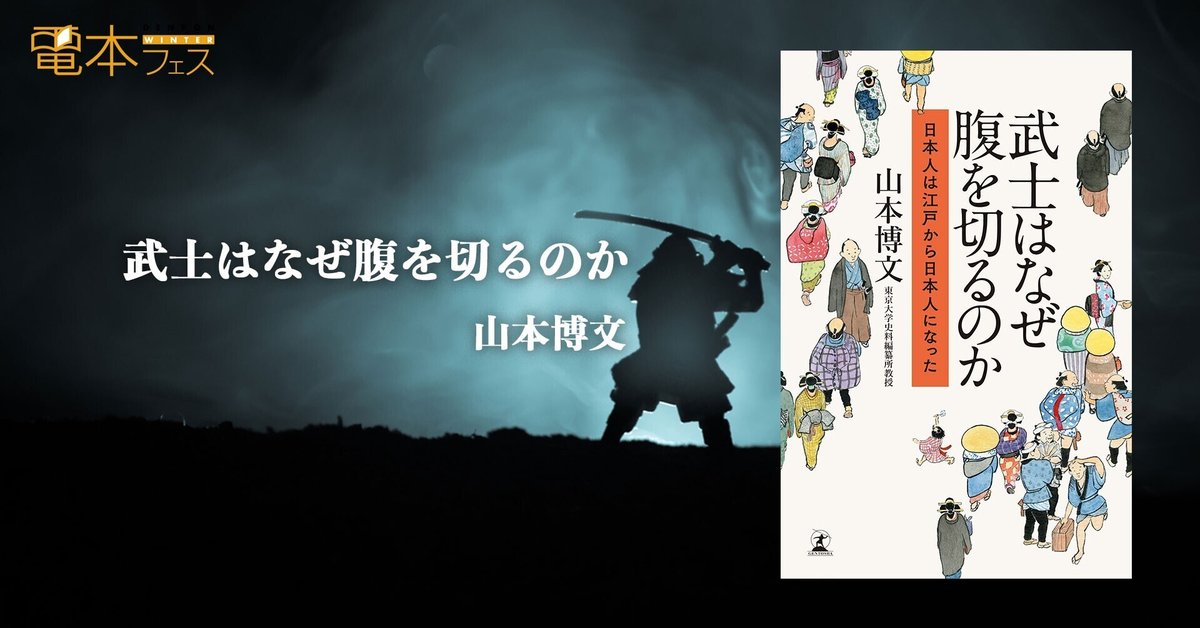
教科書では教えない!「士農工商」は身分ではなく役割だった #1 武士はなぜ腹を切るのか
「日本人は、もっと日本人であることに自信をもってよい」。そう語るのは、歴史学者の山本博文先生。江戸時代の専門家である先生は、著書『武士はなぜ腹を切るのか』で、義理固さ、我慢強さ、勤勉さといった日本人ならではの美徳をとり上げながら、当時の武士や庶民の姿をいきいきと描いています。昔の人はカッコよかったんだなあ、と素直に思えるこちらの本。一部を抜粋してご紹介します。
* * *
みんな平等、みんな対等
「日本人はたいへん名誉心が強い国民である」といったのは、日本に最初にやってきたヨーロッパ人宣教師のフランシスコ・ザビエルです。そのあとに来日した宣教師たちも、みな同じような感想を抱いています。

彼らがびっくりしたのは、日本人は、武士だけでなく身分が低いとされていた下層の農民や職人までが同じように自分の名誉を大切にしたこと。名誉心は、自尊心と言い換えてもいいかもしれません。
名誉心はもともと武士道が育んだものとされていて、武士は自分の名誉を守るためには命を棄ててもかまわないという気持ちで生きていたのですが、武士ではない人たちも、どんなにお金を積まれようとも、奴隷のように扱われることは、断固として拒みました。
というのも、江戸時代の身分制度というのは人間の上下関係のように考えられがちですが、そうではないからです。カースト制度や奴隷制度とは、そこが根本的に違います。
では江戸時代を象徴する「士農工商」という言葉は何か。それはあくまで、社会で果たす役割の違いだったのです。つまり、武士だろうが商人だろうが大工だろうが、職業や社会に対する役割が違うだけで、人間としては対等で、あくまで平等であると考えていた。お互いがそれぞれの役割を、尊重していたのです。
つまり、江戸時代というのは、決して、武士だけが威張っていた社会ではありませんでした。
自分の仕事に誇りを持っていた
くり返しますが、士農工商は、身分というよりはむしろ、社会に対する役割が決まっていたのだと考えたほうが正しい。そして、それはすべて、社会にとって必要な役割なのです。

それぞれ、社会のなかで果たす役割は違っていたとしても、その役割を誠実に果たすことで江戸っ子たちは人生の充実感を得ていたのでしょう。武士は社会の秩序維持と軍事を担い、農民は田畑を耕して食物をつくる。職人は生活に必要な道具をつくり、商人はそれらを売買して生活していたのです。
そして、役割を意識していたからこそ、日本の職人は、仕事に対する責任感から、ものすごく高いレベルで仕事をしていました。とくに、大工の技術たるや、世界的に見ても最先端です。宮大工などは、現代でも芸術の域であることは、皆さんもよくご存じでしょう。
ちなみに、士農工商制度では「最下位」に位置する商人が、江戸時代は圧倒的に裕福でした。豪遊伝説で有名な紀文(紀伊國屋文左衛門)や「現銀掛け値なし」の三井(高利)も商人です。
お金の話は別の項でもしますが、士農工商と裕福さが必ずしも正比例しないのは、江戸のおもしろいところでもあります。世界でも、こういう例はあまり多くないでしょう。
お金を稼ぐからといって偉いわけでもない。武士だといって、それだけで偉いわけでもない。武士らしい武士が尊敬されたのです。そして彼らは、“人”として、役割を果たすために江戸時代を生きたのです。
自分の役割を誠実に果たすという生き方は、世界に誇ってよい、日本の特長です。言い換えれば、それだけ日本人は、自分の人生、自分の仕事に誇りをもって生きてきたということです。
武士道だけでなく、そういう社会風潮が、名誉心の強い国民性を育んだのです。
◇ ◇ ◇
連載一覧はこちら↓
武士はなぜ腹を切るのか?

