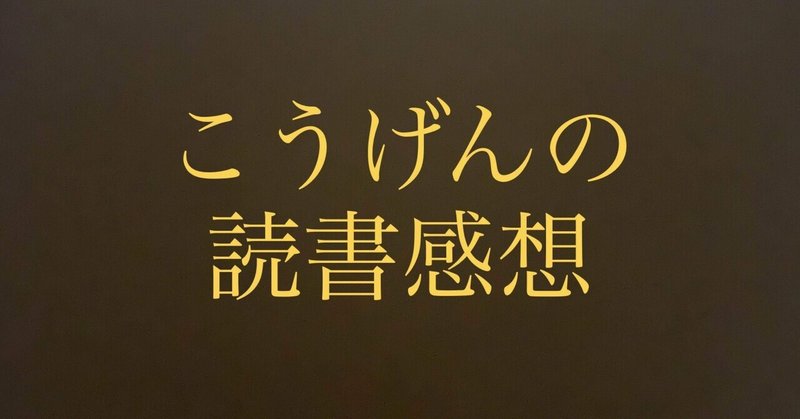
思わずためしてみたくなる行動経済学1年生
作者 :平野 敦士 カール
発売日:2022年1月
作者経歴
経営コンサルタント。上場企業を中心にアドバイザーを務めている。
親近感バイアス
地元出身だと聞くと、それだけで仲良くなれそうな気がするのが『親近感バイアス』。事実的根拠がないヒューリスティックの一つである。
ハーディング効果
人間には群集心理があり、皆と同じ行動に安心感を覚え、同じ行動をとろうとする。『赤信号、みんなで渡れば怖くない』が良く表している。
ナッジ理論で節電
アメリカと日本の実験で、自分の家庭環境と似た家庭の電力消費量、節電のアドバイスを記録したレポートを渡したところ、数%の節電効果が見られた。
損失回避性
人間は『新しいものを得られない』ことよりも、『今持っているものを失う』ことを避けたがる性質がある。
実験結果として「今年この検診を受ければ、来年も無料で検査します」よりも「今年この検査を受けないと、来年から検査できません」とした方が参加率が高かった。
オプトインとオプトアウト
同意しないことが初期設定になっているものがオプト・イン。その逆がオプト・アウト。同意することが初期設定となっているオプト・アウト形式の方が同意率は高い。
カクテルパーティー効果
「〇〇地域の方限定です」等の自分に当てはまるワードが目立つように書かれていると、気になってメルマガ等の開封率が上がる。
フレーミング効果
『50%がリピーター』『50%は二度と買いません』どちらも同じ意味だが、印象は全く異なる。ポジティブに見せたいなら、表現を変える。
極端の回避性
1000円、2000円、3000円のものがあると、7割は2000円を選ぶ。1000円、2000円の二択だと、1000円の方が多く売れる傾向にある。
おとり効果
引き立て役を置くことで、本命を魅力的に見せることができる。家電量販店の品揃えが良い例である。逆に、高すぎるものを置くのも手である。1000円のイチゴと500園のイチゴであれば、500円のイチゴばかりが売れる。
イケア効果
人間は、自分が手間をかけたものに対して高い価値を感じる。
返金制度の罠
された親切に報いなければと思う『返報性』、コスト回収したいと思う『サンクコスト効果』、そして『保有効果』が合わさった巧妙な罠である。
感想
仕事のマーケティングに活用できるかと考え、行動経済学の本をいくつか読んでいます。
本書は4コマ漫画も交え、実例も出しながら解説しているため、とても理解し易く、簡潔で効率良く学べました。
特にSNSの告知には有効活用できそうな知識が多く得られたため、後輩にも入門書籍としてオススメしました😃
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
