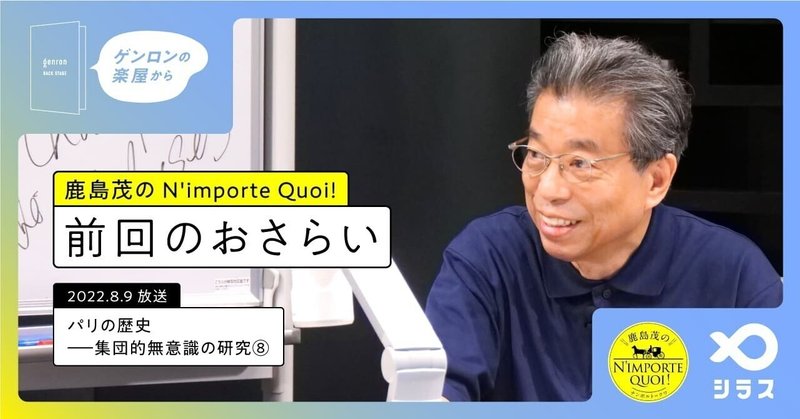
盛り場は西を目指す──鹿島茂のN'importe Quoi!「前回のおさらい」
フランス文学者・鹿島茂先生による講義チャンネル「鹿島茂のN’improte Quoi!」が好評配信中です!エマニュエル・トッドの家族人類学をテーマにしたもの、そしてパリをテーマにしたものの2本立ててお届けしています。
講義がはじまって半年以上、毎度のことながらパリに行きたい!!という気持ちが高まりすぎるこの番組。来年はラグビーワールドカップもフランスで開催されるので、なんとか休みを取って……と画策しているスタッフの野口です。
さて、7月に行われた講義では「盛り場西漸説の検討」と題して、タンプル大通り=犯罪大通りから徐々に西へと進みブールヴァール・デジアリアン(des Italian)=イタリア大通りにたどり着きました。今回の講義ではさらに西へ。20世紀の盛り場となるシャンゼリゼに向かう道のりを見ていきます。

1.パレ・ロワイヤルからイタリア大通りへ
さて、以前の講義でパサージュの原型が生まれた場所としても紹介されたパレ・ロワイヤル。1830年の7月革命でオルレアン家のルイ・フィリップによる立憲王政がはじまったところで大きな転換点を迎えます。
19世紀に入ってからも、引き続き「悪の殿堂」として名高かった……つまり盛り場として人気もあったパレ・ロワイヤルですが、王の所有する館が「悪の殿堂」はさすがにまずかろう、ということでその名の由来ともいえる「博打」と「娼婦」を追い出しにかかります。浄化されたパレ・ロワイヤルはかえって人通りがなくなり、徐々に寂れていきました。
かわりに人気が出てきたのが、そのパレ・ロワイヤルから北に向かうギャルリ・リビエンヌをぬけてグラン・ブールヴァールとぶつかって、ちょっと西に行ったあたり……つまりイタリア大通りです。1820年頃から盛り場として人気が集まりつつあったエリアですが、さらに賑わいを見せるようになりました。

ある意味でそれを示すのが複数形のブールヴァール/Les Boulvardsと、単数形のブールヴァール/le Boulvarの違い。前者はパリの内部をぐるっとつながるブールヴァール全体を指すのに対し、後者はブールヴァールの中のブールヴァールたる場所を指し示す言葉として用いられます。そこで名指されたのがdes Italians=イタリア大通りでした。
前回でも見たようなカフェ・ド・パリ、メゾン・ド・レ、カフェ・リッシュやモーパッサンの『宝石』にも登場するカフェ・アングレなどの名店・高級店が並びました。

『19世紀パリ時間旅行-失われた街を求めて‐』(鹿島茂、新潮社 P103)より
2.盛り場と住宅
さて、この盛り場に集まる女性たち……おもに娼婦だったわけですが、彼女たちはどのあたりに暮らしていたのでしょうか。ここは現代にも共通かもしれませんが、こういった仕事の基本は職住近接。イタリア大通りから少し北、ノートル・ダム・ド・ロレット教会のあるモンマルトルの丘のふもと、Nouvel Athēne=新アテネと呼ばれるあたりに多くの娼婦たちが暮らしていたといいます。
このあたりは、かつて徴税請負人たちが建てた館=folieが多くあったエリア。遊園地的な施設としてイギリスからやってきたVoxhallと対抗するTivoli(チボリ)庭園があったあたりですが、このころ分譲地としてさらに再開発が進んでいました。そしてこのあたりには娼婦だけでなく、若き芸術家や詩人たちも住んでいました。若き芸術家や詩人、というといつの世も「お金のない、貧しい人々」というイメージがありませんか?19世紀のパリでもそれは同じ。とすると、再開発の進む新築物件に住めたのはなぜ……?という疑問が湧くのですが、その理由は当時主流だったある考え方がありました。新築至上主義とも言える日本に暮らす私たちからは想像できないその理由は、ぜひ放送でお確かめください。

ともかくも、イタリア大通りのすぐ裏手あたりから盛り場に向かい、お客を捕まえて、先に挙げたような高級レストラン、そしてその個室で「仕事」をしていくわけですが、このあたりの習慣を知っていると、当時の小説などに描かれるシーンの意味がより鮮明に理解できます。例えばフロベールの『感情教育』のなかで、主人公がある女性を奮発して高級店へ食事に誘う場面があります。ところが、主人公が誘った先は個室付きのレストラン。相手がどう思ったかは……大人の皆さんはもうお察しですよね。
それ以外にもルソー以後にもたらされた感性の変化が香水の流行に見て取れたりと、歴史を学ぶことは出来事を追うだけではなく、人々の暮らしや価値観を知ることでもあるのだ、と感じるようなお話が続きます。鹿島先生ならではの歴史の面白さを実感します。
3.オペラ座建て替えをきっかけにさらに西へ
さて、このイタリア大通りに花開いた盛り場の賑わいもまた、時間とともに移り変わっていきます。転換点を迎えたきっかけの1つが1862年に始まった、オペラ座の移設。そう、現在のパリでももっとも人気のある観光名所の1つであるオペラ座は、もとからあの場所にあったわけではないのです。

ⅱが1821年~73年まで使われたオペラ座、ⅲが現在のオペラ座。当時はまだ建設予定地。
『19世紀パリ時間旅行-失われた街を求めて‐』(鹿島茂、新潮社 P106)より
現在のオペラ座ができる前、パリのオペラ座はイタリア大通りとも交差するRue Le Peletier=ル・ペルティエ通りのやや奥まったあたりにありました。その前はまた別のところにあって、1820年に移転してきたのです。その後、イタリア大通りの賑わいとともに人気を集めるのですが、オペラ座へ向かう途中のナポレオン三世が襲撃されたことを受け、現在のオペラ座のある場所への移転が決定します。当時のパリはオスマンによるパリの大改造が進行中でした。
現在のオペラ座がガルニエ宮と呼ばれるように、オペラ座を設計したのはシャルル・ガルニエ。様々な要素を織り交ぜた折衷様式を「第二帝政様式」などと称してコンペに勝利するのですが、建築工事中には1862年の着工当時の君主であったナポレオン三世の亡命と死、パリコミューンと第三共和政の発足などもあり、約13年の時間をかけ、1875年にオープンします。
これほど時間がかかった背景には、先に挙げたような歴史的な出来事はもちろん、地下を掘り進めるうちに、パリの地下に潜む石切り場=カリエールの地下水がたまった湖にぶち当たってしまった、という問題もあったそうです。「オペラ座の怪人」はこのカリエールとの関係に着想を受けた部分もあるのだとか。そういえば鹿島先生の小説作品『モンフォーコンの鼠』もカリエールが重要な舞台になっています。
何はともあれ、1875年の新オペラ座のオープン、それと合わせたオペラ大通りの開通などもあり、盛り場はイタリア大通りから西へ移っていきます。新オペラ座とイタリア大通りは決して遠くはなかったのですが、人の流れが徐々に変わっていくなかで、その中心も西へ移動していったのです。

『19世紀パリ時間旅行-失われた街を求めて‐』(鹿島茂、新潮社 P107)
他方、移設されたオペラ座に併設するように1822年に完成していたのがPassage de l'Opera=パサージュ・ド・ロペラ。盛り場の中心がすっかり移ってしまったあとの1920年代、寂れたこのパサージュにある、カフェ・セルタをたまり場にしていたのがアンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴン、フィリップ・スポー、そしてポール・エトワールらシュルレアリストたちでした。
日がなこの店をたまり場に語り合っていた彼らは、1925年、ついにこの寂れたパサージュが取り壊しになることが決まったとき、「取り壊される前に、人々はここを見に行くべき!」と新聞を通じて訴えます。その呼びかけに反応して、パサージュ・ド・ロペラに足を運んだのがヴァルター・ベンヤミン。のちに生まれる『パサージュ論』のきっかけとなる出来事でした。
さらに時を経て鹿島先生がパサージュと『パサージュ論』に出会い、そしていまこの講義が行われているのかもしれません……!
4.盛り場はさらに西に、ようやくシャンゼリゼへ。
さて、話を新しくできたオペラ座に戻しましょう。このオペラ座のオープンに合わせて、盛り場の広がりは、そのままグラン・ブールヴァールを西へマドレーヌ広場のほうへ進む方向と、オペラ通りの脇からヴァンドーム広場のほうへ進む方向と2つに分かれます。

1820年代、マドレーヌ広場の近くにAux Trois-Quartiers=オ・トロワ・カルチェというデパートが開店します。以後も人気のあったこのデパートは1930年代に新館が竣工するのですが、そこはアールデコ様式のモダンな建物だったといいます。プルーストの『失われた時を求めて』にも登場します。ちなみに19世紀末に開店したギャルリ・ラファイエットやプランタンといったデパートはアール・ヌーヴォー様式。美しいドームの丸天井などが見ることができます。デパートには当時の建築様式の流行も現れているんですね。
しかし、ひと頃に流行した建築様式も少し時代がくだると「ダサい!」とみなされて取り壊されがちなもの。講義のなかではもはや数カ所を残すのみとなったアールヌーヴォー様式のメトロの入口や、オルセー美術館に訪れた危機、さらに中央市場のレ・アールと日本の「港が見える丘公園」の不思議な関係についてもご紹介いただきます。視聴者の方から、コメント欄に参考になるURLも挙げてもらっているので、ぜひ合わせてご覧ください。
もう一方の方角・ヴァンドーム広場のほうは、19世紀末から第一次世界大戦を経て1930年代の大恐慌を迎えるあたりまで、おもに英米圏の人たちの人気を博します。特に通りを抜けてチュルイリー公園に至るところでクロスしているリヴォリ通りにかけて、英米圏の人たち向けのホテルが立ち並び、それに合わせたお店も多数オープンします。例えばヘミングウェイが滞在したRitz Paris=リッツホテルや、現在も営業中の Hotel George V=ジョルジュサンクホテル(ジョージ5世ホテル)などなど。鹿島さんの学生時代、ご友人が日本人観光客を連れて案内した高級レストランでの「いかにもパリっぽい!」と苦笑いしたくなってしまう振る舞いのお話も必聴です!

さて、西に進んできた盛り場はまだシャンゼリゼにはたどり着いていません。本格的ににぎわうのは第二次大戦後になります。
1958年に製作されたヌーヴェルヴァーグ映画の「パリはわれらのもの」(監督 ジャック・リヴェット)などを見ると、まだまだ閑散とした雰囲気のシャンゼリゼ通りが映っているそうです。先日日本でもニュースになったパリのグランキャバレー・Lido=リドがオープンしたのも1946年でした。
ということで、シャンゼリゼの話を伺う予定でしたが、ようやくシャンゼリゼにたどり着いたところでこの日の講義はおしまい。
次回9月13日の放送では、ここで語りつくせなかったシャンゼリゼのお話を少し伺って、パリを語るうえで欠かせないという「モンマルトル」を見ていく予定です。どうぞお楽しみに!
■次回放送予定
日時:2022年9月13日 19時~
モンマルトルとパリ──パリの歴史・集団的無意識の研究⑨
https://shirasu.io/t/genron/c/kashima/p/20220913

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
