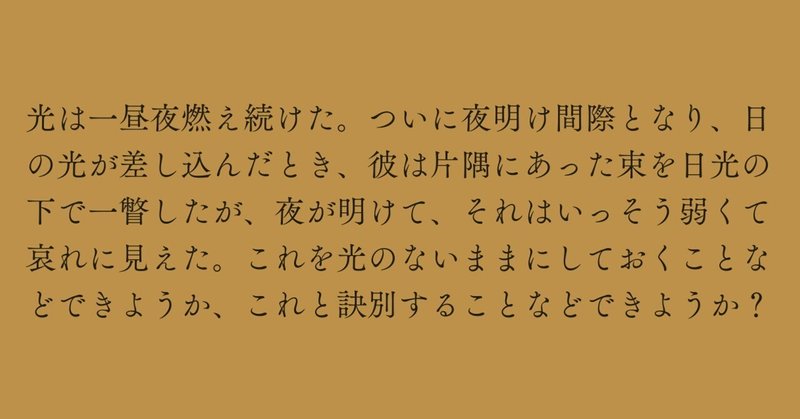
ドヴィド・ベルゲルソン/デル・ニステル『二匹のけだもの/なけなしの財産 他五篇』訳者解説(text by 田中壮泰 and 赤尾光春)
2024年5月1日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第39回配本として、ドヴィド・ベルゲルソン/デル・ニステル『二匹のけだもの/なけなしの財産 他五篇』を刊行いたします。ドヴィド・ベルゲルソン(Dovid Bergelson 1884–1952)、デル・ニステル(Der Nister 1885–1950)は二人とも旧ロシア帝国領ウクライナ出身のイディッシュ文学の作家です。
〔イディッシュとは:中欧、東欧系のユダヤ人が用いてきた言語。イディッシュYiddishは「ユダヤ語」の意。筆記の際にはヘブライ文字で表記する。居住地の言語が訛って生まれたユダヤ諸語のうちで、もっとも重要な位置を占める。10世紀ないし11世紀の上部、中部ドイツ諸方言を基礎とするが、それにヘブライ語、アラム語などの語彙が流入し、さらに14世紀中葉以降はスラブ圏の言語(とくにポーランド語)の強い影響を受けて、独自の発展を遂げた。今日ではドイツ語の近接語とみなされている。使用人口は、一時、1000万以上にも上ったが、現在では激減した。しかしなおイスラエル、ロシア、南北アメリカを中心に、世界各地のユダヤ共同体で用いられている(『日本大百科全書(ニッポニカ)』より)。〕
東欧ユダヤ文化の「生き証人」としてポグロム(虐殺)と亡命の記憶を活写した、ドヴィド・ベルゲルソン。「隠遁者」の筆名でスターリニズムのテロルを予感させる幻想的な作品を発表した、デル・ニステル。スターリン時代に粛清されたイディッシュ文学の代表作家二人の7篇の傑作短編集です(うち6篇は本邦初訳となります)。
〔ポグロム:集団的で計画的な迫害・虐殺。特に19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ロシアを中心に行われたユダヤ人の虐殺をいう(『デジタル大辞泉』より)〕。
以下に公開するのは、ベルゲルソンの翻訳者・田中壮泰さんによる解説の一節、つづけて、デル・ニステルの翻訳者・赤尾光春さんによる解説の一節です。


イディッシュ語の成立過程
ローマ帝国時代にパレスチナの地(当時はローマ帝国のユダヤ属州)を追われ、ヨーロッパを中心に世界各地に離散したユダヤ人たちは、行く先々で土地の口語を取り入れていった。そして、それらの言語に、彼らがもともと使っていたヘブライ語やアラム語の要素が混ざり合うことで、ユダヤ・ギリシャ語やユダヤ・フランス語といった様々な混成言語が生まれた。そのほとんどは時が経つにつれて土地の言語に吸収され、消滅することになるが、現在まで生き延びたものもあり、その一つがイディッシュ語である。
イディッシュ語は、遡れば中世にライン川流域に定住したユダヤ人の間で話されるようになったユダヤ・ドイツ語(中世のドイツ語にヘブライ語やアラム語の要素が混ざり合った言語で、西イディッシュ語ともいう)が元になっている。ユダヤ・ドイツ語それ自体は、18世紀頃にはドイツ国内で消滅するが、中世後期にドイツから東欧に移住したユダヤ人たちの間で生き残り、そこにスラヴ諸語が混ざり合うことで現在のイディッシュ語(これをユダヤ・ドイツ語と区別して東イディッシュ語ともいう)の形ができあがった。
カトリック教会の典礼言語であるラテン語がヨーロッパのリンガ・フランカとしての地位を失い、俗語を用いた文学が登場するルネッサンス期に、ユダヤ人たちの社会においても、典礼言語であるヘブライ語に代わるものとして、イディッシュ語で書かれた印刷物の出版が始まっている。しかし、その大部分が聖書の翻訳か翻案の類で、ヘブライ文字は読めてもヘブライ語のテクストは読めない者(その多くが女性と子供であった)のために書かれた補助的なテクストであった。イディッシュ語は長らくヘブライ語の下位に置かれてきたのである。
イディッシュ語がヘブライ語と同等の地位を獲得するようになるのは、ヨーロッパ各地でナショナリズムの意識が高まったナポレオン戦争以後のことである。この時期に近代イディッシュ文学の三羽ガラスとも称される、メンデレ・モイヘル・スフォリム(1836‐1917)、ショレム・アレイヘム(1859‐1916)、イツホク・レイブシュ・ペレツ〔1852-1915〕らが登場し、近代イディッシュ文学の基礎が作られた。そして、彼らの次の世代を担う作家として登場したのが、ベルゲルソンとデル・ニステルである。
イディッシュ語作家としてのデビュー
ドヴィド・ベルゲルソンは1884年、ロシア帝国領ウクライナの都市ウマニからほど近いシュテットル(ユダヤ人集落)のオフリモーヴォ(現在のウクライナのサルヌィ)に生まれた。父ラファエルは木材と穀物の取引で財をなした実業家で、ロシア語はできなかったがイディッシュ語の他に取引先で使われるウクライナ語とポーランド語を話した。母ドレイザはショメル(1849?‐1905)やヤンケヴ・ディネゾン(1856?‐1919)といった当時ロシアで流行したイディッシュ語による大衆小説の熱心な読者であった。ドヴィドも家ではイディッシュ語を話したが、ユダヤ教の初等学校と家庭教師を通じてヘブライ語とロシア語に習熟し、それが後に作家となるベルゲルソンの基礎を築いた。とくにロシア語のリテラシーは、ロシア文学だけでなく、ロシア語に翻訳された世界各地の文学との出会いを彼にもたらした点で重要である。また、ヘブライ語に関しては、当時ロシアのユダヤ社会で広く読まれたアハド・ハアム(1856?‐1927)やミハ・ヨセフ・ベルディチェフスキ(1865‐1921)ら新時代のヘブライ語文学を貪るように読み、シオニズムに傾倒していた時期もあったという。
若くして両親を亡くしたベルゲルソンは(父は1893年、母は1898年に他界している)、1900年頃に父と同じ実業家であった兄の一人を頼ってキエフに移住している。当時のキエフはロシア帝国が定めた「ユダヤ人居住地域」の外にあったが、学生や熟練工など、特例が認められたユダヤ人だけでなく、法の網をかいくぐって数多くのユダヤ人が集まるという、ロシアでも例外的な都市の一つであった。たとえば、キエフの聖ウラディーミル大学(現在のキーウ大学)にはロシアの大学の中で最も多くのユダヤ人学生が学んでいたという(1911年には888人のユダヤ人学生が在籍し、全学生の17パーセントを占めた)。であればこそ、まもなくキエフはワルシャワやヴィルナ(現ヴィルニュス)と並んで、ロシアにおけるイディッシュ文学の拠点の一つとして、存在感を示すことになるのである。
ベルゲルソンは両親の死後に莫大な遺産が舞い込んできたことで、大学には進学せず、文学活動に専念するが、そのタイミングで執筆言語をイディッシュ語に切り替えている。1909年に刊行された彼の最初の小説『鉄道駅 Arum Vokzal』は、ヘブライ語からイディッシュ語に書き直したものであった。書籍としては2冊目となる長編『すべての終わり Nokh Alemen』(1913)がベルゲルソンの出世作となった。前作と同様、近代化の波に取り残されたシュテットルの日常を冷めた視点で描いた本作は、ロシアやフランスの自然主義文学を取り入れた写実的な文体が批評家から高く評価され、刊行と同年の一九一三年にヘブライ語とロシア語に翻訳され、幅広い読者を獲得している。こうしてベルゲルソンは華々しいデビューを飾り、やがてキエフのイディッシュ文学界をリードしていくことになる。
ベルゲルソンが寄寓していたキエフの兄の家には、デル・ニステルをはじめレイブ・クヴィトコ(1890‐1952)やドヴィド・ホフシュテイン(1889‐1952)など、後にソ連のイディッシュ文学を代表する若い作家たちが集うようになり、詩や小説の朗読会がそこで開かれた。すでに紹介したデル・ニステルの手紙は、この時代を懐古したものであった。
アレイヘムとベルゲルソン
ところで、ベルゲルソンがイディッシュ語で小説を書きはじめた時、同じウクライナ出身のショレム・アレイヘムの文体が手本になったことが伝えられている[★03]。ベルゲルソンにとってヘブライ語を多用したメンデレのイディッシュ語は古臭く感じられ、ポーランド語訛りのペレツのイディッシュ語はウクライナの現実を描くのに適さなかった。実際、アレイヘムの代表作で、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作としても知られる連作小説『牛乳屋テヴィエ』(1894‐1914)は、ヴァナキュラーなイディッシュ語ならではの表現の可能性を追究した作品としても読むことができる。たとえば、主人公テヴィエの次の語りを見ると、ウクライナの土地の言葉(ロシア語やウクライナ語)が自然に織り込まれているのが分かるだろう。
あたしたちはずっと異教徒(ゴイ)、つまりはエサウ[★04]に囲まれて暮らしてきました。みんな村の名士たちとも気心の知れあった関係にあったのです。親友関係というか、親分子分関係というか、それこそ「テヴェリのとっつぁん(パチューシカ)」と言えば、一目置かれる存在だったんです! どんなですって? たとえば、助言が必要になればテヴェルの意見に従え(ヤク・テヴェル・スカージェ)、熱が出て薬が欲しくなるとテヴェルんとこへ行こう(ド・テヴェリャ)、借金が必要になれば、やっぱりテヴィエのところだ、ってことでして。
西成彦による『牛乳屋テヴィエ』(岩波文庫、2012)の翻訳は、ルビを振ることでテヴィエの語りの「雑種性」を読者に伝えようと工夫されているが、本書における筆者の翻訳もこの方法を採用している。イディッシュ語という言語には、土地から土地を移動しながら、それぞれの土地の言葉で隣人たちとの関係を築いてきたユダヤ人たちの長い歴史が折り重なっており、そのことを、翻訳で強調しておくべきだと考えたからである。
本書に収録した「改宗者 Di Meshumedes」(1923)が描いているのも、そのようなユダヤ人たちと隣人たちとの「共生」の風景である。タイトルの「改宗者」とは、ここでは異教徒と駆け落ちをしたユダヤ人の女を指している。女は故郷のシュテットルを去った後、そこからほど近いキリスト教徒の村で調停判事の夫と息子の三人で暮らしている。そんなある日、女の故郷からユダヤ人数名が、村の農民同士の喧嘩をめぐる裁判の証人として調停判事の家に呼び出されることになる。裁判が始まるまでの間、廊下で待機していたユダヤ人たちは、そこで、「改宗者」の幼い息子と遭遇する。そして、思わず「おいで(クム・アヘル)、あいの子ちゃん(マムゼル)」とイディッシュ語で声をかけ、子供を驚かせてしまうのである。これはそんな些細な出来事を描いた小品に過ぎない。しかし、言語も文化も異なる世界を生きたユダヤ人同士が、遠い「親戚」のように緩やかに結びついていた在りし日のウクライナが、そこから活き活きと浮かび上がってこないだろうか。
『牛乳屋テヴィエ』にも、キリスト教徒の若者と駆け落ちをするテヴィエの三女ハヴァが登場するが、アレイヘムとベルゲルソンが生まれ育ったウクライナでは何世紀にもわたってユダヤ人と異教徒が隣り合わせに暮らしてきたのであり、両者の間には恋愛もあれば結婚もあったし、血も混ざれば言語も文化も混ざり合った。
ところが、ここで急いで付け加えておかねばならないのは、アレイヘムが生きたのは、そのような隣人関係が崩壊していく過渡期でもあったということである。1881年、農奴制を廃止するなど改革路線を推し進めたことで知られるアレクサンドル二世(在位1855‐81)が革命派のテロリストに暗殺されたのを機に、反ユダヤ主義の空気が高まり、ロシア帝国領、とりわけウクライナの各地でポグロムが発生している。メンデレもアレイヘムも、まさにこの前後に作家として出発しており、シュテットルの文化が崩壊の危機に直面していた最中にシュテットルを描いた。この時期、ロシアと東欧から大量のユダヤ人難民が吐き出されたが、結果的にはそのおかげで、ロシアと東欧を戦争と革命、大規模なポグロム、そしてホロコーストが襲った後も、ロシアと東欧の外で、イディッシュ文学は生きながらえることになったのである[★05]。
イディッシュ語で書き始めた時、アレイヘムの文体を参考にしたというベルゲルソンは、その後にロシアで起こった様々なカタストロフを経験した結果、牧歌的な世界としてシュテットルを描くことのできたアレイヘムとは違う、独自のスタイルを模索することになる。その時、イディッシュ語は、在りし日のシュテットルの記憶ばかりでなく、その後のシュテットルが経験した破壊の記憶とも結びついた言語として立ち現れてくるだろう。『改宗者』は、まだアレイヘムの香りを漂わせていた過渡期におけるベルゲルソンの作品の一つであった。
[★03]Joseph Sherman, “David Bergelson (1884–1952): A Biography,” in J. Sherman and G. Estraikh (eds.), David Bergelson: From Modernism to Social Realism. London and New York: Routledge, 2007, p. 9. ベルゲルソンの経歴については、とくに断りがない限り、この文献所収の伝記ならびに各論を参照している。
[★04]旧約聖書に登場するイサクの息子で双子の兄。ユダヤの伝承によれば、エサウの子孫はエドム人となったが、家督を継いだ弟のヤコブは現代のユダヤ人の祖となった。
[★05]西成彦編訳『世界イディッシュ短篇選』(岩波文庫、2018)は、そうしてできた世界的なイディッシュ文学の広がりを一冊に収めた本である。そこにはオデッサ、キエフ、ワルシャワ、ニューヨーク、モスクワ、リオデジャネイロ、ヨハネスブルグ、パリなど様々な都市が取り上げられ、その一つに、ベルリンを代表するイディッシュ文学として、あとで紹介するベルゲルソンの短編「逃亡者」が収められている。
* * *
「ユダヤの都」ベルディーチェフ
デル・ニステルことピンヘス・カハノヴィチ(Pinkhes Kahanovitch)は、1884年11月1日、ウクライナの首都キエフ(現キーウ)から南西へ百キロほどに位置する、ベルディーチェフ(現ベルディーチウ)に生まれた。
バルザックが1850年に挙式を挙げ、その7年後にジョゼフ・コンラッドが誕生した地として、世界文学史にささやかな痕跡を留めているベルディーチェフは、ロシア帝国下に設定された「ユダヤ人定住地域」を代表する都市の一つとして、東欧ユダヤ人の集合的記憶に刻まれている。
18世紀末にロシア帝国に併合されるまで、ベルディーチェフは、ポーランド貴族の支配下で形成された東欧一帯のありふれたユダヤ人街(シュテットル)の一つに過ぎなかったが、19世紀を通じて、ロシア帝国南西部における穀物貿易や金融業の基幹都市として発展するのと軌を一にして、この町のユダヤ人人口も増加の一途を辿った。1861年の人口調査によれば、ベルディーチェフのユダヤ人人口は、約4万7千人と町の住民全体の約8割を占め、ロシア帝国内でワルシャワに次いで最も多くのユダヤ人の居住する都市に成長した。
ユダヤ教敬虔派ハシディズムの導師(レベ)たちの中でも、最も民衆に愛されたラビ・レヴィ・イツハクが、ユダヤ人に対する過酷な天の裁きに不服を申し立てて神に論争を挑んだのは、ベルディーチェフであった。爾来、この町は敬虔なる者(ハシッド)たちの間で、「ヴォルィニャのエルサレム」として尊ばれてきた。ベルディーチェフはまた、かねてよりユダヤの笑話に豊富な題材を供給してきた町であり、「イディッシュ文学の祖父」こと書籍商のメンデレ(メンデレ・モイヘル・スフォリム)は、この町をモデルにした「愚か村(グルプスク)」を創作し、株の売買や当てのない商取引にあくせくする、その日暮らしの「空気人間(ルフト・メンチュ)」の悲喜劇を描いた。こうしてベルディーチェフは、良くも悪くも東欧ユダヤ文化の真髄を伝えるシュテットルの典型として、「ユダヤの都」という異名をもつに至る。
生い立ち
同じくベルディーチェフ生まれのロシア語作家ワシーリー・グロスマンは、「私たちはショレム・アレイヘムによって描かれた貧しいシュテットルのユダヤ人のようではなかった」と述べているが、デル・ニステルは、正真正銘の「シュテットルのユダヤ人」として、イディッシュ語が日常的に飛び交い、ユダヤ教の伝統的規範がまだ息づいていた家庭で生まれ育った。
作家への質問状に対する回答に基づいて編まれた『イディッシュ文学百科事典』(1926年刊)によると、デル・ニステルの両親の一方は、「学識があり、カバラに通暁し、極めて敬虔な」家系で、他方は、「素朴な村落のユダヤ人で、働き者」の家系であった。この記述からは、デル・ニステルが、ユダヤの神秘主義と民衆文化という、二つの伝統の薫陶を受け継いだ作家として自らを位置づけることを好んでいたことが窺える。
燻製魚を商う父親のメナヘム・メンドルは、ハシディズムのコルシェヴ派の信徒であり、ユダヤ教の伝統的な教育を受けたピンヘスは、「ハシディズムの極めて強い影響を受けた」一方、母親のレアは、商売の傍ら、子供たちに世俗的な科目の習得も促したという。
ピンヘスは四人兄弟の末っ子で、二人の兄と一人の姉がいた。哲学とカバラに通暁していた長男のアルンは、ハシディズムの開祖バアル・シェム・トヴの曾孫でブレスラフ派を創始したラビ・ナフマンの教えに心酔し、その信徒となった[★02]。長女のハネは著名な医学博士となり、次男のモトルはフランスに移住し、著名な画家・彫刻家にして芸術蒐集家となった(パリのオルセー美術館には、「カガノヴィチ・コレクション」の一室がある)。ハネとモトルとともに、後にイディッシュ作家となるピンヘスが辿った道には開明的な母親の影響も読み取れるが、デル・ニステルの世界観に最も深い影響を与えたのが兄アルンの存在であったことは、衆目の一致するところである。
作家デル・ニステルの誕生
二十歳前になったピンヘスは、1905年頃、ベルディーチェフの北に30キロほど離れたジトーミルに移住し、ヘブライ語の家庭教師で糊口を凌いだ。12年には地元のユダヤ人学校の教師ロフル・ジルベルファルブと結婚し、翌年には娘のホドルが誕生。二人は、ゴルタ(現ペルヴォマイスク)のユダヤ人女学校でも教師を務めたという。
青年期のピンヘスについて知られていることはそれだけだが、ジトーミルへの移住と偽名の使用は、ロシア帝国の徴兵を逃れるためだったと言われている。この時に使用した偽名が後にペンネームともなる「隠遁者(デル・ニステル)」であり、ここにカバラ的な含意を読み取る者も少なくない。
ユダヤ教神秘主義カバラの伝統によれば、神の生きた教えであるトーラーには明示された(nigle)意味と隠された(nister)意味があり、カバリストの使命は、後者を解読してそのメッセージを実践に移すこととされた。また、原初の破壊(フルブム)によって天上界から追放された臨在の神(シェヒナー)は地上を流離(さすら)っていると信じられ、カバリストの間では、俗世を去ってシェヒナーとともに自発的に追放(ガルート)の身を引き受けることで、ユダヤ民族と世界の贖い(ゲウラー)を促すことが理想とされた。こうした神話と並んで、ユダヤの民間伝承では、この世界は素性の知られていない36人の隠れ義人(ラメド・ヴォヴニク)に支えられていると信じられた。
デル・ニステルは、ジトーミルに移住する前からヘブライ語の詩を書き、シオニズム運動の指導者の一人であったナフム・ソコロフが編集するヘブライ語雑誌「警笛(ハッエフィラー)」にも寄稿しているが、掲載には至らなかった。
その後、多くの先輩作家たちと同様、彼は執筆言語をヘブライ語からイディッシュ語に切り替えた。ユダヤ人自身の言語への拘りは、次のエピソードからも窺える。イディッシュ語をユダヤ人の民族語の一つとして公認したチェルノヴィッツ会議が開催された1908年、デル・ニステルは、元ナロードニキの作家S・アン゠スキから、ロシア語誌「ユダヤ世界 Evreisky Mir」への寄稿依頼を受けた。彼は、生計のためにこの依頼を承諾したものの、「イディッシュ語で生まれ育ったものをロシア語で最初に出す」のは「我が子に洗礼を受けさせる」ようなものだと友人の批評家シュムエル・ニゲルにこぼしている。
当時、イディッシュ文学はすでに、メンデレ・モイヘル・スフォリム、ショレム・アレイヘム、イツホク・レイブシュ・ペレツのような古典作家を輩出しており、多少とも洗練された読者、批評家、出版社は、新世代の作家による新たな作品の到来を待ち望んでいた。世紀転換期に誕生したイディッシュ作家たちは、とりわけペレツが開拓したモダニズム風の作品を手本に、イディッシュ文学刷新のための様々な実験的試みを始めていた。1907年にヴィルナ(現ヴィルニュス)で刊行されたデル・ニステル初の作品集『思考とモチーフ——散文詩 Gedankn un Motivn: Lider in Proze』は、そうした実験的作品の一つである。
「最後の人間 Der Letster Mentsh」と「ミリアム Miriam」という二つのテクストから成るこの書では、造語を散りばめ、様式化された文体を通じて、原初と終末、誕生と死といった形而上学的な主題が追究されている。イエス・キリストの母親の主題を扱った「ミリアム」は、イディッシュ文学でキリスト教の主題を扱った最初の実質的な試みとも言われている。
キエフ・サークルと「文化同盟」
1905年のロシア第一次革命から第一次世界大戦までの帝政末期には、ユダヤ文化ルネサンスともいうべき状況が生まれ、イディッシュ文学は、ワルシャワとヴィルナを中心に花開いた。
ジトーミルに戻って創作活動を再開したデル・ニステルは、ドヴィド・ベルゲルソン、ペレツ・マルキシュ、レイブ・クヴィトコ、ドヴィド・ホフシュテインなど、後にソ連イディッシュ文学の花形となる詩人や作家が活躍していた、キエフを拠点とする文学サークルの中で一目置かれる存在になる。キエフに集った詩人、作家、批評家たちは、彼らが商業主義的とみなしたワルシャワを中心とするイディッシュ文学に異議を申し立て、イディッシュ文学を世界文学の水準まで高める使命を自任した。
キエフ・サークルに特有のこうしたエリート志向は、一九一八年にキエフで結成された「文化同盟 Kultur-Lige」に受け継がれ、機関誌「己/所有 Eygns」にその捌け口を見出した。後年、イディッシュ作家のイスロエル・ヨシュア・ジンゲル(アイザック・バシェヴィス・シンガーの兄)は、キエフ・サークルの雰囲気を以下のように伝えている。
まるで田舎の女学生たちが自らの正しさを確信しているかのように、彼らは全身全霊で信じていた。文学は神聖なり、至聖所なり、と。「キエフ人」こそ神の務めを果たす唯一の大祭司なり、と。キエフこそエルサレムなり、と。〔…〕芸術的価値のある物語は、ドヴィド・ベルゲルソンによるものだけだった。残りの作品は「神秘的」で、書字狂的なほとばしりに過ぎず、「己/所有」の理論家たちは、お馴染みの詩による散文ないし散文詩を、イディッシュ文学のみならず、広く、世界文学における究極の言葉とみなしていた。名誉ある地位を占めていたのは、魑魅魍魎たる悪霊や悪鬼についてのけばけばしい物語作家、デル・ニステルだった。サークルの「理論家」たるドブルーシンは、ある会合の席で公然と言い放った。全世界の作家たちにデル・ニステルの作品を読む機会が与えられたら、筆を折ることだろう、と。
(「アメリカからの手紙」『前進(フォルヴェルツ)』1942年)
初期作品の特徴と評価
キエフ・サークルの批評家の一人であったナフマン・マイゼルによると、文化同盟の作家たちは、同時代のイディッシュ文学の動向からは比較的独立した文化的土壌の中で世界観を形成し、彼らに霊感を与えたのは、既存のイディッシュ文学以上に、ドストエフスキー、チェーホフ、ゴーリキー、L・アンドレーエフ等のロシ文学や、M・Y・ベルディチェフスキー、Y・H・ブレンネル、U・グネッシン等のヘブライ文学だったという。
メンデレやショレム・アレイヘムが確立したイディッシュ語の口語表現を拒絶したデル・ニステルのスタイルも、既存のイディッシュ文学からの継承性よりも、そこから断絶した印象の方が強い。デル・ニステルの作品世界に影響を与えたと言われるのは、カバラやハシディズム、とくにブレスラフのラビ・ナフマンの物語のようなユダヤ的源泉に加えて、ホメロスの『オデュッセイア』等の叙事詩、スカンジナヴィア神話、19世紀ドイツのロマン主義文学、スラヴの伝説とともにA・ベールイに代表される同時代のロシアの象徴主義文学、ヨーロッパの創作童話まで多岐にわたる。
謎めいたメタファーを多用し、言語の音楽的側面への拘りが顕著な初期の作品群は、精神的な探求、彷徨える主人公、原初的な景観といった主題とモチーフをもち、夢と現が交差する。その大半は抽象的な時空間で展開し、非ユダヤ的なモチーフが頻出するが、同時に、世代間の継承性がユダヤ人の生存にとって死活問題であることを強く意識していたことも窺える。初期の作品群を分析したD・ベフテルによると、デル・ニステルは、同時代の霊的指導者がこの継続性を維持する上で鍵を握るというハシディズムの思想をモダニズム風にアレンジし、「指導者がその使命を放棄したり、その到来が早すぎたり遅すぎたりすることで、世代は見捨てられ、その目的を達成することなく消滅する」という物語の基本構造を確立したという。
デル・ニステルは、「山から降りて」「読者に近づく」ことを潔しとしない高踏派的態度を貫いたが、その作品は批評家や同時代の作家から酷評されることも少なくなかった。たとえば、ヴィルナのイディッシュ文学界を牽引していた批評家のニゲルは、1912年にキエフの批評家マイゼルやベルゲルソンの助力で刊行された詩集『歌と祈り Gezang un Gebet』について、「本書の10分の9は、棘だらけの茨の藪よりも這って進むのが難しい」と評し、こう嘆いた。
デル・ニステルの新しい、そしてまたしても荒れ果てた本を、通常の文学を判断する基準で判断するならば、最初のページを読んだ後に怒って投げ出してしまうだろう。お手上げだ。いったい我々に何を求めているのだ、この狂った隠遁者(ニステル)は!
帝政末期のユダヤ文化ルネサンスを代表する作家の一人であったアン゠スキはまた、デル・ニステルを「本当の才能」をもった「将来有望な若手作家」だと認めつつも、「ポーランド風に Poylish」(1908)におけるエロティシズムへ傾倒に不快感を示し、「ミリアム」におけるキリスト教的主題の導入をユダヤ教への冒瀆だと批判した。
[★02]デル・ニステルの作品世界に決定的な影響を与えたと思われる、ブレスラフのラビ・ナフマンとブレスラフ派ハシディズムについては、拙論「ウマン巡礼の歴史――ウクライナにおけるユダヤ人の聖地とその変遷」(「スラヴ研究」50号)を参照。
【目次】
ドヴィド・ベルゲルソン
改宗者
二匹のけだもの
盲目
生き証人
デル・ニステル
酔いどれ
塀のそばで(レヴュー)
なけなしの財産
ドヴィド・ベルゲルソン[1884–1952]/デル・ニステル[1885-1950]年譜
解説 声の固有性゠翻訳不可能性──ドヴィド・ベルゲルソンの生涯と作品(田中壮泰)
解説 イディッシュ文学に殉じた隠遁者──デル・ニステルの生涯と作品(赤尾光春)
【訳者略歴】
田中壮泰(たなか・もりやす)
1980年、大阪生まれ。立命館大学先端総合学術研究科修了(学術博士)。龍谷大学、東海大学非常勤講師。専門はポーランド文学、イディッシュ文学、比較文学。論文に「イディッシュ語で書かれたウクライナ文学――ドヴィド・ベルゲルソンとポグロム以後の経験」(「スラヴ学論集」二五号)、共訳にキャロル・ギリガン『抵抗への参加――フェミニストのケアの倫理』(晃洋書房)、ヤヌシュ・コルチャク『ゲットー日記』(みすず書房)など。
赤尾光春(あかお・みつはる)
1972年、横浜生まれ。総合研究大学院大学博士後期課程修了(学術博士)。国立民族学博物館特任助教。専門はユダヤ文化研究、ウクライナ・ロシア地域研究。共編著に『ユダヤ人と自治―中東欧・ロシアにおけるディアスポラ共同体の興亡』(岩波書店)、『シオニズムの解剖――現代ユダヤ世界におけるディアスポラとイスラエルの相克』(人文書院)、共訳に『ディブック/ブルグント公女イヴォナ』(未知谷)、『トレブリンカの地獄――ワシーリー・グロスマン前期作品集』(みすず書房)など。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ドヴィド・ベルゲルソン/デル・ニステル『二匹のけだもの/なけなしの財産 他五篇』をご覧ください。
