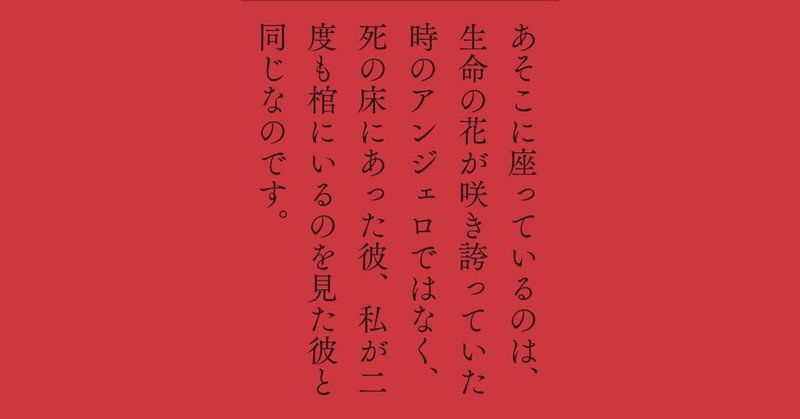
ラウパッハ、シュピンドラー 他『ドイツ・ヴァンパイア怪縁奇談集』訳者解題(text by 森口大地)
2024年1月29日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第38回配本として、ラウパッハ、シュピンドラー 他『ドイツ・ヴァンパイア怪縁奇談集』を刊行いたしました。1819年、イギリスの小説家ジョン・ポリドリが短編小説として『ヴァンパイア』を発表。この作品が話題となります。そのブームのさなか、1820~30年代にかけてドイツでもヴァンパイア文学が発表されました。本書は、ラウパッハ『死者を起こすなかれ』、シュピンドラー『ヴァンパイアの花嫁』他五作を集めた、怪縁織りなすドイツ・ヴァンパイア文学の傑作短編集となります。編者・訳者は自他ともに認めるヴァンパイア学者(ヴァンピロロジスト)の森口大地さん。本邦初訳となるドイツ・ヴァンパイア文学作品のほか、森口さんの手による「ヴァンパイア関係事項年譜」、訳者解題「ヴァンパイア文学のネットワーク」が収録されたとびっきりのヴァンパイア文学作品集になっています。
以下に公開するのは、ヴァンピロロジスト・森口大地さんによる訳者解題「ヴァンパイア文学のネットワーク」の一節です。

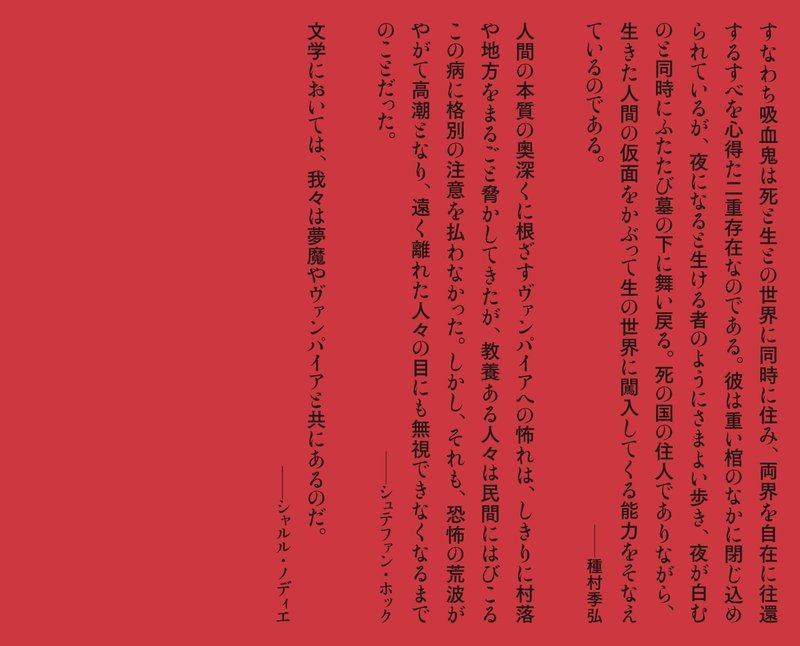
ポリドリの『ヴァンパイア』
こうして見ていくと、ポリドリの『ヴァンパイア』以前には、未発見のものもあるかもしれないが、ヴァンパイア文学と呼べる作品は数えるほどしかないのだ。一方で、ポリドリ後には、ヴァンパイアを主題にした作品は、本書の収録作品も含めて大量に出現する。それほど、ポリドリの『ヴァンパイア』が与えた影響は大きかったわけだ。出版社が、バイロンを作者と偽ったことも一役買ったのだろう。バイロンは当時から注目の的で、バイセクシャル、近親相姦、離婚など噂の種がつきなかった彼は、現代人がテレビで芸能人のスキャンダルを追うのと同じ興味を持たれていたと言える。ポリドリが書いたルスヴン卿に、バイロンが強く投影されていることも大きく働いたはずだ。
ポリドリとバイロンが顔を合わせたのは、1816年のことだ。この出会いからヴァンパイア出版までの過程はD・L・マクドナルドのPoor Polidoriに詳しい[★25]。当時、バイロンは肉体的にも精神的にも不調で(マクドナルドは誇張だとみなしている(p.53))、イギリスを離れ大陸を旅することにしたが、彼の治療にあたっていたサー・ウィリアム・ナイトンから侍医として推薦されたのがポリドリだった。同年の4月26日にバイロン一行はベルギーのオーステンデに着き、そこからオランダを回り、ドイツのケルンに足を向け、ライン川をスイスに向かった。ライン川では、ポリドリのバイロンに対する劣等感が窺える逸話がある。いくつかのバージョンが伝わっているが、ポリドリが、あなたにできて自分にできないことは何かと問うと、バイロンは銃の腕や水泳や本の売り上げなどを挙げるというものだ。ポリドリと父ガエターノの関係はうまくいっていなかったが[★26]、バイロンとポリドリの関係は、ある種この親子関係を繰り返したものだった。年長の男性に対する不安や憧れ、反発、承認欲求。これはポリドリの『ヴァンパイア』のオーブリとルスヴン卿の関係に強く投影されていて[★27]、本作を精神分析的に読む価値は大いにあるだろう。ポリドリは作家として成功するという野望を持ち、バイロンを嫉妬と憧れのないまぜになった気持ちで眺めていた。バイロンはそんなポリドリの気持ちを知っており、ポリドリが医者としても秘書としても有能でなかったこともあって、彼をからかっていた。とはいえ、ポリドリをただの被害者と見てはならない。ポリドリの問題行動もそれなりに記録に残されているし、バイロンがポリドリを気遣うこともあった。
5月25日に、バイロンらはジュネーヴのセシュロンにあるホテルに着いた。ここにはパーシー・ビッシュ・シェリーとメアリー・ウルストンクラフト・ゴドウィン(後のメアリー・シェリー)、バイロンの愛人ジェーン・〝クレア〟・クレアモント——メアリーの父ウィリアムの再婚相手の娘——も滞在していた。夏にはバイロンがレマン湖左岸のコロニーにあるディオダティ荘を借り、このメンバーが集まって、そこで『フランケンシュタイン、現代のプロメテウス Frankenstein; or the Modern Prometheus』(1818)と『ヴァンパイア』が誕生することになる。六月十五日のことだ。この年は雨の多い夏で、暇を持て余した彼らは『ファンタスマゴリアーナ Fantasmagoriana』(1812)という怪談集を読んでおり、それに刺激を受けたバイロンは怪奇物語の競作を提案した(この顛末を膨らませたケン・ラッセルの『ゴシック Gothic』(1986)という面白い映画がある)。執筆に着手したのはポリドリが最後で、18日に書き始めた。メアリーが『フランケンシュタイン』の1831年版に寄せた序文によると、ポリドリは鍵穴から覗きをした罰で頭が骸骨になってしまう女性の話を思いついていたようだ。その関係か、『アーネストゥス・バーチトルド、現代のエディプス Ernestus Berchtold; or the Modern Œdipus』(1819)というポリドリのそれほど有名ではない小説には、覗き見する女性が登場する。この競作でバイロンが書いた断片[★28]が、ポリドリの『ヴァンパイア』のもととなっている。この断片は今では簡単に邦訳で読むことができるが、ここでも年若の青年である「私」と年上の友人「オーガスタス・ダーヴェル」という構図、ポリドリ/オーブリとバイロン/ルスヴン卿を思わせる構図が見られる(ただし、ダーヴェルがヴァンパイアであることを示す描写はない)。
ポリドリは『ヴァンパイア』を出版する予定はなかったので、「ニュー・マンスリー・マガジン The New Monthly Magazine」(1819、4月1日)に本作が掲載されたのは寝耳に水だった。出版経緯のごたごたはマクドナルドとヘンリー・R・ヴィーツに詳しい。原稿がどのようにして、本誌を手がけた出版業者ヘンリー・コルバーンの手に渡ったかは定かではないが、レマン湖滞在当時にポリドリが仲良くしていた婦人を介したのではないかとされている。ポリドリが『アーネストゥス・バーチトルド』の序文の註で説明するところでは、彼がある婦人にバイロンの断片の内容を伝えたところ、それをもっともらしい物語にするのは無理だと言われたらしい。ポリドリ曰く、「3日間にわたって朝に作業し、私はその物語を作りあげ、彼女のもとに置いてきた」そうだ[★29]。この婦人は、彼が1816年の夏の間によく訪れていたブルース伯爵夫人ではないかとされる[★30]。ヴィーツが言うには、彼女はレマン湖の右岸のジャントに別荘を構えていたが、『ヴァンパイア』の原稿は1816年9月から18年の秋にロンドンに着くまで、ここにあったという。これをコルバーンに渡したのは、ジョン・ミットフォードという人物の可能性があるとされる[★31]。ミットフォードは、『ヴァンパイア』の前書きに載せられている「ジュネーヴからの手紙の抜粋、バイロン卿にまつわる逸話等々 Extract of a Letter from Geneva, with Anecdotes of Lord Byron, &c.」の著者でもあるとされている[★32]。「抜粋」の内容は、著者がディオダティ荘に赴き、近辺で使用人などに聞きこみ調査をした結果などを伝えるもので[★33]、ポリドリへの言及はあるものの、彼の名前は「抜粋」では徹底的に伏せられているため、『ヴァンパイア』の作者がバイロン卿であるという勘違いを助長させるには充分だ。
『ヴァンパイア』がバイロンの名前で売られたことは、コルバーンの経営戦略の可能性が高い。これに対して、編集のジョン・ワトキンスは後に匿名でコルバーンの行為を利益を目的とした悪行だと非難し、副編集であったアラリック・ワッツは、ポリドリの名前に言及こそしないものの、バイロンが作者ではないことを示す前書きを用意し、バイロンの著作の出版を手がけていたジョン・マレーに事情をうちあけた他、抗議の意図をこめて職を辞してさえいる[★34]。コルバーンは『ヴァンパイア』の販売[★35]が妨げられることを恐れ、ワッツの前書きを削除した。後にポリドリやバイロンが抗議の手紙を送ったが、時すでに遅く、『ヴァンパイア』はバイロンの名前で広まることとなった[★36]。
ポリドリのもたらした変革
しかし、皮肉なことに『ヴァンパイア』とバイロンの結びつきは、ヴァンパイアにパラダイム転換を起こした。セルビア事件によって有名になったvampirは、ポリドリの小説でバイロンをモデルとしたルスヴン卿と重なることで、それまでとは異なる存在になった。マクドナルド/シャーフがまとめるように、以下の四つの点において、ポリドリのルスヴン卿は革命的存在であると言える[★37]。
ヴァンパイアを現実味のある一個の人間に仕上げたこと。
ヴァンパイアに貴族という身分を与えたこと。
ヴァンパイアを放浪者としたこと。
ヴァンパイアを誘惑者としたこと。
民間伝承上のvampirは、蘇る死者であり、基本的に人格を持つ存在ではない[★38]。ただの蘇った死体として、その行動が語られるにすぎない。確かに、それまでのヴァンパイア文学では、ゲーテの『コリントの花嫁』やスタッグの『ヴァンパイア』などで人格を持った存在としてのヴァンパイアが多少は描かれてはいるが、バイロンという具体的な人物が投影されたルスヴン卿は、〈バイロン的ヒーロー[★39]〉というバイロンが描いた主人公によく見られる特性をも備えることで、人格をより強烈に打ちだしている。ポリドリの『ヴァンパイア』が掲載された「ニュー・マンスリー・マガジン」は、編集者による前書きでセルビア事件を引用してヴァンパイアを読者に説明するが、この前書きもまた、〈バイロン的ヒーロー〉としてのルスヴン卿と、それまでのvampirとの対比を強めていると言えるだろう。この対比は、20世紀になって、アン・ライスの小説で、自らのルーツを探りに東欧を旅するルイが、当地で野生動物のような、人格のないただの生ける屍としてのヴァンパイアと出くわす場面にも象徴的だ[★40]。
市民階級の台頭やフランス革命によって、当時、徐々に衰退の兆しを見せ始めていた貴族という身分は、ヴァンパイアと同じ生きながらにして死んでいる状態にあった。その意味では、ヴァンパイアの貴族性はある種の時代錯誤(アナクロニズム)だ。テオフィル・ゴティエの『恋する死女 La Morte amoureuse』(1836)のクラリモンド——貴族ではないがクルティザンヌとしてコンチーニ宮に住まう——、シェリダン・レ・ファニュの『カーミラ Carmilla』(1871‐72)のカーミラ(カルンシュタイン伯爵夫人)も、ストーカーのドラキュラ伯爵も、時代が下れば下るほど、読者からすれば過去の遺物のような存在に見えるだろう。逆に言えば、貴族的ヴァンパイアのはしりであるルスヴン卿は、フランス革命に比較的近い時期の存在だ。ルスヴン卿を舞台にあげたシャルル・ノディエがメロドラマというジャンルを選択したことは示唆に富む。メロドラマは、ノディエからすれば民衆教育の役割を果たすのであって[★41]、だからこそ悪人の典型としての貴族が生きてくる。宮廷貴族や政治家、聖職者などの上流階級による搾取をヴァンパイアになぞらえる伝統は、ヴォルテールの痛烈な当てこすりだけでなく、1732年5月の「ロンドン・マガジン The London Magazine」や「クラフツマン The Craftsman」にまで遡れる[★42]。ルスヴンの賭博癖——しかも彼は自分の儲(もう)けに関心はなく、善人から巻き上げ、悪人に負けて金を流す——もこの伝統に連なるもので、彼は放蕩(ほうとう)というステレオタイプな悪い貴族像を提供している。同じ貴族でも、ドラキュラ伯爵は、フランコ・モレッティが指摘するように、無駄を許さない資本家であり、召使がやる仕事を自分自身でする[★43]。
しかし、最も注意すべきは、ルスヴンの実際の素性が曖昧模糊(もこ)としていて、誰にもわからないという点だろう。冒頭のnoblemanという記述すら信頼できるものか怪しい。なぜなら、この物語はすべてオーブリの妄想という可能性を秘めているからだ(三人称の語りではあるが、彼は結末で、「読者がこれまで読んできた内容を冷静に語っ」てから死ぬ)。そもそも、蘇ったルスヴン卿は「マースデン伯」を名乗っている。「ルスヴン卿」という氏素性は信頼に足るものだろうか。これらは、「解きがたい矛盾(irreconciliable contradictions)」に満ちたダーヴェルの素性——「オーガスタス・ダーヴェル」という名前は仮名でしかない——と、「私」による主観的な語りと呼応する。死者が現実社会に籍を置かないのと同じように、ヴァンパイアについては、確かなものなど何もないのだ(「カーミラ」という名前がアナグラムであることが思い出される)。放浪というヴァンパイアの性質も、確固たるアイデンティティの欠如と結びつく。民間伝承でも、蘇る死者は死後に家に戻ってくるという、ある種の旅をしているのだ。
放浪者としてのヴァンパイアは、マクドナルド/シャーフが言うように、放浪詩人としてのバイロンや、彼の『チャイルド・ハロルドの巡礼 Childe Harold’s Pilgrimage』(1812‐18)、『異教徒(ジャウア)』における罵倒(「ヴァンパイアと化して、地上に出でて〔…〕生地を跳梁跋扈(ばっこ)するがいい」)、またバイロンの断片におけるダーヴェルと「私」の旅によって形づくられている。これに付け加えるならば、さまよえるユダヤ人のような、M・G・ルイスの『破戒僧 The Monk』(1796)やC・R・マチューリンの『放浪者メルモス Melmoth the Wanderer』(1820)などのゴシック小説で好まれたモティーフも無関係ではないだろう[★44]。また、ここには英国貴族の子弟が教育の一環として体験するグランド・ツアー[★45]の名残も見いだせるかもしれない。ヴァンパイアの貴族性は、グランド・ツアーを介して放浪者としてのヴァンパイアと繋がっているのだ。さらに言えば、ストーカーの『ドラキュラ』冒頭も旅行記として読むことができる[★46]。もっとも、ここで旅するのはジョナサン・ハーカーであって、ドラキュラ伯爵のロンドンへの旅は、むしろ貨物としての輸送でグランド・ツアーとはほど遠い。いずれにせよ、異国趣味(エギゾティシズム)はセルビア事件の報告書の頃から、ヴァンパイアと切り離せない関係にある。神聖ローマ帝国の役人は、自国の領土周縁で起きた事件を奇異の目で見ていた。しかし、この奇異の目は、同時に魅了された者の目でもあり、ルスヴン卿を見る周囲の人間の目と同じなのだ。我々は、どこか奇妙で普通ではないものに惹かれる。それはポジティヴな心理に思えるが、同時に偏見というネガティヴな心理と表裏一体でもある。この好奇心が、ヴァンパイアにはつねに働いているのだ。エドワード・サイードの〈オリエンタリズム〉は、この点と強く関わってくる[★47]。
誘惑者としてのヴァンパイアは、クリスタベルやレイミアなどをヴァンパイアと結びつけることになったきっかけでもある。この一面は、『ドラキュラ』のルーシー・ウェステンラが体現するような、19世紀末から20世紀にかけて見られた〈新しい女(New Woman)〉にまで受け継がれているし、〈ダンディズム〉とも通ずるところがあるだろう。1820~30年代に制作されたポリドリの『ヴァンパイア』の舞台翻案では、原作以上にルスヴン卿のプレイボーイな面が強調されるが、ここにはロレンツォ・ダ・ポンテ台本/ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲の『ドン・ジョヴァンニ Don Giovanni』(1787)の影響もあるかもしれない。民間伝承やセルビア事件の頃からすでに、就寝中の人々を襲ったり死後に妻と性交渉を持ったりと、性的要素を孕(はら)んではいるものの、誘惑者という性質をヴァンパイアが手にしたのは文学に入ってからのことだ。オッセンフェルダーの詩『ヴァンパイア』では、酔った男が娘を誘惑する際に、己をヴァンパイアになぞらえている。
以上の四つの性質は、ポリドリの『ヴァンパイア』を受けて制作された、フランスとドイツの多数の舞台翻案にも確認できる[★48]。フランス幻想文学の父とされるシャルル・ノディエは、友人シュプリアン・ベラールの小説『ルートヴェン卿、ヴァンパイアたち Lord Ruthwen, ou les Vampires』(1820、ただし、ほぼノディエが書いたという説もある)を後援したあと、自分でも共同台本でメロドラマ『ヴァンパイア Le Vampire』(1820)を執筆。本作はポルト・サン゠マルタン劇場で上演され、好評を博した。これが大量の後追い作を生み、ハインリヒ・ルートヴィヒ・リッターによるノディエの独訳(1822)を受けて、ドイツ語圏も流行に続いた。オペラに詳しければ、ハインリヒ・マルシュナーの名前を耳にしたことがあるかもしれないが、彼が作曲を手がけた『ヴァンパイア Der Vampyr』(1828)はノディエの戯曲がなければ存在しなかっただろう(マルシュナーの『ヴァンパイア』は、2022年にもハノーヴァーで上演され、期間限定で無料配信もされていた)。それどころか、本書に収録された多くの作品は、ノディエの『ヴァンパイア』、ひいてはポリドリの『ヴァンパイア』がなければ存在しなかったはずだ。
もちろん、ポリドリが後世に与えた影響を慎重に見積もっていく必要があることは言うまでもない。例えば、ユーライア・デリック・ダーシーの『黒人ヴァンパイア The Black Vampyre』(1819)は、その序文や註を見ると、ポリドリの作品を意識していることが明らかだし、ジェイムズ・マルコム・ライマー(/トマス・ペケット・プレスト)の『ヴァンパイアのヴァーニー Varney the Vampyre』(1845‐47[★49])では、ポリドリ伯爵という人物が登場し、ポリドリの『ヴァンパイア』の舞台翻案のように、自分の命を救ったヴァーニー——このあたりの章では、彼の名前は基本的に伏せられて、主にthe stranger(ヴァンパイアのよそ者的・放浪者的性質が思い出される)と表記されている——を娘と結婚させようとする[★50]。しかし、後世の他の作品との関係は要検討だ。ポリドリの『ヴァンパイア』が、革新的なヴァンパイア像の先駆であるとは言えるが、これは果たして、そのまま『ドラキュラ』まで何の差し障りもなく受け継がれてきたのだろうか。このあたりは、今後の研究で詳らかにしていく必要がある。ヴァンパイアについてまだまだ語るべきことは多いが、きりがないのでこのあたりで止めておこう。
[★25]Cf. Macdonald, Poor Polidori, op. cit. (n. 23), pp. 177–88. 以下も参照。アンドレ・モロア『バイロン伝』(大野俊一訳)角川書店、一九六八年、第三部/楠本哲夫『永遠の巡礼詩人バイロン』三省堂、一九九一年、第三章。
[★26]ガエターノは幼いポリドリに高い水準を要求しており、それに対してポリドリは父を満足させられないのではないかという不安を抱いていた。これが二人の親子関係に深く根をはっている。Macdonald, ibid., p. 5–14, 18. 邦書文献では、以下がこの点に触れている。相浦玲子「バイロンとポリドリ―ヴァンパイアリズムを中心に」、「滋賀医科大学基礎学研究」九巻(一九九八年、三月)、九‐三〇頁所収。
[★27]Cf. Ken Gelder: Reading the Vampire. London / New York: Routledge 1994, p. 31, 58; Oliver Hepp: Der bekannte Fremde. Der Vampir in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien 2016, S. 128, Anm. 257.
[★28]未完のため、後に「断章(A Fragment)」と題されて、バイロンの『マゼッパ Mazeppa』(一八一九)という詩に掲載される。George Gordon Byron: A Fragment. In: idem: Mazeppa, A Poem. London 1819, pp. 59–69. これまでもバイロンの著作を出版していたジョン・マレーはこれを勝手に掲載したため、バイロンはそれに抗議している。「断章」はバイロン自身の手になるもので、ここで描かれている「私」の描写から、ポリドリにどのように見られていたかをバイロンがよく理解していたことがわかる。
[★29]The Vampyre and Ernestus Berchtold; or, the Modern Œdipus. Edited by D. L. Macdonald and Kathleen Scherf. Claremont (CA): broadviewpress 2008, p. 63, n. 1. この註で、ポリドリは自分の『ヴァンパイア』がバイロンの断片に基づいていることを認めている。
[★30]ポリドリの日記にはMadame Bとしか書かれておらず、彼の日記を編纂した甥ウィリアム・マイケル・ロセッティは、Madame BrelazかComtesse de Breussではないかとしている。Cf. The Diary of Dr. John William Polidori. 1816. Relating to Byron, Shelly, etc. Edited and Elucidated by William Michael Rossetti. London: Elkin Mathews 1911, p. 152. ポリドリはMadame Bと互いに好意を抱きあっていたことをほのめかしている。Cf. Ibid., pp. 145f. ヘンリー・R・ヴィーツは後者(Breuss)説をとっていて、彼によると、Breussという名前は、ポリドリの妹のシャーロットがポリドリの原稿を誤って書き写し、それをロセッティが編纂の際に引き継いだ結果で、実際はキャサリン・ブルース伯爵夫人Countess Catherine Bruceというロシア生まれの貴族だという。Cf. Henry R. Viets: The London Editions of Polidori’s “The Vampyre”. In: The Papers of the Bibliographical Society of America, Vol. 63, No. 2 (Second Quarter, 1969), pp. 83–103, here p.88.
[★31]Cf. Macdonald, Poor Polidori, op. cit. (n. 23), p. 178; Baldick / Morrison, The Vampyre and Other Tales of the Macabre, op. cit. (n. 16), p. 235.
[★32]「抜粋」の著者はこれまで様々に推測されてきた。ロセッティは、ポリドリの日記にも出てくるガテリエ夫人Madame Gatelierだとし、ジェイムス・リージャーはこの説を支持しているという。バイロン自身はポリドリが書いたのだと考えており、ピーター・D・グルディンはこれを支持しているという。Cf. The Vampyre and Other Tales of the Macabre, ibid. ポリドリはそもそも『ヴァンパイア』の出版を予定していなかったうえに、自分が作者であることを主張している彼が自分の名前を伏せるとは考えにくいので、少なくともポリドリの可能性は低い。
[★33]Cf. Extract of a Letter from Geneva, with Anecdotes of Lord Byron, &c. In: ibid., pp. 236–40.
[★34]Cf. Viets, op. cit. (n. 30), pp. 91ff.
[★35]出版時のいざこざに劣らず、出版形態もややこしい。ロバート・モリソン/クリス・ボルディックによれば、雑誌掲載の後、一八一九年に書籍形態で七つの版printingが出たらしいが、詳しい論証はない。Cf. The Vampyre and Other Tales of the Macabre, op. cit. (n. 16), p. x. D・L・マクドナルド/キャスリーン・シャーフも初年のうちに英語版で七つの版editionが出たとしているが、詳しい論証はない。Cf. The Vampyre and Ernestus Berchtold, op. cit. (n. 29), p. 11. ヴィーツによれば、ロンドンで五つの版editionが出ているので、数に食い違いがある。Cf. Viets, op. cit. (n. 30), p. 84, 97. 奇妙なのは、モリソン/ボルディックとマクドナルド/シャーフは、ヴィーツを参照しているにもかかわらず七つの版とみなしていることだ。ヴィーツが挙げているアメリカで出た三つの版edition(ニューヨーク、フィラデルフィア、アルバニー)とパリで出た英語版を考慮しても計算が合わないし、ヴィーツが巻末で挙げている版は六つある。いずれにせよ、「ニュー・マンスリー・マガジン」掲載後に、コルバーンは『ヴァンパイア』を書籍形態でも出版しようとしたわけだが、ヴィーツによれば、書籍形態のコルバーン版first stateは現存せず、当時もほとんど出回らなかったという。コルバーン版はsecond stateのみが残されている。その他には、シャーウッド/ニーリー/ジョーンズ版の第一刷first issue、第二刷second issue、第三刷third issueと、ミラー版―当時、「ニュー・マンスリー・マガジン」には著作権がなかったので無許可で刷られた―が存在するので、書籍形態の『ヴァンパイア』は、コルバーン版first stateを除外すれば、五つの版が残っている計算になる。コルバーン版のsecond stateには、ポリドリの名前が記されてはいるものの、「バイロン卿が医師ポリドリに語った物語(a tale related by Lord Byron to Dr. Polidori)」とバイロンを著者扱いしていることに変わりはない。シャーウッド/ニーリー/ジョーンズ版のthird issueにはポリドリ自筆の修正が加えられており、ポリドリが望んだかたちに近い。マクドナルド/シャーフが編集した『ヴァンパイア』はこれに基づいており、例えばルスヴン卿の名前がストロングモア卿——ポリドリと父、あるいはバイロンとの関係を考えると興味深い名前——に変更されている。
[★36]とはいえ、「エディンバラ・マンスリー・レヴュー Edinburgh Monthly Review」のように、当時からすでにバイロン作であることを疑っていた書評もある。Cf. The Vampyre and Ernestus Berchtold, op. cit. (n. 29), p. 241.
[★37]Cf. D. L. Macdonald and Kathleen Scherf: Introduction. In: The Vampyre and Ernestus Berchtold, ibid., pp. 9–31, here pp. 11–14.
[★38]民間伝承の蘇る死者の話は、記録に書きとめられる以前は現地人の間で口伝えに伝わっていたはずだが、そのために昔話などの口承文学の登場人物に見られる「平面性」や「一次元性」とも無関係ではないだろう。マックス・リューティ『昔話と伝説―物語文学の二つの基本形式』(高木昌史/高木万理子訳)法政大学出版局、一九九五年、二九‐三五頁参照。
[★39]この概念は以下に詳しい。マリオ・プラーツ『肉体と死と悪魔——ロマンティック・アゴニー』(倉知恒夫/草野重行/土田知則/南條竹則訳)国書刊行会、一九八六年、一〇四‐一〇八頁/門田守「バイロニック・ヒーローの変容―その語りの三様態について」、名古屋大学英文学会「IVY」第二五号(一九九二)、四三‐六四頁。過去の拙論でも少し触れている。森口大地「ラウシュニクの『死人花嫁』に見られるヴァンパイア像―一〈宿命の女〉と〈宿命の男〉の二重構造」、京都大学大学院独文研究室「研究報告」第三二号(二〇一八)、一‐二二頁所収。簡潔にまとめるならば、謎めいていて、罪の意識、情熱や憂鬱に苛まれた精神を有する、プライドの高い反逆者といったところだろうか。十九世紀の批評家トーマス・バビントン・マコーレーによれば、「誇り高く、むら気で、皮肉屋、顔つきは反抗的、しかし心中は悲嘆にくれ、独特なやり方で軽蔑を示し、復讐においては執念深く、だが深く強い情を示すこともできる男」を指す。Thomas Babington Macaulay: Critical and Historical Essays. Contributed to the Edinburgh Review. The fifth edition. Vol. 1. London 1848, p. 344.
[★40]アン・ライス『夜明けのヴァンパイア』(田村隆一訳)早川書房、一九九三年[一九八七]、三〇〇‐三〇三、三一一頁参照。
[★41]藤田友尚「ノディエのメロドラマ『吸血鬼』―「狂熱派」演劇の一側面」、関西学院大学「エクス―言語文化論集」第四号(二〇〇六)、一一七‐一三三頁所収、一二三‐一二五頁/ジャン゠マリ・トマソー『メロドラマ フランスの大衆文化』(中條忍訳)晶文社、一九九一年、一六‐一七頁参照。
[★42]Cf. The London Magazine. May 1732. In: The London Magazine: or, Gentleman’s Monthly Intelligencer. Vol. 1 (1732). London 1732, pp. 76–78.; Voltaire: Question sur L’Encyclopedie, par des amateurs. Neuvieme partie. S. L. 1772, pp. 310–17; The Craftsman. No. 307. Saturday, May 20, 1732. In : The Craftsman by Caleb D’Anvers. Vol. IX. London 1732, pp. 120–29.
[★43]フランコ・モレッティ『ドラキュラ・ホームズ・ジョイス―文学と社会』(植松みどり/河内恵子/北代美和子/橋本順一/林完枝/本橋哲也訳)新評論、一九九二年、二一、二八‐三三頁参照。
[★44]ヴァンパイア文学とゴシック小説の関係は間違いなく深く、さらなる研究が俟たれるテーマだろう。ヴァンパイア文学には、ホレス・ウォルポールの『オトラント城 The Castle of Otranto』(一七六四)に始まるゴシック小説のエッセンス―中世趣味、異国趣味、グランド・ツアー、ピクチャレスク、〈崇高〉概念、悪漢、夢や自動筆記、牢獄、幽閉、廃墟、怪奇現象etc.―が見られる。この文学潮流は、アン・ラドクリフ、レ・ファニュやウィルキー・コリンズを介してストーカーにも受け継がれている。Cf. Dictioinary of Literary Biographie. Vol. 304. Bram Stoker’s Dracula: A Documentary Volume. Edited by Elizabeth Miller. Detroit / New York / San Francisco / San Diego / New Haven, Conn. / Waterville, Maine / London / Munich: Thomson Gale 2005, pp. 98–113.
[★45]グランド・ツアーについては以下を参照。岡田温司『グランドツアー―18世紀イタリアへの旅』岩波書店、二〇一〇年。
[★46]Cf. Stephen D. Arata: The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonization. In: Victorian Studies. Vol. 33. No. 4 (Summer 1990), pp. 621–45; 下楠昌哉「隔絶された風景の逆襲:視覚の変容を記録したメディアとしてのブラム・ストーカー初期諸作品」、「静岡文化芸術大学紀要」第三巻(二〇〇三)、二三‐三一頁所収/下楠昌哉「ぎざぎざの鋸岩と、尖った断岩―ブラムストーカー作『ドラキュラ』における風景描写」、「静岡文化芸術大学研究紀要」第四巻(二〇〇四)、七‐一七頁所収/河内恵子「19世紀末ロンドンの旅人たち―旅行記としてのゴシック小説を読む」、河内恵子/松田隆美/坂本光/原田範行『イギリス文学と旅のナラティヴ―『マンデヴィルの旅』から『ドラキュラ』まで』慶應義塾大学出版会、二〇〇四年、一五三‐一八八頁所収。
[★47]エドワード・サイード『オリエンタリズム』(板垣雄三/杉田英明監修、今沢紀子訳)、一九八七[一九八六]年、「序説」/森口大地「血色の研究(1)ヴァンパイアをめぐる距離」、「Brunnen」第五二九号(二〇二三、四月)郁文堂、一〇‐一四頁所収参照。
[★48]これについては以下が詳しい。Roxana Stuart: Stage Blood: Vampires of the 19th-Century Stage. Bowling Green (OH): Bowling Green State University Popular Press 1994; 藤田、前掲書(★41参照)/森口大地「矮小化されるルスヴン卿―一八二〇年代の仏独演劇におけるヴァンパイア像」、京都大学大学院独文研究室「研究報告」第三三号(二〇一九)、一‐二三頁所収。その他、邦書で舞台翻案に触れているものとしては、例えば以下を参照。デイヴィッド・J・スカル『ハリウッド・ゴシック―ドラキュラの世紀』(仁賀克雄訳)国書刊行会、一九九七年、二八‐三一頁/種村季弘『吸血鬼幻想』河出書房新社、一九八五[一九八三]年、一七三‐一七七頁/日夏、前掲書(★03参照)、一五五‐一七〇頁/マシュー・バンソン『吸血鬼の事典』(松田和也訳)青土社、一九九五[一九九四]年、「ノディエ」や「吸血鬼」の項目/エリック・バトラー『よみがえるヴァンパイア』(松田和也訳)青土社、二〇一六年、四四‐五二頁/岸田理生「血こそ生命なればなり 第五回 吸血鬼文学小論」、「新劇」(第三一巻、第八号)白水社、一九七四年、八八‐九七頁所収、九三‐九五頁。
[★49]作者に関しては、サマーズがプレスト説を唱えてからしばらくはそちらが主流だったが、J・G・メルトンとクリストファー・フレイリングによれば、ライマー自身のスクラップブックを入手したルイ・ジェイムズの一九六三年の研究以降、ライマー説が主流となっているという。ただし、ライマーが大部分を書いたとはいえ、プレストが書いた部分もあるとする説もある。Cf. J. Gordon Melton: The Vampire Book. The Encyclopedia of the Undead. Third Edition. Detroit: Visible Ink Press 2011, p. 598; Christopher Frayling: Vampyres. Lord Byron to Count Dracula. London / Boston: Faber and Faber1991, pp. 145f.; Summers, His Kith and Kin, op. cit. (n. 10), Introduction, p. xii. ジェイムズ曰く、フランク・アルガーという蔵書家が手に入れたものを彼が現在所有しているという。アルガーの蔵書は、ライマーの小説のうちの一作の校正刷りを含んでいる。他にも、定期刊行物からの切り抜きにライマー自身の手になる署名入りのメモがあり、すべて自分の作品であると書かれているという(ただし、『ヴァーニー』に関しては明確な説明がない)。Cf. Louis James: Fiction for the Working Men: 1830–1850. Third, expanded edition with new Introduction. Brighton: Edward Everett Root, Publishers 2017 [1963], p. 41. また、ヘレン・R・スミスによれば、ライマーやプレストと関わりの深い出版人エドワード・ロイドによる「ロイドのロンドン週刊新聞 Lloyd’s Weekly London Newspaper」(一八四五年九月二十一日付)の『ヴァーニー』の広告に「Don Caesar de Bazanの著者による」と書かれていることも、ライマー説を補強しているという。Cf. Helen R. Smith: New Light on Sweeney Todd. Thomas Peckett Prest, James Malcolm Rymer and Elizabeth Caroline Gray. Bloomsbury: Jarndyce Antiquarian Booksellers 2002, p. 19; Lloyd’s Weekly London Newspaper. Sunday, September 21, 1845, p. 6.『ドン・セザール・ド・バザン―スペインのロマンス Don Caesar de Bazan. A Romance of Spain』(一八四五)はサマーズによるとライマーの作品。Cf. Montague Summers: A Gothic Bibliography. London: Fortune Press [No Date], pp. 43f. 『ヴァンパイアのヴァーニー』を編集したE・F・ブライラーの文体分析によると、プレストではなくライマーの手になるという。例えば、ライマーと異なり、プレストは「言う(say)」を様々に言い換えていたり、withを用いた修飾句ではなく、「言う」に副詞を用いて様子を表わしたりしており、一文の長さが平均三行と短めらしい。Cf. E. F. Bleiler: Introduction to the Dover Edition. In: Varney the Vampyre, or the Feast of Blood. Vol. I. Mineola / New York: Dover Publications, Inc. 2015 [1972], pp. v–xv, here p. viii–ix (see also A Note on Authorship, pp. xvii–xviii). いずれにせよ、詳細な比較研究が必要であることは言うまでもない。
[★50]Cf. Uriah Derick D’Arcy: The Black Vampyre. A Legend of St. Domingo. Second Edition, with Additions. New York 1819; James Malcolm Rymer: Varney the Vampire, or, The Feast of Blood. With an Introduction by Dick Collins. London: Wordsworth Editions 2010, Ch. 161–65, pp. 961–76. 残念ながら、邦訳『吸血鬼ラスヴァン』では『黒人ヴァンパイア』の冒頭にある『ウォール街 Wall-Street』(一八一九)の著者に向けた献辞と、併せて出版された「道徳(Moral)」と「ヴァンパイアリズム(Vampyrism; A Poem)」は訳されていない。『ウォール街』とは、正確にはWall Street, or Ten Minutes Before Three(一八一九)を指すと考えられる。本戯曲については以下を参照。Cf. Charles R. Lown, Jr.: The Businessman in Early American Drama. In: Educational Theatre Journal. Vol. 15, No. 1 (Mar., 1963), pp. 47–54; Monroe Lippman: The American Playwright Looks at Business. In: Educational Theatre Journal. Vol. 12, No. 2 (1960), pp. 98–106.
【目次】
死人花嫁 ゴットフリート・ペーター・ラウシュニク
死者を起こすなかれ エルンスト・ラウパッハ
ヴァンパイアの花嫁 カール・シュピンドラー
ヴァンパイア アルスキルトの伝説 J・E・H
狂想曲——ヴァンパイア イジドーア
ヴァンパイアとの駆け落ち ヒルシュとヴィーザー
ヴァンパイア ワラキア怪奇譚 F・S・クリスマー
註
ヴァンパイア関係事項年譜
訳者解題 ヴァンパイア文学のネットワーク
【訳者略歴】
森口大地(もりぐち・だいち)
1990年生まれ。ヴァンパイア学者(ヴァンピロロジスト)。京都大学文学研究科博士後期課程修了後、『ドイツ語圏を中心とした初期ヴァンパイア文学史——セルビアの事件からルスヴン卿の後継者まで』で京都大学博士号(文学)を取得。現在、関西学院大学ほか非常勤講師。専門はヴァンパイア学(ヴァンピロロジー)。主に18~19世紀のヴァンパイア史、ヴァンパイアを題材にした史料・文学テクストや論文。業績と連絡先についてはリサーチマップを参照(https://researchmap.jp/vampirforscher)。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ラウパッハ、シュピンドラー 他『ドイツ・ヴァンパイア怪縁奇談集』をご覧ください。
