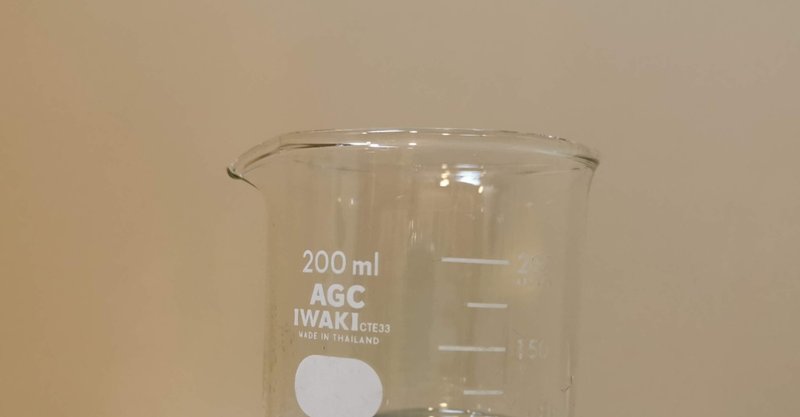
ガラスは固体?液体?
ガラス(ケイ酸塩でできた物質)とは具体的にどんな材料なのか?
一見、硬い固体のように見えます。
そして、ガラスは非晶質です(分子が規則正しく整列したのが結晶)。
ガラスを構成する分子は規則正しく並んではいません。
もちろん、固体=結晶ではありません。
例えば、透明なプラスチック材料として使われるメタクリル樹脂は、非晶性の樹脂です。
また、ペットボトルに使われるPET(ポリエチレンテレフタレート)は結晶性の樹脂ですが、結晶化温度付近で急速冷却することで、結晶部分の少ない透明な固体になります。
ガラスには二つの意味があります一つは物質の状態です。
昇温によりガラス転移現象を示す非晶質固体。そのような固体となる物質。このような固体状態をガラス状態と言う。(Wikipedia)
もうひとつは、物質そのものです。
ケイ酸塩を主成分とする硬く透明な物質。グラス、玻璃(はり)、硝子(しょうし)とも呼ばれる。(Wikipedia)
ふつう、ガラスと言ったらケイ酸塩を主成分とするグラスを指すことが多いですね。
しかし、化学では物質の状態を指すときに使うことが多いと感じます。
特に、非晶質の材料が硬くなる(or 柔らかくなる)温度をガラス転移点(Tg)と呼び、高分子の研究では定番の用語です。
ガラス転移点より高い温度では柔らかいゴム状態になり、転移点より低い温度では硬いガラス状態になります。
身近な例はチューインガムです。体温付近で柔らかいゴム状態になり、体温以下だと固いガラス状態です。
ケイ酸塩のガラスは液体を過冷却して作られたもので、ガラス転移点を持っています。ある温度で急激に状態を変化させます。
過冷却で出来た不安定な状態のため、ガラスは常に液体に戻ろうとしていると言われています。
実は「ガラスは目に見えない速度で少しずつ流れている」という指摘もあります。もちろん、数万年かそれ以上かけないと分からないくらいのスピードです。
そうなると、ガラスは流動性のある液体と言えます。
ガラスの固体なのか、液体なのか?
その長年の疑問に一つの答えが出ました。
東京大学、上海交通大学、グルノーブル大学の国際研究グループが、コンピュータシミュレーションによってガラスを構成する分子の動きを観察・解析した結果、ガラスの分子が位置を変えながら振動している事を発見しました。
つまり、ガラスは液体と固体の中間の性質を持っていると言えます。
これは、ガラスを液体状態から急激に冷却して作っていることが原因と考えられます。
液体状態から冷却することで、徐々に安定な状態になります。急激に冷却すると、ギリギリ安定な状態で固化します。そのため、固体と液体の中間の性質を持つことになったと推測されます。
この研究結果によって、分子の熱運動だけでは説明できなかったガラスの性質や現象の理解が進むことが期待されます。
とても興味深い研究結果ですね。
読んでいただけるだけでも嬉しいです。もしご支援頂いた場合は、研究費に使わせて頂きます。
