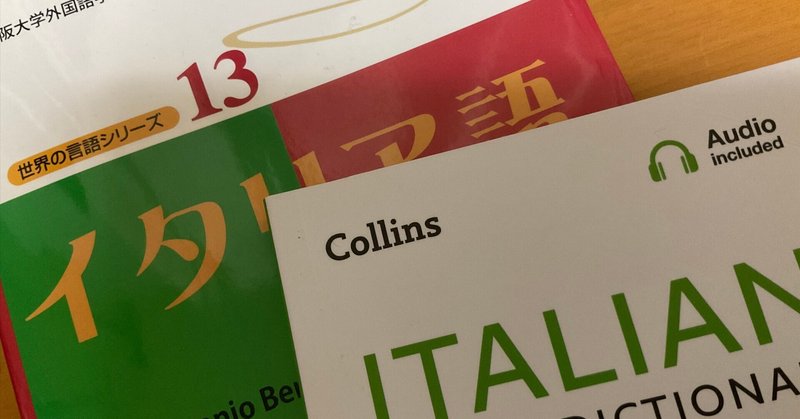
5月某日 何のために学ぶのか
最近、何のために学んでいるのか、学ぶ理由をなんとなく摑めた気がする。
昔は「学びたいから学ぶ」という、「山がそこにあるから登るのだ」のような理由で学んでいた。しかし、学ぶ事柄をある程度選んでいることに気づいてからは、それだけではないと思った。
たとえば、今力を入れている語学。これは、その国に行くにあたって、その国のことをより深く知り、感じるために学んでいる。もちろん、その場に行くことで得られることもたくさんある。けれど、その場を楽しむためには知識があることが大事だ。「紅茶をきちんと注文できるかどうか」ということで悩んでいては、店の違いに気づくほど周りを観察することはできないだろう。
つまり、自分の見ている世界の解像度を上げるために学んでいると言っても過言ではないのだ。
なぜ、解像度を上げるのか。これは、どんなことでも観察してしまう私の特性に理由がある。観察し、分析し、思考の結果を言語化する、ということをごく自然に行ってしまう私にとって、材料はあればあるほど正確に物事が見れる。まっさらな状態だと、その場を乗り切ることで精一杯になってしまって、何もできない。事前情報があることで、余裕ができるのだ。
また、最近、言語化することに不安を覚えたことがあった。確信できることしか口に出せない、知らないことに対して何も言う資格はない、と思っていたのだ。それらに対する策は2つ。その場では話さず聞き役に徹することと、自分でも調べてみることだ。不安の原因は、知ろうとしない私の姿勢に向いていた。私はきっと、知への欲求がとても強いのだと思う。知るからにはとことん知りたい。それこそ自分で分析ができるようになるまで。
そして、分析したら披露したくなるのが性というもの。披露するからには生半可な知識ではいけない。世界への解像度を上げることは、間違った知識を広めないことにつながると私は感じている。
立場としては一般人の端くれであるが、姿勢としては研究者のそれに近いものを持っているのだと思う。だが、研究者になりたいと思ったことはない。合間の人間として、世界の橋渡しができたらいいな、という大それた夢を持っている。こんなことが言えるのも恵まれたことで、一般人とはほど遠い高等遊民めいた精神だということはわかっている。中途半端な人間にもできることがあるのではないか、と考えた結果がこれなのだ。
世界の隅っこで、いろいろ考えたり、観察したり、分析したりしている変なヤツ、に最終的にはなりたいな。
追記
なんだか大げさなことをいろいろ書いてしまったが、こういう「自分に何かしらを負わせる」ところがストレスの大本なのではないかと思い始めている。
何者にもならなくていいんだよ。イタリア語の語彙が増えて「uovo」が「卵」だとわかったり、台湾の地名をピンインで発音できたりして成長を感じるのは楽しい。そうやって楽しく世の中生きていけたらそれで充分ではないか。
わからないことは「わからない」と言えばいいし、これから学べばいい。学んでいなければ声を上げてはいけないということはない。
自分で自分のハードルを上げてしまっていたんだな、と気づいてから楽になった。時間があるから好きなことを勉強する、というだけでいいのだ。
きっとこれからも自分で自分に理想を押しつけるときがあると思う。そういうときにこの文章を読み返すだろう、未来の自分のために記録しておく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
