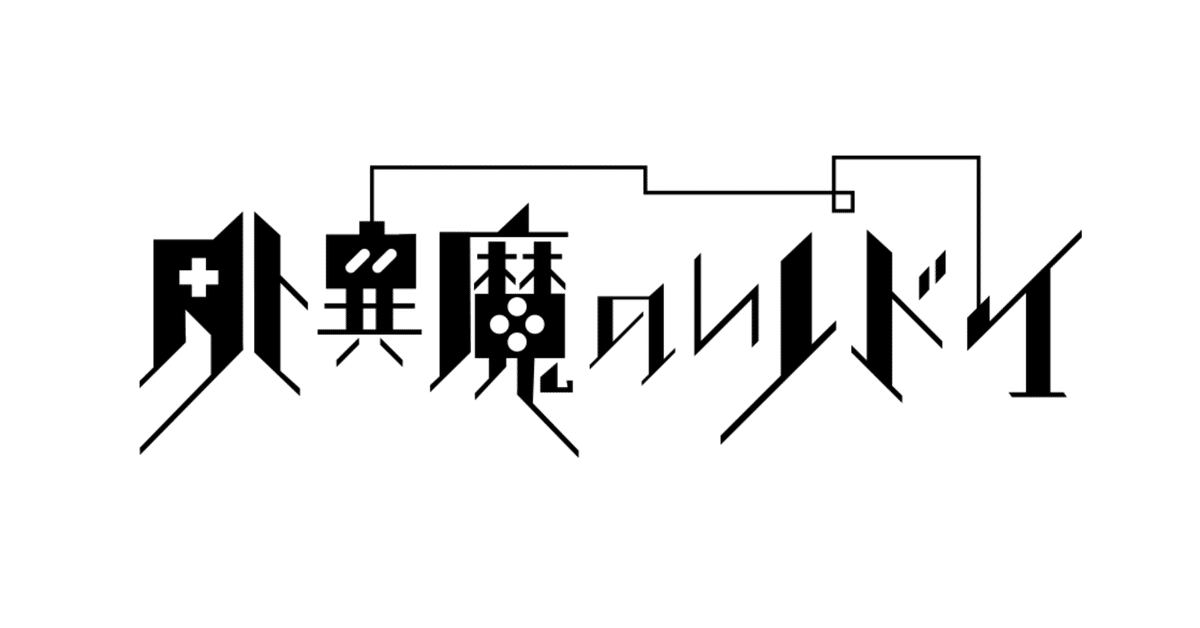
【小説】外異魔のツドイ #1
うっかり季節をひとつとばしたような暑さだった。
六月に入ってから振り続けた雨がようやくあがり、東京の各区で記録した降水量と、今年初の真夏日になりそうだという予報が、朝のニュース番組を賑わせた。ついでに、今年の夏は例年以上に暑くなる見込みらしい。この時期になると毎年誰かがそんなことを言っている気がするが、それが常に当たれば東京はいつか人が住めなくなる。
昼休み前の授業はホームルームだった。凪渚は担任の話を真面目に聞くふりをしながら、教室の窓のぴったり閉じられたカーテンを眺めていた。目を凝らすと、熱気の立ち込めるグラウンドがくっきり見え、そこで授業を受ける生徒たちがぜいぜい言っているのが聞こえてくるようだった。実際目に写るのはその薄い布で、耳に入るのは担任の声だが、それがわからなくなるくらい今日の太陽は張り切っている。
そうやって日差しの透けたカーテンをぼんやり見たり、昼食にうどんと蕎麦のどちらを食べるか悩んだりしていたら、授業終了を知らせるチャイムがなった。どうやら五十分間喋り続けていたらしい担任が、教卓の上でファイルや名簿をまとめながら「今週金曜日に回収するので、それまでに記入してください」と言った。手元の配布物に目を落とすと、それは『第一回進路希望調査』と書かれたプリントだった。つまり担任の話も大方そんな内容だったのだろう。
この春に高校二年生になってから、高校卒業後の進路や将来何を目指すかという類のことを聞いたり考えたりする授業が何度かあったが、どのときも、渚の心はそこになかった。将来のことを、考えていないわけではない。ただそこに楽しみが見つけられないだけだ。自分の人生が救いようもないほど不幸だとは思わないが、明日が待ち遠しいと思うことは一度もなかった。十年前のあの日から、今日までずっとそうだった。
顔を上げるとすでに担任の姿はなく、生徒たちの声や椅子と床がこすれる音で教室が賑わっている。
渚はプリントを通学カバンにしまうついでに財布を取り出し、席を立った。
渚が食堂のカウンター席で蕎麦をすすっていると、紗織が隣の席に座り、サンドイッチの封を開けながら「学食来るなら声かけてよ」と言った。箸をおき、広く使っていたカウンターを片付ける。顔の前で手のひらを立て、口の中のものが全てなくなってからようやく「ごめんごめん」と返した。
紗織は唯一友人と言えるクラスメイトだ。学校で同級生たちと積極的に会話をしない渚となぜか話したがり、よく声をかけてくる。初めこそ意図のわからない行為に戸惑ったが、不思議とすぐその関係に馴染んだ。一度、なぜ自分に話しかけるのかと紗織本人に聞いたことがあるが、返事は「なんとなく」だった。未だその真意は不明だが、紗織の性格がわかってきた今、本当に「なんとなく」だったのかもしれないと思う。
身のない話題で談笑していると、紗織がそういえばと切り出した。
「さっきのあれ、なんて書くの?」
あれ、とはおそらく先ほどの授業で配られたプリントのことだろう。渚がどう答えようか言葉を探していると、それを見て質問の意図が伝わっていないと思ったのか、紗織は折り畳んだ紙を渚の目の前でひらひらと振って見せた。受け取って開くと、やはり『第一回進路希望調査』だった。記載された内容を確認するふりをしながら「紗織はなんて書くの?」と質問で返す。記入欄はまだ空白だった。
「”中央区で就職いたします”かな」
「やっぱり、中央区なんだ」
「うん。渚は?」
「私も同じこと書こうと思ってた」
渚がそう言うと、紗織は心から安心したという顔で「よかったぁ、一緒で」と言った。
近年、渚たちが住む東京では働き手が不足しているらしく、就職を希望すればそれだけで進路が保証される。教師たちは生徒に「高校卒業後は東京で就職するように」と説く。そのためほとんどの学生は義務教育である高校を卒業すると同時に働き始める。中には進学する者もいるようだが、極めて稀な例だと以前担任が言っていた。
今回提出を求められた『第一回進路希望調査』も希望の勤め先を記入させるような文言になっていたが、あるいは「就職」以外の回答をする異端者を把握するための調査なのではないか——と渚は考えていた。
紗織はこういうところで働きたい、あんなところに住みたいという将来像を楽しそうに話したが、渚はその間ずっと居心地の悪さを感じていた。友人が素敵な夢を抱くのは大いに結構だが、その話題に付き合えるほど渚は自分の交友関係に前向きではない。紗織には申し訳ないと思いながらも、会話が途切れるのを待ってから、他の話題を出す。
「ねぇ、紗織。少し前に変なメールが届いたんだけど、見てくれない?」
スマートフォンの画面にそのメールを開いて手渡す。
「へぇ、なになに」と紗織は一瞬好奇の目を向けたものの、冒頭の数行を読むとさっさと下までスクロールしてしまう。「何これ、ただの詐欺メールじゃん」
まるで予想通りの反応だった。ひとまず話題を変えることには成功したが、紗織はすでに興味を失くしているように見える。
「私もそう思ったんだけど、気になることがあって……」
話題を元に戻したくないというのが本意ではあったが、渚がそれをよくある迷惑メールだと思えない節があるのは本当だった。
メールを受け取ったのはちょうど一週間前、なかなか寝付けずに布団の中で何度も寝返りを打っていたときだ。
午前二時ぴったりに受信したそのメールは、<凪渚様 シェアハウス集い荘の新規オーナーにご当選されました>という件名だった。普段なら開封もせず削除するような内容だったが、それはなぜか渚の興味をそそった。宛名が本名だからか、他の何かか、理由はわからない。
メールには、『集い荘』というシェアハウスが新しいオーナーを募集していること、その抽選に渚が当選したこと、オーナーになりたければ七日以内に返信するように、ということが書いてあった。
もちろん、そんなものに応募はしていない。つまりどこをどう読んでも怪しいのだが、一つ気になることがあった。
メールの内容だけでは、オーナーになるとどうなるか、わからないのだ。具体的に言えば、オーナーになるとこんな利益がありますよ、という記載がない。人を騙すつもりなら、何かしら”エサ”を用意するはずではないか? それが渚にはどうしても引っかかった。
同じメールを受け取った人が見つかるかもしれない、と思いインターネットで検索すると、『集い荘』のホームページらしきものが見つかった。
早速ページを開くと、『集い荘』のロゴが画面いっぱいに表示された。誰でも作れそうな、文字をただ楕円で囲っただけのロゴだった。あとは軽いモザイクをかけたような画質の——『集い荘』の内装と思われる写真が数枚あるだけで、シェアハウスの詳細や肝心のオーナーについては書かれていなかった。以前妹の汐が小学校で作ったと自慢してきたプロフィールページの方がまだ親切なページだったと思う。
その粗末さに渚は心底がっかりしたが、よく見ると写真の下に小さな文字で住所が書かれていた。渚の自宅がある南区の住所だった。それも自宅や学校から徒歩で行けるような距離だ。
偶然、見知った土地の名前が書いてあるだけだ。そう思いながらも、何か、見てはいけないものを見てしまったような感覚があった。事件に巻き込まれているのでは——。そんな恐怖と純粋な好奇心がが足並みを揃えてじわじわと迫り、その夜はまともに眠れなかった。
渚がその一連を話し終えると、紗織はにやにやしながら「やっぱりね」と言った。
「やっぱりって、何が?」
「渚って頭はいいけど、案外騙されやすいタイプなんじゃないかと思ってたんだよね」
「でも、こんなに近所だったらさすがに気にならない? 件名も名指しだったし」
「その住所、スマホのマップで確認してみた?」
「……してない」
そう言うと、紗織にまた「やっぱりね」と言われた。なるほどこういうところが「案外騙されやすいタイプなんじゃないか」に繋がるらしい。
スマートフォンでマップアプリを開き、例のページに記載されていた住所を検索する。表示形式を地図情報から視覚情報に変更すると、画面表示が実際その場に立っているような視点に切り替わった。
該当する住所には、しっかり建物があった。あったのだが、それは小さな木造の平家で、見た目にはごく普通の——というには小さすぎるくらいの一軒家だった。マンションやアパート、何かの施設であれば建物名も地図上に表示されるはずだが、その位置にはピンが立つだけで、<シェアハウス>とも<集い荘>とも表示されなかった。
一緒に画面を覗いていた紗織にも「さすがにこれで”シェアハウス”は無理あるでしょ」と言われ、納得する以外の選択肢がなかった。
ただ——。
いつでも行ける距離にあると思うと、どうにも気になるものだ。メールを受け取ってから今日まで、常に頭の片隅にあった。それが紗織に話したことで掘り起こされ、マップを見たことでいよいよ無視できないくらい輪郭がくっきりしてしまった。
渚は午後の授業を受けている間、気づけば脳内で地図を開き、学校から『集い荘』までの道のりを何度も歩いていた。
幸い、週に五日出勤しているアルバイトが休みの日だった。全ての授業が終わると渚はすぐに帰り支度をした。日差しは少しも傾いておらず、学校を出ると一瞬で全身に汗がにじんだ。セーラー服の上に羽織っていたカーディガンを脱ぎ、カバンにしまう。異常な暑さに心の中で悪態をつきながら、”例の住所”に向かう足取りはスキップをするように軽かった。
学校から徒歩三分ほどのところにある商店街のアーケード通りを抜けると、細々した住宅街に出た。建っているのは一軒家やアパートばかりで、背の高い建物はない。家と家はぴったり寄り添うような間隔で並び、隣家に面している窓はみんな揃って雨戸が閉じられている。道幅は狭く、車一台通るのもやっとだろう。初めて来た場所だったが、同じ南区内に住んでいる渚にとっては見慣れた街並みだった。
南区の中でも特にこの一帯は戦争の被害が少なかったため、以前の建物がほとんどそのまま残っている。戦後急激にテクノロジーが発展した東京で、南区のそんな景色は大人には懐かしく、若者には珍しいようだ。通ってきた商店街も東京で一番古く、他の区から買い物に訪れる者もいるらしい。そういう話を聞くたびに、人はどこに住んでいても満たされないんだな、と渚は思った。
ひときわ細い路地に入ると、突き当たりにそれらしい瓦屋根が見えた。学校からここまでは徒歩で二十分ほどだったが、暑さのせいか数時間も歩き続けたような気分だった。マップを開いていたスマートフォンをスカートのポケットにしまい、手の甲で額の汗を拭う。
近づいてみると、その建物はやはりシェアハウスには見えなかった。
まず、どう見積もっても小さすぎる。四人で慎ましく暮らしている渚の自宅よりもはるかに狭そうだ。敷地も細く奥まっているため、まるで家と家の隙間を埋めるために建てられたように見える。
造りはかなり古そうで、いたるところが劣化しているのが見た目にもわかる。屋根に取り付けられた雨樋はところどころ外れてだらしなく垂れ下がり、家を囲むように植えられた低木も長い間手入れはされていなさそうだ。お世辞にも綺麗とは言えない建物だった。
そんな外観のせいで、全くそこに目がいかなかったのだろう。ドアの横にかけられた表札のかすれた文字が『シェアハウス 集い荘』と読めることに気がついたのは、無駄足だったという事実を認めて引き返そうとしたときだった。
ここが本当に『集い荘』なら、あのメールも、渚がオーナーに当選したというのも、本当なのかもしれないと思った。むしろそれが嘘なら、何のために送られたメールなのか。
——入ってみようかな。
好奇心には逆らわないというのが渚の行動方針だ。非常識だということは理解しつつ、迷う時間はそれほど長くなかった。
オーナーになるか、と聞かれればもちろん返事は「いいえ」だが、メールの真意は気になる。それに、ここは人が集まって暮らすシェアハウスで、メールを信じるのであればオーナーになる権利を渚は持っているはずだ。入った途端に命を取られるなんてことはない。と思う。
周りに人がいないことを確認し、敷地に入る。
敷地内は砂利が敷かれていた。入り口に続く飛び石があるものの、ひび割れや欠けているものが目立つ。足元に集中していても、一歩ごとにパリッ、ピシッと何かを踏む音がなった。
ドアの前に立つ。鼓動が速い。まるで体の中から心臓を小刻みに叩かれているようだった。大きく吸った息を吐き出すのと一緒に「よし」と小さく声に出し、自分を奮い立たせる。
探して初めて気がついたが、この建物にはインターホンがない。仕方なくコンコンと弱めにドアをノックする。ゆっくり十秒数えても反応はなかった。ドアノブに手をかけゆっくり回すと、鍵はかかっておらず、そのまま手前に引くと簡単に開いた。
恐る恐る中を覗いてみると、薄暗いそのリビングのような部屋に人影はなかった。誰かが近づいてくる様子もない。
「……すみません」
声をかけても返事はなかった。シェアハウスというのは、得てしてこういうものなのだろうか。勝手に開けておいて言える立場ではないが、さすがに無用心ではと思う。
「どなたかいらっしゃいますか」
今度は部屋のさらに奥まで届くよう意識してみたが、やはり誰も来ない。
シェアハウスでも、無許可で入れば住居侵入罪になるだろうか。いや、何かあればあのメールを見せて「オーナーになれると聞いて来た」と言えばいい。大丈夫、私は悪いことをしていない、と根拠のない免罪符を自分に言い聞かせる。
渚はそっと部屋の中に入り、素早くドアを閉める。
足元を見る。玄関がない。フローリングの床にスニーカーで立っていると、足の裏がそわそわした。小さく「お邪魔します」と言うと、反響した自分の声が何重にもなって聞こえるようだった。
あらためて部屋を見回すと、外から見るより広く、天井も高く感じた。簡単に「気のせい」で片付けられない程度には違和感がある。
渚が背にしている出入り口の正面、部屋の中央にベージュ色のソファがある。三人がけくらいの大きさで、ソファと同じ色の四角いクッションが二つ乗せられている。背もたれにはたっぷりと厚みがあり、座り心地のよさそうなソファだ。
部屋の奥にはL字型のキッチンが備え付けられている。ソファの脇を通って四つ口のあるIH式コンロの前に立ってみると、何人か並んでも広々と使えそうなスペースがあった。しかしここには使用者がいないのか、はたまた几帳面に片付けられているのか、調理器具などは一つも置かれていない。深めのシンクや壁の白いタイルも、新品のように綺麗だ。自宅でたびたび台所に立つ渚にとって、まさにそれは憧れのキッチンだった。
あとは壁際に渚の背丈ほどの棚があるだけだ。その棚にも物は一切置かれておらず、部屋は全体的にがらんとしていた。キッチンの横に擦りガラスのはめられたドアがあったが、その先には入居者の部屋があるのだろうと思い、開けるのはやめておいた。
全く生活感がないのは気になるが——外観から受けるイメージとは裏腹に、そこは確かにシェアハウスの住人が使う共用スペースのようだった。少なくとも、渚にはそう見えた。
渚が部屋を見て回っている間も、自分の足音以外に物音はしなかった。
今この部屋に建物の関係者が現れれば、穏便に済むかわからない。現れなかったとして、後からバレないという保証もない。それならこのまま帰るより、誰かが帰宅するか部屋から出てくるのを待って、事情を話すほうが得策ではないか。
それに、ここまで踏み込んだのなら答え合わせがしたい。
三十分待って何もなければ帰ると決め、中央のソファに腰をおろした。ソファの座面や背もたれは、見た目の印象よりやわらかかった。目を閉じると全身が何かに包まれているような、水に浮いているような、不思議な感覚になる。ふーっと深く息をつくと、どこまでも体が沈んでいくようだった。
気を抜くとこのまま居眠りしそうだ。さすがにそれはまずい。重い瞼を持ち上げ、スカートのポケットからスマートフォンを取り出す。時刻は午後四時を少し過ぎたところだ。ふとネットワークの接続状態を見ると、そこには<圏外>と表示されていた。東京で圏外になる場所なんて、聞いたことがない。今どき地下でも電波が入るのに——と怪訝に思い、顔を上げた瞬間。
渚が入ってきたのと同じドアがガチャリと音を立てて開き、背の高い細身の男が現れた。男は渚と目が合うと驚いたように一瞬動きを止めたが、すぐに「どちらさまですか?」と言いながら後ろ手でドアを閉めた。両手にビニールの買い物袋を持っているところを見ると、おそらくここの住人だろう。
渚はいきなりのことに返事ができず固まっていると、男がすぐそばまで来て、
「もしかしてオーナー希望の方ですか?」
と言った。男はよいしょとフローリングに両膝をついて座り、買い物袋を両脇に置く。
あのメールは本物だったということか。
渚はしばらく言葉が出てこなかったが、男は何も言わず、上目遣いの笑顔をじっと渚に向けていた。
渚がここに来た経緯を説明している間、男は「うんうん」「なるほど」としきりに相槌をうった。
よく見ると男は端正な顔立ちをしていた。切れ長の目にスッと通った鼻筋、控えめな厚さの唇は血色もいい。白い無地のTシャツにグレーのパーカーを羽織り、ズボンは黒いスエットというカジュアルな服装だ。今は床に膝をつけているが、先ほどの立ち姿からしてかなりの高身長と見受けられる。無造作に伸ばされた黒髪にはところどころ寝癖がついているが、それも男の容姿によく馴染んでいる。歳は二十代半ばくらいだろうか。
渚は話しながら、帰ってきたのがこの人でよかった、と場違いなことを考えていた。不法侵入者である自分の話を聞いてくれている。怒るでも怯えるでもなく、笑っている。きっといい人に違いない。おまけに顔も好みだ。
渚の話が終わると、男は「すいません、早とちりして」と言って頭を下げた。
「こちらこそすみません。勝手に入ってしまって……」
「いや、ぜんぜん大丈夫ですよ」男は笑い、「僕、ここの管理人です。初めまして」と言った。
こんな若そうな人が管理人ということに驚き、オーナーと管理人だとどちらの立場が上になるんだろう、と思った。学生服姿の渚を見て真っ先にオーナー希望かと聞いたということは、そこまで重要な役職ではないのか。そもそも、このシェアハウスにはどれほど住人がいるのだろう。キッチンやリビングの綺麗さからして、たくさん人が住んでいるとは思えない。
何も言わない渚を見かねてか、男はもう一度「初めまして」と言って右手を差し出した。
渚はそれを聞いて我に帰り、男にならって右手を出し「初めまして」と返す。
緊張しながら男の手を握ると、それはまるでプラスチックだった。無機質で、体温がない。
渚は咄嗟に手を離し、男の顔を見た。
まさか——。
「あ、気がつきましたか」男は表情を変えずに言った。「僕、外異魔なんです。見た目じゃわからないでしょ?」
外異魔——。それについて、渚の知識は少ない。
知っているのは、それが人間でも動物でもない”何か”だということ。
十年前、どこからともなく現れたそれらと、人間が争ったこと。
その戦争に、両親が殺されたこと——。
渚が何も答えずにいると、男は引っ込めた右手で頭頂部の寝癖を撫でつけながら「へへっ」と笑った。困ったような、悲しそうな顔をしていた。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
次 ▶︎ 第2話
小説「外異魔のツドイ」
原案:KC
小説:ヌゥ
※小説「外異魔のツドイ」はフィクションです。
実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
