
一人の越境が組織を変える「これからの時代の組織をいかにつくるか」vol.4 イベントレポ
「これからの時代の組織とは?~組織システムと個人の相互発達~」をテーマに、「これからの時代の組織」を探究している全4回の本シリーズ。
ラストを飾る第4回は、「越境学習」がテーマです。個人が組織からはみ出して活動する重要性や効果、ゲストの方々の実際のご経験を伺います。
「個のための組織」時代のメンバーと組織の関係性
岩波:現在、とても大きなパラダイムの変化が起きています。今までは「お国のための個」、「企業のための個」、等と「組織のための個」という認識で、組織・社会システムを作ってきました。たしかに、これまではその方が都合がよく、働く人は給料が増えて、生活が良くなっていきました。

本シリーズ全4回モデレーター:岩波 直樹(株式会社eumo 取締役)
しかし、科学や技術の発達と、人の価値観の変化によって、今は「個のための組織」の時代がきています。この流れはコロナによっても加速しており、おそらく、この流れは変わりません。そのため、「個のための組織」という時代において、どのように人と組織を作り上げていくのかが非常に重要になります。

「こんなことをしたい」個人の欲求が元になって、そこに「一緒にやりたい」「手伝うよ」と共感が生まれ、人が付いてきて、結果として組織やネットワークになっていく。そんな時代に、入っているのですね。
一人ひとりの意識構造や価値の捉え方の変化によって、その人たちが作り出す組織の仕組みが変わっていきます。一方で、仕組みや文化、その時の常識も人の意識構造や価値の捉え方に影響しています。この両輪が重要です。ちょうどこのシリーズのの第3回の山下さんは前者を、第2回の武井さんは後者を語ってくださったことになりますね。

越境による4つの効果
さて、こういった時代に必要になってくるものとして、今日のテーマに掲げているのが「越境」です。個人が組織を越境していくと、個人と組織それぞれの認識の発達を促します。

自分の認識を拡大し、発達していくためには、自分の見えている世界と異なる世界が見えている人と接する、違う文化に触れてみる、そういった自分の価値観ではないものと触れることが必要です。
また、自分の会社だけで可能なことが今とても少なくなってきているのも注目すべき点です。
自社の範囲を超えた社会問題に対し、会社の壁を越えて、会社同士で役割を分担できるようになれば、結果として、社会問題へのアプローチができたり、そのネットワークの存在そのものによって社会課題そのものが解決したりできます。壁を超えて横でつながり合うことで、問題の根源みたいなものが薄まってきます。
さらに、社内の問題においても、これまでのパラダイムの延長線上では解決できない問題が増えてきています。こうした問題においても、企業同士で壁を超えると問題の解決ができることがあります。例えば、企業同士でサービスを提供し合ったり、ある時期は社員を共有し合ったり、そうした企業連合的な意識が、非常に重要になってくると思います。
今までは、どちらかと言えば、参入障壁を作って、自社の独自のやり方を生み出して、それを隠し通して、自社が一番儲かることを優先する時代でした。これからは、その壁を解放していくことが大切になってきます。そういったことをやっていると、意味の創造、まさにイノベーションが生まれてきます。
越境が個人にもたらす効果としては、内面の深まりや全体性の獲得も挙げられます。

こういった効果を最大化するためには、場の作り方が重要です。内在的自己、つまり、「本当の自分でいられる」状態が必要です。現代人はいつも何かの相対価値に脅かされ、鎧を着ています。「自分はこんな風に出来ている」と見せなくてはいけない認識の中で生きていることが多いです。越境をして、対話したり、内省したりする際は、内在的自己でいられる場、良質なエネルギーの場があることが重要です。
「社員の越境」を具体的に考えてみる
ただ、こうした越境の効果が生まれるために、乗り越えないといけない壁があります。自社の社員を自社の利益のみに貢献させようという認識で育てようとしていると、越境させる意味はあまりなくなってくると思います。
不確実性のマネジメントや今までにない価値を生み出すことが求められるとき、いろいろな世界を認識している、いろいろな世界を知っている、いろいろなつながりを持っている、そのような社員が多ければ多いほど、そういった領域で創造できる可能性が増えていきます。
越境の際、重要なのが「実際に関わること」です。一緒に働いて、具体的に何か一緒に価値創造してみないと、価値観の根本的な違いや暗黙知に触れられないのです。

現代社会でこれから生きていくためには、 エコノミックキャピタルだけに頼っているとますます生きづらくなっています。お金だけに頼り続けると、常にお金の不安に追い立てられたり、お金で何かを動かしていく方法しか取れなくなったりします。
一方で、複数のコミュニティに属し、自分の足場が出来てくると、3つの資本*1のバランスが取れ、生きやすくなったり、やりがいを感じる仕事が増えたりします。

*1 3つの資本 (エコノミックキャピタル・ヒューマン・ファンダメンタルズ・キャピタル・ソーシャル・キャピタル)
実際に関わっていくことで、価値のようなものを感じられるようになり、そのコミュニティの価値創造に貢献ができると、コミュニティからも必要とされてきますね。
企業にとっても、組織に共感した自律した人が増えた方がサステイナブルでレジリエンスの強い組織にもなってきます。だから、そういう場を会社として作ったり、自分がそういう生き方をしたりして、越境の機会を少しずつ増やしていくことが重要です。
岩波さんから越境が必要な背景や効果についてお話しいただきましたが、
実際に、越境を体験した方々はどのように越境をみているのでしょうか?
西坂とゲストのお二方に越境体験について話を伺いました。
被災地・女川でひらめいた越境プログラム
西坂:これまで組織は基本的に求心力で作ってきました。特に理念型の経営は、求心力を大切にしていて、画一的になってきます。これからは、真反対の越境やオープンな組織制度等、遠心力が重視される方向に世の中が変わっていくと思っています。しかし、私たちはその経験をほとんどしたことがなく、ベストプラクティスを持っていないのです。新しい時代に変わっていくのですから、立ち行かなくなる前に、試行錯誤してベストプラクティスを見つけないといけません。個人においても、会社においても、チャレンジしないことはリスクだと感じています。

パネラー:西坂 勇人(GCストーリー株式会社 代表取締役)
女川町は、日本で最も震災の被害が大きかった街です。街の8割が流される程の被害を受けました。行ってみると、街の人たちの当事者意識、内発的動機がとても強いように感じました。例えば、温泉に入った時、老年のお二方が「どうしたら女川に人来てくれるかな」と話をしてるのですね。女川は6000人ぐらいの街ですが、その規模の街の人たちが街全体をのことを本気で考えてる様子を目の当たりにしたのです。内発的動機のある組織の1つのモデルがここにあるなと思いました。
西坂の越境体験から出来上がったGCストーリーの女川リトリートプログラム。
当プログラムへの参加経験があるゲストにご自身の越境体験についてお話しいただきました。
ゲストの越境体験①越境による不安や葛藤が変化を生む

ゲストパネラー:佐々木義郎さん (株式会社ダイブ 人事部 部長)
佐々木:当時、一気に社員が増えたことで、各チームごとのカルチャーが出来上がってしまい、部署間での歯車がうまく回らなくなっていました。全社横断の施策を実行してもなかなか長続きはせず、人と組織が変わらないと苦戦をしていました。そこで今回、GCさんの女川プログラムに参加することになりました。

私としては、一番良かったと思うのが、夜の交流の場です。
多くのメンバーがカルチャーショックを受けていました。本当に街の方々の熱量に圧倒されていました。街の方々の一人称が、「自分」ではなくて「街」になっていましたね。メンバーから「なんでこんな想いでやってるんですか」等と、質問が飛び交っていました。

翌日に、実際に「自社」「自チーム」「自分」という視点を持って、俯瞰的に自社のことについて考えてみました。
こういうワークは自社でやってはいました。しかし、当たり前のように思っていたチームのカルチャーや自分の考えすらも、課題として出てくるようになっていましたね。

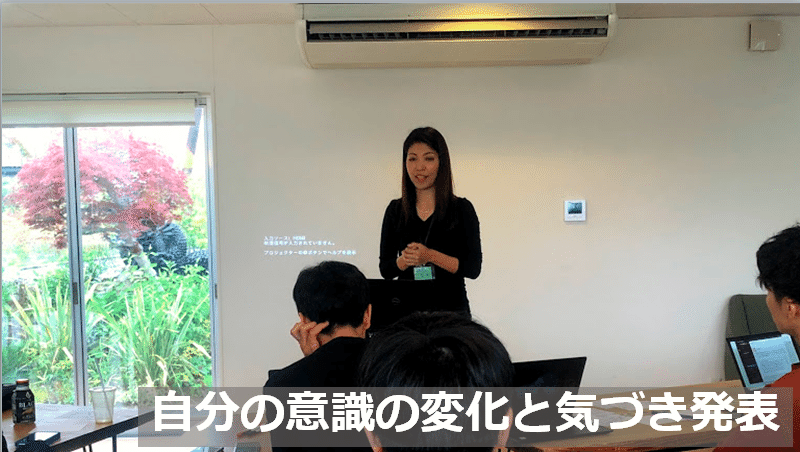
ある女性社員のエピソードを話させてください。
彼女は、街の方が「個でなくて全体」や「自分でなく利他」と話されている様子をみて、「自分の人生これでいいのだろうか」と危機感を覚えたみたいです。「自分のチームが、実は他のチームことを考えてない」等の課題を感じ、「もっと自分ではなくて他にベクトルを向けて、チームを支えて会社を変えていきます」とこの場で話しました。それから実際に全国の支部をまわって、「他のチームのために自分に何が出来るのか」と他のチームの課題を吸い上げて改善をしていくと、他の人も行動をし始めたのです。同じチームのメンバーも同じように動き始めて、組織間の良いコミュニケーションが起こる変化がありましたね。

研修で感じたことは、スキルや行動など、一部分を変えても持続しないということです。根本的な部分が変わらない限り、会社としては連動しません。ところが、街のために生きる方々の異なる価値観に触れ、一人の女性の価値観が変わりました。それから、社員の研修も社内でするのではなくて、場所を変えてやろうと意識をし始めました。人は無意識的にそのチームの暗黙のルールや価値観に染まってしまうのですね。

日常の場所から離れる体験をすると、どこかで「自分はこれでいいのかな」というような不安や葛藤を感じると思いますが、この不安や葛藤が今回の一人のメンバーの行動を変えて、結果的に組織が変わっていったので、やはり会社の組織を変えるにあたって、個の変化が大切だと思いました。
ゲストの越境体験②越境は思い込みや現状維持思考をほぐす

ゲストパネラー:阿部章さん (株式会社 パルサー代表取締役)
阿部:越境体験として、一つは私個人に関して、もう一つは会社の社員に関してお話しますね。
私は EO north JAPAN という経営者の集まりに入っています。成長意欲はかなり高く、先進的に組織づくりに取り組む経営者が多く所属している組織になります。
一年前に入ってからいいなと感じていることは、新しい組織に入ったり、新しい人たちと関わったりして、気づきを得られたり、情報知識を得られたりすることですね。それらによって、新しい展開を思いついて、とても積極的に行動したくなります。逆にそれがないと、とても積極的には行動に移りません。現状維持しようとする意識が働いている感じを受け取っています。具体的に実践をしているたくさんの人を見て、「これって自分がしたかったことじゃん。」と人を幸せにする具体策が見つかり、行動したくてしたくてしょうがなくなります。
二つ目の社員の越境についてです。10社100名ほどが集まった「幸せって何だろう」という切り口の(固定観念を払拭する)セミナーに参加しました。それが、うちの社員とっては大きな刺激になっていて、「変わらないよね」という思い込みが払拭された感じがありました。
私も社員と女川に行ったのですが、女川に行ったメンバーが社内に向けて伝える言葉と、社外の人から聞く言葉は、言葉の意味自体は同じでも、誰が言うかによって伝わり方が全然違うのですね。「この人もこう思ってるんだ。うちの会社で言ってることは、確かに意味があると考えていいのかもしれない」と考えるようになります。腹落ち感、納得感が越境をすることで得られましたね。
イベント参加者のみなさまへのお礼
4回のシリーズにわたり、組織と個人の相互発達についてお届けして参りました。いかがでしたでしょうか?
今後とも私たちGCストーリーは、「越境」に関するプログラムを打っていこうと考えております。社外留学、研修体験、リーダーのアドバイス術勉強会、女川リトリートプログラム等、現在、構想を鋭意検討中です。詳細が決まりましたら、またご紹介させていただきます。
改めて、この度は大きな歴史の転換期にみなさまと一緒に未来を考えるお時間を過ごせたことに心から感謝を申し上げます。みなさまとともに、それぞれが考えるステキな組織、社会をつくっていけたらうれしいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
▶第三回までのイベントレポートはマガジンからどうぞ。
