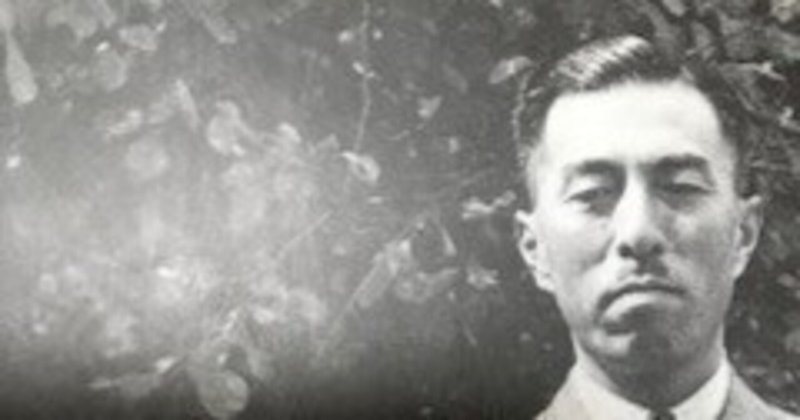
仏印”平和”進駐の『第2次近衛内閣』総理大臣・近衛文麿のこと その②
その① 仏印”平和”進駐の『第2次近衛内閣』総理大臣・近衛文麿のこと その① からの続きです。
第2次近衛文麿内閣の外務顧問だった斎藤良衛氏の著書『欺かれた歴史』(1955)には、この当時の外交方針は2つあり、「軍部懐柔のための表面的方針」は「国策決定文書等の文書となって残っている」が、もう一つの「隠密の方針」は「漏洩がもたらす恐ろしい結果を慮って、文書には全然載せず」「近衛と松岡だけのふくみにとめられ」、「閣僚にさえ知らされなかった」。そして、「近衛と松岡が死んだ今となっては(松岡外交の全貌を)知る者は、私以外にはない」と言っています。
そうならば、戦前の記録文書として戦後第一級史料として扱われ、あちこちで参考にされ、証拠とされる記録や文章は、上述の「表面的方針」であり「近衛と松岡が表面上取った方針」である可能性が濃い筈です。これに関して斎藤博士も、
「終戦後外交文書の少なからぬ部分が、連合国側に押収され、何らかの形で、その内容がかなりに多く公表されている(中略)しかるに外交官のベテランや、外交問題の権威者たちの著述を読んでみると、(第2次近衛内閣の)松岡外交についての記述や見解にはなはだしく間違っている部分がある。これらの人々は別に嘘をつくつもりで書いたのではないことは、わかりきっているが、それを訂正するなり補足するなりしておかねば、誤った事柄が後世まで伝えられることになる。」
こうおっしゃっています。その為、以下に斎藤良衛博士のみが知っていたという第2次近衛内閣外交の「隠密の方針」を見て行きながら、公けの文書から作られた戦後(当然今現在)の近衛文麿像(と松岡洋右像)とどう異なるか検証したいと思います。。。
まず、大前提として当時の日本上部の実態確認です。
「侵略方略のための軍部の傍若無人ぶりは、第2次近衛内閣時代よりもずっと以前からはじまっていたことはすでに幾度も述べた」
「例を仏印進駐問題にとってみる。広東を占領した軍部は、早くも仏印からタイ、タイからスマトラ、ボルネオへと、石油、錫、ゴムの莫大な資源地獲得のための南方進撃を図った。」
斎藤博士は、「第2次近衛内閣のずっと以前から、何故陸軍がこうも乱脈になったかの理由」として、
「時勢の推移というものもあったが、大きなものは人的関係である。軍部、なかんずく陸軍に豪い統率者があって、部下を十分に引き締め得た時代には、軍事と外交とのけじめは立派に保たれ、外交一元化が実現された。高島、山県、川上、桂などの睨みが陸軍に大いに利いた時代がそれである。これはむろん文官側に伊藤、陸奥、小村、後藤、原といった傑物がいて、軍人にあまく見られるようなことをしなかったことにもよる」
要するに、国家とは常に微妙なパワーバランスで以て国力と国防を辛うじて保っているが、このバランスが崩れればいとも簡単に一方に傾いてしまい新しい全体主義に走って行くということでしょうか。。。
そう考えると、私は最近知ったんですけど、欧州では1950年代頃より、次に台頭する『新全体主義』を『エリート官僚、技術官僚による全体主義』と予想してずっと警告を鳴らしている研究者の方々がいるそうです。
そうかぁ、そうですよね。武器がハイテク化すれば、ハイテクを制す者の一強となりパワーバランスが崩れ、ハイテクを制した者による全体主義の始まりは、私のような田舎の主婦にも理解できる程如何にも単純な理屈に聞こえます。でも、あれ、💦 あの頃の帝大卒の超エリートの軍人の皆さまがこれを解らなかった?? やはり「全体主義」には一種の魔力があるのか、、、恐るべし。💦💦
何れにせよ、パワーバランスの崩れが一方の全体主義化を招き、支配・弾圧、挙句に対外戦争へと繋がってしまうとすれば、まあそんな心配は無用かも知れませんが、近年の日本もエリート官僚全体主義の発生に気を付けないとです。。。😅
「かかる軍部の統制の保たれたのは、上原(勇作、元帥)が参謀総長だった時代までで、それ以後、軍の統制はだんだんと乱れて、下剋上が年々ひどく」なり、そして「軍の下剋上は、外交にもそれを移した」そうです。
「第2次近衛内閣はこうした時代にでき」ました。
「…近衛も松岡もしばしば若い軍人の面詰にあった。それがしばしば痛い目を覚悟して(中略)近衛も松岡もみな用心棒をかかえていたが、5人や3人の武道家も、青年将校の団結力の前には、まったく無力に見えた」
「歴代内閣は、これに気づかぬほどの馬鹿では無かったのだが、思い切って体当たりするだけの気力も実力も持っていなかった」
この「気力も実力も持っていなかった」歴代内閣の首相のお一人に近衛文麿氏も数えられるのですが、、😅
でも、近衛氏の前後に沢山の数の総理大臣就任者がおり、その皆さん殆どが数か月の短命(数か月)政権という残念な感じで、その中にあって当時の近衛氏と松岡氏は至って普通、いや逆に頑張った方なんじゃないか?と、私も斎藤良衛博士と同じ印象を私も持ちましたが、どうでしょうか。
だって、当時はですね、
「…行き詰った日本の前途打開が、軍事力を背景とせねば不可能だと考えたものもあって、外交官出身者の間にすら、それが皆無ではなかった。軍はいつもこうした連中を拾い集めて傘下に収め(中略)、おだてて引っぱり、握手して、侵略主義の片棒をかつがせた。(中略)この時代から終戦頃までに、すばらしく早く出世したり、一文なしからちょっとの間に千万長者になった者の少なからぬ部分が、侵略主義の片棒担ぎであった」
現代にも劣らぬ(笑)忖度一色の状態は、「知る人ぞ知るであった」と言います。「具眼の士」もいたが、「いつとはなしに権勢から離れるか、または殺され、もしくは自殺し、犬養毅が話せばわかると叫びながらあの世へ送られたのも、2.26事件で高橋是清が非業の最期を遂げた」のも、「2人とも軍部の思う通りにならぬ硬骨漢であったから」だと言います。
当時はまあ、なんとも物騒な日本だったのです。。。
こんな状況の中で、まだまだ人材が豊富だったうちは軍部と争って潔く死ぬという選択肢も残っていた。けれど、味方との諍いで命を落とすより日本を戦争の泥沼に沈めぬ為にと、近衛氏は松岡氏と共に上述の「表面と隠密の2つの外交方針」を立てることに決めました。
「斎藤内閣(第30代斎藤実内閣、元海軍大臣)以降の日本の政府は、みな軍部と協調して来た。軍部の主張する政策に危険があるとみれば、政府は危険を少なくするか、または施行を引き延ばすことにつとめてきた」
『近衛手記』より
近衛氏の『近衛手記』から⇧この文章を引用し、斎藤博士は、「事実は妥協でなく降伏である。」と述べ、
「第1次近衛内閣崩壊直後、私は虎ノ門の霞山会館に彼を訪ねて、軍部の侵略主義の危険を説いて、彼の奮起を求めた」にも拘わらず、近衛文麿氏は、総理の重任から退いたばかりの気のゆるみからか、何となく元気なく、「軍人のやり口に横やりを入れることは、命がけの仕事だ」といって逃げを打ったと少々批判をしています。
そして、こうしたやり方は、「果たして軍部の暴挙を少しでもとめ得たか」と問い、答えは「否、少しも止め得なかったばかりか、ますます増長せしめた」だけだった。それでも、松岡氏と近衛氏の2人が、共に「軍の侵略方針には心からの忿怒を感じ」行動したことを評価して、こう援護しています。
「…彼らの闘争方式は、面と向かって論難するような陽性のものではなく、ひそかに外交謀略を用いて、軍部を他国との協議へ引きずって行こうとつとめた。抵抗が陰性であったため、彼らの方策は、きわめて少数の者以外には知られなかった」
「彼等の苦心に並々ならぬものがあったことは、現にこの闘争にたずさわった私には、よくわかる」
この頃は、もうこの2人以外には、例え陰性であろうとも、誰も勇気を奮って軍部を止めようとしなかったのだから、という意味でしょうか。。。
こ、こわいですね、、全体主義は怖いですねー。あー、こわ。😵💫😵💫😵💫
近衛氏から松岡氏への入閣、外相就任要請の場面はこんな感じだったそうです。⇩
「第2回の大命が近衛に下る前、彼は飄然と軽井沢の別邸に赴き、当時浪人の松岡をただ一人呼び寄せ、外相就任を懇請した。その際近衛は、軍人の外交干与を抑えうる人物は、君をおいては外にいない」。
こうおだてて就任を承諾させた理由は、この後の「四巨頭会談(=荻窪会談、東條陸相、吉田海相との4人で近衛氏自宅に集まった時のこと)」に於いて松岡氏が、「外交の一元化方針を東條および吉田の軍部大臣に(眼前で)承諾させ、その上ではじめて外相就任に最後の承認を与えた」というエピソードからも判るように、やはり「軍部の外交関与を蛇蝎のように嫌っ」た気骨ある松岡氏の言動を見込んだこと。加えて、直前の2者会談で「(支那)問題の解決を一つの根本方針と決め」たことなどが、外相就任懇請の決め手だったかと思います。
そうしてスタートした内閣の成立直後は、「近衛と松岡との関係は、きわめて良好で、外交は全部松岡まかせの時代だった」と斎藤博士は言います。
「頭脳といい、弁舌といい、容貌までが、なかなかにさえて、同輩からずば抜けていた」という松岡氏は、内閣成立直後の帝国議会で、「東亜新秩序を、無侵略、無併合、無賠償の三原則によって、建設する」と言い切って、「当時の2つの著述にも同じことを書き、3国同盟御批准のための枢密院御前会議にもこの信条を繰り返し、果てはソ独伊訪問のための旅先でも、スターリン、ヒトラー、ムソリーニあたりを説き回った」そうですから、近衛首相益々の信任が厚くなったと思います。
近衛氏が松岡外相に置いた厚い信任と賭けた期待は、斎藤博士によれば、「近衛もまた全面撤兵論者」であり、「中国からの全面撤退による日華事変の解決」に、松岡氏が「外務大臣就任以前からこの考えを持って」いたことで意見が完全に一致していた為です。
「日華(支)事変の急速なる解決を必要としていた日本人のうちでも、もっとも痛切にこれを望んでいたのは近衛であったように思う。」
斎藤博士のこの述懐と全く同じことが、昭和20年(1945)12月15日-自決の前の日、長男の道隆氏に書いた紙(これが、最後の「遺書」になった)に書いてあります。
「…。殊に僕は支那事変に責任を感ずればこそ、此事を事変解決を最大の使命とした。そして此解決の唯一の途は米国との諒解にありとの結論に達し、日米交渉に全力を尽くしたのである。」
しかし、斎藤博士も言うように、「日支事変は、軍部の大陸積極政策から出ている」から、「その執念と因縁は深く一内閣一閣僚の力ではどうにかなる」筈がない。しかし、「真面目で正直な」(←斎藤博士は、ご著書で何度も繰り返し強調されています)近衛氏は、「これが起こったのが、第一次近衛内閣時代であっただけに、近衛は深く責任を感じ、なんとかして有利急速な解決をつけなければならぬと考え」ていたというのです。
しかしですね、なかなか思うようには行きません。何と言っても、「第2次近衛内閣時代には、軍人外交がもっとも猛威をふるいはじめ、(中略)(近衛、松井らの)文官グループのその間に処する苦心は並大抵のものではなかった」状況だったからです。
そして、この荒れ狂う時代の中の、近衛文麿氏の元来の性格のやさしさ、弱さにも言及します。「日本中のだれも彼もが、軍部の気勢に圧されて、意気地のない態度をとっていたのだから、近衛だけを責めるわけにはいかないが」と前置きした上で、
「…近衛は、軍部の不当な圧迫を乗り切る気力に欠けていた」といい、「その生い立ちから見てもお上品、また受身な性格からしても、この難局を切り抜き得なかった。」と評します。
同様に、犬養道子氏も、ご著書『ある歴史の娘』の中で、「伯父様」と呼ぶ岩永裕吉氏の軽井沢宅の庭で、岩永氏と非常に親い仲の近衛氏の散歩のお供をしたときの印象をこう書き遺しています。
「あれはいつごろであったろう。第2次近衛内閣のころか」
「たじろいだような微苦笑と、何か受け身の姿とが、私に咄嗟に、この人は非常にすぐれた聡明な知性のある人だが、ひとつかぼそい、ひとつひよわいと思わせた。明晰な知性とある頑なさを持ちながら、終始一貫の不動のものと不退転の剛毅とを彼は持たない」
「もし今日のような善き時代(=戦後のこと)に、(中略)その才能と人となりの善さと知性と教養とは、水を得た魚より生き生きと生かされたにちがいない。歴史は彼にむごかった」
そして、ご自身を「生意気な小娘」と謙遜しつつ、近くで見知っていた「近衛さん」の人間像に想い到るのです。
「目先を八方丸くおさめることのみが人生至上の理想となるほどに辛酸孤独相剋の幼年期を送った人」
近衛文麿氏は、1891年に五摂家筆頭の家系に生まれました。3歳の頃日清戦争、13歳日露戦争。欧州大戦に世界恐慌。46歳総理大臣就任で日支事変です。そして54歳で敗戦、A級戦犯指定を受け自決されました。。
比べるのは失礼かもしれませんが、、、💦💦 私の若い時なんて、漫画とテレビばっかりで、おしゃれとか海外旅行で遊んでばっかりでしたから、😅なんとも、生まれ落ちる時代によって人生とはこんなにも異なってしまうのかと。本当に本当に大変な時代でした。そして、今の私達の平和な時代とは、こうした先人の犠牲の上に成り立っているのだと、改めて気が付かされます。
「きわめて良好で、外交は全部松岡まかせの時代だった」という第2次近衛内閣は、長続きしませんでした。当然ですが、「軍の圧力は、歴代の外の外相とは比べ物にならぬほどに(松岡外相に対する圧力は)強烈だった」からです。この圧力は様々な陰謀の形となって襲い掛かります。
例えば、「政権末期の松岡内閣の陰謀」が悪意を以て嘯かれ、松岡排斥が進められたり、松岡氏の訪独時に「外務省とは全然無関係に行われた日米交渉で、近衛、野村(吉三郎、海軍大将)とが主導」した「日米諒解私案」が松岡氏抜きで進められたりしました。
この「日米諒解私案」は、近衛氏がご遺書の中で、「…。そして此解決の唯一の途は米国との諒解にありとの結論に達し」と言及しています。これに関しては、別途後日記事に纏めるとして、結局この「日米諒解私案」の扱いを巡って、松岡氏の態度を誤解、批判する声が突如として内外で噴出したのです。
「しかるに当時、松岡は日米妥協に絶対反対であるという噂が、かなりに広く流布され、アメリカへもそれが何度となく伝えられた。しかしそれは大きな誤報」
どうして、こんな正反対の「誤報」が、地球の反対側のアメリカに伝わってしまうのか? それに『誤報』なら、在米大使館などが必死に否定することも出来た筈ですが。『誤報』が外国で垂れ流しになっておれば、当然ですけど、こうなります。⇩
「当時、アメリカの民論は、日に日に反日に傾き、松岡に対する反感もまたはなはだしく、彼をもって、軍閥の侵略手記の事実上の指導者であるかのごとくに考えていた有力者が少なくなかった。(後になっての話であるが、日米交渉(=日米諒解私案)に関し、ハル議案が国務長官ハルから対し野村に提出された際、この一部をなした文書に、暗に松岡を指して、某国務大臣を免職せねば、日米交渉の効果は、期待し得ないという趣旨のことが載せてあった)」
こ、これは、大変です。。。「日本及び日本の友人たるアメリカ人の作成」した「私案」とはいえ、やっと陸軍(岩畔大佐、この時駐米陸軍武官に転職)や海軍(野村吉三郎駐米大使で海軍大将)等が、支那事変解決に繋がる「日米交渉」に自発的に動いてくれて、どうもそれが上手く行きそうだ、と振って湧いたようないい話です。近衛首相に取れば絶対に逃したくなかったに違いありません。
「6月21日付けの「諒解私案」付属書の一部に「日本のミニスターズが反米宣伝をしているのは怪しからぬから辞職させろ」といった趣旨の文書をよこした」
と、⇧こうなってしまい、斎藤博士の表現を借りますと、「近衛と松岡とのあれほどしっくりした間柄は突如疎隔」になりました。その結果、
「1941年(昭和16年)7月16日の形だけの改変となり、松岡をはじめ秋田、河田(烈、蔵相)等は閣外に放り出された」
松岡洋右を外しての第3次近衛内閣の組閣となりました。
要するに、この在アメリカ日本軍人頼みの日米交渉=「日米諒解私案」の成功懇請が、「松岡外し」の第3次近衛内閣組閣の核の目的だった訳ですから、当然ですが、近衛氏は主張を変えませんでした。⇩
「近衛は第3次近衛内閣の時までも、全面撤兵主張を変えなかったとみえ、1941年9月6日の御前会議から間もなく、単独で東条陸相と会見し、アメリカに戦争を挑むことの危険を警告し、宜しく中国から撤兵するべきだと説いた。しかしながら東條は反撃に出て、このような譲歩は、アメリカを増長させるばかりでなく、日本軍の士気を崩壊させ、日本の面目はまるつぶれになるとして、いたく近衛を非難したそうである。」
この辺りの経緯は、東條陸相(当時)も、東京裁判に提出された「宣誓供述書」で同じ様に供述されました。
「…、四、松岡外務大臣の態度を原因としたる第二次近衛内閣の総辞職ー-(中略)四の内閣変更の措置は、我方は如何にしても日米交渉を継続したいとの念願で、内閣を更迭してまでも、その成立を望んだのでありまして、我方では国の死活に関する問題として此の交渉の成立に対する努力は緩めませんでした」
しかし、松岡外相を辞めさせたのに、「日米交渉=日米諒解私案」は泡沫として消え行くのです。
「9月の上旬に至るも、なお停頓の状態でありました。(中略)「ハル」国務長官は10月2日の口上書を寄せたのでありました。その内容には互譲の精神の片鱗も認められないのです。」
ハル国務長官の口述書を日本が受け取ったのは、10月14日。「この前後に於ける陸軍統帥部の態度及び見解は概ね次の如く」だったそうです。
「(一)以上の如き互譲の様子なき米国の態度に鑑み対米交渉妥結の見込はない。」
既に、「十月上旬を目途として日米交渉の最後の打開を為し、その時期までに我要求貫徹の目途なき場合は、直ちに対英米蘭戦争を決意すとの国家意思が決定せられて居りました」、
と言い、また、「同年同月14日閣議に於いて豊田外相(海軍大将)と陸軍大臣たる私(東條陸相)との間に今後の国策遂行の方策に関し意見の相違を来し」たと言う事です。
そして、「遂にその結果は遂に同内閣の総辞職となった」のでした。
支那無条件撤兵と日米交渉継続を切望していた近衛首相は、第3次内閣でとうとうほっぽり出されてしまったことになります。。。
此の事を、斎藤博士はこう言っています。
「第3次近衛内閣がたおれ、東條内閣ができたのは、それから間もなくのことであったことを思い合わせると、軍部が自分のいいなりにならぬ内閣を、勝手に倒した最後の実例である。」
以上、その①でフランスの圧制に苦しむ仏領インドシナから日本を目ざして来たベトナム人を快く受け入れて教育してくれた「東京同文書院」の近衛篤麿公に触れました。その篤麿公のご長男で、「大亜細亜協会」の評議員でもあり、第2次、第3次と、日本にとって仏領インドシナが重要地点として浮上して来た時期の内閣総理大臣近衛文麿氏については、ベトナム人の夫に嫁ぎ、今ではベトナム人として物事を考えている時間の多い私に取りまして、絶対にあの時のご恩だけは一生忘れてはならない、と何故か😅常々思って来ました、これは今後も変わりません。
私のベトナムの義父は、多分1945年以前のことは直接良くは知らなかったでしょうけど、周囲の大人から直接色々聞かされて育った世代だと思います。いつも優しく笑顔で、生前一切何も語ってくれませんでした。
一つ鮮明に覚えていることがあります。まだ嫁いだばかりの頃、私が「日本も(アジアを侵略して)悪かった」というようなことを言いましたら、突然声を荒げて烈火の如く「日本はいい国だ!」と反論されました。日本人の私が「日本は悪い」、ベトナム人の義父が「日本は悪くない」で押し問答の末、私がバカバカしくなりました。。。
「ベトナム人は、一度受けた恩は忘れない民族だ。」と、義父に自慢されているように感じて、自分が恥ずかしい気持ちになった日のことを今でも思い出すのです。
仏印”平和”進駐の『第2次近衛内閣』総理大臣・近衛文麿のこと その①|何祐子|note
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
