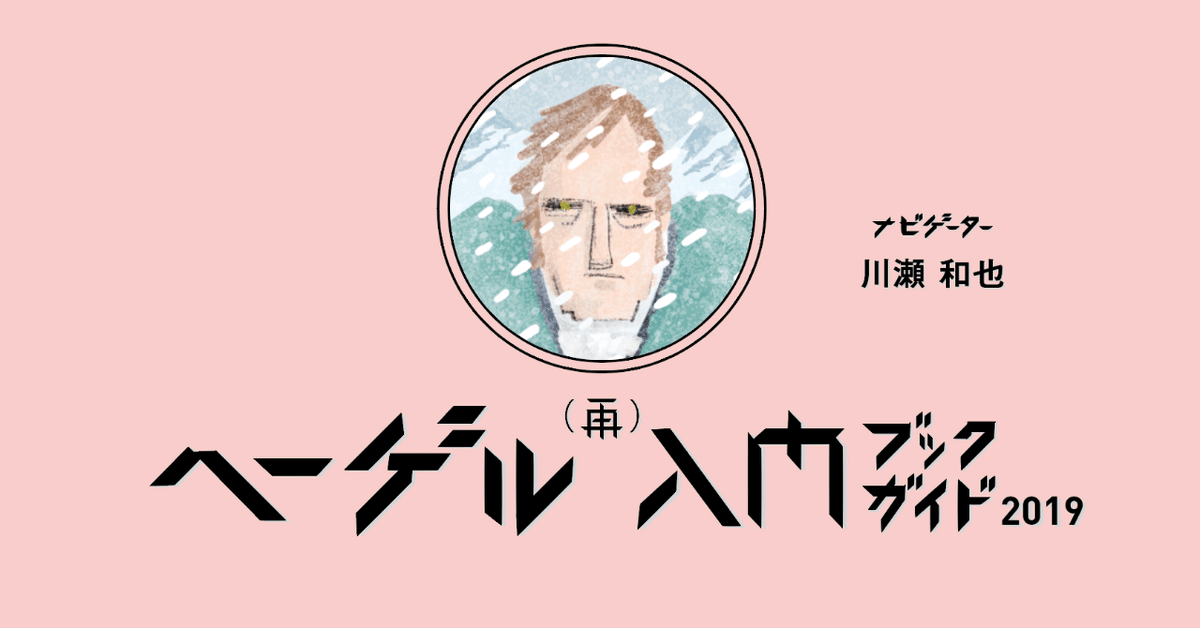
ヘーゲル(再)入門ブックガイド 2019
12/22(日)に東京セミナー学院(池袋)で川瀬和也さんによる『精神現象学』にスポットを当てた講座「ヘーゲル(再)入門ツアー 2019→2020」を行います。
「ヘーゲル(再)入門ツアー 2019→2020」
日時:2019年12月22日(日)12:30〜15:50
会場:東京セミナー学院(池袋駅より徒歩7分)
お申し込みはこちらから
それに合わせて以前川瀬さんが作ってくださった『ヘーゲル(再)入門ブックガイド 2019』をこちらにもアップしておきます。気になった本があればぜひ実際に読んでみてください。そして講座にもご参加ください!(GACCOH太田)
----------
カテゴリ1:ヘーゲル(再)入門
西洋哲学に興味のある者でその名を知らぬ者はいない、と言ってもよい大哲学者ヘーゲル。しかし、彼の思想を学ぶことには独特の困難が伴う。
ヘーゲルの文章は非常に難解で、西洋哲学の中でもトップレベル。ヘーゲル自身も書簡でうまく書けないと嘆いており、専門の論文でも、例えば英語ならdense(濃縮された)やnotorious(悪名高い)と言った表現に何度も出会うほどである。いきなりヘーゲルの著作を開いて、数行で挫折してしまった、という方も少なくないだろう。
また、ヘーゲルは日本で盛んに研究されてきた研究者で、多くの研究が蓄積されているが、新たに学び始めようとする者にとっては、これがかえってハードルになりかねない。なにしろ図書館のドイツ・オーストリア哲学の棚の前に言ってみても、新旧の研究書がずらりと並んでいる状態。しかも適当に手に取ってみると、難解なヘーゲル用語が並んでいて予備知識がなければ読めないような本にぶつかる確率が高い。何から手をつけて良いのか、学生時代の私がそうだったように、困惑してしまうだろう。ブックガイドが最も必要とされる哲学者だと言えるかもしれない。そこで、まずは初心者が自力で読み進められる本をいくつかピックアップしてみたい。
①
まずは新書から。『新しいヘーゲル』は、ヘーゲルの翻訳でも知られる在野研究者の大御所、長谷川宏の著作。ヘーゲルの著作の長谷川訳については、かなり大胆な意訳が施されており、専門家の間では否定的な意見もよく聞かれる。私自身も、どこからが長谷川による解釈なのかがわかりにくいという点で、このブックガイドでは長谷川訳は除外している。しかし、長谷川の平易な語り口が、入門者にとって有益であることは間違いない。
『新しいヘーゲル』は、新書サイズで、多岐にわたるヘーゲル哲学の全体像を、平易に示す、という挑戦的とも言える一冊。その分全体に薄味の叙述にはなっているが、ヘーゲルについて学び始めるにあたって「地図」のように役立てられる著作である。
②
中央公論新社から10年程前に公刊された『哲学の歴史』シリーズ。同シリーズは各章が独立したミニサイズの新書のようになっている。読むときにも、最初から順番に読んでいくというより、気になった哲学者についての章を一冊の本のようにしてつまみ食いしてゆくとよい。その中で、いわゆるドイツ観念論を扱った本巻の「ヘーゲル」の章は、日本で最も重要なヘーゲル研究者、加藤尚武によって書かれている。
加藤の文章の魅力は、ヘーゲルの欠点をも一切手加減せずに指摘する、ユーモアたっぷりの語り口にある。例えば「ヘーゲルで完成している哲学思想はない」だとか、「ここには「論理の展開」などというものは何もない。イメージがあるだけというのが実情であろう」、あるいは「「ドイツ観念論」の中に人類の知的遺産として永遠に記憶されるべき一行の言葉があるかどうかも、おぼつかない」といった辛辣な、しかしどこか軽快なヘーゲル批判には、ニヤリとせずにはいられない。
もちろんこれが可能なのは、その裏にヘーゲルへの深い理解と、自らヘーゲルとともに思索し是々非々で臨むという強い意志が潜んでいるからである。読み進めるうちに、「西洋近代哲学の完成者」というヘーゲルの虚像が打ち砕かれ、より興味深い、格闘する哲学者ヘーゲルの実像へと引き込まれることだろう。
③
2016年に公刊された本書では、ヘーゲルの思想の発展を編年体で追うことと、それぞれの著作の内容をかみ砕いて示すことの両方が実現されている。著者の人柄を彷彿とさせるとっつきやすい語り口も本書の魅力の一つだ。
本書の最大の特徴は、伝記的な事項についてもかなり詳しく踏み込んだ叙述がなされていることである。ヘーゲルの思想の内容についてわからないところが残ったとしても、伝記として楽しんで読み進めることができる。同時に、著作の内容もかなり細かく紹介され、各著作のキーワードを知ることができる。初学者にはそれでも凝縮された文体に感じられるかも知れないが、入門者の段階を超えて、各自の興味に応じた勉強をすすめるときにどの本に進むべきか、考えるヒントとなるだろう。
④
哲学史のなかでも躓きやすいカント以後のドイツ哲学。1977年発行の本書は、その中心となる4人の思索を俯瞰する書物として、今でも最初に参照されるべき一冊である。
カントを主要な研究対象としていた岩崎だが、この著作ではフィヒテ、シェリング、ヘーゲルにも、一人の哲学者として真摯に向き合い、自分なりの合理的な解釈を作り出そうとしている。ヘーゲルについても、「全く価値がない」という評価と「非常に重要な哲学者」という評価の両方があるという出発点から、ヘーゲルに意義があるとしたらそれはどのような意義なのかへと、思索が展開されている。単なる紹介にとどまらない哲学の書として、時代に左右されない魅力を持つ一冊。
⑤
最後の1冊は、選者の恩師でもある高山守の近著で、放送大学のテキストを元に大幅な改稿を加えた一冊。
高山のヘーゲル論の魅力は、ヘーゲルの晦渋な叙述を自らの哲学的関心と関連付けながら、明快な解釈を構築しようとする態度にある。選者が学生として出席した演習では、「具体的にはどういうことか?」と何度もより明快な解釈を求められたことを鮮明に覚えている。このような魅力を持つ高山の研究のエッセンスを、コンパクトな入門書のスタイルでも犠牲にせず、可能な限り展開しているのが本書。ヘーゲルを読み、それについて自分で考え、自分なりの解釈を提示する。本書において読者は、そうしたヘーゲル研究の目指すべきあり方の好例に触れることができる。
------------
カテゴリ2:『精神現象学』に挑む
ヘーゲルの主著として最もよく知られているのがこの『精神現象学』である。小説のような独特の語り口を持つこの書は、多くの哲学者達を魅了してきた。しかしこの書は同時に、知覚論かと思えば宗教や哲学史、ギリシャ悲劇、フランス革命、道徳、宗教といった多様な主題が次々に現れ、扱いの難しい書物でもある。ここでは、『精神現象学』を楽しんで読むための本を集めてみた。
①②
昨年12月に出たばかりの新訳。訳者は、カントやレヴィナスの翻訳でも名高い哲学者・熊野純彦である。これまで、初学者が手に入れやすい『精神現象学』の翻訳には、平凡社ライブラリーとして再版されている樫山欽四郎訳(平凡社)と、大胆な意訳が特徴の長谷川宏訳(作品社)があった。しかし、前者の樫山役は堅実な訳ではあるが、1966年の訳を補訂したもので、すでに50年の時を経ていた。また、後者の長谷川訳は、あまりにも大胆な意訳が散見され、訳者の解釈とヘーゲルのもとの議論を区別しにくいという難点があった。これらの点から、新訳はヘーゲル自身の思想を現代の日本語で伝える訳として注目される。
③
実は私にとって思い出の一冊。学部3年生のとき、ぼんやりとヘーゲルを専門にしようか悩んでいた頃に読み、それまで何を読んでも理解できなかったヘーゲルが、少しだけ理解できた気がした。長谷川氏はヘーゲルの訳者としての顔がよく知られているが、『新しいヘーゲル』と並び、この書のような解説書が氏の真骨頂ではないかと私は思う。
「『精神現象学』はまさしくヘーゲルの青春の書だった」という一文を読んだときのことを、今でも鮮明に思い出すことができる。私自身はその後、むしろこの若書きの書を離れ、『大論理学』の研究へと向かうことになるが、その際には、より完成されたヘーゲルに触れてみたいという気持ちがあった。ヘーゲルにとって、37歳で書かれた主著『精神現象学』とは何だったのか、この本とともに考えてみてほしい。
④
奇しくも③と同じタイトルを持ったこの本も、学部時代にお世話になった思い出の一冊。こちらは、認識論から歴史、宗教に至るまで多岐にわたるトピックが扱われる『精神現象学』の、それぞれの章の専門家によって書かれた、手堅い入門書である。③と比べて読むのもおもしろい。この本で『精神現象学』のあらすじをしっかりつかんでおけば、『精神現象学』に言及する他の哲学者の書物や研究書を、ぐっと理解しやすくなるだろう。
⑤
1791年から1804年にかけて起こったハイチ革命。世界史に詳しい方なら、「黒いナポレオン」と呼ばれたトゥサン・ルベルチュールの名前を覚えているだろう。『精神現象学』のクライマックスの一つ「主人と奴隷の弁証法」の背景に、このハイチ革命と、黒人奴隷の解放に向かう世情があった、という解釈を提示した一冊。ハイチ革命を取り巻く実証的な知見に基づいて、ディーター・ヘンリッヒやルートヴィヒ・ジープといった大御所の解釈をなぎ倒していく叙述は痛快ですらある。
「主人と奴隷の弁証法」は、『思想』2019年1月号に訳出されたマクダウェルの論文「統覚的自我と経験的自己――ヘーゲル『精神現象学』「主人と奴隷」の異端的解釈に向けて――」の主題でもある。合わせて読みたい。
------------
カテゴリ3:知られざる『論理学』の世界
ヘーゲル第二の主著、いわゆる『大論理学』。『精神現象学』に比べると知名度で劣るが、重要さではひけをとらない。何を隠そう、選者は20代のほぼ全てをこの書物の解釈に捧げた。その意味で最も個人的な思い入れの強い書物でもある。
専門家にはよく知られていることだが、『精神現象学』は体系そのものではない。ヘーゲル哲学体系の全貌知るためには、なんとしてもこの『大論理学』を読みこなさねばならない。また、「弁証法」や「矛盾」、「質と量」といった、よく知られたヘーゲル哲学の鍵概念について扱われるのもこの『大論理学』においてである。これらについて知りたければ、やはりどうしても『精神現象学』だけでなく、『大論理学』も読まなければならない。ここでは、この難解な大論理学に挑むための書籍を集めた。
①②③(目玉)
ヘーゲル論理学には、1812年から1816年にかけて書かれた三分冊の論理学と、「論理学」、「自然哲学」、「精神哲学」の三部からなる『エンツュクロペディー』の第一部としての「論理学」がある。両者を区別するため、前者は『大論理学』、後者は『小論理学』と呼び習わされてきた。
この翻訳では、通称としての『大論理学』ではなく、本来のタイトルを直訳した『論理の学』が表題に採用されている。2012年から2013年にかけて公刊された新訳である翻訳書は、現代の日本で『大論理学』を読む際に第一に選択されるスタンダードといえる。
④⑤⑥
①②③の山口訳に加えて、あえてもう一つの翻訳書を並べたのには二つ理由がある。
一つは、第一分冊「存在論」の底本が異なっていること。ヘーゲルは晩年、『大論理学』の改訂を企てていた。しかし、第一分冊「存在論」の改訂が終わったところで病に倒れ、休止してしまう。このため我々の手元には、「存在論」のみ第1版と第2版が残され、「本質論」「概念論」については第1版のみが残された。このため、山口訳や岩波全集版の武市訳では、「存在論」のみ第2版を用い、「本質論」と「概念論」では第1版を用いるという方策がとられている。これに対し、寺沢恒信によるこの訳は、「存在論」の底本に第1版を用いている。「存在論」第1版の翻訳はこの訳でしか読むことが出来ない。
もう一つの理由は、それ自体で価値を持つ詳細な訳注がつけられていることである。寺沢の訳注は、たんに情報を補うにとどまらず、ときにはヘーゲルに批判的に叙述の意義を検討した、それ自体研究書と呼べる性格のものである。しかも、そこで論じられている内容のレベルは非常に高い。このため、この訳には、単に訳文の比較のためでなく、訳注を読むためにも、手元に置いておくだけの価値がある。
⑦
著作集の中の一冊だけがここに並べられていることに、違和感を抱く読者もいるかもしれない。それでもこの書物を選んだのは、『大論理学』について著者・加藤尚武が様々な媒体で論じてきた単行本未収録の論文の数々が、ここに集められているからである。
著者本人による解題にあり、帯にも採用されている、「ヘーゲル論理学の主要な箇所について、哲学的に「深い」解釈をするまえに、何について、どういう内容を書いているのか明らかにする必要がある」という著者の言葉に、私は強い共感を覚える。驚くべきことかもしれないが、ヘーゲル論理学が何を論じているのか、200年以上が経った現在でも、全く明らかではないのだ。この問題意識を前面に打ち出し、自らこの状況を変えようとした著者の論文の数々をまとめて読めるようになったことは、ヘーゲル論理学研究を着実に前進させる一歩となるはずだ。
⑧
ヘーゲル論理学の具体的な内容が明らかでない、という問題に、伝統的に正面から向き合ってきたのは、マルクス主義的な解釈だった。図書館などで、見田石介『ヘーゲル大論理学研究』(全3巻、大月書店)を手に取ったことのある読者も多いのではないだろうか。
ヘーゲル自身の観念論を無視して唯物論として読み替えるという態度はアクロバティックではあるが、この解釈の伝統を全て単なる誤読として退けるのももったいない。この解釈伝統には、少なくともそう言いたくなるだけの蓄積がある。そして、これを引き継いで現代的な解釈論と接続するという仕事が見事に遂行されているのが本書。特に第I部「ヘーゲル論理学とは何か」は必読である。見田石介の論理学解釈について、問題点が丁寧に指摘され、そこから新たな解釈の可能性が開かれる。
------------
カテゴリ4:ヘーゲルと行為の哲学
『思想』2019年1月号の私の論文は、ヘーゲルを現代行為論に接続するロバート・ピピンの試みを紹介するものであった。選者は、ヘーゲル研究と合わせて、現代の行為の哲学の研究にも取り組んでいる。『思想』論文は、両者の接点をさぐる試みでもあった。
行為の哲学は、20世紀の分析哲学の歴史の中で、最も発展した哲学の分野の一つである。エリザベス・アンスコム(『インテンション』産業図書)とドナルド・デイヴィドソン(『行為と出来事』勁草書房)という二人のスターをはじめ、様々な画期的な研究が生み出され続けてきた。ここには、ヘーゲルと行為論を結びつけて理解するために読むべき本を集めた。
①
私の論文「行為者性の社会理論」は、ロバート・ピピンが『ヘーゲルの実践哲学』で企てた解釈をコンパクトに整理した上で、その問題点を検討するものだ。ピピンはアメリカで最も重要なヘーゲル研究者だが、『ヘーゲルの実践哲学』では、英語圏の行為の哲学で扱われてきた行為者性の問題に、ヘーゲルの実践哲学を接続することが試みられている。
我が国でも英語圏におけるヘーゲル研究が少しずつ脚光を浴びるようになってきたが、この分野については、邦訳が出たにもかかわらず、きちんとした紹介がなされてこなかった。それを補い、ヘーゲルに親しんだ読者には行為者性の問題とはどのような問題で、なぜそれがヘーゲルと関わるかを理解できるよう、また、行為論に親しんだ読者には、ヘーゲルの立場がなぜ考慮に値するかが理解できるように論じた。
②
ジョン・ロールズのもとで博士号を取得したコースガードは、現代のメタ倫理学と行為の哲学において「カント的構成主義」を主張する立場として知られる。その彼女の主著が本書である。
カント倫理学の鍵となる自律。人はいかにして自分で自分を律することができるのだろうか。しかもその自律が道徳的な正しさを保証するとなぜ言えるのだろうか。コースガードは、人は行為において、自らのアイデンティティを形成しているのだと言う。よい行為はアイデンティティの統一性を高めるし、悪い行為をすればそれだけ、アイデンティティがぐらつくことになる。コースガードはこのような観点から、道徳的義務と自己立法の議論を捉え直そうとする。③では、このアイデンティティの形成はヘーゲル的な人倫に関連するはずだという批判が展開される。
③
著者のピピンは、現代のアメリカで最も重要なヘーゲル研究者。彼の主著『ヘーゲルの観念論』(1989年、未邦訳)は、現代につながる英語圏のヘーゲル復権のうねりをもたらした。この『ヘーゲルの実践哲学』は、そんな彼の唯一の翻訳書となっている。
ピピンの真骨頂は、ヘーゲルの難解な議論を再構成し、現代の哲学上の問題を考えるうえでも無視できない立場へと彫琢してゆく手腕にある。『ヘーゲルと実践哲学』においては、この彫琢は、クリスティーン・コースガードの現代カント主義を検討することを通じてなされる。ピピンによれば、コースガードの言うアイデンティティは、人倫としての社会や歴史との関わりを抜きにしては理解することはできない。ここにヘーゲル主義への道が出現する。
私が見るところ、ピピンは1990年代以後のヘーゲル研究において、世界で最も重要な人物である。ピピンを読まずしてヘーゲルを語ることはできない時代が、すでに到来している。現代一流のヘーゲル研究に、この書を通じてぜひ触れてみてほしい。
④
②と③を正しく理解するための、最良の入門書。ピピンが批判するコースガードの構成主義は、倫理的な「善さ」は主観的なものなのか、それとも客観的なものなのかという、100年以上にわたって英語圏の倫理学の中心にあり続けた問いを背景に提示されている。その背景をスッキリ整理して提示してくれるのがこの一冊。コースガードの構成主義についても詳しく解説されている。
⑤
メタ倫理学とともに、ピピンやコースガードの議論の背景にある行為の哲学。『言葉の魂の哲学』(講談社)で話題を呼んだ古田徹也の出世作でもある本書では、「責任」の問題にこだわりながら、人間の行為の諸特性が解き明かされる。
行為の哲学は、20世紀後半以後の分析哲学の展開の中で、最もめざましく発展した分野の一つである。人間精神と物理世界の接点となる「行為」は、哲学的問題の宝庫である。本書を通して、行為の哲学の広がりに触れてほしい。
⑥
行為者性の問題と自由の問題の間には、切っても切れない関係がある。本書では、自由とは何かという問題が、コースガードにも影響を与えたハリー・フランクファートに依拠しながら明晰に語られる。⑤と⑥、それに絶版ながら『自由と行為の哲学』(春秋社)を合わせて読むことで、コースガードとピピンの議論によって、カントとヘーゲルがどのような論争状況の中に置かれたかを理解できるはずである。
------------
カテゴリ5:ヘーゲルとプラグマティズム
近年になって、にわかに注目が高まっているプラグマティズム。プラグマティズムは、「実用主義」であり、俗っぽい哲学であるかのように言われることも多いが、これは誤っている。そもそも、「真理とは道具である」のようなプラグマティズムのテーゼは、「真理とは何か?」という西洋哲学の伝統の中心にある問いを正面から引き受けたところにしか出てこないものだ。プラグマティズムはこの問いに新しい仕方で答えてはいるが、それは伝統を放棄したのとは全く異なる。
こうした流れの中で、ヘーゲルとプラグマティズムの関係についても注目が集まっている。プラグマティズムは、カントやヘーゲルといったドイツ哲学が大流行する時代に生まれた思潮である。この意味で、意外に思われるかも知れないが、アメリカで生まれたプラグマティズムは、いわばドイツ哲学の血を引いている。しかも、ローティやブランダムといった、現代に復活したプラグマティズムの重要論者たちは、こぞってヘーゲルの重要性を指摘している。こうした流れを背景に、このカテゴリでは、特にヘーゲルとプラグマティズムの関係を理解するのに役立つ書籍を集めた。
①
ヘーゲルの影響を受けた現代の哲学について、複数の若手研究者が論じた一冊。選者は第3章「アメリカのプラグマティズム」を執筆した。そこでは、W・V・O・クワインからリチャード・ローティを経てロバート・ブランダムへと至るアメリカにおけるプラグマティズムの伝統に光を当て、とくにブランダムの「推論主義」について詳しく論じた。
ブランダムは、ヘーゲルからの影響を公言しながら、同時に英語圏の言語哲学研究の成果を受け継いだ研究を展開している。これを読むことで、ブランダムの立場の概要と、それがなぜヘーゲルに関わるかの2点を、初心者でも無理なく理解できるはずである。
②
ジョン・マクダウェルはイギリス・オックスフォードで学界にデビューし、現在はアメリカ・ピッツバーグで活躍する哲学者。『思想』1月号では彼の『精神現象学』に関する論文が訳出されている。また、『ヘーゲルと現代思想』には松岡健一郎による、マクダウェルのヘーゲル論についての解説がある。
この『心と世界』はマクダウェルの主著。私たち人間の心が、客観的な世界を知ることができるのはなぜか? という哲学の大問題について正面から論じられる。ウィルフリド・セラーズの「所与の神話」批判(『経験主義と心の哲学』、岩波書店)と、ドナルド・デイヴィドソンの整合説(『真理と解釈』、勁草書房)の検討を、カントの「内容なき思考は空虚であり、概念なき直観は盲目である」という指摘に接続する手腕は鮮やかで、さすがと言うほかない。
選者にとっては、本書は本格的に分析哲学を学び始めるきっかけとなった思い出の書でもある。マクダウェルの文章は決して読みやすくはないが、続きを読みたいと思わせる不思議な魅力がある。分析哲学に慣れない読者でも、苦しみながらも親しみをもって読み進められる書物である。
③
現代アメリカのヘーゲル主義といえば筆頭にあげられるブランダム。『推論主義序説』は、彼の主著『明示化』の解説版・簡略版として書かれた書。冗談で電話帳や枕に例えられるほど分厚い『明示化』に比べるとずいぶんコンパクトではあるが、それでもかなり歯ごたえのある書物である。ライカン『言語哲学』や飯田隆『言語哲学大全』(いずれも勁草書房)で周辺知識を補いながら読み進めるのが得策だろう。
なお、本書の帯には「よみがえるヘーゲル!」とあるが、これは少し言い過ぎに思える。本書で直接的なヘーゲル論が展開されることはほとんどないからだ。(なんとヘーゲルは「私はヘーゲルについての本をかくつもりだ」という例文の中にしか登場しない。)ブランダムのヘーゲル論はむしろ、『大いなる死者たちの物語』(ハーヴァード大学出版会)など未邦訳の書物で展開されている。それでは本書での議論はヘーゲルと深い関わりを持っている。そのつながりについては、①に所収の拙論「アメリカのプラグマティズム」で詳しく論じたので、ぜひ併読をおすすめしたい。
④
本書は、古典的プラグマティズムから、ローティやブランダム、そして最新の動向までをカバーした一冊。プラグマティズムの全貌を学び、その多様性を知ることも出来る。新書で手軽に読めるのも魅力。ヘーゲルとの関係については詳しくは論じられていないが、本書から始めることで、次に紹介する⑤や⑥へと進んでいくことができるだろう。
⑤
現代哲学の姿をわかりやすく伝える啓発的な著作で人気を博す哲学者・岡本裕一朗。ビジネスマンを対象に書かれた『いま世界の哲学者が考えていること』(ダイヤモンド社)はベストセラーにもなった。その岡本によるネオ・プラグマティズムの解説書が本書である。
岡本はヘーゲル研究から出発している。しかも、現代につながるネオ・プラグマティストとして著名なローティ、マクダウェル、ブランダムの三人は、いずれもヘーゲルにしばしば言及している。このため、本書でも両者の接点に目が行きとどいた記述がなされている。
⑥
パースからローティに至るプラグマティズムの流れを解説したのが本書。注目すべきは、ヘーゲルのために一章が割かれていることである。
ブランダムが「ヘーゲルはプラグマティストである」という主張したことは有名だが、これは決して荒唐無稽な主張ではない。そもそもプラグマティズムという思潮そのものが、ヘーゲルとの関わりの中で発展してきたものだからである。本書でヘーゲルが大々的に取り上げられていることは、その証左といえる。現代哲学につながるヘーゲル主義の意外な鉱脈を見つけることができるだろう。
「ヘーゲル(再)入門ツアー 2019→2020」
日時:2019年12月22日(日)12:30〜15:50
会場:東京セミナー学院(池袋駅より徒歩7分)
お申し込みはこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
