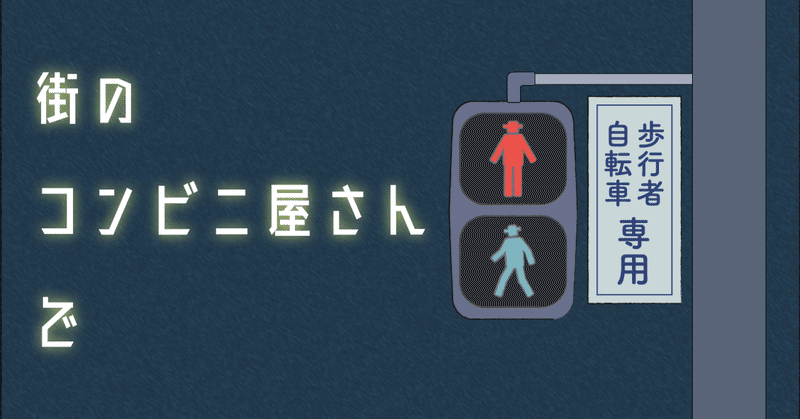
街のコンビニ屋さんで
本当に何にもなくてさ、と何度その街を卑下してきたことだろう。最寄りの駅を聞かれるのが憂鬱だ、という発言さえも嫌味になる、23区の南の方。パリジェンヌのつもりで付けられた(かは知らんけど)呼称に、センスがネーゼと言いたくなる街。身の程知らずと思うから、表立っては貶してばかりいたけれど、私の人生双六には載ってさえいないようなハイソな住所。そこに自宅のピンが立っていたことは、純粋な誇らしさも少しある。
本当の本当に、何もないところ。スーパーも駅直結のデパ地下もどきか、少し歩かされるのにキャベツがひと玉168円(デパ地下もどきと同じ)もする都内限定チェーンしかない。ここでしか買えない肉屋のコロッケもないし、ここでしか会えないマスターも大将もいない。居たのかもしれないけど、常連になる前に破産してしまうだろう。あるのは、タワマンと、プラスティックの模型みたいなマンション群、急に現れるボロボロのトタン屋根の家。どれも気配がなくて、それでもその街を入れ物に、出入りするのはやはり生身の人間である。
家から一番近くのコンビニは、某入店音の青と緑色。異国に来たかと見紛うくらい、従業員に日本人がいない。聞き慣れない言語を遣って、すごい連携を見せたりする。あんたら同じお国なん?この、地下鉄しか通ってない街で、偶然揃う言語ではなさそうだけど。ところで今、私の方を軽く指差してなんて言うたん?「見ててみ。こいつ絶対タバコ買ってくで」とか?「脂っこいものばっか買ってるくせして、いつもサラダつけててウケるよな」とか?あまりのアウェイ感にこちらが恐縮してしまう。「すみません、116番ふたつください。あ、86じゃなくて、ヒャクジュウロクです。すみません、あ、すみません。」
そんなコンビニに「リーさん」が登場したのは、住み始めて1年くらい経った頃だ。「116」と言いかけて、あれ、いつもの店員さんと違うなと気がついた。一見すると日本人の女性にも見えたけれど、肌の陶器感から察して名札に目をやる。マジックで「リー」と書かれているのに確信を得て、116と言いかけた口をヒャクジュウロクの方にシフトする。
「袋入りますか?」先を越されてリーさんから飛び出した声は、彼女の凛とした雰囲気に合う低音で、耳の中でサラリと漢字に変換された。”ヒャクジュウロクモード”にした自分を恥じるくらいに、違和感のないイントネーション。「あ、あ、あえっと86…じゃなくて、えっと116番ください、ふたつで。」こちらの方がよっぽどぎこちない日本語で情けない。リーさんは後頭部をこちらに向けて、短く束ねた黒髪を揺らしながら、「116番、116番」と棚を指でなぞっていく。「はい、こちらですね。ハイライトのメンソール。カッコイイネ」最後の「カッコイイネ」のイントネーション以外は完璧だったし、思いがけず私に向けられたコミュニケーションに面食らう。面食らったもんだから、目を逸らして「ど、どうも」。最悪の形でコミュニケーションのシャッターを閉じてしまった。ガシャーン。乱暴過ぎ!と申し訳なく思ってリーさんを見ると、人情味とサービスの中間にあるほかほかの笑顔を向けてくれて、それはこの無機な街との初めての対話だった。
夜中の2時にアイスを買いに行ったり、平日の15時にバナナとヨーグルトを買ったりしている私と、いつ寝てるん?というくらいよく見かけるリーさん。利発な印象から、隣の隣の駅にある医学部の留学生かな?なんて考えたりもしたけれど、こちらだけが名前を知っている狡さを思うと、それ以上は想像するのも遠慮した。
特に多くの言葉を交わすわけでもなく、「寒くなったネ」「ねー、ピザまん買っちゃおうかな」とか、「バレンタインだから」とリンドールを2粒渡して「わあ、すみません。ありがとネ」とか、それくらいのやり取りを繰り返した。「今日はタバコいいの?」「あ、じゃあふたつ」が挨拶代わりになっていた1年後の春先、リーさんが手渡したタバコがひとつだった。ふたつって言ったのに。言わなくたってタバコはふたつで決まりなのに。でも、会計もひとつ分だったから、私は何も言わなかった。次の日、リーさんはコンビニから消えた。突然、無機な街に逆戻り。コンビニではぶっきらぼうなムンさんが、「ん!」と袋を突き出してくる。それは言語の壁ではないと思うで?と、心の中で少し笑いながらも、「そういえば最近リーさんはどうしたの」なんて聞けない、”あくまでもコンビニ”という箱そのものの無機さをも突きつけられた。
あくまでもコンビニ。それ以外を過ごす、家や電車やカフェでの日常に埋もれて、2週間後にはリーさんのことも思い出さなくなっていた。アイスボックスとミンティアをレジに出して、ヒャクジュウロク!をふ・た・つ!と言いながら、カウンターの向こうに焦点を合わせると、そこにはリーさんが立っている。咄嗟に「お、久しぶりですね!」と言ったけれど、親しげ過ぎてキモいかなとオドオドする。ちょっと間が開いただけでこちらもコミュ障に逆戻り。リーさんは愛嬌のある笑顔で、「ちょっと国に帰ってました。中国!」と言った。そっか、なんか勝手に台湾かと思ってたけど中国か。台湾と中国は絶対に一緒苦茶にしてはいけないからね。中国か!なんていうのも変だよ。うだうだ考えて言葉が出ない。遂に飛び出した「おかえりなさい」という訳のわからない返答にも、「ありがとう!」と、リーさんはさらに爽やかさを増すばかりだ。またこの店に来よう。いやいや、最寄りのコンビニなんだけど。
それから更に1ヶ月。コロナの影響を大きく受けた私は、フリーの仕事では不安になって、転職活動を始めていた。人生の節目は、「メイク道具が一気になくなる」レベルで重なるもので、マンションの更新に合わせて引っ越しまですることに。予期していなかった転機と、慣れないスーツで強張る首肩。手応えのなかった面接の帰りに、改札を通り抜けながら考える。リーさんのいる店でタバコを買って、それから今日は夜ご飯もお弁当でいいか。昇りのエスカレーターに立って思う。こんな格好しちゃって、うだつの上がらない感じがバレないといいな。入店音を聞きながら自動ドアをくぐる。リーさんは接客をしていてこちらには気が付かない。適当におにぎりを二つ選んで、レジへと向かう。どうもという感じで軽く会釈するとリーさんスマイルが返ってくる。「あと、タバコふたつお願いします。」「はい!」リーさんは後ろを向いて直線距離でハイライトのメンソールに手を伸ばす。キビキビとした動作でまたこちらに振り返るリーさん。
「あ、今日はスーツ!珍しい。カッコイイネ」
引っ越した先は、その頃よりもずっといろんなものがある街だったけれど、相変わらずコンビニでは「メルカリ、ネコポス!」と単語での簡潔な注文が必要だ。無事に就職先も決まった。めっきり出番が少なくなった、お気に入りの私服達を横目に「今日もスーツか」と思う朝、リーさんのカッコイイネが脳裏で眩しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
