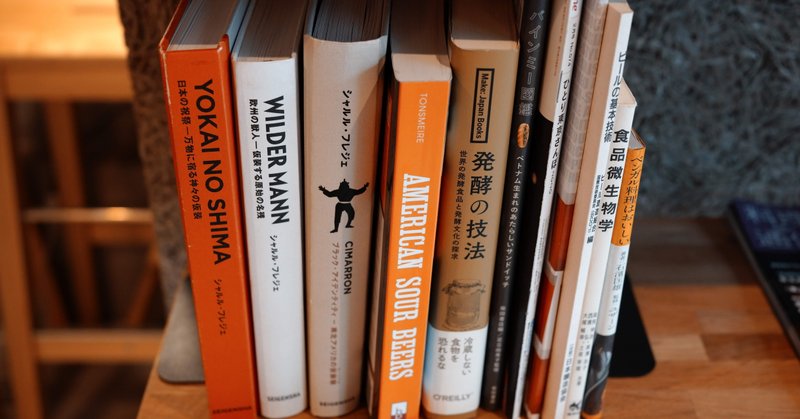
4月に読み終えた本
3月と打って変わって本を読む時間がとれた。理由はもちろん外出自粛体制だが、引っ越しがだいたい落ち着いたというのも大きい。本を読む以外にも、アニメ見たりゲームやったりラジオ聴いたり走ったりと、いろんなことに時間を使えるようになっているので、外出自粛といってもあまり退屈することはない。もちろんできなくなったこともあるけど(チェロ…)。
4月も後半になるとアニメやラジオが放送休止になったり隔週更新になったりして、ますますやることが先鋭化してきている。そしてどこからともなく「自炊せよ」という《聲》が聴こえるのであった…。
大山顕『新写真論――スマホと顔』(ゲンロン)
『ゲンロンβ』での連載のころからちょくちょく読んでいて、単行本化を楽しみにしていた。
著者は『工場萌え』で有名な写真家で、他にも団地やジャンクションなどを撮影しているのでもよく知られている(同人でも写真集を出していて、絶対買うサークルのひとつである)。その著者が書いた写真論ということで絶対おもしろいと思っていたら、やっぱりすごくおもしろかった。
本書のテーマは(副題にもなっているように)スマホと顔(自撮り)で、もともと大判カメラで建築物を撮っていたことと比べると意外ではある。でも、スマホというテクノロジーが「可能にした」自撮りが実は写真の「先祖返り」であって、従来の(とはもう言い切れないかもしれない)カメラによる「見る/見られる」という関係はこれまでのテクノロジーによる制限から生まれた、限定された写真論だったのではないか、という著者の問いはすごく興味深いと思う。スマホによる写真はこれまでの写真論にアップデートを促すものかもしれない。現代のカメラを写真を撮る装置としてでなく、スクリーンショットを撮る装置として捉えているのは慧眼だと思う。
また、帯にも引かれている「もしかしたら写真は人間を必要としなくなるのではないか」という言葉は、写真がその他のデータと同じようにAIの学習データとなっていく(これも視覚の特権性の剥奪と言える)さまを端的に表していて、写真家の言葉として考えるとすごいなと思う。そういう意味で大山のテクノロジーへのまなざしが一貫していて、非常に興味深い。写真論とか興味ない人もおもしろく読めると思う。
小川哲『ゲームの王国』(ハヤカワ文庫JA)
この小説は、クメール・ルージュ政権以前から(現在から見て)近未来のカンボジアを舞台にしている。
SFだと聞いて読み始めたが、上巻は完全に歴史小説で驚いた。クメール・ルージュという単語、ポル・ポトという人物、そして大量虐殺があったことなどは知っていたが、ほとんどははじめて知ることだった。といっても小説なのでどこまでが史実でどこまでが創作かという話はあるが、Wikipediaなどで読む限りは大枠は事実なのだろう。
登場人物も多くて、最初は誰が主人公(?)なのかよくわからなかった。それぐらい一人ひとりのエピソードが書き込まれていて、魅力的に映る。最終的にはムイタックとソリヤという男女の話に収斂していくが、そういう意味ではボーイ・ミーツ・ガールものと見てもおもしろい。
他には土を食べることで土と会話したり操って攻撃する人物や、政治などの不正を感じ取ると勃起するTVプロデューサーが登場してきて、なんじゃこりゃと思うが、そんなマジックリアリズム的なインパクトだけではなく、それらの人物同士の関係も巧みに構成されていてすごい。
SF的な要素は下巻で登場するが、それも全体を構成する一部といった感じで、いろんな要素をうまく組み合わせている印象があっておもしろかった。
自分でも読後の感想がよくわからずとりとめもなく書いたけど(小説の感想を書くのはむずかしい)、クメール・ルージュやポル・ポトのことを知ってみたいと思った。月並みな感想だが。
平鳥コウ『JKハルは異世界で娼婦になった』(ハヤカワ文庫JA)
いろんな方面からおもしろいと聞いていたので、読んでみた。
異世界転生ものとしてみると、主人公ハルがチート転生を裏から眺めつつも、ある意味正統派?なチートを駆使する後半はそうきたかーという感じでおもしろかったし、カタルシスもあった。
ただそれが、この世界の中だと、ハルのチートさを持ってしても大きな男尊女卑(作中では「男尊&女卑」と書かれる)構造を崩すことができないということがあっけらかんと書かれる。このあっけらかんと、ある種爽やかに書かれているのがすごいし、主人公ハルの魅力になっていることがわかる。他の登場人物も同じくらい魅力的だ。
異世界転生ものという物語形式を下敷きにしてその上で何を描くのかが重要になってきて久しいが、遅ればせながら読んだこの作品、異世界転生+フェミニズム文学というあわせ技ですごくおもしろくて意味深いものになっているなと思う。
最後に今期の異世界転生アニメのイチオシをご報告します(全体としてもイチオシ)。『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』です。内田真礼さんの最高の演技を味わいましょう。
平鳥コウ『JKハルは異世界で娼婦になった summer』(ハヤカワ文庫JA)
そして短編。本編?以前や以後の話、別キャラクターの掘り下げなどが読める。
本編ではハルの成長を中心に話が進むけれども、この短編集では周りの登場人物の成長が描かれて、キャラクターたちがさらに魅力的に思える。
千葉(ハルと一緒に異世界転生してきた同級生)も、本編ではわりとしょうもない(しかしどこか読んでいる自分にも刺さる)のだが、それでも異世界の経験や成長するハルを見ることで成長していくさまが見れて、ああ、いいなあと思う。
キヨリ、ルペ、スモーブといったキャラたちも同じで、好きな人、尊敬できる人から素直に何かを受け取れるのは清々しい(というか、ハル自身がそういう人なのだ)。タイトルの「summer」に反して夏の話が多いというわけではないのだが、爽やかさという意味でそういう題になったのかなと思う。
本編はけっこうな性描写があるのだが、この短編集は少ない。ただ一編だけクソみたいな(褒めてます)下ネタが連発される章があって、くだらねーwと思いつつめちゃめちゃ笑ってしまった。でもこの章もめっちゃ爽やかで良いのだ…。
村上春樹『猫を棄てる――父親について語るとき』(文藝春秋)
村上春樹が折々に「文章にしなければならない」と言っていた彼の父親についてのエッセイ。届いてみると、小さめのハードカバーで、挿画も見慣れない人(この方の漫画が同時に電子書籍になっていて、なかなか良かった)で、珍しいなと思った。短いのですぐ読み終わる。
二人称と三人称が混ざり合って書かれているような印象があった。身内を語るとしても、歴史(三人称)として語ることが必須だったのいうのが伝わる。ここで書かれている(一人称としての)「偶然」の感覚(父が戦死していたら、母の婚約者が戦死していなかったら)は、歴史(を知ること)によって成り立っているのだろうと思う。自分も親族から戦争の話を聞いて、同じようなことを思ったことがある。
(そしてまた、その書き方の「ぎこちなさ」が、著者と父親との関係もうかがわせる、とか言えるかもしれないが、まあつまらん解釈ではある)
まあそんなことは著者自身があとがきで書いていることだし、彼の小説作品でもたびたび出てくることだが、それがエッセイというかたち、しかも自身の父に関する文章として出てきたのは貴重だなと思う。また読みたくなるかも知れない。
『世界哲学史4――中世II 個人の覚醒』(ちくま新書)
相変わらず読み続けている。
前巻は全然わからんみたいな感じだったが、この巻は知っている名前がよく出てきた(知っている≠わかる)。トマス・アクィナスとか朱熹(朱子)とか鎌倉仏教の開祖たちとか…。
大学受験のときに日本史選択で、とくに文化史などが得意だったので、鎌倉仏教についての固有名詞を見てなつかし〜と思ってしまった。蘭渓道隆とか夢窓疎石とか宗峰妙超とか、名前のいかつさだけは記憶にすごい残っていて、ほか何も覚えていなかったので復習になった(なったか?)。
なんだか1巻からダラダラと読み続けているだけな気もするが、なんとなくの流れみたいなものが知れているような気もするので、これからも読み続ける気がする。
