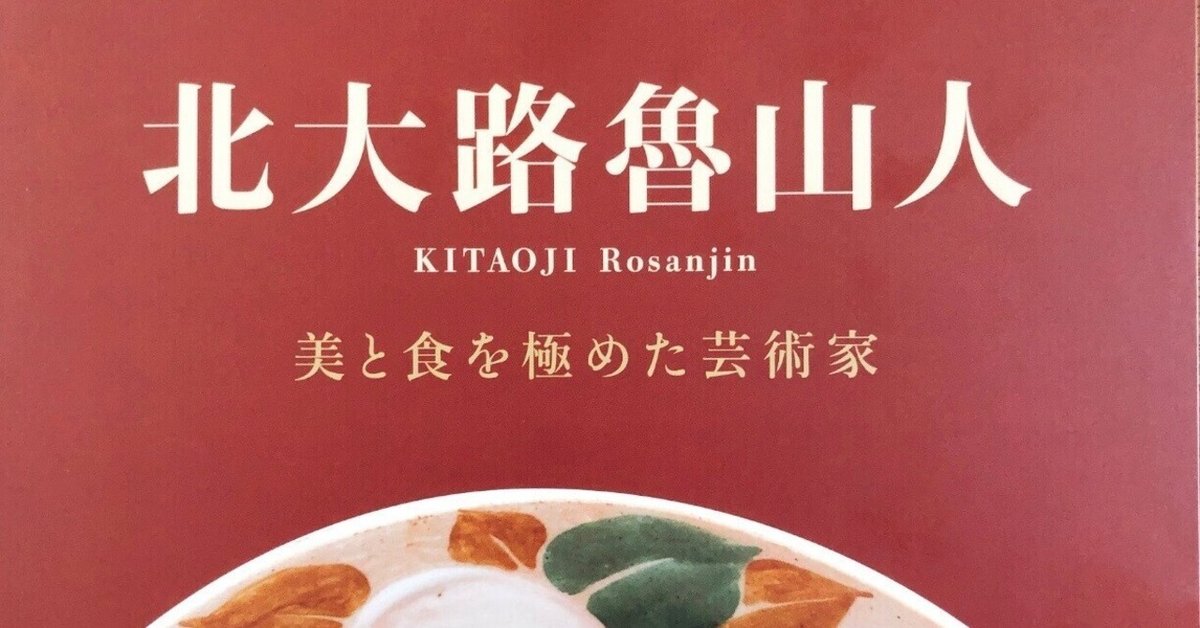
足立美術館・後編 ~器は料理の着物~
前回は足立美術館で榊原紫峰の絵に感動したり、横山大観の富士山にげんなりしたり、テンションがジェットコースターよろしく乱高下した。今回はその続き、魯山人館のコレクションを見た感想を書いていく。
私が足立美術館を長年訪れたかった理由、それは同館が所蔵する魯山人の作品群が見たかったからである。3年前にそれらを集中的に展示する魯山人館ができて以来、その思いはコロナ禍の中で一層強くなるばかりだった。同館から取り寄せ、眺めては嘆息していた作品群をついに今日、生で見ることができる。魯山人館へと向かう足取りが自然と軽くなってしまう。
絵画でさえ生で見ればサイズ感や画材のマチエール、そこに光が当たって生ずる陰影など図録からでは得難い情報が得られるのだ。いわんや立体物である彫刻や陶磁器をや。口縁の鋭さにリズム感、写真に写っていない裏面の様子、等々。その点に関しては実に「期待通り」であった。もっともここで言う「期待通り」とは「図録以上に楽しませてくれた」という意味である。図録と違わないことを確認する程度でいいならハナから安来まで出かけていく必要なんて無いのだ。
ところで、作品の「作者」とは誰を指すのだろう。前回挙げた《雪中棲小禽》などは榊原紫峰が自ら描いたものだから、作者は榊原紫峰だと言える。しかし魯山人は工房の職人に指図して土練りやろくろ成形をさせ、自分で形を整えたり絵付をしてから窯に詰めた。魯山人自身は「誰がやっても同じ所までは態々自分でやらなくても良い」との考えに基づいて職人にそうさせたのだが、これをして「魯山人の器は職人との合作じゃん」と言う人もいる。
では、そういう人はピカソの陶器をピカソと職人の合作と言うのだろか。ピカソの絵画をピカソと絵の具メーカーの合作と言うのだろうか。先の理屈が通るなら富嶽三十六景は北斎と彫師や摺師の合作ということになるし、弟子に擦らせた墨や挽かせた胡粉で描いた日本画は師匠と弟子の合作になる。白山吉光は素材となる鉄を製錬した大鍛冶と、小鍛冶である粟田口吉光とその相槌、鍛えた刀身を研磨する研師の合作になる。
「作品は、完成するまでの全工程において関与した人間すべての合作」というスタンスを取り続けるなら、それはそれで構わない。しかし私としては、作品を作品たらしめる核となる部分を手掛けた人を作者と呼んで構わないと思う。

図録『北大路魯山人 美と食を極めた芸術家』
(足立美術館)より
この皿(平向)は魯山人の代表作の1つであるカニの平向である。色々なバリエーションがあるが、ここまで緑釉が淡いものは初めて目にした。これは職人が練っただろう粘土を魯山人が成形し、釉薬をかけ、絵を描いて、職人が焼成した「魯山人」の作品です。ではこれに料理を盛り付け、他の酒器を取り合わせたらどうなるでしょう。

この写真は上記の図録からの引用だが、魯山人館内でも平向の横に展示されていた。刺身の鯛、山葵と薬味のトリコロール配色、取り合わせられた徳利と酒呑、それら全てが程良く調和し、器単独で見た場合よりも面白みが増している。
私の考えでは、この取り合わせは魯山人ではなく料理人による作品となる。どの器にどんな料理を盛り付け、どんな器と合わせるか。明確な美意識をもって巧みに取り合わせられ、人の心を動かしうるのであれば、それは料理であっても立派に創作や表現、作品と呼んで差し支えない。
今回の足立美術館訪問において、魯山人館の魯山人作品は期待通りに私を楽しませてくれた。そして名も知らぬ料理人による「器と料理の取り合わせ」という作品は期待以上に私を楽しませてくれた。足立美術館、遠いけどまた行きたくなる美術館である。願わくば次は雪化粧した庭園が見たいものだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
