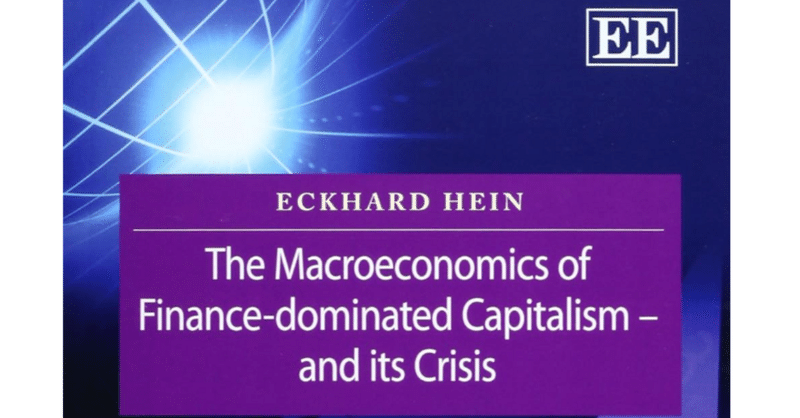
Stock-Flow Consistent ApproachとSFC Modelの隔たり、学派の融合はおこりえるか?[ポストケインジアン経済学]
本稿の目的は、Stock-Flow Consistent Modelが演繹する結論に観察される多様な解釈が、様々な学派を統合するための統一的形式体系としてStock-Flow Consistent Approachをコンセンサスに据えることの重要性を考察することである。
ストックフロー一貫アプローチ(SFCA)は、Relaventにフローとストックの関係性を一貫して書くための手法を教えてくれる。SFCAが規定するのは、その絶対的な一貫性のみであり、その一貫性を保持できるなら、そのアプローチの上に構築されるモデル群に方法論的制約を課さない。したがって、これはモデルを構築する上での前提であり、経済モデルがどうあるべきか?を規定する形式体系そのものであり、モデルがどのような方法論を持つかを規定はしない。実際、合理的な規範を持つ主体を考えて、SFCAに準したモデルを立てることは何らおかしな事ではないし、エージェントベースSFCはその先進的な例と言ってよいだろう。
問題は、そうして作られたSFCAに準じたモデルが示す結果が、解釈するにはあまりに多様すぎることにある。というのは、HeinのThe macroeconomics of finance- dominated capitalismで示されるカレツキアン型SFCモデルは、その典型例と言っていいほど、短期から長期までのモデルの示す情報に思想的一貫性を見出すことが難しい。
この記事はHeinの本(The macroeconomics of finance- dominated capitalism – and its crisis)を丸々翻訳することを目的としていないゆえに、Hein自身が著しているモデルへの解釈を説明することはない。あくまで、Heinのモデルは本稿の目的を示す上での例でしかない。
静学ストック・フロー一貫企業負債モデル
これは私の知るうえでも、最も単純かつ分析的なストック・フロー一貫成長モデルの一つである。これは標準的なカレツキアンの立場からSFCA上に構成されたモデルが、カレツキアンモデルの伝統的な帰結を否定する良い例である。また、これは今まで紹介したことのない「静学的SFCモデル」で企業負債のみを考慮した、政府部門を取り除いたモデルとなっている。
モデルの導入
これは一財モデルで、レオンチェフ型生産関数を採用し、資本係数は1とする。またバドゥーリ・マグリン型投資関数の亜種を採用する。
主体はWorkers' household(労働者)とRentiers' household(資本家)、Firms(企業)の三者で構成される。このうち資本家と企業のみがストック変数を持ち。労働者は強い信用制限を課されているとする。
価格決定はマークアップ式を採用し、マークアップ率は利子率の関数であり、その一階微分は正である。
短期均衡は、ストック変数の変化を考慮せず、稼働率が完成している状態とする。中期均衡はストック比率の定常点収束が達成されている状態であり、長期均衡は経済の自然成長率への収束を意味する。
以下はモデルのマトリクスである。


価格決定と分配
価格: $${ P=[1+m(\rho)] \times( \frac{w}{y}) }$$
m , $${ \frac{\partial m}{\partial \rho}>0 }$$:マークアップ
w: 一人当たり名目賃金
y: 労働生産率
利潤分配率: $${ h=\frac{\Pi}{PY}=\frac{m(\rho)}{1+m(\rho)}}$$
総利益: $${\Pi=h\times{PY}}$$
Y: 実質生産高
ρ: 要求利子率
資本のファイナンス、資本家の収入
総資産利益率:$${r=\frac{\Pi}{PK}=\frac{\Pi}{PY_f}=hu}$$
稼働率: $${u=\frac{PY}{PY_f}}$$
K: 実質資本ストック
Y_f: 最大実質生産高
外部資金比率: $${\gamma=\frac{B+E_R}{pK}}$$
内部資金比率: $${\phi=\frac{E_F}{PK}}$$
利息と配当: $${R=\rho(B+E_R)}$$
財市場均衡、貯蓄・投資関数の定義
貯蓄関数(σ)
$$
\sigma =\frac{\Pi-R-s_r\times R}{PK}=r-(1-s_r)\rho\gamma
$$
投資関数(g)
$$
g=\frac{I}{PK}=\alpha + u\beta + h\tau - \theta\rho\gamma
$$
s_r: 資本家の貯蓄性向
I: 投資高
α, β, τ, θ: 投資関数の係数
注意されたいのは、利息と配当の定義より、利子率が二つの負債に等しくかかっていると考えたくなるが、実際はそうではない。これは、あくまで有利子負債からの収入と株式からの配当の総和が、有利子負債と株式の総和に利子率をかけた値と同じでなければいけないと定義しているだけであり、個別の負債にかかっている収益率は未定義である。二種の負債を用意しているのに、それらのポートフォリオ選択を明示化しないのは不可解に思われるかもしれないが、このような定式化は、むしろ制度的な側面や、ヒューリスティクスを考察する余地をモデルに残すための措置であり、ストックフロー一貫ながらも資本構成の詳細をブラックボックス化させる手法の一つである。
短期均衡
ケインジアン安定条件($${\frac{\partial \sigma}{\partial u}>\frac{\partial g}{\partial u}}$$)が成り立っているなら、経済は安定的に均衡稼働率に収束する。そのような稼働率は以下のとおりである:
$$
u^*=\frac{\alpha+h\tau+\rho\gamma(1-s_r-\theta)}{h-\beta}
$$
また均衡の稼働率より、短期均衡総資産利益率と成長率がわかる。
$$
r^*=\frac{h[\alpha+h\tau+\rho\gamma(1-s_r-\theta)]}{h-\beta} \\ g^*=\frac{h(\alpha+h\tau)+\rho\gamma[\beta(1-s_r)-h\theta]}{h-\beta}
$$
まず、すべての短期均衡において、アニマルスピリット・自律的投資($${\alpha}$$)の上昇は正の効果をもたらす。
$$
\frac{\partial u^*}{\partial \alpha}>0,\frac{\partial r^*}{\partial \alpha}>0,\frac{\partial g^*}{\partial \alpha}>0
$$
これ自体は特異ではないが、のちに重要になる。
次に、要求利子率が与える短期的影響を考える。要求利子率による各均衡値の一階微分は以下のとおりである。
$$
\frac{\partial u^*}{\partial \rho}=\frac{\gamma(1-s_r-\theta)}{h-\beta} \\ \frac{\partial r^*}{\partial \rho}=\frac{h\gamma(1-s_r-\theta)}{h-\beta} \\ \frac{\partial g^*}{\partial \rho} =\frac{\gamma[\beta(1-s_r)-h\theta]}{h-\beta}
$$
ひとまず、ケインジアン安定条件より分母は常に正である。したがって、一階微分の正負は分子によって決定される。すると、短期における要求利子率の変化が経済に与える影響は、複雑な条件に加えて幾分か特異な結果をもたらすことが見て取れる。
レジーム分析
"Contractive" regime
縮小的レジームは最も理解がしやすい。このレジームの発生条件は以下のとおりである。
$$
1-s_r<\theta
$$
この時、すべての一階微分は負となる。つまり、「$${\theta}$$:利益分配への反応係数」がもたらすネガティブな作用が、要求利潤率の上昇によって引き起こされる資本家への利潤収入増加では相殺できず、その負の影響が投資・生産高・利潤のすべてにおいて現れてしまうようなレジームである。
"Profit without investment" regime
次に、投資なき利益レジームである。
このレジーム発生条件は:
$$
\theta<1-s_r<\frac{h\theta}{\beta}
$$
このような条件において、短期均衡の一階微分は以下の通りになる。
$$
\frac{\partial u^*}{\partial \rho}>0, \frac{\partial r^*}{\partial \rho} >0, \frac{\partial g^*}{\partial \rho}<0
$$
つまり要求利子率の増加は、レジームの名前の通り、投資量を減らしながら利潤を増やす。このレジームは、利子率の増加は投資をトレードオフに利潤を増やしている。これは最も直感的なレジームの一つでもある。利息と配当支払いを増やしたことで、投資に資金を回すのではなく分配しているのだから、成長率が犠牲になる代わりに利潤率を上昇させる事ができるのは不思議ではない。
"Finance-led growth" regime
最後は金融牽引レジームである。
このレジームの発生条件は:
$$
\frac{h\theta}{\beta}<1-s_r
$$
であり、その際の要求利子率が与える経済的影響は:
$$
\frac{\partial u^*}{\partial \rho}>0, \frac{\partial r^*}{\partial \rho} >0, \frac{\partial g^*}{\partial \rho}>0
$$
であり、すべての項目において正の影響をもたらすことになる。さらなる利潤要求は、市場の利子率と配当率を上昇させる。しかしながら、それが投資をトレードオフにすることなく、加速度的に投資高も引き上げる結果となる。
マクロとミクロについて
縮小的レジーム・投資なき利益レジームの二つは、ポストケインジアン的ミクロ企業論と接続できる。x軸を成長率、y軸を総資産利益率とするグラフにファイナンスフロンティア(FF)・拡張フロンティア(EF)と貯蓄関数を描画してみると以下のように図解できる。ここで、マクロレベルの要求利子率の増加は、ファイナンスフロンティアと拡張フロンティアに影響を与えないとする。

わかりやすさの為に、経済がFFとEFの交差点にあったとし、要求利子率が増えた場合の曲線のシフトを描画した。σ0よりσ1へとシフトしたことで、ミクロでの企業が経験する変化には二種類あることがわかる。このグラフ内で、貯蓄関数はマクロレベルで存在可能なすべての成長率と総資産利益率の組み合わせを示している。そして、FFとEFはミクロで存在可能な成長率と総資産利益率の境界線を示している。すると、少なくともマクロレベルで存在不可能かつ、ミクロレベルでも存在不可能な利益と成長率を経験している企業が長期的に持続可能でないことは想像に容易い。つまり、成長最大化を行う企業にとっては、FFと貯蓄関数の交点で表される成長率と利益率が持続可能な組み合わせの限界点であり、持続不可能な成長率と利益率は持続可能なそれに引き戻されなければならず、これは縮小レジームと同じ反応である。そして同様に、利益優先とする企業は、EFと貯蓄関数の交点までが持続可能な組み合わせの限界を示している。
問題は金融牽引レジームだが、それを描画すると以下のようになる。

金融牽引レジームは、成長率と利益率の両方を押し上げるが、これはミクロからすれば実現可能でない領域に存在しており、合成の誤謬といえるだろう。
中期均衡
短期均衡が常に達成されているとし、外部資金比率(γ)や内部資金比率(φ)といったストック変数の定常地点を分析する。
企業の株式と有利子負債の変化量は、トランザクションマトリクスの定義より、以下の通りである。
$$
\Delta(B+E_R)=\rho s_r(B+E_R)
$$
よって、外部資金比率(γ)の変化率($${\hat{\gamma}}$$)は、対数をとって時間で微分すると:
$$
\hat{\gamma}=\rho s_r-g^*
$$
したがって均衡外部資金比率は:
$$
\gamma^*=\frac{s_r\rho(h-\beta)-h(\alpha+h\tau)}{\rho[\beta(1-s_r)-h\theta]}
$$
となる。中期均衡が安定的である条件は$${\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial \gamma}<0}$$であり、これが達成される条件は:
$$
\frac{h\theta}{\beta}<1-s_r
$$
これは金融牽引レジームの発生条件と同じである。
この結果の特異性を理解するために、金融牽引レジームの説明を思い出してほしいのだが、このレジームは加速度的な利潤・投資増加が利子率の引き上げによって起こされるような経済なのである。つまり、利子率の上昇に対してネガティブな反応を示すような、利子率の上昇が投資を抑制し、新たな借り入れを抑制する経済ではなく、利子率の上昇がさらなる投資を呼ぶ直感的に安定でないような経済レジームのみが中期安定性を保証している。
中期均衡の考察と解釈
このモデルの中期均衡は非常に面白い性質を持っている。
まず均衡成長率に関して言えば、中期均衡の定義より以下の値でなければならないことがすぐにわかる。
$$
g^{**}=s_r\rho
$$
問題は、この均衡は純粋に構造的要因によってのみ決定されているということで、これはむしろ古典的・スラッフィアン的な視点に近い。ポストケインジアンにとって、この式と最も見た目が似ているのはケンブリッジ方程式だろう。
$$
r=\frac{g}{s}
$$
この式は投資が利潤率を決定し、その逆ではないことを示す。最も初歩的なポストケインジアンの教科書(Lavoieなど)で頻繁に登場する恒等式の一つである。しかし、このモデルの中期均衡は明らかに逆の因果を示している。要求利子率と貯蓄性向が成長率を決定するのであれば、それはカレツキアンの主張する長期的な有効需要の役割を否定したことになる。なぜなら、これが中期における成長率であるなら、中期的に自立投資が経済に与える影響は:
$$
\frac{\partial g^{**}}{\partial \alpha}=0,\frac{\partial u^{**}}{\partial \alpha}<0,\frac{\partial r^{**}}{\partial \alpha}<0
$$
のみならず、有効需要に関する反応性(β)も上記と同様の結果をもたらす。よって成長率に有効需要は変化を起こせないだけでなく、稼働率と総資産利潤率に関してはネガティブな影響を与えているのである。
これを正しく理解するためには、なぜこの均衡が「要求」されるのかを、より深く理解する必要がある。
上記の式は中期均衡の条件から直接導かれるが、中期均衡達成のために調整式が果たす役割を思い出してほしい。調整式は、ストックとフローが一貫するような経済モデルならば保持されるストック比率の変化に関する定義を示しているだけに過ぎない。その「ストックフロー一貫性」とは、トランザクションマトリクスより、資本家の保有する有利子負債+株式(=企業外部資金)の変化率が資本ストック(企業総資産)の変化率より大きいなら、資本家の資産は企業の総資産に比べて相対的に減っている必要があるということである。したがって、この”中期均衡成長率”は「SFCAから構造的に要求された値」であるのだから、中期均衡成長率というよりは、ストック比率の一貫性と安定性を保つための「要求成長率/Warranted Rate($${g^{**}}$$)」と呼ぶべきであり、本稿ではそう呼称する。この要求成長率が、カレツキアンモデルの否定ではないこと、有効需要の否定ではないことが分かった。しかし同時に、スラッフィアン・古典的な均等利潤率の概念とも共存可能といえるのではないかと思えてくる。
ちなみに、短期の「縮小的レジーム」および「投資なき利益レジーム」の条件の下では、資本家の利子所得が増加すると投資が減少し、均衡には到達しない。これは中期的な外部資金比率の不安定性を意味し、要求成長率$${g^{**}}$$は、ナイフエッジを髣髴とする不安定性を含んでいる。
$$
\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial \gamma}=\frac{-\rho[\beta(1-s_r)-h\theta]}{h-\beta} \\ \frac{\partial g}{\partial \gamma}=\frac{\rho[\beta(1-s_r)-h\theta]}{h-\beta}
$$
上記より、要求成長率からのどんな逸脱も、この成長率からの爆発的な逸脱を引き起こし、中期均衡の不安定化プロセスは「外部資金比率の上昇と成長率の継続的低下」または「外部資金比率の減少と成長率の継続的増加」のいずれかである。ちなみに、これはシュタインドルの「負債のパラドックス」と似ている。彼の「負債のパラドックス」は、成長率の低下(上昇)は企業に外部資金比率を減少させる(増加させる)試みを促すが、そのような行動のマクロ経済的効果は逆説的に外部資金比率が増加する(減少する)ような現象を意味する。
どちらにせよ、これは長期的には有効需要が関係ないとっているわけでない。要求成長率に回帰するには、そもそも金融牽引レジームを成り立たせる必要があり、その条件には有効需要に関する項(β)が入っている。強調されるべきは、要求成長率が要求利子率・貯蓄性向といった「他者をクレジットし、リソースをコントロールできる主体が任意に決定できるような変数」で決定されていることだ。また、確かに中期均衡は金融牽引レジームでしか達成できない、しかしこれは「投資なき利益レジーム」や「縮小レジーム」が現実に存在できないと主張するものでもない。なぜなら、経済には他の力(特に経済政策)が働いており、この不安定性を抑える可能性があるからだ。確かなのは、シンプルなモデルの結果に基づいて、「縮小レジーム」および「投資なき利益レジーム」の条件を満たすような経済は、本質的にシステム的で中期的な不安定性が存在するということだ。
長期均衡
最後に、軽く長期均衡の問題に触れておこう。
レオンチェフ型生産関数を使っているので、自然成長率と雇用率の関係性は簡単に示せる。ここでの自然成長率($${g_n}$$)は:
$$
g_n=\hat{n}+\hat{y}
$$
nは人口成長率、yは労働生産性であり、ハット($${\hat{}}$$)がついているので、上記はその変化率を意味する。
次に雇用率の変化率は以下のとおりである。
$$
\hat{E}=g-g_n \\ \hat{E}=g-\hat{n}-\hat{y}
$$
Eは雇用率を示す。雇用率は当然0から1までの範囲しか取れないため、永遠と下がり続けるもしくは、上がり続けるような経済はあり得ない。いづれ成長率は自然成長率と均衡しなければならない。
両者を一致させるために調整できるのは貯蓄率と要求利子率の二つのみである。仮に至極端的に、雇用が増えているなら何らかの貯蓄性向と要求利子率の変化によって要求成長率が低下し、減っているなら増加するように調整したとしよう。そうすると、長期均衡雇用率は経路依存性を持っているとわかる。経済のどこにも、完全雇用を保証するようなメカニズムは存在しない。
したがって、要求成長率というのはハロッドの「保証成長率/Warranted rate of growth」とは全く違い、完全操業を意味していない。
結論
まとめると、標準的なカレツキアン的過程に基づいてSFCA上に作られたこのモデルは、カレツキアンモデルのもたらす一般的な結論を否定し、むしろスラッフィアンや古典派のような性格を持っていた。
これは、SFCAがもたらす構造的制約によるものだったが、この構造的制約という観点から古典派・スラッフィアンを再解釈し、統合してゆく事は、ポストケインジアンの発展に正に寄与するのではないかと考えている。SFCAというフレームワーク自体は、カレツキアン、スラッフィアン、古典派etc..などなど、イデオロギーに問題なく統合することが可能である。そうすれば、そこからカレツキアンSFCM、古典派SFCM、etc….というようにモデルを作ってゆけば、今回のように、相反する主張や結論に、それらを矛盾なく統合的に共存させる道が見えるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
