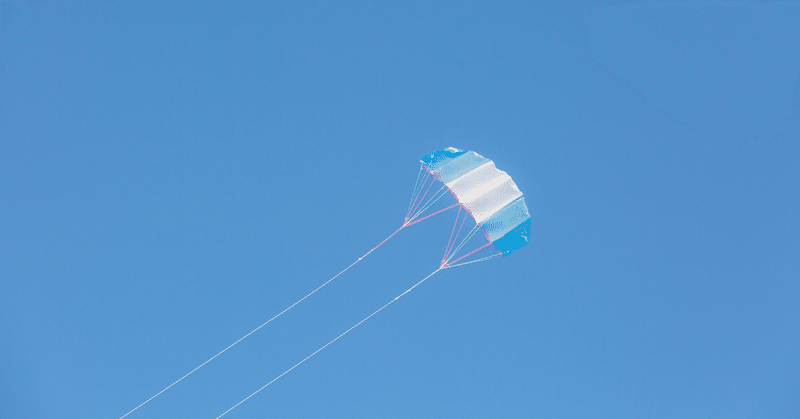
思考コードについて、思考を整理する
今日は思考コード、関連してブルームの認知タキソノミーの話をしようと思います。
思考コード開発の重要人物である本間勇人氏(私立学校研究家・聖パウロ学園校長)とリフレクションをしたのもあり、私がどういう理解をしているのかを整理するために、記録として記してみます。
2015年前後から、東京の私立学校や模擬試験会社である首都圏模試センターで「思考コード」という指標を用いて教育活動を行うという動きがあります。
ちなみに、首都圏模試センターの思考コードと、例えば聖学院中学校・高等学校、工学院大学附属中学校・高等学校、静岡聖光学院中学校・高等学校、和洋九段女子中学校・高等学校をはじめとした21世紀型教育機構(21st CEO)加盟校の思考コードは、少し趣が異なります。
つまり、
思考コードは2つある
ということです。
首都圏模試センターの思考コードはブルームの改訂版タキソノミーの認知的領域「のみ」をもとにつくられています。
理由はシンプルで、首都圏模試センターは「模擬試験会社」なので、試験問題の分析のために取り扱うという事情があったからです。
そもそもブルームがタキソノミーをつくったのは「大学のテスト項目の分類を主たる目的で開発されたという経緯があるから、親和性が高いというわけです。
横軸は改訂版タキソノミーの簡略版
記憶・理解=知識理解思考【A軸】
応用・分析=論理的思考【B軸】
評価・創造=創造的思考【C軸】
縦軸は認知の操作の複雑性
手順操作・単純関係=単純【レベル1】
複雑操作・カテゴライズ=複雑【レベル2】
変換操作・全体関係=変容【レベル3】
ちなみに、文部科学省が掲げる学力の三要素である「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」はそれぞれブルームの認知のタキソノミーのアナロジーと言って差し支えないと思われます。
ここまでの話を整理すると、以下の通りです。
知識・技能=知識理解思考【A軸】≒(過去から現在にかけて積み上げられた)基礎的な知識・技能=知識・技能
応用・分析=論理的思考【B軸】≒(過去から現在にかけて積み上げてきた)知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、行動する力=思考力・判断力・表現力
評価・創造=創造的思考【C軸】≒(過去から現在にかけて積み上げてきた知識や技能の良し悪しを評価し、よりよくしようと取り組もうとする意欲=アクティブ・ラーニング=主体的・協働的・深い学び≒主体的・対話的・深い学び≒学びに向かう力・人間性等
このあたりは以下のサイトをもとに、思考コードや改訂版タキソノミーをベースに、文部科学省における議論を照合して整理してみたものです。
細かいところの差異はあるかとは思いますが、おおよそこのような話だと理解しています。
なお、ブルームは認知心理学者ですので、ピアジェを通過しています。
ピアジェの発達段階理論と照らし合わせると、ブルームの「認知の」改訂版タキソノミーがアナロジーしている様子がわかると思います。
感覚運動期・前操作期(物事を自分のイメージを使って区別・認識できるようになる、0-7歳)≒知識理解思考【A軸】
具体的操作期(論理的思考が発達し(相手の気持ちを考えて行動できるようになる)7-11歳)≒論理的思考【B軸】
形式的操作期(知識・経験を応用し、結果を予測して行動や発言ができる、11歳-)≒創造的思考【C軸】
一方、21世紀教育機構加盟校の思考コードは、学校における教育活動の指針として用います。
それは首都圏模試センターの思考コードのように「認知の」タキソノミーだけでは不足するからです。
ここまでお読みいただくと、文部科学省の学力の三要素の難しいところが見えてくると思います。
ベースは「認知」のタキソノミー。
それをベースに「情動」「精神運動」を埋め込んだ形ですが…
それが「学びに向かう力・『人間性等』(態度)」となったところが…
詳しくはまた改めて。
認知・情動・精神運動、乱暴にいえば「あたま」「こころ」「からだ」全てが絡み合うのが人間としての活動だし、生き方であるということ。
だから、横軸は認知のタキソノミーでよいのだけれど、縦軸は「情動」「精神運動」、そして「人としてどう生きるべきか」という倫理コードを埋め込んでいます。
基本的には
自己の成長のための学び=レベル1
ローカルコミュニティのための学び=レベル2
グローバルコミュニティのための学び=レベル3
という位置付けです。
ただし、各校ともにアレンジをしています。
例えば工学院大学附属中学校・高等学校の思考コードは縦軸と横軸が逆転しているし、知識理解思考と論理的思考を思い切ってA軸にまとめ、創造的思考の中の「批判的思考(過去から現在にかけて積み上げられてきた知は本当にこれからの世界にとって重要な役割を担っているのか、と問うこと)」と「創造的思考(どうすれば自らの才能を世界づくりに役立てられるのか、アクションを起こせば良いのか、起こしたか)」とを切り分け、それぞれをB軸・C軸と置いています。
※ただし、これは2017年のもので、毎年思考コードのあり方を検討・修正しています。今は多分変わっているかと思います。
一方、静岡聖光学院中学校・高等学校は「世の光・知の塩」という世界観をどう思考コードに埋め込みました。
思考コード自体は21世紀型教育機構の標準的なものですが、A軸を「鍛錬」、B軸を「理知・探求」、C軸を「叡智」と意味づけしながら、教育活動を行なっています。
ちなみに、最近以下の記事が拡散していますが、私の理解で読み解くと、上記の2つの意味の思考コードが混在している様子が伺えます。
さて、ようやく本題。
基礎学力のコペルニクス的転回という記事です。
私の理解では
同じものを見ているのだけれど、地と天によって見え方が違う
ということです。
21世紀型教育はA3-B3-C3-C2-C1を基礎とし、その問いからA1-A2-B1-B2との往復をする流れを汲みます。
逆に、既存のいわゆる基礎学力はA1-A2-B1-B2と捉えています。
A1-A2-B1-B2は情報収集すれば載っていることばかりだから、21世紀型教育を推進する側からすると、そもそも「A1-A2-B1-B2を習得することが基礎学力だ」と主張することにどれだけの価値があるのかと問いたくなるということです。
ピアジェがこういう教育観で中等教育をやっている人々を見たら「もう形式的操作期なのに、いつまでその前段階やってるの?」って突っ込んできそうですね。
翻訳すれば、C軸やらずにずっとA軸B軸やっててどうするの?ということ。
ちなみに、総合型選抜対策の側からすると、C3を目指し、A3-B3-C1-C2の往復運動と、その精緻さを追うためにA1-A2-B1-B2との往復運動を続けるわけだけど、それは21世紀型教育と同じ世界観。
集団授業でA1-A2-B1-B2をやると、往復運動がこの領域の中で留まってしまうんですよね。しかもそれで今までの教育実践はそこまででよかった。
だからA3-B3-C1-C2-C3にはみ出ることを避けるし、そもそも知らないし、教育実践を踏襲してもその枠は出られないんですよね。
私はA1-A2-B1-B2から順に外側にはみ出ようとするストーリー、つまり「習得→活用→探究」という段階を踏む流れは否定も肯定もしないんです(経験的にはうまくいかないだろうなと思うんですけど)。
ただ、そもそもその順序になるとは限らないなと。
だから、教科書はよいのだけれど、それをそのまま指導書の通りに扱っていくと習得させるところから離れられないんですよね。
教科書や指導書のようにシステマティックに授業するツールに対する疑問を抱くのは、ここなんです。
教科書を使ってもコペ転できるけど、それができない、やらない。
それはそもそもの学力観の相違から起こっていることだし、骨の髄までA1-A2-B1-B2の学力観が染み付いている証でもあるんですよね。
コペ転したときの想定の細やかさは、他のファクターがなければ指導者側でコントロールする必要はあんまりないのかもしれません。
学び手が情報収集するときの支援やリテラシーの欠如への対処やリスク管理のほうが大事かも。
もしA1-A2-B1-B2への往復に対する細やかさが求められると想定した場合、「教科書範囲を終わらせなければならない」「受験まで間に合わない」というところが大きいと思います。
習得自体は大事なんだと思います。知がないと新たな知がつくれないので。
でも、私が持たない知をあなたがもっている、あなたが持たない知を私が持っているという関係性を許容し、それを対話の中でお互いに持ち寄って新しい知をつくりあげるという地道だけどクリエイティブな営みがもっと大事で。
知を一方的に吸収し、自己完結で終わるのは、世界をつくらないなぁと思います。
ここで、この記事。
「A3B3C3が基礎学力になる」ここが、今ひとつ分かりづらいのかな、と。
そもそも「学力」って何だ、という問いからですね。
日本の今までの教育観だと、三観点でいうところの「知識・技能(主にA軸)」の習得が基礎学力にあたるというイメージから出発していますね。
それをもとに追って「思判表(主にB軸)」が足されて…というところですね。
しかも、その「知識・技能」「思判表」は「自己の(レベル1)」学力向上のため、「グループでの(レベル2)」学習活動のために行われるという現実があるんです。
だから、
思考コードで言えばA1-A2-B1-B2で終わる教育活動となる基礎学力観だという話
だと理解しています。
この基礎学力観と違う見方がA3-B3-C1-C2-C3です。「世界」の諸問題や未来のため(レベル3)、自己の才能を発揮してクリエイティブに生きる(C軸)とところを起点にしています。
これを基礎学力と捉えれば、学びもあり方も変わるでしょう?という問いかけだと思います。
これをもっと乱暴に言えば、
出発点がそもそも違う。
「自分のために学ぶ(個人のパフォーマンスを重視する学力観)」のか「世界や未来のために学ぶ(他者との協働によるパフォーマンスを重視する学力観)」のか、ということなのかなと思います。
後者は「自分は何者でありたいのか」ということを問われ続ける営みです。
前者の教育観が強い日本で「自分は何者かが問われない」のは当然かなと。
ちなみに、学力を英語で訳すとacademic ability(学術のための能力)。knowledgeではないんです(だから知識偏重の教育が否定されるのは、こういう感覚を持っている方に多いのではないかなと推測します)。
では、何のための学術なのか、能力なのか、ということが問われるわけです。
しかもA1-A2-B1-B2で終わる学力観で育つ子どもたちは、「世界」「協働」「クリエイティビティ」の種が育ちにくいというところが問題で。
それらの能力を鍛えられる教育環境で育った高度外国人人材が日本にやってきたときに、そうした人々にその子たちが使われてしまうという絵面が想像できます…考えすぎなのかもしれませんが。
もっというと、目的というのもレイヤーがあって、ここでは最上位の概念を共有しましょうということなんですよね。
黄金律をブリッジにしてどういう宗教でも土着の文化を持っていても隣人愛は共有しているよね、と。
しかもその隣人愛は隣人の隣人も含まれる(Men for othersではなくMen with others)を共有できるか、です。
教育基本法の前文に教育の目的が示されていますが、「世界の平和」「人類の福祉の向上」と示されているということを、常に教育活動の中で参照することが大事なのだと思います。
教育を通してこういう世界観を伝えることが、我々の使命だと思っています。
大きな大きな目標となるので、光が見えては消え、見えては消え、の繰り返しだし、どれが答えかわからない中での模索になるのですが、それこそが「答えのない問い」であるのだなと身に染みています。
「答えのない問い」を平易に捉えてしまう向きがありますが、それは本当に自己と世界が繋がっていることを意識してのものなのかは、きちんと見極める必要がありそうです。
何でもかんでも「答えのない問いだ」というのはちょっと…
予備校講師や塾経営者や学校コンサルティングというやや俗世間寄りの立場ではあるのですが、こういう思いは忘れないように日々生きていこうと思います。
本年も皆様方のご支援に心から御礼を申し上げます。
良いお年をお迎えください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
