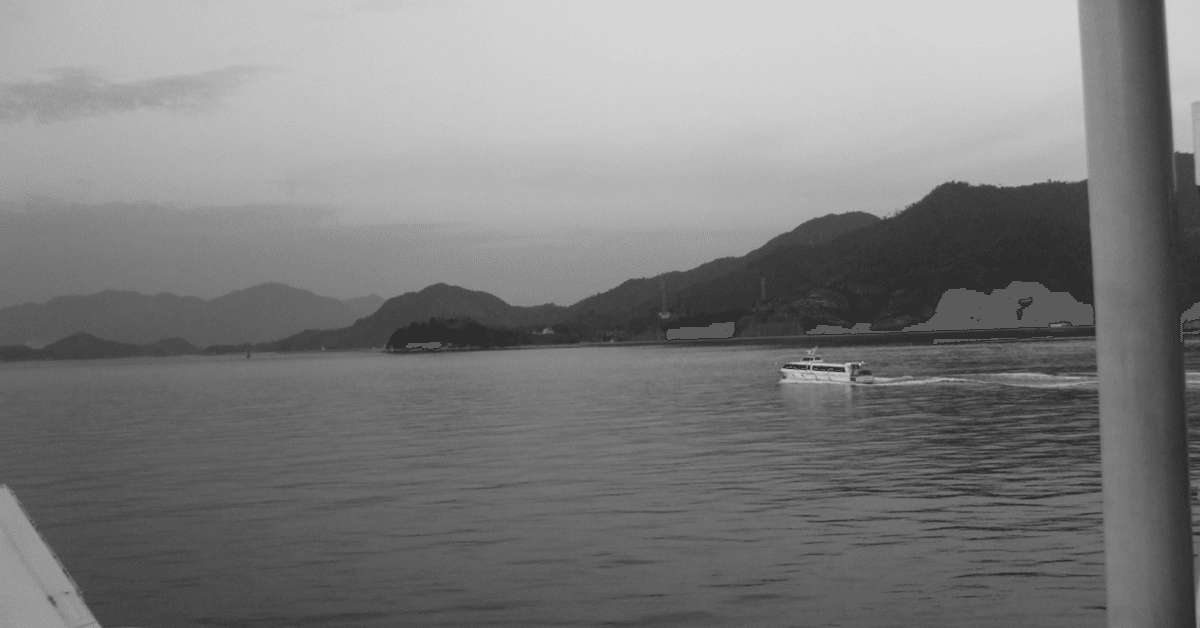
「浦からマグノリアの庭へ」 小野正嗣
白水社
小野正嗣の書評とエッセイ
大分県佐伯市…昔の蒲江町出身の小野氏の(たぶん)初エッセイ。前に読んだボルヘス論の他、W先生とM先生のラブレーは宮下志朗訳ガルガンチュア第1巻の解説からの再録。
研究者・詩人・翻訳家そして菓子職人のクロードのオルレアンの家にお邪魔してのフランス生活。を描くエッセイ編を挟んで、こうした書評や批評が並ぶ。その中には「ミスター・ヒップ」、「死者の軍隊の将軍」「アラブ、祈りとしての文学」など、自分が読んでいた本も含まれて嬉しい限り。
まだたどり着いていないけど、後の方に、クルタークの家に行く、という話があってそこまで読みたい。リゲティと同じ出身の作曲家だが、クルタークはずっとルーマニアに留まった。
(2020 02/28)
ラブレー二大訳者
上のラブレー論。最初の方こそW先生(渡辺一夫)とM先生(宮下志朗)の翻訳の比較で楽しみながらニヤニヤする展開だったが、後半になると、看過できない指摘が次々出てきて困った?展開に。
『ガルガンチュア』の「前口上」において、飲み食いの場所と言葉が発せられる場所が一致していることに注意を促すミシュル・ジャヌレの指摘は傾聴に値する。
(p44)
そしてこのラブレーの時代、ルネサンスの流れで、読書という行為が変わりつつあった時期でもあった。文献学の発達とともに、テクストをそれが書かれた時代・文脈を理解して読んでいく、という今では当たり前になっているそういう読み方が出来上がりつつあった。
ルネサンス期の注釈の発展は、賞味され研究されるべき「創造的作品・芸術作品」としての「本文テクスト」と「批評」としての「注釈」とのあいだの分離を促進するが(それが十七、十八世紀に「文学」という概念が生まれる)、同時に、その境界を曖昧にする傾向も生まれる。注釈行為そのものをテクスト内部に取り込んだ「作品」が生じるのである。
(p49)
(2020 02/29)
浦の作家
前に(たぶん)読んだボルヘス論のところは抜かして、マリー・ンディアイのところから書評の半分まで。
このインタビューで、とても印象的だったのは、マリー・ンディアイがまるで着慣れた肌触りのよいショールのように身をまとっていた静けさだった。僕が問いを発するたびに、そのショールがかすかに揺れるのが見えるようだった。ショールはこちらの質問の声を吸収し、沈黙を作り出す。そしてそれはまた、僕に答えて発せられるンディアイの声ー穏やかでやさしい声ーを包み込むので、そのために彼女の声が僕に届くまでに時間がかかる。
(p102)
ンディアイの魅力自体もそうだけど、その場に居合わせているかのような小野氏の書き方に惹かれる。
ンディアイの夫、ジャン=イヴ・サンドレもまた作家。静のンディアイに対して動のサンドレという感じらしい。そのサンドレはブルターニュの小さな村での、老先生による児童虐待行為を摘発した(その後それに関する本も書く)。ンディアイの方の作品については「家族」というものの捻れた拘束性と身体的表現に特徴があるという。
次のマグノリアの章は、例のポルトガル系のイネスというヘルパーさんの一家に降りかかる悲劇が中心。
「悪」は触れるだけで感染する。「悪」は、日常的なものとして、つまり生活の前提としてそこにある場合、いわば知覚や判断を限界づけるものとして、子の思考・行動を癒やしがたく左右する。
(p109)
その他、学内いじめのリーダー的存在の少年の父親が、学校関係者及びいじめの被害者の親(アルジラというイネスの代わりに来た人もその一人)らの前で、ベルトを振り上げ罰するというより破壊欲求を満たすように少年を痛めつけてという挿話も痛ましい。その父親が移民としての理不尽さに耐えてきたことの転移でもあるだろうから。
書評ページから。
デニス・ジョンソン「ジーザス・サン」から
現実が非現実のただなかに浮かぶ小島のようなものだとしたら、この小説の声はまさしくその波打ち際から聞こえてくる。意味の模様を描く淡い波の下に、意味が切り出される無意味の「地」までが、見えなくてもいいものまでもがありありと目についてくる。
(p144)
姜信子「イリオモテ」から
他者の言葉が、それを運ぶ息が分かちがたく自分と混じり合う。それはもう単に「聞く」ことでも「読む」ことでもない。いっしょに「歌う」ことだ。見知らぬ土地でふっと途切れた、見知らぬ人たちの命とその記憶の糸を著者とともに「つないで、結んで、響かせ」ることなのだ。
(p147)
書評ページに入ったところで、2008-2009のここでの紹介された本を列挙…
フリオ・リャマサーレス「狼たちの月」
エンリーケ・ビラ=マタス「バートルビーと仲間たち」
堀井照陰「限界集落」
大江正章「地域の力」
レナード・ツィプキン「バーデン・バーデンの夏」
コーマック・マッカーシー「ザ・ロード」
アルベルト・マングェル「図書館 愛書家の楽園」
マリー・ンディアイ「心ふさがれて」
ポール・オースター「幻影の書」
堀江敏幸「未見坂」
岡真理「アラブ、祈りとしての文学」
沼野恭子「ロシア文学の食卓」
デニス・ジョンソン「ジーザス・サン」
フィリップ・プティ「マン・オン・ワイヤー」
姜信子「イリオモテ」
ロイド・ジョーンズ「ミスター・ピップ」
イスマイル・カダレ「死者の軍隊の将軍」
ガルシア=マルケス「生きて、語り伝える」
蓮實重彦「映画論講義」
アール・ラヴレイス「ドラゴンは踊れない」
村上春樹「1Q84」
エルサ・モランテ「アンダルシアの肩かけ」
リュドミラ・ウリツカヤ「通訳ダニエル・シュタイン」
オスネ・セイエルスタッド「チェチェン 廃墟に生きる戦争孤児たち」
マリー・ンディアイは「ロジー・カルプ」(小野氏訳?)も。
「1Q84」から
素晴らしい作品は読者一人ひとりの心と同じ大きさの空間を作り上げる。だが自分の心の大きさを把握している人などいない。作品の途方もない広がりと深さに触れることで、私たちは自分の心の複雑さや豊かさ、奥の暗がりでうごめく非合理なものや暴力的なものの存在をしるのである。
(P156)
「アンダルシアの肩かけ」から
夢と現実のあいだの境を気づきもしないで踏み越えることができるのは、子供だけに許された特権なのだろうか。本書に収められた短編に出てくる少年や少女はみな夢見がちで、「秘密の遊び」の子供たちのように、物語や空想を現実以上にリアルに生きる。だが理想化された架空の人物になりきった子供たちが、現実とちがうゆえにいっそう甘美な〈生〉に陶酔して、文字通り〈我を忘れる〉とき、その(我〉は暗く冷たい死の影のなかに置き忘れられている。
(p158)
次のマグノリアの章は、クロードとエレーヌのところにやってくる移民・難民の人たち。カンボジア、コートジボワール、イラン…(フランスでは国内で生まれた子供は基本的にフランスで保護されるが、親はそうではない。だから親は苦悩する)
基本的に「書く」ことは孤独な営みである。他者の書いているものと自分の書いているものを比較するなんて不可能だ。それぞれが自分のトンネルを掘るように書きつづけるほかない。
(p171)
(2020 03/06)
カズオ・イシグロと大江健三郎
昨夜はこの続きで第4部「ふるさと」からカズオ・イシグロと大江健三郎のところまで読んだ。前者ではイシグロの作品では作者が全く消えて作品の語りに同化しているという指摘(「普遍的で明確なテーマを、いわば現実の陰影だけで浮かび上がらせる」訳者飛田茂雄の言葉)、後者では大江健三郎の古義人三部作?に出てくる分身・二人組の存在と人はそもそも誰かの生まれ変わりであるという四国の木に止まって生まれる命を待っている魂という伝説を踏まえての指摘。
坂口安吾と中上健次
続いて今日は坂口安吾と中上健次の章。
まずは「ふるさと」について安吾から。
しかし、安吾の「ふるさと」は、「透明な切なさ」のなかにある。抽象的でインパーソナルな無機質な世界にある。
(p208 柄谷行人「坂口安吾と中上健次」)
という「ふるさと」という言葉とは正反対だと思えるこうしたイメージを取り掛かりとして論は進む。
私たちはいきなりそこで突き放されて、何か約束が違ったような感じで戸惑いしながら、然し、思わず目を打たれて、プツンとちょん切られた空しい余白に、非常に静かな、しかも透明な、ひとつの切ない「ふるさと」を見ないでしょうか。
(p217 坂口安吾「文学のふるさと」から)
バルザックとの共通点(安吾はバルザックを愛読していた)「海辺の髭」や「ルイ・ランベール」などとの比較も興味深い。
蒼い空と海、砂浜、松林ーこれは満たされない欠乏を満たすために見出された風景である。あるいは欠如に満たされた風景だといってもよい。
(p224)
前文と後文は本当に等価なのか?
一方中上健次は、さっきの柄谷行人に坂口安吾を読むよう勧められ「ふるさと」論に感化される。でも安吾の拒絶されたような風景とは異なり、中上健次の「ふるさと」は容器であるように思える。主に「鳳仙花」から。
その堤に立っていると、いまさっきまでいた闇市も路地も幻のように思え、それが勝一郎なのか龍造なのか分からないが、フサの恋した草の匂いのする男が、向う側の山から川を泳ぎ渡ってすぐそばに歩いてくる気がするのだった。
(p226)
相手の男のそれぞれの輪郭が曖昧にぼやけてくる。それは匂いというものの特質であろう(ここで取り上げられているフォークナーだけでなく、草という言葉からクロード・シモンも思い出す)。
不在の現前。匂いは存在を空間的に偏在させるだけでなく、時間のなかに拡散していき、失われた過去をも連れてくる。
(p226)
(2020 03/07)
副テーマとしてのサミュエル・ベケット
最終章のマグノリアから。ここでの大きなテーマは「受け入れる」こと…
呼びかけそのものが贈り物なのかもしれない。呼びかけられるとはどういうことだろうか。呼びかけるものが僕たちの存在を認めている。僕たちがここにいることを受け入れてくれているーそういうことではないか。自分の存在をありのままに受けとめてもらえることほど貴重な贈り物はない。
(p244)
言葉は発せられ、書きつけられた瞬間、望もうが望むまいが他者へと差し出されている。そして、それを受け取りたいと思っている人がいる。
(p246)
受け取るとは、自分の「内部」に「外部」を受け入れる空間を作り出すことでもあるのだろう。
(p252)
この辺、自分が一番苦手としているところではある。
話題としては、旧ユーゴスラビア紛争から逃れてきたクロードの友人を介してのクルタークの家訪問(ンディアイと同じく、この時期はボルドー近郊に在住)、アブダビでの翻訳プロジェクト、クロードと共に韓国の詩人、作家との交流など。
この本、これで読み終えたわけなのだが、実は隠しテーマというのがサミュエル・ベケットなのではないか、と特に後半に関して思った。大江健三郎のところでも、坂口安吾のところでも、クルタークのところでも。自分にとってベケットというのはどうしてもアイルランドのイメージだけしかなかったのだが、ベケットは英語とフランス語半々で書いている。小野氏にとって、ベケットは生涯追いかけている作家に違いない。
というわけで、最後にここを引いておく。
そういえば、サミュエル・ベケットの『モロイ』の最後の場面で、語り手のモランは庭に出て、野生の鳥たちの声に耳を澄ます。「私は彼らの言語をよりよく理解しようとしてみた。私自身の言語に頼ることなく」。その直後、彼は自分にあれをしろ、これをしろ、と言ってくる「ひとつの声」について語る。彼はどこかから聞こえてくるその「声」の命じるままに動いてきたわけだが、彼はその「声」を自分が本当に理解しているのかどうか確信が持てない。「私ははじめ声が何を意味しているのかわからなかった。しかし私はついにその言語を理解した。私は理解した、理解している、たぶん不正確に」。人間の使う言葉では、モランを動かす「声」の意味も鳥たちの鳴き声の意味も理解することはできない。その「声」は、たぶん鳥たちの鳴き声と同じ言語に属している。鳥たちの言葉がわかるようになれば、人間存在をつき動かすこの不思議な「声」の正体ーそれがどこから発せられ、何を伝えようとしているのかーがわかるようになるのかもしれない。
(p255-256)
たぶんこれが、翻訳、そして芸術活動全てにわたる過程になるのだろう。
ところで、クロードとエレーヌの庭40周年には果たして行ったのかな。
(2020 03/08)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
