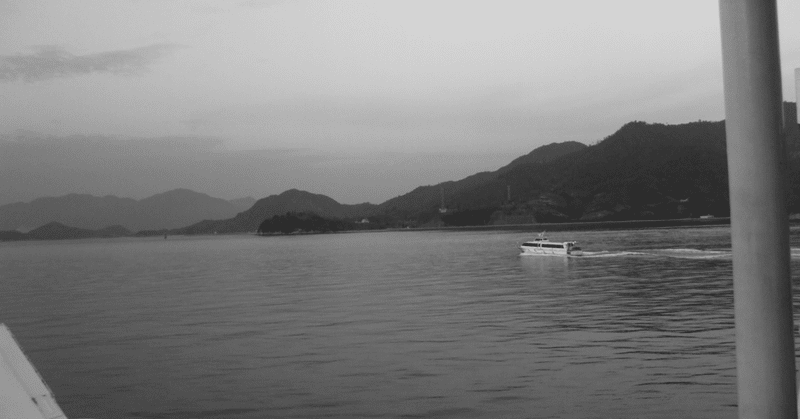
「贈与論」 マルセル・モース
吉田禎吾・江川純一 訳 ちくま学芸文庫 筑摩書房
カワウソの子
昨日からモースの「贈与論」読んでいる。
ここで議論の中心になっている「贈与」とは、人間世界に広く見られ、この当時はメラネシアや北米インディアンの間で多く注目されていた「ポトラッチ」等などを指している。それは贈与→受取→返礼と続く一連の活動で、しばしばそのモノの浪費やもっと言えば破壊なども伴う。前に読んだマフリノスキーのトロブリアント諸島のクラもその一つ。モースはそのクラも例に引きながら、他の地域の事例と比較していく。
標題のカワウソの子というのは、出発点である贈与に関する神話。アラスカのインディアンでの伝承。息子がカワウソの姿で生まれた首長は、これまで通り(カワウソの捕まえた魚などを)周りの人々に与える(贈与)。これらの人々は、首長の息子がカワウソの姿をしていると教えられ、カワウソを見ても殺さないように頼まれる。が、ある有力者をその場に呼ぶのを忘れてしまった。ので、カワウソ息子は殺されてしまった…という話…は贈与の場がどんな場かを教えてくれる。
あと、このような慣習を持つ人々の中では、「買う」と「売る」に対応する単語が一つしかなく同じ概念なのだろう…とか、全ての社会で物々交換から売買契約が発展したわけではなさそうだ…
(2011 03/31)
モノの追跡権
「贈与論」一昨日の夜読んだ分で気になったのは、モノの取り引きが結構命がけ?であったこと。それはなにゆえかというと、モノを手放しても元の所有者のイキはなにがしかはかかっている、というところから。
元の所有者は、現在の所有者がそれをどうゆう取り扱いをしているか、チェックする。気に入らなかったら、何か呪い?をかけることができる。
近代前の契約というものの理論が少しは見えてきたかな…
(2011 04/02)
モースの意志表明
贈与論の結論の残りを読んだ。
「贈与論」…なんか、ほんとに100年近く前に書いた本なの?って思うくらいまさに今な議論の仕方で驚いた。最後のアーサー王円卓の比喩は深く印象に残るものがある。昨日で立ち読みした「コモンズの地球史―― グローバル化時代の共有論に向けて ――」秋道智彌氏著も思い出される。
われわれは全体を考察することによってのみ、その本質を、その全体の運動を、その生きた側面を、社会や人間が自分たち自身と他者に対する位置を情緒的に意識するその儚い瞬間を、捉えることが出来たのである。
(p285)
デュルケーム始めとして、その他ドイツ観念論やゲシュタルト心理学にも関心を持っていたモースの意志表明。個人的には「その儚い瞬間」って表現にゾクゾクしたのだが、「はかない」ってニンベンに夢なのか。考えさせられるなあ(モースとは関係ないけど)。
しかし幸福になれるのは、円卓の騎士団のように共通の富の周りに座ることができた場合にのみに可能である。善や幸福を遠くまで探しに行っても無駄である。それが存在するのは、平和状態、公共のためと個人のためとに交互にリズムよく行われる労働、蓄積され再分配される富、教育によって身につく互いの尊敬と寛大さの中なのである。
(p291)
ポイントはその1カール・ブッセは無駄なことをしてた、ということ…抜け駆けは御法度、囚人のジレンマ理論もそれを証明している。
その2、「公共のためと個人のためとに交互にリズムよく行われる労働」のところ。「交互」というところはクラのイメージかもしれない。同じ労働内容に2つの意味を重ね合わせるやり方もあるのかもしれない。でも、ミソは公共オンリーでもダメ、個人オンリーでもダメ、というところだろうか?
(2011 04/03)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
