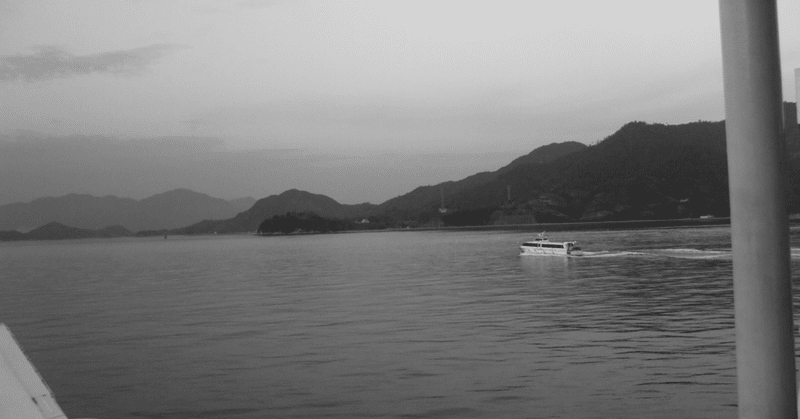
「ベンヤミン・コレクション2 エッセーの思想」 ヴァルター・ベンヤミン
浅井健二郎・三宅晶子・久保哲司・内村博信・西村龍一 訳
ちくま学芸文庫 筑摩書房
「蔵書の荷解きをする」、「子供の本を覗く」
最初に「翻訳者の使命」読もうとしたら結構難しく、最初からにした。ちくま学芸文庫の「コレクション」ものはなんか冒頭に異様に難解なものを持ってくるというイメージがなんでか自分の中にできていたけど、この文庫は最初は気楽?なものから始まる・・・
「蔵書の荷解きをする」というなんかの講演原稿らしいエッセーで、ベンヤミンは本を手に入れたいろんないきさつや引越の後で蔵書を荷解きしながらいろいろ夢想にふけるといった自分にも経験たくさんある(まだ荷解きなんてしてないじゃないか!という声はほっといて・・・)話をしながら、「所有」ということについてのアンビバレンツな思いをふと出しているらしい。らしい、というのはそこまで読んでいる時には感じなかった(「所有」って言葉になんか引っかかっているなというくらいにしか思わなかった)からで、ブルジョアとコミュニズムの中で引き裂かれていたベンヤミン像は自分の中ではまだ形成されていないのだが・・・
続いての「子供の本を覗く」から。
創造的な想像とは反対に空想的な直観は、色彩を見ることにおいて原現象として認識される。というのもおよそあらゆる形態、人間が知覚するあらゆる輪郭には、これを生み出す能力という点で人間自身がこれに照応する。身体そのものは舞踏において、手は線を描くことにおいて輪郭をまね、これをわがものにする。けれどもこの能力は、色彩の世界において限界にぶつかる。人間の身体は色彩を生み出すことはできない。身体は創造的にではなく受容的に、すなわち色を帯びてほのかに輝く目において色彩に照応する。
(p45)
形態のところは人間の知覚と身体と知識の関係を述べていて心理・人類学的にも重要なところとなっているが、形態と色彩のこういう分類は初めて聞いた。ものを選ぶ時に外向的な人は形から、内向的な人は色から選ぶという話は小耳に挟んだけど、それが直観と子供につながってくるのが意外。それにジャン・パウルやゲーテがつながってくるという。
(2014 09/28)
「模倣の能力について」は短いけれどなかなか濃い内容。言語は模倣からなっているというのはヴィーコを思い出す。ベンヤミンの壮大な企みの一端をかいまみる一編。
(2014 11/28)
ドストエフスキーとジッド、鏡合わせの世界
「ベンヤミンコレクション2」、ちょっと前に読んだドストエフスキー論と昨夜読んだジッド論は、子供という視点からちょうど鏡合わせな関係なのかな、と。大人→子供の前者と、子供→大人の後者。でも後者の手法だと失敗してしまう…「狭き門」においてジッドはその崩壊を示したいのでは、とベンヤミンは言う。
この書物全体の動きは火口の巨大な陥没に似ている。自然と幼年時代とが欠けているので、人間性はただ破局的な自己破壊においてのみ達成されるのだ。
(p90)
これはドストエフスキー「白痴」論から。
(2014 12/27)
罰する者である父親は、同時にまた告訴人でもある。彼が息子を咎める罪は一種の原罪であるように見える。
(p113)
カフカとゲーテ
いきなり父親が怒り出して息子が入水自殺するわけわからないカフカの「判決」のガイド文となるか。「ベンヤミンコレクション2」のベンヤミンのカフカ没後10年のエッセイから。息子の側から見ると、自分の存在=原罪となるのだからたまらない。でも原罪とはもともとそういうもの。では怒り出した父親はいったい何者か?
「ゲーテ」はもともと百科事典の為の原稿なのだという。
そこからの一文。
市民的な文化世界の展開を、ゲーテは自分の先駆者および後継者よりもずっと包括的に押し進めたのではあったが、その展開を、しかし彼は、醇化された封建国家という枠のなか以外のかたちでは考えることができなかった。
(p223)
まあ、とりあえずはここを。だから、ブルジョアの解放闘争という点ではシラーの方がよく引用され、ゲーテは遅れて評価されたのだ、という。
(2015 01/02)
ヨッホマン「詩の退歩」
「ベンヤミンコレクション2」からヨッホマンのところ。ヨッホマンはリヴォニア地方(今のバルト三国辺り)の出身。フランス革命期にパリへ。
ロースは、すでにはびこっていた悪行を除去するために書いた。ヨッホマンは、まさに生まれつつあった害悪に対する緩和材を提供した。
(p260)
ロースは新即物主義のオーストリアの建築家。で、ここに悪行やら害悪やら書いてあるのはロマン派のこと。ロマン派を挟んで入口と出口で呼応する。
ヨッホマンは「詩の退歩」という文章を出す。で、そこで原始社会では詩の源泉たる想像力が今よりはるかに充満しており、一方言葉の使用環境に関してははるかに劣っていた。そこで言語活動をする時には全て歌(詩)に委ねていた、とする。だから現代は詩に関しては「退歩」している、とそんな感じ。これらはかなりヴィーコの「新しい学」に負っている。
というようなヨッホマン「詩の退歩」に自作の序文をつけて復活させたのがベンヤミン…
(2015 01/09)
ベンヤミンのヘーベル
「ベンヤミンコレクション2」からヘーベル。この人は主に暦につけた小話で知られている人…らしい。「今忘れられているこの人を大々的に推奨する、というわけにはいかない」なんて、のっけから微笑というか突っ込み誘わせておいて、その後からじわじわとこのヘーベルという作家について語る。
第一の極はルター訳聖書のドイツ語、第二の極は方言である。ヘーベルにおいてこの二つがいかに浸透しあっているか、これが彼の職人的な名人芸の秘密を解く鍵なのだ。
(p278)
このことは単に言語の問題だけでなくその背後の文化社会的なことも含めてなのだろう。こういう視点は自分は今まで持ってなかったかもしれない。
この本の解説を見ると、この間のヨッホマンのところからこのヘーベルを経て「経験と貧困」までを第5セクションとして、詩・芸術の退歩をテーマとしている、とある。ヨッホマンはその導入の意味もあったのだ。しかもこうしたベンヤミンの考え方はこのコレクションシリーズの1にあるボードレールから複製技術の流れのエッセーとも共通するという。
退歩しつつある人類の想像力に対してベンヤミンは、古いものへの味わいの視点と、現在を零としてそこから全く新たに積み上げるという2つの方法を意識しているという。しかもそれは共同してコラージュという手法で編み出していく。この本の第1セクションのエッセーやこのヘーベルなどはそうした戦略の一環なのだろう。そしてその成果が「一方通行路」や「パサージュ論」なのだろう。
(2015 01/11)
プサンメニトスの謎
「ベンヤミンコレクション2」から「物語作者」。副題にはレスコフの名前があるが、レスコフは一例に過ぎず、この間読んだヘーベルほかいろいろな例が挙げられている。今のところ半分くらい読んだところだが、物語る能力、経験を交換する能力がなくなってきている、というのが一番大外の考え方。かっては船員と農民がそうした能力の持ち主で、それらが同居したのが中世職人の師弟(職人は若い頃は徒弟遍歴をする)。
いろいろ興味深い話があったのだが、その中での一番は、情報と物語の差異に関してヘロドトスのプサンメニトスの物語。エジプト王プサンメニトスはペルシャとの争いに敗れ、ペルシャ王からの辱しめを受ける。王の親族が辱しめを受けているのを見ても涙をこらえているくらいなのだが、下僕が辱しめを受けているのを見た瞬間泣き始める。これが何故かをモンテーニュ始めいろいろな人が考えて答えを導き出している。情報はこういう時に全てを矛盾なく説明しなくてはならないけれど、物語は謎をできるだけ素っ気なく提示する。
だからこそ古代エジプトのこの話は、何千年を経た後にもなお、驚きと思索を呼び起こすことができるのだ。それは何千年ものあいだピラミッドのなかの小部屋に密封されていて、今日に至るまでその発芽力を保持していた穀物の種に似ている。
(p298)
長編小説の主人公は薪
「ベンヤミンコレクション2」の「物語作者」後半を昨夜。この文章は物語と長編小説を対比させていろいろ書いてあり、ベンヤミンの思い入れがあるのはタイトル通り前者なのだが、ベンヤミンの時点からも更に約百年経過した今日では、物語というものはかなり遠くに行ってしまったのか、自分が読んでいて気になるのは後者の方が多い…
生身の人生ではなく、小説化されることによってよく乾かされた素材となれば、読者の興味の炎はこれを薪のように呑み尽くして燃えたち、しばしの温もりが得られるのである。
(p318)
これは原注から。だから?長編小説の主人公は死を迎えることが多い…死を迎えなくても、小説自体が突然に終わる…という。
(2015 01/15)
ベンヤミンの「ベルリン・アレキサンダー広場」論
海に対しては、もちろん、実にさまざまな態度をとることができる。たとえば、浜辺に寝ころんだり、寄せては砕ける波の音に耳を傾けたり、波に打ち寄せられる貝殻を拾い集めたりできるーこのようなことをするのが叙事詩人である。だがまた、海を航行することもできる。…(中略)…このようなことをするのが長篇小説作家なのだ。
(p336)
ベンヤミンの「長篇小説の危機」というエッセイはデーブリーンの「ベルリン・アレキサンダー広場」に関して。これをベンヤミンはジッドの「贋金つかい」と対極にある、しかしどちらも長篇小説の危機を表した作品として論じる。
モンタージュという様式原理が「長篇小説」を破砕する、構造的にも文体的にも破砕する。そしてこの原理は、新たな、非常に叙事的な可能性を開くのである。
(p341)
デーブリーンのこの本では、不幸がその陽気な面を見せつける。不幸は人間たちといっしょに同じテーブルに着く。けれども、だからといって会話が途切れることはなく、人びとはきちんと座り直して、料理に舌鼓を打ち続けるのである。
(p345)
つぎはぎ、コラージュ、モンタージュ・・・というのは、デーブリーンと共にベンヤミン自身がそこに立脚する技法。技法のみならず、それはベンヤミンの「経験の貧困」な現代に対する態度でもある、そしてそれはデーブリーンも同じことではないか。
後者の文はディケンズとも共通するところ。不幸が「料理」だという表現が面白い。
(2015 01/31)
経験と貧困
昨日はまた「ベンヤミンコレクション2」を持ち出して、少しだけ先に進めた。「経験と貧困」という作品。ベンヤミンによれば第一次世界大戦後、人間固有の経験なるものは貧困化したという。戦争により経験の虚が暴かれたと。
経験の貧困ーこのことを、人間たちが新しい経験を切望しているかのように理解してはならない。彼らはいま、新しい経験を求めているのではなく、そもそも、もろもろの経験から放免されることをこそを切望している。
(p382)
こうした経験から解き放たれた芸術・技術がクレーの絵でありブレヒトの演劇であり、ロースやコルビジェの建築でありシェーアバルトの小説であるという。最後のは、自分は初耳な人物だけど、20世紀のヴェルヌ的な作品を書く(けどヴェルヌとは正反対だとベンヤミンはいう)この人についての評論も結構しているらしい。
とにかくこの作品も「複製技術」と同じように作者のアンビバレンツ的な性格が現れている。
(2015 06/02)
「翻訳者の使命」
「ベンヤミンコレクション2」では、三度目の挑戦?となる「翻訳者の使命」。今回もよくわからなかあった表現は結構あったけど、とりあえず読むことはできた。
では、翻訳者の使命とは何なの?
翻訳者の使命は、翻訳の言語への志向、翻訳の言語のなかに原作の谺を呼び覚ますあの志向を見出すことにある。この点に、創作とはまったく異なる翻訳の特徴がある。
(p401)
ベンヤミンによれば翻訳は単なる原作の書き直しではなく、原作と共に成長していく言語活動の一つの環なのだという。そこには実在はしないけれどなんだか?そこに向かっていくところの純粋言語(人類唯一の言語)への志向がある。
接線が円に接するのはほんの束の間、ただ一点においてだけであるように、そして、接線がさらに無限へとその直線軌道をたどる法則を規定しているのは、この接触であって接点ではないように、翻訳は、言語活動の自由のなかで忠実の法則に従いながらその最も固有の軌道をたどるために、束の間、意味という無限に小さな点において原作に接触するにすぎない。
(p408)
接触と接点の違いがわからないが、接線と円の比喩はこの論文の中で一番鮮やかな印象を残す。
こうやって純粋言語という仮定をみていくと、やはりベンヤミンは社会主義的というかコミュニズム的な土台に立っていたのだな、と思う。現在ではなかなか受け入れられない考え方だけに、逆にそれに思いを巡らすことは重要になってきているようにも思える。特に「谺を呼び覚ます」の辺りなど。
(2015 09/06)
「プルーストのイメージについて」から
「ベンヤミンコレクション2」から標題のプルースト論を読んだ。「オデッセウス」のペーネロペイアは昼織った布を夜に解いていたが、プルーストは逆に夜織って昼に解きほぐしていた、という。
オルテガはプルーストの登場人物に植物的な生活を見出したとベンヤミンは言う。彼らは自分の生活環境に薮のように絡みあって生きている。そして太陽や風に左右されている。そんな中にいる一匹の昆虫、それがプルーストなのだ、とベンヤミンは言う。また長くなるけど引用する。
この生活圏から、文学者プルーストの方法として、擬態というものが生まれてくる。彼の最も精確で明晰な認識がその対象のうえにぴたりと張りついているさまは、ある種の昆虫が葉や花や幹のうえにとまっているのに似ている。こうした昆虫は、そこにいることをまったく悟らせない。それがぴょんと跳ねたり、ひとつ羽ばたきしたり、ぱっと飛んだりしたときはじめて、驚いた観察者は、そこにひとつの気まぐれな独自な生命が、自身とは異質な世界のなかに、目立たぬように忍びこんでいたことに気づく。
(p429)
ベンヤミンとプルーストとはどこが同じでどこが違うのだろうか?
(2015 10/11)
ジッドとプルースト
プルーストのなかには、彼が実現するに至らなかったたくさんのものが、綻びることのついになかった蕾の数々があった。
(p450)
「ベンヤミンコレクション2」から「アンドレ・ジッド」。ベルリンでのジッドへのインタビューをまとめたもの。上はジッドが語るプルースト。蕾のまま、というのがポイント。
島を離れるとき、われわれはそれに〈救いの島〉という名を与えた。
あるものに別れを告げるときにはじめて、われわれはそれに名を与える。
(p452)
次の文2つは、前がブーガンヴィル航海記からのジッドが引用したもの。後ろがそれを受けたジッド自身のつけたし。
私の作品にはなにか叢林のようなところがあって
(p454)
最後は、先のプルーストについての文との比較で、ジッド自身の発言。
ジッドは実はあまり読んでいないけど、プルーストとお友達だけあって、表現がいちいち?巧い。
(2016 02/27)
昨夜はベンヤミンコレクションから「ジュリアン・グリーン」。グレアムと違ってこっちは読んだことないなあ。階段を転げ落ちるような、しかも一段も飛ばすことなく落ちる、そんな受苦の運命を描いたという表現が面白かった。
(2016 11/15)
カール・クラウス
一昨日の夜からちびちびと、「ベンヤミンコレクション2」からカール・クラウス。確かカネッティも取り上げていたこの人。ベンヤミンのこのエッセイでは新聞報道に対しての批判雑誌「ファッケル」を中心に今のところ書かれている。
公衆の関心はもっぱら判決にある。裁く公衆でなければ、まったく公衆の名に値しない。
(p487)
だけど、新聞はその公衆の裁く機会を奪っている、という。
深刻な時代になるかもしれないという可能性を眼前にして死ぬほど笑いころげてきて、そして己れの悲劇にびっくりしながら気晴らしに手を伸ばし、みずからの悪事の現場を押さえながらうまい言葉を探す、この深刻な時代。
(p492 クラウスの講演から)
深刻さの回避というのはある意味人類の進化の結果の一つかもしれない。
(2016 12/10)
さてさて、対象に一回も触れたことがないまま、それに対するエッセイを読むというのもなかなかきついものだけれど、まあとりあえず(いつも、とりあえず(笑))ベンヤミンコレクション2の「カール・クラウス」は読み終えた。
引用2つ。
韻の音に、子供は自分が言語の稜線に辿りついたことを知る。そこで子供は、根源に湧き出るすべての泉のざわめきを聞きとるのだ。
(p539)
ここは前に読んだ「純粋言語」と通底するものがあるのかな。次の引用は引用について。
引用は言葉を名で呼び出し、この言葉をそれが置かれている連関から破壊しつつ切り出すのだが、しかし、まさにそのことによって、引用はこの言葉をその根源へと呼び戻しているのである。引用された言葉は韻を失うことなく、その音を響かせつつ、調和しながら、新しいテクストの構造のなかに姿を現す。韻としてその言葉は、自身のアウラに包まれて、似たものを呼び集め、名としては、孤独に、表現を持たぬまま佇んでいる。
(p544~545)
自分などは全くできていない「引用」の理想型。韻と名、根源と破壊、言語活動そのものの力動性・・・
このエッセイの特に第3部には、根源、天使、アウラ、引用などなど、ベンヤミン思想の頻出用語が初出のものの含め揃って出てきている。後に「パサージュ論」「複製技術」「歴史の天使」などに結実するそれらがどう「引用」されているのか。この作品でもそうだけど、ベンヤミンはまた自己引用の才を持っていた。
(2016 12/11)
収集家にして歴史家フックス
「ベンヤミンコレクション2」からエードゥアルト・フックス。この人に関してはクラウス以上に何も知らなかった。名前も初耳。
収集家としては、従来の芸術品からはみ出てしまうもの、カリカチュアやエロティシズム芸術を多く集め、書物にまとめている。とはいえ、その本に収集過程を全く書き込まず、収集家ではゴングール兄弟(彼らはそういう文章を結構残している)よりも、バルザックの従兄ポンスに似ている、とベンヤミンは言う。
歴史家としては、弁証法的歴史家(ものやことを力動的に過去から未来へ変化していくものと捉える)の側面が強い。ランケの静的歴史主義を批判していたベンヤミンにとっては、少し不徹底なところも見られたらしいけれど。
で、とにかく、これで「ベンヤミンコレクション2」をやっと読み終えた。足かけ何年?
(2017 01/04)
フックスについて補足
まず、ベンヤミンにフックスを教えたのはホルクハイマーだったということ。フランクフルト学派つながりか。あとはこの論考がのちの大衆芸術論や複製芸術論そして歴史学のテーゼとして発展していくということ。
(2017 01/05)
関連書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
