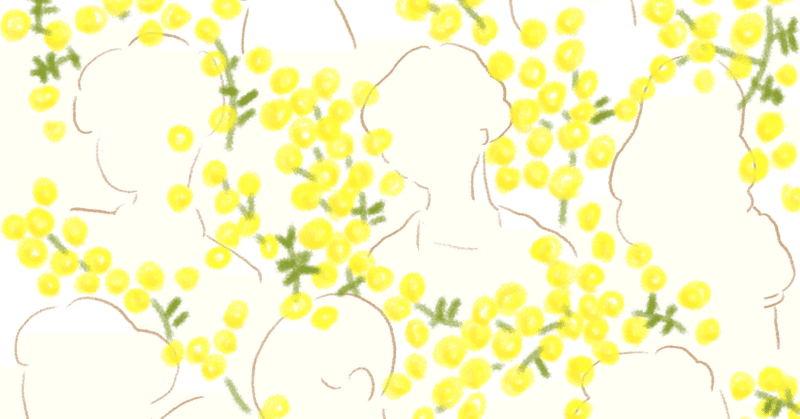
言葉はドアスコープ
他人が見ている、生きている世界を覗くことができるドアスコープのような役割が、言葉にはある。
最近話題の『無痛おねだり』というワード。
1 甘えたり、無理に頼んだりしてほしいものを請い求める。せがむ。せびる。
2 難くせをつけて要求する。ゆする。
3 ぐずぐず文句を言う。ごねる。
わざわざ調べなくても、おねだりの意味が【立場の弱い人間が立場の強い人間に"請う"行為】ということはわかるはずだ。
私はおねだりという言葉をざっくり分けて
「子供が親にゲーム機をねだる」
「恋人に洋服やカバンをねだる」
くらいでしか見たことがない。
他には、小遣い制のサラリーマンが妻に何かをねだるような場面も想像できるかもしれない。
あの『おねだり発言』のあとに、掲載された謝罪文はこう。
《僕の発言で傷つけてしまった方がいるようです。ごめんなさい。費用はかかってしまうけど恐怖心を緩和するためにも、一つの大切な選択だと勉強をしていたのでそれをご家族で話し合われる事もいいのではないかとお伝えしたかったのだけど言葉足らずでした。というか変な伝え方をしました。以後気をつけます!》
「【おねだり】ではなく【話し合う】のつもりでした!」
「はい、わかりました!」
とはならないだろう。
【話し合う】という言葉が【ねだる】と互換性のある言葉なら
「進路について親とねだる」
「試合に向けてチームでねだる」
「退職を希望する部下とねだる」
という文章が存在するはずだ。私はそんな【ねだる】は聞いた事がない。
(実は本人が特殊な日本語をあやつるコミュニティに参加していて、マジで【ねだる】を【話し合う】の同義語として扱っていたのならそれはそれで興味深いが…)
全く意味の違う言葉をあとから差し替えて「勘違いさせちゃったね!」の態度をとられてしまえば、私たちは言葉をどう信じればいいのかわからなくなる。
たとえば、飲食店のメニュー表にカツ丼の写真があったとする。
写真の下には"カツ丼"と表記がある。
「よし、カツ丼を食べよう」と思った私はカツ丼を注文する。
しばらく経って、なぜか親子丼が提供されたので「私が頼んだのはカツ丼です」と店員の間違いを指摘する。
間違いを指摘された店員は、メニュー表のカツ丼の写真の上に親子丼の写真を貼り付け、"カツ丼"の文字をマジックで塗りつぶし、その下に"親子丼"と書き足してから「あーごめんごめん!これは親子丼のつもりだったの!変な書き方しちゃったね!」と颯爽と厨房に戻っていく。
そんなことがあれば誰でも「いや、書き方がどうとかではないだろう」と不服に思うはずだ。
後からサッと言葉をすり替えて、相手の捉え方のせいにしてしまうのは本当にずるい。
本人の生きている世界には「女性が男性と対等に話し合う」という価値観やシチュエーションがきっと存在しないのだろう。
だから「無痛分娩について妊婦が夫と話し合う」というシュチュエーションに対して【おねだり】という言葉を当てはめてしまう。
これを「女性蔑視ではない」「あれくらいで」と済ませられてしまうのは悔しい。
本人の言葉を通して覗いてしまった女性蔑視の世界に、私はNOと声をあげつづけていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
