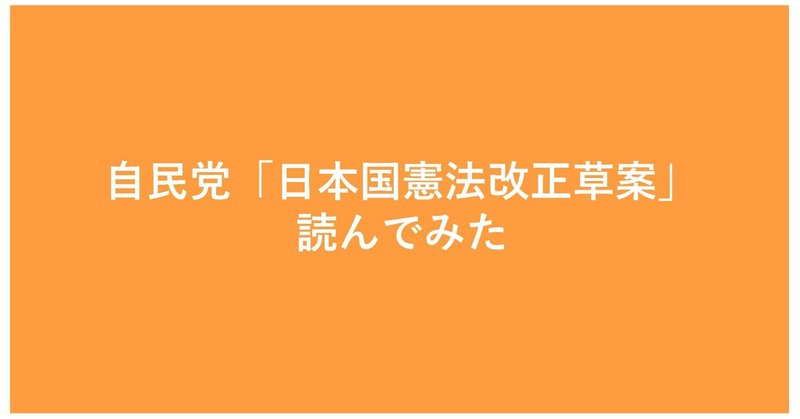
ところで、日本国憲法って何条あるか知ってますか?
第9条も終わったし、そろそろ疲れてきましたので、もういいかな。憲法って、この先長いんですよね。なので、息抜きコラム。
日本国憲法は、何条あるのか
第3章は長いんです。第10条から第40条まで。
1章あたりの条項数としては最大です。この後どのくらいあるのかというと次のようになります。
第4章国会が、第41条から第64条まで。
第5章内閣が、第65条から第75条まで。
第6章司法が、第76条から第82条まで。
第7章財政が、第83条から第91条まで。
第8章地方自治が、第92条から第97条(現行憲法では95条)まで。
第9章緊急事態は、自民党草案での新設。
第10章(現行憲法では第9章)改正が、第100条(現行憲法では96条)
第11章(現行憲法では第10章)最高法規が、第101条と第102条(現行憲法では97条から99条)
自民党草案は、この後付記になりますが、現行憲法では、第11章補則となり、第100条から103条までありますが、憲法制定時のイレギュラーな状況に伴う補足なので、実質的な条文とは言えません。
つまり、日本国憲法というのは、現行憲法で99条、自民党草案で102条という物量からなるものなのです。
普段、憲法議論の中で、前文と9条くらいしか出てこないので、憲法は10条くらいしかないんじゃないかと思っている人もいるかもしれませんが(いないか)、10章100条からなるということを知っていただきたいです。
これだけ多くの条文があれば、中にはおかしなものも、時代の変化でそぐわないものも出てくる可能性はあります。実際、いくつかの条文には見直した方が良い文章や内容があるのではないでしょうか。
なので、護憲派と言われる人たちが、憲法を全く触らないような改正反対論議をしますが、やはり検討は続ける必要があると思います。
憲法は検討されているのか
ただ、そのための組織である憲法審査会が国会開催時に申し訳のように開催されるだけで、議論も選挙年齢の引き下げと国民投票のことばかりという状況はいかがなものでしょうか。
憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関です。 本審査会は、第167回国会の召集の日(平成19年8月7日)から、国会法第102条の6の規定に基づき「(衆議院に)設ける」とされています。
以前は憲法調査会という名前でしたが、2007年から憲法審査会という名称で常設されています
第167回国会から、衆議院と参議院の両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くことを定める国会法改正法が施行された。
平成24年ごろは、内容についての議論もあったのですが、最近はもっぱら国民投票法と年齢引き下げの議論だということが資料からわかります。
憲法審査会の前に5年という期間で設けられた憲法調査会での議論以降、熱心な憲法論議は行われていないように見受けられます。
この報告書では、その憲法調査会の報告書から抜粋が掲載されています。なので、元に当たってみました。
平成17年に提出されています。英語版、中国語版、韓国語版もあるのがすごい。
衆議院憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的な調査」を行うため、第 147 回国会の召集日(平成 12 年 1 月 20 日)に、衆議院に設置された。
日本国憲法の下で、憲法改正の発議権を有する国会に、このような機関が設置されたのは初めてのことである。
この憲法調査会での議論の一部については、前文のところで紹介しました。
現場の審査会に比べて、時限組織であったことで目的がはっきりしていたせいか、議論がされています。
本調査会は、設置以後、その任務を達成するため、日本国憲法について、その「過去」「現在」「未来」のあらゆる観点から調査を実施してきた。すなわち、「日本国憲法の制定経緯」に関する調査(=「過去」の調査)から開始し、「戦後の主な違憲判決」に関する調査(=違憲判決を通して見た「過去」から「現在」に至る調査)を経て、「21 世紀の日本のあるべき姿」に関する調査(=「未来」の調査)を実施した。その後に、本調査会の下に四つの小委員会を設置して、前文を含む全 103 箇条の憲法全体をいくつかの条文ごとに適宜テーマに区切りながら、専門的かつ効果的な調査(=「現在」の調査)を実施した後、最後にその全体を通じた締めくくりの調査を行ってきたところである。
本報告書は、このような調査会の 5 年余りの調査活動をあますところなく要約・整理したものであり、いわば「衆議院憲法調査会の縮図」とも言えるものである。われわれとしては、現在の国民はもとより、将来の国民による批判にも堪えられるような、丁寧で分かりやすい調査を心がけてきたつもりであるが、その最終的な評価は、歴史に委ねるしかない。
今後、この報告書についても随時、取り上げていきたいと思います。
中山太郎という会長だからなし得たこと
議論したこと、そして、それを後世に残したことが、素晴らしいと思いますし、もちろん公的な審議は、そうあるべきなのですが、最近の政府のあり方を見ると…。この報告書は自民党の中山太郎さんが会長としてまとめています。
中山太郎さんの考えが「前書き」の中で触れられています。
「『人権の尊重』『主権在民』『再び侵略国家とはならない』との三つの理念を堅持しつつ、新しい日本の国家像について、全国民的見地に立って調査検討をしてまいりたい」
その趣旨は、「憲法論議を進めようとする人々は、何かそら恐ろしいことを行おうとしているのではないか」という国内外の人々の誤解を解くとともに、タブーのない憲法論議こそが、主権者国民がその主権を自らの手にすることを目指すものなのだ、ということを分かって欲しかったからである。
憲法論議というと「9条の改悪」だとか「権力のための改憲」などという言葉が出てきますが、そうではなく、「憲法は国民のもの」であり、憲法学者だけのものではなく、みんなで議論することが重要だという姿勢が、中山さんにあったことがわかります。
この報告書を読むと、この会長が中山太郎さんだったから成立したのではないかという感慨にとらわれます。
自民党の重鎮であり、初の女性閣僚を母にもつ大正生まれのリベラルな政治家でした。安倍晋三さんの父・安倍晋太郎さんに仕えた人で医師出身として臓器移植法の議員立法に尽力された人でした。
硬骨漢という感じがしました。
内容については、うまく紹介できればいいなと思います。
こういう資料も読みつつ、さらに自民党草案を読んでいきましょう。
サポートの意味や意図がまだわかってない感じがありますが、サポートしていただくと、きっと、また次を頑張るだろうと思います。
