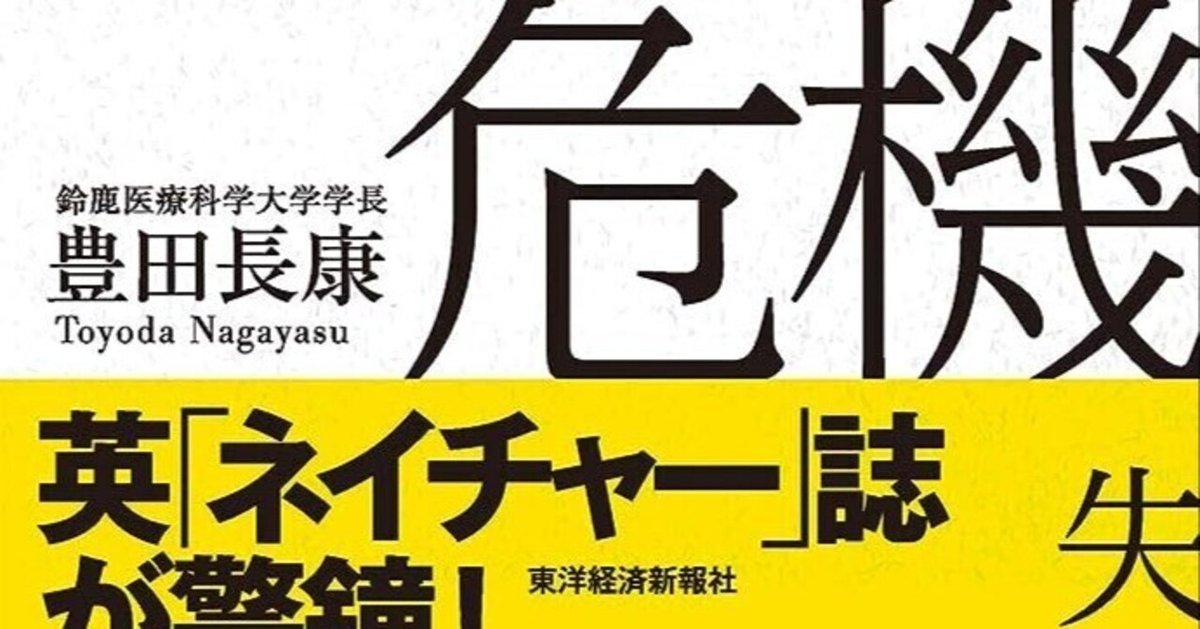
科学を「数値」で測ることの意味-豊田長康「科学技術立国の危機」を読んで
この記事は,以下の書評,および書評で扱われた本である豊田長康「科学技術立国の危機」を受けて作成したものである.
現在,我が日本国における学術研究を取り巻く様々な環境は,一言で言って「悪い」という印象しか持てない.例えば,常勤の教員は増大する書類仕事に忙殺され十分な研究時間を取れない,また博士号を取得してもポストが任期制であったり,そもそも少子化の影響か自分の専門領域にてポストがなかったり,給料等の条件においてその専門性に値する十分な報酬が設定されていなかったりする.また,大抵の民間企業のようにコンプライアンス意識がまだ十分に浸透していないので,いまだにハラスメントの問題が根深い.このように,SNS上などでいわゆる「アカデミア」に関する悪い噂はいくらでも観測できるがいい噂を目にした記憶はない.
もちろん,個人的に尊敬できる研究者の方はいくらでも交流を持っていただけているのだが,とかく環境面に関しては諸手を挙げて「環境がいい」という人はいないであろう.
かくいう私も,実は博士後期課程への進学を予定しているのだが,「絶対何がなんでもアカデミア」という意識ではもちろんない.いまをときめく情報系,特に機械学習が専門だということもあり,企業に勤めるより低いとはいえ多少の金をもらって,身体的・精神的能力の総合値が最大である20代後半に自由に好きなことやれるならそれでいいや,という感じで進学を決めたのである.(ここら辺は正直,属する専門領域によって状況がだいぶ異なると思われる.哲学,数学,文学など基礎的な領域にて博士進学する人の覚悟はすごいと感じてしまう)
さて,日本のアカデミアにおいて大きな問題とされるものの一つとして,「論文数/論文生産性」が低いというものがある.この「科学立国の危機」は大まかにその問題に焦点を当て,議論したものだと思われる.ただ,ひたすら具体的なデータが並べられており,最後まで集中力を保ったまま内容を読み込めているのか若干微妙な部分はある.そこら辺を含めて,この本の印象,書評ということでご容赦願いたい.
先ほどあれほど日本のアカデミアをこき下ろした私ではあるのだが,それは主に待遇面や環境面の話であり,こと「論文数/論文生産性」の観点からの議論は問題点やもっと考察するべきポイントがあると思われる.
そもそもアカデミアにおける生産物を,「数量化」する意味や意図
当たり前の話であるが,なんらかの対象を数量化して比較するには,それぞれの間で共通となる指標や基底を設定しなければならない.要するに,物差しがなければ複数のものなんか比べようがないよねというお話である.ただ,残念ながら,ある対象に物差しを当てた時点で,「その物差しで測れるもの以外は全て捨象され」てしまう.野球とサッカーとバスケットボールのプレイヤーのパフォーマンスを,「得点数」という一つの物差しのみで測れば有効な議論などできやしないことは明白であろう.現実の複雑さをあまりよく観察せず,強引に「物差し」で測った場合,結局何の情報も得られないのである.この「強引に物差しを当てる」という行為の問題点は「論文数/論文生産性」の議論にも当てはまると考える.そもそも,分野や領域によって「論文」というものに対する文化や価値が全く違うのにそれをひとまとめにして議論したら射程から外れる対象や事象が続出するということは想像に固くない.例えば,私の所属している情報系の領域では(採択率が低い,CHIやAAAIなどの学会ならば)学会発表でも十分に「業績」として考慮されるのだが,物理化学ではどんな学会であれほぼ考慮されないと聞く.また,我が国における社会,人文科学領域においては日本語で論文を執筆するのが基本だと思われるが,これでは「国際的な論文の数/生産性」の指標には載ってこないことが明らかであろう.そもそも,日本語研究など日本語でしか議論し得ないような領域もあるのだが,そういう領域に従事している研究者は「国際化されていない,評価が低い」研究者なのだろうか?
このように,ある「物差し」を当てれば,その物差しで測れるもの以外は全て捨てる,考えないということである.数字,特に「業績の”数”」や「生み出したお金」などという指標は目にも煌びやかであるため,それで全てが測れるかもしれないという錯覚を産んでしまうが,高々一つの「物差し」でしかないため限界がある.
そもそも,目で見えてわかる「数字」など結構な割合で人の手によりいじれるものなのである.例えば,論文の「価値」にはどれだけその論文が引用されたのかという数が重要だとされるのだが,国や研究グループによっては積極的に他の人の論文を引用しまくることで見た目には引用数を多く見せるということをしている場合もあるそうなのである.「物差し」がある以上,それに対応する方策などいくらでも思いつくのであろう.そうなれば,もはやなんのために評価を行っているのかどんどん意図や意義が不明瞭になっていく.そうなれば,資本主義と同じで,行き着く先はアカデミアからの人間の「疎外」であろう.実際,「評価」のための書類作成に忙殺される教員や,困窮を極めているポスドク問題などは,その「疎外」の最先端であると言える.
もちろん,特に公的な基金から研究費を投入する場合,その出資者に対し「説明責任」を果たさないといけないので,説明に目に見えてわかりやすい「論文数/論文生産性」という指標を用いてしまいがちなのは理解できる.ただ,それも,先ほど述べた「物差しの限界」を理解しないまま議論を行えば,容易に自家中毒と自己目的化を引き起こすであろう.学術活動を行う際はよく「立つ観点を明確にする」ということがまず求められるが,畢竟,それは「今立っているところからでは見えないもの」を意識するということである.
それは,「コスパ」という言葉のように何でもかんでも数量化でき,同じ基底で以って比較可能だという前提を取っているような,現実の複雑性を捨象しまくった結果何一つ有益な情報を得られていないある意味とても「幸福」な考え方が流行ってしまっている現在の社会に対しても同じことが言える.
今こそ,科学,いや学問の基本,すなわち「何かを議論することは,それ以外の何かを議論しないということ」,「何かを明らかにするということは,その他の何かが明らかになっていないということ」を理解するという姿勢に立ち返るべきではないだろうか.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
