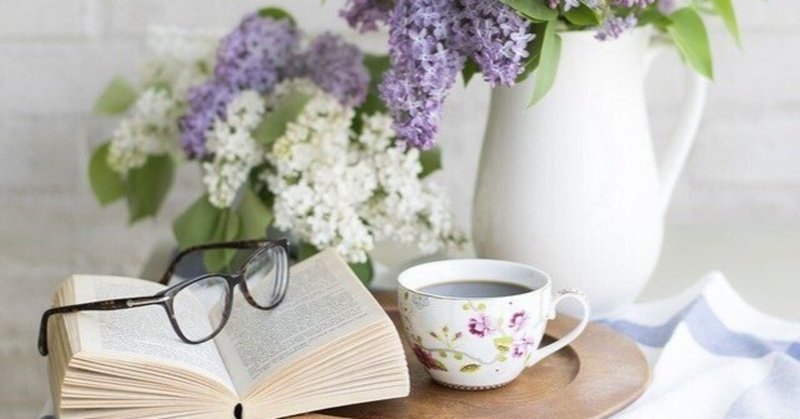
「書く習慣」と「noto完全マニュアル」
きっかけは「書く習慣」
noteを始める少し前、1冊の本と出会いました。
いしかわゆきさんの「書く習慣」という本です。
本を買うときはいつも、帯や裏表紙に書いてある文字をじっくり読む派なのですが、本書の帯に書かれた「たのしく書くためのコツ」という文字にぐっと引き寄せられました。
そして裏表紙側に書かれた「『習慣』にしちゃえば、文章は勝手にうまくなる!」という言葉は、もしかして私にもできるのでは?という淡い期待を抱かせるものでした。
こうして手に取った本書はとても読みやすく、かつ書くことへの精神的ハードルを下げてくれるものでした。
学生時代に日記を書いたことがあります。自分が思ったこと、感じたことを吐き出せる場所でした。でもそれは誰にも見せない、自分以外誰も読まないという前提のものでした。だからこそ自由に書けたのです。下手な文章でも自分だけが読むのだから、好きなことを好きなように思いのままに書くことができたのです。外に向けて発信するのは、文章が上手な人でなけれならないという思い込みがありました。でもこの本は、そんな考えを冒頭から吹き飛ばしてくれました。
■「書く」ってもっと身近なもの
■必要なのは「書いてみよう」と思う気持ちだけ
■文才がなくても文章を書いていい
■誰でもなく、「自分のため」に書いていい
■「うわぁ~」と思ったら「うわぁ~」と書いてしまえ
紹介しきれないくらい全文に心に刺さる言葉がちりばめられていて、読み終わった瞬間、「もしかして、わたしも書いていいのかな?」と思ってしまったのでした。自分以外の人が読むものを書くのは勇気が必要でしたが、「書いてみたい」という気持ちが膨らんでいきました。そしてnoteについて、いったいどんなものなのかをもっと知ってみたくなったのでした。
こうしてわたしのnoteへの扉は開かれました。
「noto完全マニュアル」に助けられて
さて、noteとはどんなんものなのか、インターネットで検索すればたくさんの情報があっという間に集まります。もちろんnoteさんの公式ページも拝見しました。なんとなく雰囲気はわかった!……気がする。
いつものわたしならここで、インターネットの情報を頼りに「早速noteを始めてみよう!」と考え、「とりあえずアカウントを作成するぞ!」となるところです。
実際そうしようとしていました。しかし、これまで「わかった気がする」と雰囲気だけで始めたものはたいていどこかで躓いていたことを思い出し、還暦も過ぎたことだし、ここはちょっと慎重に、と自分に言い聞かせました。
改めてnoteを始めるにあたってわかりやすい本がないかを検索してみたところ、いろいろなサイトでおすすめされていたのが、秀和システムさんから出版されていた「note完全マニュアル」という本でした。電子書籍ではなく、ページを開けばすぐにみられる紙の本にしました。書き込みができたり、付箋を貼ったり移動したり、忘れっぽい私には紙の方があっていると思ったからです。
この本に助けられてわたしはnoteを始めることができました。2020年11月に出版されたもので、現在のnoteは本の中で使われている画像や機能とは異なっている部分もありましたが、IDの重複に備えていくつかの候補を考えるなど事前に準備しておくことができたので、すんなりと始めることができました。
今回notoを始めるにあたっては主に本書の前半部分を参考にしましたが、慣れてきてもっとnoteを活用してみたいと思ったときには、後半部分を参考にできそうです。
2冊の本との出会いが、わたしにnoteで書くという新たな扉を開いてくれました。この出会いに感謝して、書くことを通じて自分の世界を広げていけたらいいなと思います。
読んでくださってありがとうございます!もし気に入っていただけたらサポートいただけると嬉しいです。猫さまのために使わせていただきます。
