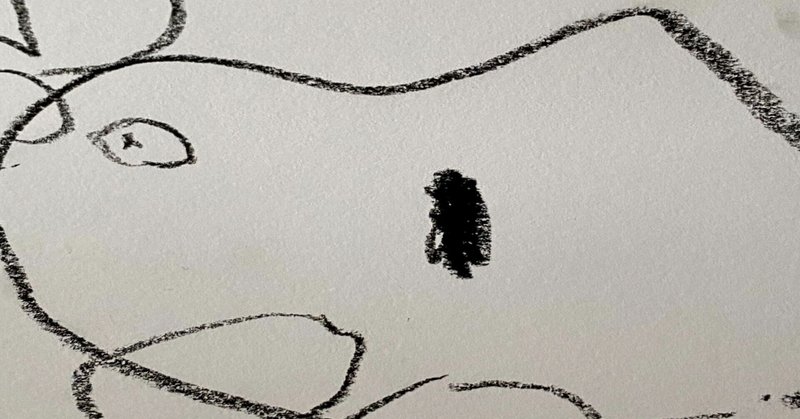
新学期に気を付けたい先生の目
新年度が始まって2カ月が経ちますね。
今年度1号の主任だよりです。
3月から事務の業務をしていると、保育とは全く違うことを考え続けています。保育中も行事準備も使いものにならず、すみません。研修やこの主任だよりを書くことで、たまに保育の脳に戻るきっかけをください。
ということで、今回は新学期に気を付けたいことを2点書きます。時間のある時に読んでみてください。
学級経営案について
5月のはじめに学級経営案の発表を行いました。クラスの目指すゴールやそこに向けて具体的にどんな仕掛け(環境設定)をしていくかがまとめられました。3月のゴールができましたね。
ただ、ゴールができると問題もあります。
それは、ゴールに向かって「全力で」走ってしまうことです。それから「最短で」ゴールを目指してしまうことです。
ではなぜ「全力」と「最短」がいけないのか。
ゴールを知っているのは、クラスで先生だけです。子どもは知りません。そして、子どもたちはゴールを知っているからといって、すぐにゴールに向かえるわけではありません。その子がその子なりに成長するには、時間差もありますし、そもそもこの一年間でゴールするとは限りません。なんてったってゴールは先生が決めただけですから。
3月のゴールを決めたことで方向性は見えやすくなりますが、決してそこに向かって子どもたちの手を引っ張っていかず、背中を押し支えたり手を繋いで進んであげてください。これが「全力ではなく」という部分です。
そして3月にたどり着くゴールであることもお忘れなく。ゴールが決まったからといって焦ると、今の子どもを受け入れることができず批判の目ばかりになってしまいます。「ありのままの姿を受け入れる」というやつですね。これが「最短ではなく」という部分です。
学級経営案は10の姿の考え方に似ているかもしれませんね。達成目標ではなく、方向目標です。
子どもを見る目について
2カ月も経つと、先生も子どもも新しいクラスに慣れて子どもの姿がいろいろと見えてきます。そうすると、その子の良いところも見えるし、気になるところも見えます。
その割合ってどのくらいですか?
これは先生の保育観や子どもを見る目のクセによって違います。「良い8:気になる2」の人もいれば「良い1:気になる9」の人もいます。どちらが正しい、とか幼稚園の先生らしい、とかはないです。
ですが、自分の見る目のクセは知っておくべきだと思います。気になるところが見えやすいクセの人は、意識的に子どもの良さを見つける努力が必要です。反対に良いところが見えやすい(気になるところをスルーしてしまう)クセの人は、意識的に気になるところを見つける努力が必要です。この場合「気になるところ」よりも「さらに伸びてほしいところ」と言い直した方が良い場面もあるかもしれません。
さて、先生の目の話をしましたが、3月の私たちは3月の子ども、つまり一年間を終える時期の子どもたちを見ていました。一年で成長した子どもたちですね。そうすると、3月に見た姿と新年度の4月の子どもの差に脳が追いつけないことが起こります。「あれ、去年の子はもっとできてたはず」なんて錯覚も起こります。おそらく去年も同じでしたが、3月までの成長を見てきたので忘れているだけです。子どもは次の学年に進みますが、私たちは一年間成長した子どもから急に4月のスタートの子どもに戻されるので、変な違和感を持ちます。タイムリープみたいですね。
そんなことも知っておくと、違和感や現状に焦らなくなります。
それから、先日汐見先生のお話をオンラインで聞く機会がありました。「保育をどうしよう未来会議」というセミナーです。そのお話での学びは「子どもを善く見る」です。詳しくはみなさんも講演を見てほしいのですが、汐見先生は昨年から子どもを善く見なさい、不満や愚痴は控えなさいとお話しています。私は賛成です。ちなみに善くというのは肯定的、楽観的という意味です。反対に悪くというのは批判的、課題的という意味だと私は解釈しています。
同じ場面の子どもを善く見ても悪く見ても、現状は何も変わりません。 それなら善く見た方が良くないですか?というのが根拠の一つ。 不満や愚痴はその目でばかり見てしまいやすくする、というのがもう一つ。
考え方はそれぞれですが、私はこう考えています。
まとめ
新学期に気を付けたい考え方を二つ、まとめてみました。
最後に、最近私の中で好きな言葉があります。
出来ていないを子どもが自分の力で出来るようにするのが、私たちの仕事
です。出来ていないを出来るにする、というと認知能力的に聞こえてしまいますが、そうではなく出来るにするためにどんな仕掛けをしようかな、と考えるという意味です。
トイレが嫌な子どもがトイレに行けるために「トイレに好きなキャラクターを置く」のか「トイレに行けたらシールを貼る」のか「好きな音楽をかけてトイレBGMにする」のか。要は仕掛けをどう作るか、ですね。それは物かもしれないし、曲かもしれないし、声かけかもしれません。
「この子ぜんぜんトイレに行かない」という出来ないことに対して、 「私が何をしたら行けるようになるかな」を常に考えてください。
食事も、支度も、集団も、考え方は同じです。
ただ、疲弊してしまわないように、いっぺんにやらず出来そうな時とタイミングでお願いします。実践というより考え方として覚えておいてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
