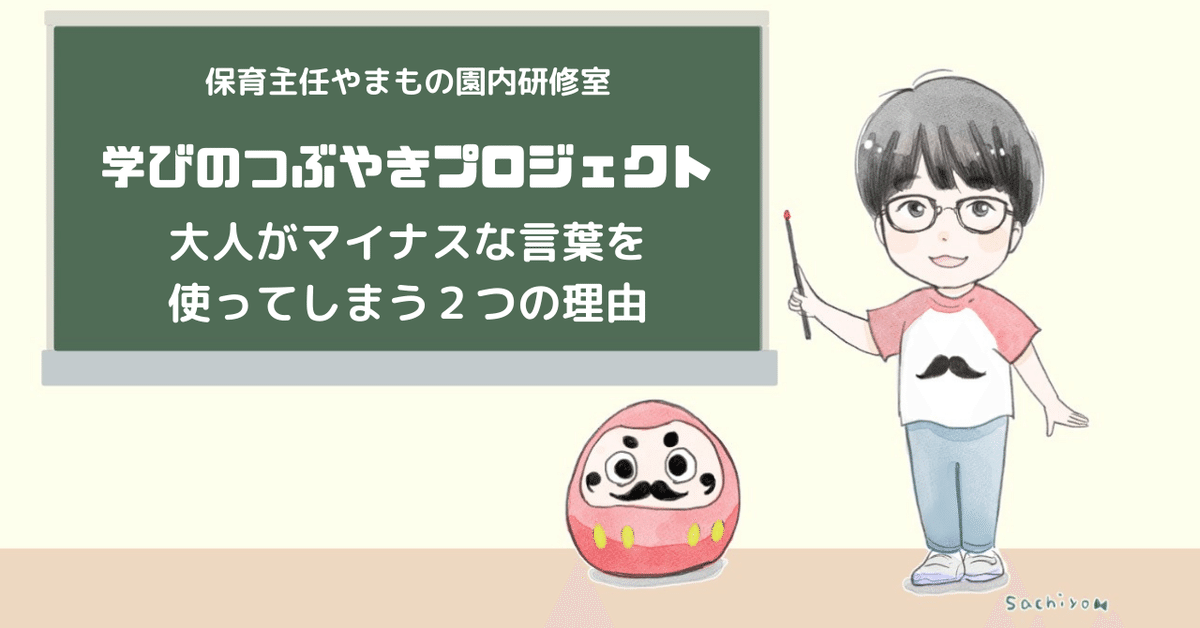
学びのつぶやきプロジェクト #4
どうも、主任やまもです。
幼稚園教諭をしたり、大学で講義をしたり、主任やまもの園内研究室を運営したりしています。
「学びのつぶやきプロジェクト」というのをゆるゆると進めております。新任の保育者や実習生に伝えたい言葉をツイートから探していく企画です。
最終的に冊子になればいいなと思っています。
学びのつぶやき解説
本日のつぶやきはこちら。
「お片付けしないとおやつ食べられないよ」など
— オニっち@幼児教育 (@tocotoucan443) April 16, 2021
ついつい大人の時間で子どもにマイナスな言葉をかけてしまいがちだけど、
「お片付け終わったら早くおやつ食べられるね」など
プラスの声かけをしていきたい😶
そして何より、子どもの行動の意図をしっかりと考えていきたい🙂
「○○しないと、✖✖できないよ」や、
「○○しないと、✖✖だからね」といった言葉…
実は現場あるあるです。
子育てあるあるでもあります。
つまり、多くの大人が癖になってしまっている言葉です。
ツイートにもあるように、この言い方はマイナスな言葉です。
「マイナスな言葉」について説明をしておくと、
しない、できない、とり上げる、時間がなくなる、とられる など
否定的で不利益が起こり、不快になる言葉です。
大人も言われて嬉しい人はいませんよね。
その反対が「プラスな言葉」です。簡単です。反対にすればいい。
する、できる、もらえる、時間ができる、使える など
肯定的で、言われた人にとって利益がある言葉です。
このマイナスな言葉を減らしてプラスの言葉を増やそうね。
というのが、オニっちさんのツイートです。
大人の立場で分かりやすい例えというと…
「働かないと、給料あげないからね」 でしょうか。
「うっせ!」と言い返したくなりませんか?笑
働いてお給料をもらうのは、当たり前のことです。
ただ、それを言葉にされると「うっせ!」となります。
では、
「働いてくれたので、お給料をあげます」だと、どうでしょう。
これも当たり前のことですが、悪い気はしませんよね。
言葉ってそんなもんです。
当たり前のことでも、プラスであれば気持ちは明るくなるし、
マイナスであれば気持ちが暗くなります。
子どもの話に戻ります。
ツイートにあるように、
「お片付けしないとおやつを食べられないよ」
「お片付け終わったら早くおやつを食べられるね」の
2つのほぼ同じ意味の言葉があります。
あなたはどちらを使いますか? ということです。
ここまでの話の流れで、当然後者を選びますよね。
単純な話です。
ここからは、それが単純にいかないお話をしていきます。
マイナスな言葉を使ってしまう2つの理由
プラスな言葉は大人も子どもも嬉しいのが分かっているのに、マイナスな言葉を使ってしまう。そんなことがあります。
なぜでしょう。
ここでは、私が考える2つの理由お話します。
理由1:マイナスな言葉は強くて、効果がすぐ見える
マイナスな言葉は良いことが取り上げられる不快感が強く、それを避けるために強制的にやらざるを得ない状況をつくります。
さらに、家庭内や学校内で大人より立場が弱い子どもだからこそ、効果は抜群となります。
例えば「宿題しないとテレビ見せないからね!」という言葉で考えてみます。すると、テレビを見せる見せないの権利があるのは大人であり、子どもは従わざるを得ないのです。可哀そうな子どもたち。
大人の立場としては、子どもが(従わざるを得ないので)動くので「しめしめ」と思うでしょう。大人の思うつぼになるからです。
そうすると、マイナスな言葉を多用したくなります。気持ちは分かります。効果があることは何度でも使うでしょう。
ですが、子どもが大きくなった時が心配です。
「宿題をしないとテレビ見せないからね!」とマイナスな言葉で育った子どもが、一人暮らしを始めたらどうなるでしょう。
従わざるを得ない状況から抜け出したこの子どもは、テレビをどのように見ていくでしょうか。予想の域を超えませんが、おそらく「宿題をしなくてもテレビを見れる!一人暮らし最高!」と際限なくテレビを見るでしょう。
一方、「宿題が終わったらテレビが見られるね」という言葉で育った子どもは、ひと頑張りの後のご褒美や楽しみを持って取り組めます。
この考え方が身についていたら、学業だけでなく仕事へ向かう気持ちも変わってくると思いませんか?
私たちの一言一言が、子どもたちの将来に繋がっているのを実感します。
理由2:マイナスな言葉を使っている自覚がない
こちらはけっこう深刻な問題です。
「マイナスな言葉は使っていません」と自分で思っていながら、実際子どもを目の前にして使っているということがあります。
これは最初にお話しましたが、マイナスな言葉を使うことが”癖”になっていることで起こります。
今までマイナスな言葉が子どもを動かしたい時に効果があり、実際に使ってきた人にとって、マイナスな言葉は日常であり口癖です。
また、プラスな言葉に慣れていない場合「じゃあどうやって言ったらいいの!?プラスな言葉は効果がない(薄い)し!!」となり、「そもそも子どもが悪いんだからマイナスな言葉をかけられても当然でしょ!仕方ないことでしょ!!」となるわけです。
この問題を周りから直すのは正直難しいです。
なぜなら、人を変えられるのはその人だけだからです。
人は人を変えられない。変えられるのは自分だけ。
今回の記事のように情報は教えられます。
「こうがいいよね」と伝えることもできます。
直したい人に伴走して寄り添うこともできます。
ただ、変わろうと思えるのは、最後は自分自身の意志です。
投げやりなつもりはありませんが、私の考えです。
まとめ
言葉にはマイナスな表現とプラスな表現がある、というお話でした。
プラスな言葉の話をあまりしませんでしたが、デメリットはあります。
効果が薄いことと、子どもが動くのに時間がかかることです。
じっくりコトコトとプラスを実感していくのです。大人も、子どもも。
そして、マイナスな言葉をいいだけ否定してきたように見えますが、実はそうでもないというどんでん返しで終わります。
「マイナスな言葉は使わない方がいい」
この言葉は間違いだと私は考えます。
私がマイナスな言葉について誰かに伝える時は、
「マイナスな言葉とプラスな言葉のバランスを考えた方がいい」
と言います。使うか使わないかの話ではなく、バランスです。
だって、マイナスな言葉が必要な時ってあるんですよ。
マイナスな言葉を使ってでも子どもに伝えたり、動いてもらったりしないといけない時があるんですよ。
「仕方ない」 そうなんです。分かります。
だからこそ、本当に「仕方ない」時のために、普段は使わないでおいてください。伝家の宝刀は、いざという時に使うんです。
それがバランスです。
なので、
「今はプラスな言葉でいくか、マイナスな言葉でいくか…
どうしよっかなー?」
と思える余裕と余白を持って保育したいものです。
ではでは。
【学びのつぶやきプロジェクト】のTwitterアカウントはこちら↓↓
――――――――――――――――――――――――――――――――――
保育主任やまもの活動
【平日更新】声のブログ(stand.FM)はこちらから
【すべての活動をお知らせ】主任やまものTwitterはこちらから
【NEW】主任やまもの園内研修室LINEの登録はこちらから
――――――――――――――――――――――――――――――――――
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
