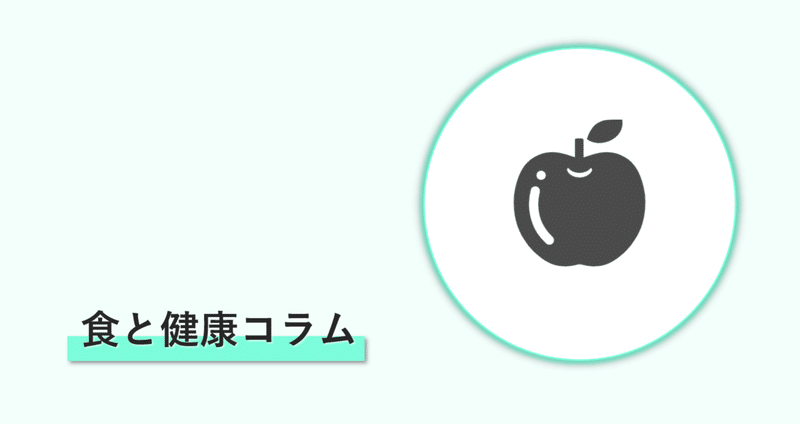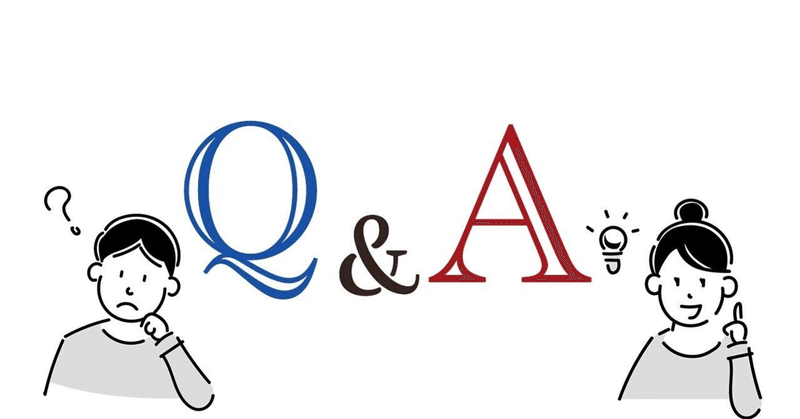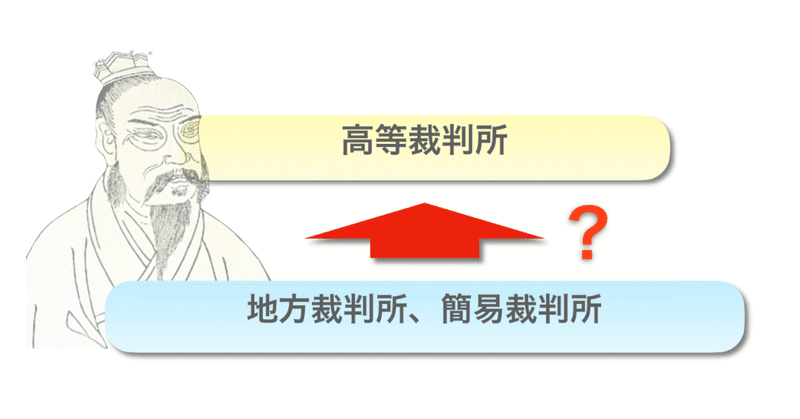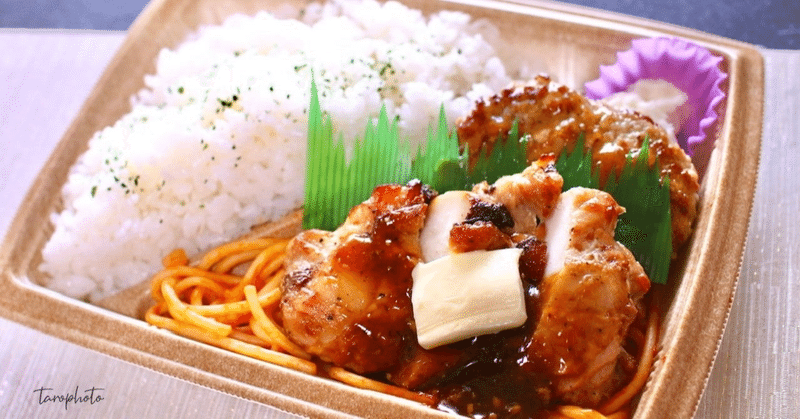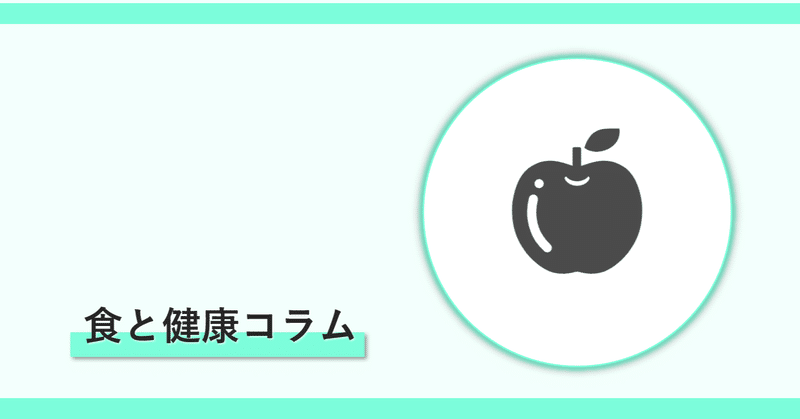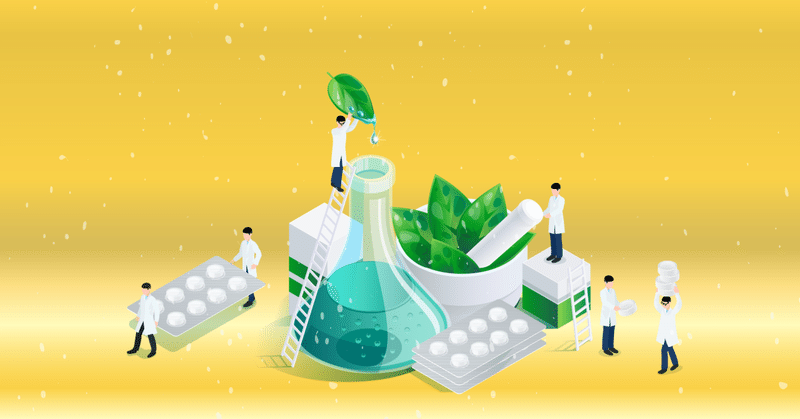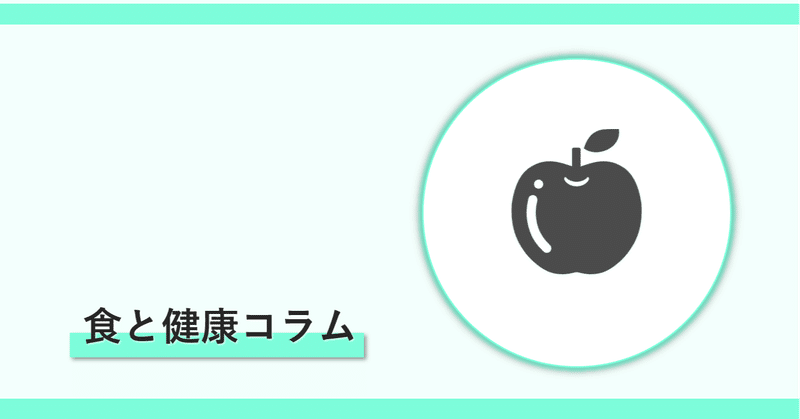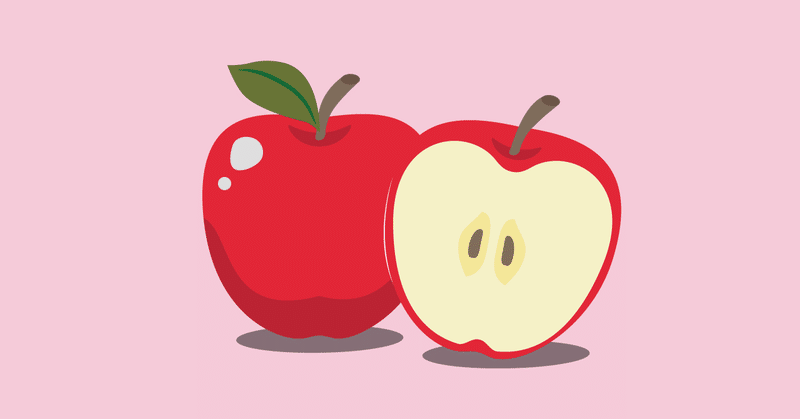#研究

腎臓結石の疑いがあって念のため紅茶を控えるように言われたそのとき、食品研究者の私の頭に思い浮かんだ一抹の不安と疑念を言葉に残しておく
プロローグ先日の人間ドックで、エコーの結果腎結石の疑いというという、絶対その先の尿路結石に進みたくないという状況に追い込まれ、泌尿器科に駆け込んだのですが、再確認したらなんら問題ないとのこと。ふー。 医「でも小さいのが見えなくもないので、普段から水分摂取を意識するのと、シュウ酸を多く含むほうれん草とか紅茶は摂りすぎないようにしてくださいね。」 ほー、シュウ酸ですか。気をつけよう、うんうん。 しかし、私の中である疑問が生まれます。 なんで紅茶なん?? 紅茶がダメって言