
アカデミー賞歴代作品賞95作品全部見たから全部レビューする(全54000字)
つい先月、A24製作・配給の『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が第95回のアカデミー賞作品賞を受賞し、また主演のミシェル・ヨー(以下敬称略)がアジア系史上初の主演女優賞に輝いたことで、ワイドショーやネットニュースを中心に大いに話題となりました。
しかし、数ある映画賞の中で、オスカーがこれだけ特別視され、権威と誉れある賞として多くの人に受け入れられているのはなぜでしょうか。そもそもアカデミー賞とは一体なんなのでしょうか。
このnoteでは、第1回から第95回までの作品賞受賞作にフォーカスして、アカデミー賞(オスカー)の歴史とその変遷を追っていきたいと思います。その際、参考のために作品のオススメ度を「☆〜☆☆☆」の形で付しておりますが、こちらはあくまで個人の感想ですのでどうかお気を悪くなさらないでください。
非常に長くなりますが、ご興味のある方はどうか最後までお付き合いいただけると幸いです。作品鑑賞時に索引としても使えるように全ての作品に目次をつけています。
アカデミー賞はいつから?
アカデミー賞が生まれたのは、1920年代末のことです。この時代は無声映画の最盛期であり、映画産業の成熟期にも当たります。しかしこの頃のハリウッドはある問題を抱えていました。それが労働組合(ユニオン)との衝突です。
1920年代中頃には、多くの撮影所でこの労働組合が結成され、経営陣に労働条件の改善や賃金の引き上げなどを要求するようになりました。このまま組合が幅を効かせるようになってはまずいと考えたMGM映画(ハリウッドの最大手)の総帥ルイス・B・メイヤーは、経営者主導の御用組合「映画芸術科学アカデミー(AMPAS)」を作ってこれに対抗する案を思いつきます。
映画芸術科学アカデミーの当初の目的は「映画芸術および科学の質の向上をはかること」でしたが、その活動の一つとして付随的に「優れた業績に対する表彰」というものがありました。そう、これがアカデミー賞の始まりです。つまり、アカデミー賞というのはもともと組合対策として生まれた、映画人のエリート・クラブによる内輪の賞なんですね。設立の経緯はざっくりとこんな感じです。
アカデミー賞はなぜ特別?
映画の祭典として、アカデミー賞が特別なのはなぜでしょうか。普通、映画祭の賞というのは、その映画祭で上映された作品にのみ与えられるものです。しかしオスカーはその限りではありません。アカデミー賞の面白いのは、前年に全米で公開されたすべての映画が(細いか規定や資格はありますが)審査の対象になるというところです。
さらに特殊なのは、その審査を行う投票者が、映画評論家や観客(映画ファン)ではなく、監督・俳優・各種部門のスタッフなど、作り手側自身であることでしょう。これが最大の特徴と言ってもいいかもしれません。労いと敬意を込めて、同業者が同業者に拍手とビック・ブラボーを送る。それがアカデミー賞の大きな意義の一つでもあります。そして、だからこそ、映画人にとってオスカーはずっと特別な賞なのです。
1929年(アカデミー賞のはじまり)
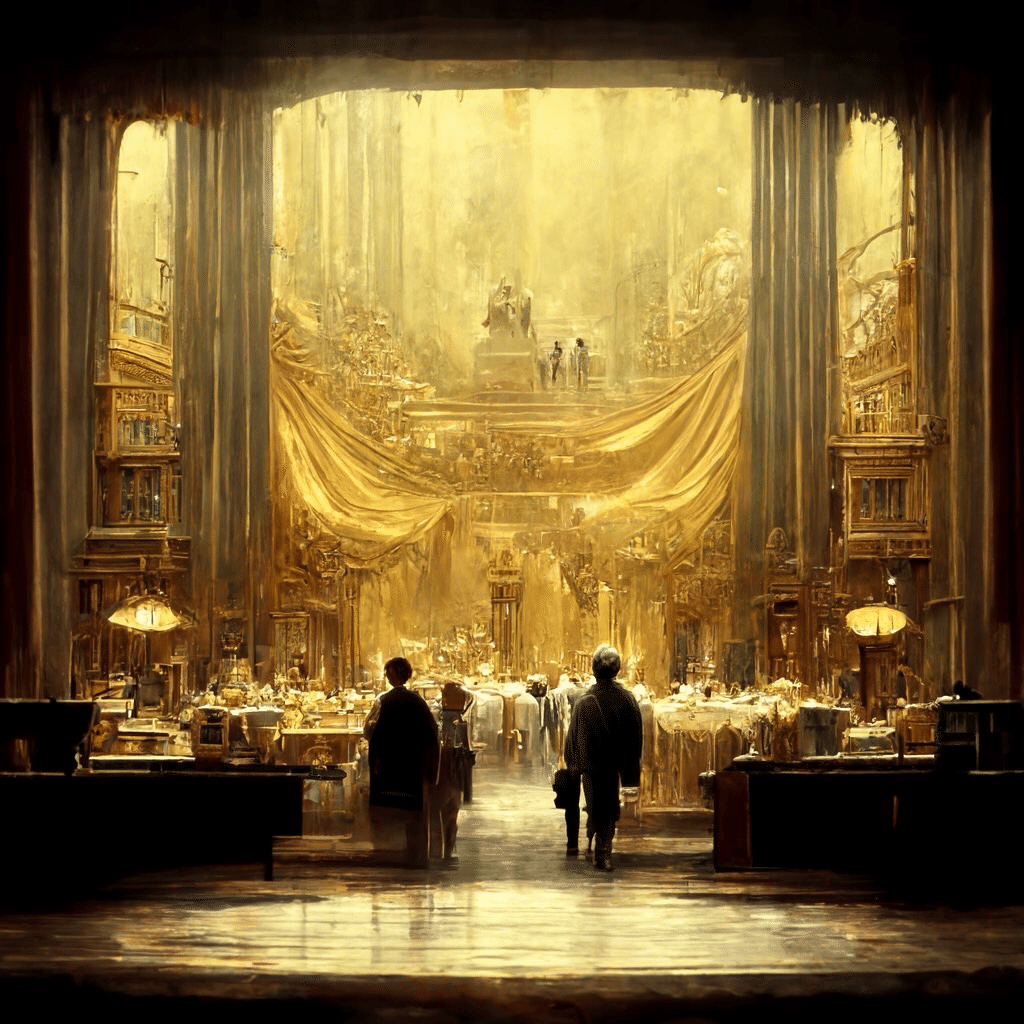
1929年5月16日、ハリウッドのとあるホテルのブロッサム・ルーム。参加者は約200人。「映画芸術科学アカデミー」の創立2周年記念を兼ね、アカデミー賞の第1回の受賞者たちを称賛する晩餐会が開かれました。アカデミー賞の歴史の始まりです。
しかし、当初のアカデミー賞授賞式はあくまでディナー・パーティーの延長線上にある催しに過ぎず、現代のような華やかさや豪華な演出はありませんでした(3ヶ月前にはすでにアカデミー会報に受賞者名が掲載されており、あくまで形式的でささやかなものにとどまったそう)。
審査の対象作品の公開期間は1927年の8月1日から、1928年の7月30日までの1年間で、現在の暦年制度(1月1日〜12月31日まで)とは異なります。またこの時点では受賞部門はわずか12部門と少なく、助演賞や音楽賞はまだ設置されていませんでした。監督賞が[ドラマ]部門と、[喜劇]部門の二つに分かれているのも今とは違います。
では、ここから早速各作品のレビューに入りたいと思います(あらすじ程度の若干のネタバレが入りますので、その点ご了承くださいませ)。
○第1回受賞作『つばさ』(製作年:1927年)
記念すべきアカデミー賞作品賞第一回受賞作。先の第一次世界大戦最中を生きる空軍青年パイロットのお話です。
世界初のトーキー映画は1927年の『ジャズ・シンガー』(正確には歌唱シーンのみの部分トーキー)ですが、この作品の上映はそれより少し前の同じ27年でまだサイレントです。アカデミー賞も第2回受賞作の『ブロードウェイ・メロディー』からトーキー映画に取って代わられるわけなので、歴代作品賞の中では2011年の『アーティスト』とこの『つばさ』だけが無声映画になります(ちなみに、『ジャズ・シンガー』を製作したワーナーには同年特別賞が贈られました)。
戦争映画でありながらも、ロマンスやコメディの要素が入り交じって反戦色はそれほど強くありません。本作の白眉は空中戦の迫力ある撮影で、この時代にこんな風に撮れるんだなあという素朴な驚きがあると思います。ちなみに、公開年(1927年)の5月にリンドバーグの大西洋横断があり、航空機熱が高まっていたので、当時としてはかなりの興行的成功を収めたそうです。
トム・クルーズの『トップガン』(1986)がヒットしたあと、米軍のパイロット志望者が前年比500%になったという逸話がありますが、この映画が当時の若者に与えた影響もかなり大きいものがあるんじゃないでしょうか。
活弁つきで観られるものもあるので、サイレントに忌避感がある人はそちらをおすすめします。
♦︎オススメ度:☆
(撮影技術に目を見張るものはあるもの、特別面白くはないため)
1930年代〜

1930年代は無声映画から有声映画(トーキー)へという、映画産業における歴史的な大転換の時期です。政治的・経済的な背景には1929年からの大恐慌や、日本・ドイツ・イタリアでのファジスムの台頭があります。映画界も30年代前半は恐慌の煽りを受けたものの、30年代中頃からは動員数も回復し、大作と呼ばれるような作品が続くようになりました。
○第2回受賞作『ブロードウェイ・メロディー』(1929年)
メイヤーのMGMによる初の全編トーキー映画。タイトルからもわかる通り、ミュージカ仕立ての映画で、更にミュージカルの現場が舞台となった「バック・ステージ物語」と呼ばれる類の作品です。
ブロードウェイに憧れて上京した姉妹と、夢見る若手俳優との三角関係のようなものが描かれているのですが、男(エディ)がただのクズ男なので観ていて結構不快です。映画史上のメルクマール、ターニングポイントとして意味をもつのも分かりますが、トーキーの黎明期に同じような映画は無数にあり、この作品が際立って面白いということはないように思います。
「おどけてみよう ブロードウェイでは 悩んでるなんてカッコ悪い」
♦︎オススメ度:☆
○第3回受賞作『西部戦線異常なし』(1930年)
今なお語り続けられる戦争映画(反戦映画)の金字塔です。ちょうど最近Netflixでリメイクも作られていたので、作品の名前を聞いたことのある人も多いと多います。プロパガンダに乗せられ、軍に志願したドイツ人の青年が戦争の悲惨さに直面するという話です。原作はあるんですが、アメリカでは珍しいドイツ視点の映画になります。
俺は歩兵隊になりたい!騎兵隊になりたい!銃剣を使ってみたい!と最初は意気揚々とした学生たちも、いざ戦場に出るとパニックに陥り、目の前で同胞が死んでいくのをただ見ていることしかできないやるせなさを味わいます。
セリフの無い戦闘シーンが印象的で、ゲームとして楽しむもの、放心状態で神経衰弱になるもの、戦場で怪我をしこんな姿でもう生きていたくないと嘆くものなど、戦争の狂気がよく描かれていると感じます。前線の非情な現実が世間には全く伝わっていないというのもリアルで恐ろしいです。この大戦の別視点からの映画として、エルンスト・ルビッチ監督の『私の殺した男』(1932年)もお勧めします。
「ほとんど塹壕で過ごして、毎日、戦闘を繰り返す。必ず誰かは死ぬ。それだけだ」
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第4回受賞作『シマロン』(1931年)
原作は人気作家のエドナ・ファーバー女史。舞台は19世紀末。西部開拓時代のアメリカを描いた一大抒情詩です(「シマロン」とはスペイン語で無法者の意)。冒頭のランドラッシュ(オクラホマ入植のシーン)が大変迫力ある映像に仕上がっています。
大恐慌の影響もあり、作品賞受賞作の中では唯一の赤字ということで有名です。また西部劇での作品賞受賞は、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』(1990年)と『シマロン』のみになります。
熱血漢のように描かれる主人公ヤンシー・クラバットの放浪癖が中々ひどく、妻子を置いて好き勝手やってるだけなのであまり人間的な魅力が感じられませんが、もしかしたら妻の方を主人公として観るのが正しい見方かもしれません。
♦︎オススメ度:☆
○第5回受賞作『グランド・ホテル』(1932年)
舞台はベルリンのとある一流ホテル。出自も仕事も何もかも違う男女5人が、たまたま同じホテルに居合わせるという偶然。ホテルという非日常の空間で起こる数々のドラマ。そんな人生の妙を味わう映画で、「グランド・ホテル形式」と呼ばれる作品群の先がけとなったオムニバス風の群像劇です。主役はグランド・ホテルそのものといってもいいでしょう。
ジョン・バリモア、グレタ・ガルボらをはじめ、当時のMGMのオールスター集結と気合いのに入った映画ではありますが、作品賞だけのノミネートにとどまり、そのまま作品賞だけ受賞した最初で最後の映画でもあります。
「グランド・ホテルは変わらない。人々が来ては去ってゆく。すべては元のままだ」
♦︎オススメ度:☆☆
○第6回受賞作『カヴァルケード』(1933年)
およそ30年の英国近代史(ヴィクトリア時代から第一次世界大戦まで)を、ある中上流階級の一家の視点で描いた作品。今みると本当に全然面白くなくてすごいです。記録映画のような気持ちで観るのがいいかと思います。
オスカー像の命名をめぐってはいくつかの都市伝説があるのですが、とにかく「オスカー」という言葉が初めて記録されたのはこの第6回のアカデミー賞で間違いないみたいです。
♦︎オススメ度:☆
○第7回受賞作『或る夜の出来事』(1934年)
歴代のアカデミー作品賞受賞作で、主要5部門(作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚本賞)全てを総なめにした初の映画です。当時のハリウッドでマイナーだったコロムビア製作の映画がアカデミー賞5部門を受賞するのは大変な快挙で、これは『カッコーの巣の上で』の受賞まで41年間他の追随を許さなかった圧倒的な記録です(他には『羊たちの沈黙』のみ。)
それも頷けるほどの傑作で、内容こそベタなスクリューボール・コメディであるものの、現代人が見ても十分に面白い作品になっています。二人の邂逅のシーンは『ローマの休日』(1953)や『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』(1995)なんかにかなり似てるなあと思いましたが、そもそもこっちのほうが先だから似てるのは逆の方ですね。
前年のアカデミー賞で『カヴァルケード』の“フランク”・ロイドに敗れた雪辱を、“フランク”・キャプラ監督が見事に果たす結果となりました。また、この年にアカデミー賞には音楽部門が導入されています。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第8回受賞作『戦艦バウンティ号の叛乱』(1935年)
製作費200万ドルを投じた海上スペクタルの大作です。「バウンティ号の反乱」と呼ばれる、海上で起きた実際の暴動に基づいた物語で、冒険活劇、サスペンスの風味がある作品になっています。
日本では二・二六事件の影響を受けて、「叛乱」という二文字が使えなくなり、『南海制服』という邦題で1938年に公開されています(完全版の上映は戦後の1952年)。20世紀中に何度かリメイクもされているんですが、個人的にはあまり面白いと思える内容ではありませんでした。監督は『カヴァルケード』と同じフランク・ロイド監督です。
♦︎オススメ度:☆
○第9回受賞作『巨星ジーグフェルド』(1936年)
実在したブロードウェイの名プロデューサー、フロレンツ・ジーグフェルドの半生を描いた伝記映画(かつミュージカル映画)です。MGMらしくお金のかかった大作で、ミュージカルシーンが劇中に丸々組み込まれているのが印象的です。
面白い部分も結構あるにはあるんですが、上映時間177分と流石にちょっと長いのでだんだん飽きてきます。舞台セットが壮大なので、どうしても、カラーで見れたらなあと思ってしまいます。
映画キャリアがほとんどないにも関わらず、若くしてこの『巨星ジーグフェルド』と翌年の『大地』(37年)で主演女優賞を獲得したルイーゼ・ライナーは、その後あっという間にハリウッドから姿を消してしまったので、これ以降、受賞後に日の目を浴びなくなった俳優、作品に恵まれなかった女優には、“オスカー・カース“(オスカーの呪い)を受けたという評価がついて回るようになりました。
♦︎オススメ度:☆
○第10回受賞作『ゾラの生涯』(1937年)
前年に続いて、作品賞はまたも伝記映画です。自然主義の作家として知られるエミール・ゾラの生涯を、特にドレフュス事件に主眼を置いて描いた作品で、社会派の法廷劇としても見どころがあります。
この年にはアーヴィング・G・タールバーグ賞という特別賞が創設されています。当初はタールバーグの名の通り、名プロデューサーに贈られるものでしたが、後年には、優れた業績を残しながらも、監督賞や作品賞受賞に至らなかった映画監督に贈られる「お詫びの賞」のような位置づけとなりました。タールバーグ賞は86年のスピルバーグの受賞でも有名ですね。
♦︎オススメ度:☆☆
○第11回受賞作『我が家の楽園』(1938年)
ピューリッツァ賞受賞の舞台劇を映画化した作品。フランク・キャプラ監督の3度目の監督賞受賞作でもあります(二度目は『オペラ・ハット』での受賞)。
階級差のある恋愛と、愛かお金かというよくあるテーマを扱った映画で、別にそんなにおもしろくないような気もします。よくできた「いい話」すぎて白々しいというか、結局いいところの坊っちゃんの話なので、「お金よりも大切なものがあるよね」と言われてもあんまりピンときません。同監督の『素晴らしき哉、人生!』が好き人にはハマるかと思います。
♦︎オススメ度:☆☆
(個人的な好みでは☆)
1940年代〜

大戦の時代にあって、戦争と映画の結びつきが強化され、映画は優れた視覚メディアとして多くのプロパガンダに利用されるようになりました。一方戦後には、映画人を対象とした下院非米活動委員会による聴講会(1947〜)が開かれ、共産主義者やそのシンパ、そして疑義をかけられたものがことごとくハリウッドを追放されるという事態が起こります。1950年代まで続くハリウッドの“冬の時代“です。また、アカデミー賞においては、『風と共に去りぬ』(1939年)の8部門受賞によって、注目を集めた作品による賞の総取りなどが懸念され始めるようになりました。
○第12回受賞作『風と共に去りぬ』(1939年)
言わずと知れたテクニカラーの大作。南部戦争時のアメリカ南部を舞台に、その時代を逞しく生きたスカーレット・オハラの壮絶な半生を、231分という長尺で描きます。物価の変動を調整した映画の興行収入ランキングでは、全米/全世界ともに、今でも『風と共に去りぬ』がその1位の座を死守しています。
映画界屈指の不人気ヒロインとしても有名なスカーレット・オハラですが、なりふり構わずアシュレーへの愛に生きた彼女を、身勝手な女性とみるか、自分の信義を貫く誇り高き女性とみるかで評価は変わってくるかもしれません。
今作では乳母役のハティ・マクダニエルが、黒人女優として初めてオスカー(アカデミー助演女優賞)を獲得していますが、次にアフリカ系出身の女性がオスカーを貰う(『ゴースト/ニューヨークの幻』(1990年)のウーピー・ゴールドバーグの受賞)までには、なんと50年も間が空いています。BLM運動の最中に、黒人差別を肯定しているとしてVODでの配信が停止されたのも記憶に新しいです。
♦︎オススメ度:☆☆
○第13回受賞作『レベッカ』(1940年)
ヒッチコックがアメリカ(ハリウッド)に渡ってから撮った一作目の映画です。妻を亡くし、崖から飛び降りようとする、富豪マキシムとの出会いから物語は始まります。
舞台がイギリス(マシキムの故郷マンダレイ)に変わると甘いラブストーリーは一転。映画はサイコスリラーの様相を呈し、キリキリと不安を掻き立てるような演出が目立つようになります。徐々に明らかになる「レベッカ」の死の真相と、恨めしい記憶の亡霊。彼女はそんな奇妙な渦に巻き込まれてゆき・・・という作品。
ちなみに、本作で主演女優賞を受けたジョーン・フォンテインは、『風と共に去りぬ』でメラニー役を演じたオリヴィア・デ・ハットの妹に当たります。オリヴィアも『レベッカ』のヒロイン役を望んでいたものの、所属事務所との契約の関係で叶わなかったようです。
上で見た通り、オリヴィアは助演女優賞争いでハティ・マクダニエルに敗れ、オスカーを逃しているので、スターダムを上り詰める妹との間で、だんだんと確執が深まっていきました。1946年に『遥かなる我が子』で悲願の主演女優賞を勝ち取った際、(主演男優賞の)プレゼンターとして登壇する妹フォンテインに、オリヴィアは背を向けて一瞥もくれなかったという話が有名です。あとこれはあまり知られていませんが、実は二人とも日本生まれなんですね。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第14回受賞作『わが谷は緑なりき』(1941年)
西部劇の神様として知られるジョン・フォードによる社会派映画です。前年に『怒りの葡萄』、その前年に『駅馬車』を撮っていることを考えると、おそろしい体力と映画センスですね。
ある炭鉱町を舞台に、労働階級の家族(モーガン一家)の現実を悲喜こもごもに描いた作品。わが谷は緑なり“き“。つまり、「緑だった」という意味で、田舎の哀切が感じられる映画です。この年の本命にはもう一つ、オーソン・ウェルズの『市民ケーン』があったんですが、そちらは脚本賞<オリジナル脚本>しか撮れませんでした(ノミネートは9部門)。
「祈りというのは、ひたすら真っ直ぐ物事について真摯に考えることだ」
♦︎オススメ度:☆
○第15回受賞作『ミニヴァー夫人』(1942年)
ウィリアム・ワイラー監督作品。ミニヴァー夫人を話の中心に、戦時下でのロンドンの暮らしを描きます。戦争高揚のための映画と言われたらまあたしかにそうかと思うんですが、逆に反戦映画と言われたら反戦映画にみえてくるくらいの絶妙なつくりの映画です。
いわゆる「ホーム・フロント(銃後)」映画の一つで、戦闘シーンはなく、徹底して“待つ側“にスポットが当てられています。
この回では、「『不思議の国のアリス』みたいな気分です」と話し始めたグリア・ガーソン(主演女優賞)のスピーチが5分半も続いたので、翌年から受賞スピーチに制限時間が設けられるようになりました。
♦︎オススメ度:☆
○第16回受賞作『カサブランカ』(1943年)
「君の瞳に乾杯」を始めとする聞き馴染みのある名セリフを堪能できるドラマ。仏領モロッコの都市カサブランカで、戦争によって引き裂かれたかつての恋人(イルザ)と再会し・・・というお話です。不倫ですが。ドイツに占領された本国からアメリカに逃れるためには、カサブランカの街を経由する必要があったので、ここに多くの人が集まっていたんですね。
ダンディズムという言葉を体現したような渋カッコいい主人公が印象的な映画ですが、その一方で、ヒロインのイルザの魅力が十分に伝わってこないのが残念です。しかし上映時間が103分と短めなので、観やすいかと思います。最近だと『ラ・ラ・ランド』(2016年)で本作の名前が挙がっていたのを覚えています。
「カサブランカでは誰もが悩んでるんだ。なんとかなるよ」
♦︎オススメ度:☆☆
○第17回受賞作『我が道を往く』(1944年)
主人公オマリー神父を演じるのは『スイング・ホテル』(1942年)のビング・グロスビー。財政難にある田舎町に赴任した新任の牧師が、教会を再建するという心温めるヒューマンドラマです。7部門獲得の圧勝。
お節介焼きで"いい人"のオマリーと、頑固な老神父との交流、不良少年たちとの出会い、成長、が描かれます。中だるみ感が否めないものも、古き良きクラシックという感じ。クリスマス映画的な要素もあります。ミュージカル映画とまではいかないけど、結構歌がメインの映画です。『天使にラブ・ソングを…』な(1992年)なんかが好きな人にはハマるかもしれません。
本作で助演男優賞を受賞したバリー・フィッツジェラルドには、自宅でゴルフの素振り中にオスカー像を打ってそのまま割ってしまったという有名なエピソードがあります(当時は大戦中でオスカー像が石膏で作られていたため)。
♦︎オススメ度:☆
○第18回受賞作『失われた週末』(1945年)
売れない小説書きでアルコール依存症の主人公バーナムは、これは依存症に陥った人間を作品に描くためなんだと言い聞かせ、酒に溺れる自分を正当化します。そんな自己愛の強い拗らせた主人公を描いたかなりパーソナルな作品ですが、第1回のカンヌ国際映画祭でパルム・ドール(最高賞)も受賞しています。
主演男優賞を受賞したレイ・ミランドはかのジーン・ケリーをおさえての受賞だったので、これ以降、アル中の演技をすると「名演」として評価されるという伝統が生まれ、「アカデミー賞が欲しかったらアル中を演じればいい」というセオリーが生まれたとか生まれてないとか。また、あまりにも飲酒の描写が多かったため、当初は一般公開が躊躇されるほどだったそう。
ちなみに、作品賞とパルム・ドールとの同時受賞を果たしたのは、本作と第28回の『マーティ』、第92回の『パラサイト 半地下の家族』のみです。
「この広いコンクリートのジャングルにはどれだけ僕みたいな男がいるんだろう。激しい渇きに恐れている男が」
♦︎オススメ度:☆☆
○第19回受賞作『我等の生涯の最良の年』(1946年)
またもやウィリアム・ワイラー監督作品。大戦後に故郷へと帰った3人の兵士(復員兵)を映した群像劇。戦時中のトラウマを抱えながら仕事探しに奔走するフレッド、酒に溺れるアル、戦争で両腕を失ったことにより、自尊心を大きく傷つけられ、心を閉ざしてしまうホーマー。
空軍のフレッド、陸軍のアル、海軍のホーマー、と3人のバランスがよく、それぞれの抱える苦悩が丁寧に描かれています。46年の時点でこんな内省的な映画が撮れる余裕がすごいなあと思ってしまうんですが、製作者の構想は既に44年の夏にあったみたいで驚きです。
ホーマーを演じたハロルド・ラッセルは実際の復員兵(義手もホンモノ)で、非職業俳優ながら、見事助演男優賞を獲得しています。
これは今観てもかなり面白いのでオススメです。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第20回受賞作『紳士協定』(1947年)
『エデンの東』(1954年)や『波止場』(1954年)に並ぶエリア・カザンの名作。カリフォルニアからニューヨークへ越してきた人気記者兼ライターのフィルは、<反ユダヤ主義の実態を探る>という旨の連載企画を担当することに。数字や統計よりも、自身の体験を重んじる彼は、実際に自分が「ユダヤ人」となることを連載の切り口にするものの、至るところで差別にぶつかり、その根深さを身をもって知ることになります。つまりこの「紳士協定」とは、暗黙の了解として存在するユダヤ人差別のことなんですね。
難しいテーマを扱った秀逸な映画で、私たちが傍観者となって見て見ぬふりをすることもまた、差別への加担に他ならないということを改めて強く思い知らされます。この年の対抗馬には、同じく反ユダヤ人問題を扱った『十字砲火』(エドワード・ドミトリク)があるのが印象深いです。
♦︎オススメ度:☆☆
○第21回受賞作『ハムレット』(1948年)
シェイクスピアの古典的名作であり、“四大悲劇“と称される戯曲『ハムレット』の映像化作品(イギリスの製作)。あらすじはそのまま、父を毒殺してデンマーク王位につき、母を妃とした叔父に復讐を誓う王子ハムレットの物語です。しかし、その計略はもつれにもつれ、悲劇が次の悲劇を呼ぶことに・・・。
監督・脚本・主演を果たしたローレンス・オリヴィエの名演はさることながら、荘厳なオーケストラの演奏にも注目してほしいです。「悲劇」の名の通り、次々に人が死ぬため、本当に誰も救われず、誰も幸せになりませんが、ラストの剣戟のシーンは中々魅力的だと思います。
「人間とは概してそういうものだ。生まれながらにしてその内にもつ悪を通して、またある性質が肥大化することによって、理性の壁がつき崩される。あるいは、習慣に押しつぶされる。そんな人間は、ただ一つの、欠点を持っているために、その気品や純粋な心が隠され、非難の的となり、堕落する。たった一つの欠点ゆえに」
♦︎オススメ度:☆☆
1950年代〜

戦後、軍事大国として経済的な繁栄を究めたアメリカ。1950年代はその経済効果と思想的不寛容が結びついた順応主義(コンフォーミズム)の時代です。他方、テレビの台頭と従来のハリウッド・システムの崩壊によって、アメリカ映画は苦闘を強いられます。オスカーにおいては、秀れた外国映画が目立つようになり、1956年には(名誉賞とは別に)外国語映画賞が設立されました。外国語映画賞の受賞は、アメリカ本邦での公開が条件ではなく、各国の映画団体(日本では映倫)が一本を選んでアカデミーの審査を受けるという仕組みです。
(1950年代のハリウッドが置かれた状況について、詳しくはこちらをご参照ください。)
○第22回受賞作『オール・ザ・キングスメン』(1949年)
実在した政治家の腐敗を描いた社会派作品。子どもたちが巻き込まれたある事故をきっかけに、政治家の汚職に声を上げ、州知事に当選したウィリー・スターク。政治の浄化を訴える彼でしたが、政治的な野望が肥大し、次第に権力にのまれてゆきます。
個人的には結構好きなテーマで面白いんですが、小説原作の映画化ということで、すっ飛ばしている部分も多く、ラストも含めて全体的に粗っぽい印象があります。
監督のロバート・ロッセンは、授賞式の直前に共産党員であった過去が発覚して、監督賞・脚本賞を逃しています。『オール・ザ・キングスメン』でポピュリズムと政治腐敗を描いた彼が、マッカーシーの赤狩りによって一時映画界を追放されてしまったというのは何とも皮肉です。
また、アメリカにおける政治の腐敗を描いた作品であったため、当時(1949年)米国の占領下にあった日本では公開が見送られたそうです。2006年に、ショョーン・ペン&ジュード・ロウ主演で再度映画化されているので、そっちを観たことのある人の方が多いかもしれません。
「人は罪と腐敗に生まれる。真理だよ」
♦︎オススメ度:☆
○第23回受賞作『イヴの総て』(1950年)
ジョセフ・L・マンキウィッツ脚本・監督作品。彼は、『市民ケーン』の脚本を書いたハーマン・J・マンキウィッツ(マンク)の弟にあたる人物です。
憧れの女優マーゴの住み込み秘書となったイヴの成り上がりストーリーで、モノローグと回想で話が進みます。華やかなショー・ビジネスの裏側を描いた作品ですね。
自分の欲に正直でありながら、その野望を前面には出さず、あくまで狡猾に、トップ女優の座を狙うイヴの姿に感服です。まだ売れる前のマリリン・モンローもチョイ役で出演しています。
♦︎オススメ度:☆
○第24回受賞作『巴里のアメリカ人』(1951年)
作品賞受賞作では、『風と共に去りぬ』に次ぐ2作目のカラー作品。芸術の都パリで、画家を夢見る一人の男の話です。ガーシュウィンの軽快な曲にあわせて物語が始まります。
ストーリーは薄っぺらなラブロマンスで正直微妙なんですが、ジーン・ケリーの高い身体性を伴った演技にはやはり目を見張るものがあります。
ミュージカルが好きな人は、『オール・ザット・ジャズ』(1979年)や『ラ・ラ・ランド』といった後年の名作のサンプリング元ともなった本作を、『雨に唄えば』(1952年)と併せてぜひ観てほしいですね。
この年には、黒澤明の『羅生門』(1950年)が、最優秀外国語映画賞(名誉賞)を受賞しています。
「街が美しくなっても、君がいないんじゃ辛すぎる」
♦︎オススメ度:☆☆
○第25回受賞作『地上最大のショウ』(1952年)
世界一を誇るサーカス団が、「地上最大のショウ」を作り、それを演じるために奮闘するお話。最近では、スピルバーグ監督の幼少期のベストということで話題になりました。
サーカスのシーンは見応えがあって面白いんですが、ダラダラしていて長いので、流石にちょっと後半は飽きてきます(152分)。ちなみに、監督のセシル・B・デミルは、この映画を『十戒 』(1956年)の長い撮影中に撮りあげたそうです。
本作は、映画歴40年のご老公(当時62歳)のセシル・B・デミルに対する功労賞であるという見方も強く、事実、この作品で監督賞は受賞していません(監督賞はジョン・フォードの『静かなる男』)。
また、テレビ局がアカデミー賞の放送権を10万ドルで買ったため、これ以降、毎年NBCで授賞式が放映されるようになりました。衰退期にあった映画界を支えたのは、実はそのライバルのテレビだったんですね。
「ご来場の皆様、本日のショウはこれでお終いです。ぜひまたの機会に、ご家族そろって地上最大のこのショウにお越しください。日頃の苦労や悩みを忘れて、楽しい思い出だけをお持ち帰りください。それでは皆様、またお会いできる日まで、さようなら。」
♦︎オススメ度:☆
○第26回受賞作『地上より永遠に』(1953年)
変則的ですが、『地上(ここ)より永遠(とわ)に』と読みます。かの有名な『ローマの休日』を抑えての8部門受賞。ラッパ隊からハワイの歩兵隊へ転隊(転属)してきた主人公プルーイットが、徹底的な縦社会の中で、友情に恋愛に翻弄されてゆきます。
メロドラマ、スポーツ、友情物語、戦争映画と色々な要素を詰め込みすぎたからか、それとも米軍への忖度からか、全体としてはとっちらかった印象を受けます。『巴里のアメリカ人』、『地上最大のショウ』とカラー作品が2年続いて、また白黒に戻りました。翌々年に『マーティ』で主演男優賞を勝ちとったアーネクスト・ボーグナインが脇役で出演しています。
ここからは少しトリビアのような話。兵卒アンジェロ役で助演男優賞に輝いたフランク・シナトラは、この頃人気が下火となり、またレコードも売れなくなり、52年には所属事務所との契約を解除されていました。イタリア系マフィアとの黒い噂や女性スキャンダルもあり、今後のキャリアは潰えたと思われていた彼ですが、本作での受賞により見事に名誉を挽回。映画化される前から原作を読みこんでいたシナトラは、このイタリア系アメリカ人の軍人の役がもらえるよう、コロムビア映画の社長に直談判をしたそうです(この時、マフィアがシナトラのために裏で動いたという“都市伝説“が、『ゴッドファーザー』(1972年)の冒頭で描かれています)。
そういえば、トッド・フィリップス監督の『ジョーカー』(2019年)で、アーサーがシナトラの歌を口ずさんでいましたね。
♦︎オススメ度:☆
○第27回受賞作『波止場』(1954年)
『紳士協定』に続いて2作目のエリア・カザン作品。『欲望という名の電車』(1951年)でタッグを組んだマーロン・ブランドが、今度は波止場の日雇い労働者を演じます。
彼が働く波止場の領有権はギャングに牛耳られており、不正を告発しようとした友人のジョーイが殺害されるような有り様。その悪行に苦しむジョーイの妹や、神父との交流、また兄チャーリーの死を通して、一介の“ゴロツキ“であったテリー(マーロン・ブランド)は良心を取り戻し、ギャングと真っ向から対峙することを決意します。
一度体制への忠誠を見せたカザンの撮るこの映画に多くの批判が向けられたようですが、テリーが孤軍奮闘する様子には、「裏切り者」のレッテルを貼られながらも、(それが良いか悪いかは置いておいて)ハリウッドで映画を取り続けたカザンの姿が重なる部分もあります。
また現代にも通ずる、「メソッド演技」と呼ばれる演出の方法論を取り入れているため、古臭さを感じず今でも観やすいと思います。スタローンはこの『波止場』に感銘を受けて、「ロッキー」を書いたそうです。
オススメ度 :☆☆
○第28回受賞作『マーティ』(1955年)
タイトルロールを演じるアーネスト・ボーグナイン(当時38歳)が適役です。作品賞をとった歴代の95作品の中では、最も上映時間が短い(91分)本作ですが、テンポがよく、まとまりもあって、個人的には非常によくできた作品だと思います。
容姿にコンプレックスを抱えて拗らせた中年男のマーティが、同じく冴えない女教師のクララと心を交わしてゆきます。親友のラルフ、母親とその妹、いとこ夫婦など、視点が何度か入れ替わり、飽きさせない工夫もあります。元がテレビ・ドラマだからでしょうか。
前時代的な価値観が背景にはあるものの、“結婚”という普遍的なテーマを扱っているため、いつの時代にも通ずる面白さがあります。ダンスホールでクララと出会った夜、浮き足立ってふらつき回るマーティは、『雨に唄えば』のあの有名な歌唱シーンを彷彿とさせるようです。
こちらはVODでの配信が一切ないので、GEOのネットレンタルでディスクを借りて観るのが一番手取り早いかと思います。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第29回受賞作『80日間世界一周』(1956年)
ジュール・ヴェルヌの同名小説を映像化した作品。上映時間が3時間弱(169分)とかなり長めです。舞台は19世紀英国ロンドン。80日間で世界一周は可能だと豪語する主人公フォッグが、全財産2万ポンドを賭けて、社交クラブの同輩との大博打に乗り出します。
80日間どころか、数百時間で世界一周が可能になった21世紀。しかし今や、却って国境を超えたグローバルな移動に制限のかかる時勢ですから、いつでも世界旅行の気分を味わえるこういった娯楽映画は面白いかもしれません。
クレジットが出るまで気づかなかったんですが、この映画にはバスター・キートン、フランク・シナトラ、マレーネ・ディートリッヒなど、当時の大物俳優もキャストとしてカメオ出演しているみたいです。そのエンドロールの演出もアニメーション仕立てとまた凝っています。
「希望の地平線か 破滅の深みへ到達するかは この狭い世界に生きる人々の知恵にかかっています」
♦︎オススメ度:☆
○第30回受賞作『戦場にかける橋』(1957年)
舞台は日本軍が占領中のタイ・ビルマ国境付近の捕虜収容所。バンコクとラングーンを結ぶ鉄道を建設中の第16収容所に移送されたニコルソン大佐(イギリス兵)は、ジュネーブ条約によって将校を労役につかせることはできないのだと、毅然とした態度で日本軍の齋藤大佐(早川雪洲)に向かっていきます。
アカデミー賞作品賞の中で、日本人がメインの登場人物として描かれる作品はほとんどないに等しいので、一見の価値がありますよ。後半は、イギリス軍の爆破作戦と鉄道の敷設工事が同時並行で進む構成になっています。
300万ドルをかけた実物大セットでの撮影(セイロン・ロケ)の効果か、CGには出せない凄みがあります。また、純粋な戦争映画(戦地が舞台の映画)での受賞は、第3回の『西部戦線異常なし』以来のことです。明るく軽快なマーチと戦争の無情さとのギャップが印象深いですが、実は、かの有名な「クワイ河マーチ」は本作の主題歌なんですね。
この年のノミネートは国際色が強く、アメリカ人/イギリス人以外では初めて、日本人のジャズ・シンガー「ミヨシ・梅木」(23歳)が『サヨナラ』で助演女優賞を獲得しています。
♦︎オススメ度 :☆☆☆
○第31回受賞作『恋の手ほどき』(1958年)
『巴里のアメリカ人』のヴィンセント・ミネリ監督によるミュージカル映画です。社交界での華々しい出会いのため、歴史に語学にテーブルマナーにと、英才教育を受けるお転婆娘のジジを、レスリー・キャロンが演じます。彼女は『巴里のアメリカ人』でもヒロインを演じていましたね。
いわゆる「ブロック受賞」というやつで、『風と共に去りぬ』『地上より永遠に』『波止場』の8部門受賞の記録を破ったんですが(9部門受賞)、この映画からしか得られないエクスタシーのようなものは特になく、『マイ・フェア・レディ』(1964年)のような作品と比べるとどうしても見劣りする出来栄えです。
ミュージカル映画が大好きという人以外にはちょっとオススメしづらいかもしれません。
「パリの人はいつも恋のことしか頭にない」
♦︎オススメ度:☆
○第32回受賞作『ベン・ハー』(1959年)
後に『タイタニック』(1997年)『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』(2003年)と続く、アカデミー賞歴代最多「11部門」受賞作。前年9部門受賞の『恋の手ほどき』を大きく上回りました。
友メッサラの裏切りによって奴隷船送りとなったユダヤ人青年のベン・ハー(ジュダ・ベン・ハー)による再起の物語かつ、彼の成長譚となっています。異次元の製作費(1500万ドル)をもって作られた超大作で、特撮・CGなしの大迫力の映像は圧巻です。
序曲、間奏曲、……と叙事詩のつくりになっており、冒頭30分は少し間延びした印象を受けますが、そこからは引き込まれて3時間あっという間です。日本映画史上初の天覧上映も行われました。『ジョジョの奇妙な冒険』第2部の、柱の男ワムウとの戦車戦はベン・ハーの大競馬がモデルではないかとよく噂されています。
♦︎オススメ度:☆☆
1960年代〜

1950年代の順応主義の反動を受けて、価値観の多様化、国内の分裂、公民権運動が60年代アメリカの主題になりました。非WASP(WASPはアングロ−サクソン系で新教徒である白人のこと)のケネディー候補の当選などは、まさにリベラリズムの幕開けを象徴するものです。このような対抗文化(カウンターカルチャー)の潮流は、アメリカン・ニュー・シネマのような形で、アメリカ映画の領域にも見られます。
アカデミー賞では、『アラビアのロレンス』(1962年)の作品賞・監督賞のダブル受賞を始めとして、『トム・ジョーンズの華麗な冒険』(1963年)『わが命つきるとも』(1966年)『オリバー!』(1968年)などイギリス映画の受賞が相次ぎ、オスカーへの「イギリスの侵略(ブリティッシュ・インベイション)」の時代でもありました。
○第33回受賞作『アパートの鍵貸します』(1960年)
『サンセット大通り』(1950年)や『情婦』(1957年)で知られるビリー・ワイルダー監督作品。映画史に残る不朽の名作です。
自分の住むアパート(の鍵)を、上司の情事のために貸し出すことで昇進・出世を目論む主人公のバド(ジャック・レモン)。しかし、部長の相手をする女性は、彼が想いを寄せるエレベーターガールのあの子だった・・・というあらすじです。アカデミー賞では珍しいラブコデメィです。こういう冴えない、少し残念な男性像というのは、今だったらジム・キャリーが演じるような役柄ですよね。
この年の大本命はジョン・ウェインの撮った西部劇『アラモ』だったんですが、大々的なキャンペーンと予想に反し、こちらは音響賞での受賞のみにとどまりました。愛国的な主題を扱った大作ではなく、不倫や自殺といったインモラルなテーマを面白おかしく扱った本作に軍配があがったというのは、受賞傾向がだんだんと変わってきていることのあらわれかもしれません。
「あなたに恋してればよかった」
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第34回受賞作『ウエスト・サイド物語』(1961年)
大ヒットしたブロードウェイ・ミュージカルの映像化作品。アカデミー賞10部門受賞の名作です。現代版「ロミオとジュリエット」と言ってもいいでしょう。2021年には、スピルバーグ監督が本作のリメイク版である『ウエスト・サイド・ストーリー』を撮って話題になりましたね(その際は作品賞にもノミネートされました)。
舞台はニューヨークのダウンタウン、ウエスト・サイド。移民の多いこの街では、イタリア系の不良グループジェット団と、プエルトリコ系の不良グループシャーク団が日夜争いを繰り広げている。そんな中、シャーク団リーダーの妹であるマリアは、ふとした出会いをきっかけに、対立するジェット団の元リーダートニーに想いを寄せるようになり・・・というお話。結構救いのない結末を迎えるので、もっと愉快なものを想像して観るとちょっと違うかもしれません。
貧困や移民といった人権問題が背景にあるというのが、この時代を象徴しているようです。
「家が怖いんすよ。環境が悪い。親の愛もない。最悪。外にいなきゃおれたち不良になっちまう」
オススメ度:☆☆
○第35回受賞作『アラビアのロレンス』(1962年)
『ベン・ハー』(1959年)の212分に次ぐ上映時間207分の超大作。当時はこれをCGなしのロケのみで撮ったというんですから、その労力と監督の力量に脱帽です(ロケ地はヨルダンのワディ・ラム砂漠と呼ばれる場所)。前述した通り、本作はほとんどすべてイギリスのキャストとスタッフでつくられました。
時は遡って、1916年。主人公であるイギリス将校ロレンスは、オスマン帝国(トルコ軍)の弱体化を図るため、アラブ人に独立のための武装蜂起を促します。要するに、ロレンスはイギリス側の工作員ですね。そんな彼が、政治的な駆け引きや争いに巻き込まれながらも、アラブ独立のために奔走、奮闘するという映画です。内容は、現代中東史への前提知識があると理解が早いかもしれません。
とても美しいシーン、カットの連続で、監督が画づくりや視覚効果にとにかくこだわりをもっているのが伝わってきます。これほど映画的な多幸感、臨場感にあふれる映像体験はそうそうないでしょう。でも流石に長いので、気軽にオススメはしづらい作品です。3時間以上となると、集中力を持続させるのも厳しいので、そういった面からも、やはりこういう大作は劇場の大きなスクリーンで観たいなあと思います。
1988年には、デヴィット・リーン本人監修のもと、完全版(227分)が製作されています。ちなみに、ティモシー・シャラメ主演で再び映画化された『DUNE 砂の惑星』(2020年)の原作は、『アラビアのロレンス』の参照元である『The Seven Pillars of Wisdom』を参考にして書かれたものだそうです。
オススメ度:☆☆
(長すぎるため)
○第36回受賞作『トム・ジョーンズの華麗な冒険』(1963年)
アカデミー賞作品賞を全作品観よう!と思いたったときに一番ネックになるのが『マーティ』とこの作品なんですが、こっちはDVDがほとんど出回っておらず、知名度もないので、アクセスするのがすごく難しいんですね。それが去年は、U-NEXTにサイレント追加されていたので有難いことにそれで観られたんですが、今年に入ってまた見放題から外れてしまったようです。ネットオークションでも一万円近い値段が付いているので、今は大きな公立図書館のAV資料室、大学図書館、渋谷のTSUTAYAなんかをあたってみるしかなさそうです。
じゃあお話の方はというと、舞台っぽい設定のピカレスクロマンで、正直全然面白くないです。逆にいえば、面白くなくて印象が薄いから知られていないんですが。いいところは、カメラアングルの手数の多さくらいですね。お色気ドタバタコメディのような内容が、当時としては新鮮でウケたのかもしれません。もの好きの方はぜひ探して観てみてください。
「明日は明日さ」「今日まで生きてきたのだから」
♦︎オススメ度:☆
○第37回受賞作『マイ・フェア・レディ』(1964年)
映画史を語る上でも欠かかさない名作。オードリー・ヘップバーンの魅力がここぞと詰まった映画です。バーナード・ショーの戯曲『ピグマリオン』を原作としています。
路上で花売りをするイライザが、言語学者のヒギンズ教授に見初められ、立派な「レディ」を目指すというストーリー。イギリスという国(特に当時)はその人の使う「言葉」、またその発音によって、上流、中流、下流と瞬時に判断される文化があるので、まずその訛りを矯正するために、徹底的に発声の練習を行んですね。大学でイギリス英語を勉強した人は聞いたことがあると思いますが、「RP(Received Pronunciation)」と呼ばれる発音体系があって、それを学んでいくのに映画内でもかなりの時間を費やします。
この年は、同じくミュージカル映画の『メリー・ポピンズ』と『マイ・フェア・レディ』の決戦となり、最終的には作品賞・監督賞ともに後者が受賞する結果となりました。ワーナー配給の作品が作品賞を受賞するのは『カサブランカ』以来21年ぶりのことです。最後ちょっと男性側に都合のいい話であんまり気に入らないんですけど、面白い映画だと思います。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第38回受賞作『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年)
『ウエスト・サイド物語』のロバート・ワイズ監督による王道ミュージカル。もしかしたら、学校の音楽の授業なんかで観たことがある人も多いかもしれません。
1938年のオーストリア。修道女になるための修練に励むマリアであったが、どこか少し抜けたところのある彼女は、外の世界の常識に触れるため、トラップ大佐の家の家庭教師を任されることに。マリアはそこで出会った7人の子どもたちと、そして大佐と、音楽を通して心を交わしてゆきます。
「サウンド・オブ・ミュージック」の名にふさわしい傑作ミュージカルで、歌唱によるストーリーテリングが心地いいです。「そうだ 京都、行こう」のCMでお馴染みのmy favorite thingsや、ドレミの歌(Do-Re-Mi)、エーデルワイスなど、ありきたりですが、元気と勇気を貰える映画です。1938年当時のドイツとオーストリアの複雑な関係が背景になっているため、意外にも後半は政治色が強いものになっています。
この年、日本人として初めて、勅使河原宏(『砂の女』)が監督賞にノミネートされています(受賞はロバート・ワイズ)。
「この自信だけが私の持ち物」
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第39回受賞作『わが命つきるとも』(1966年)
舞台は16世紀イギリス。その半生をヘンリー8世に尽くすも、キャサリン妃との離婚問題において彼と真っ向から対峙し、斬首刑にせられた大法官トマス・モアの最期(晩年期)を描きます。戯曲原作で、フレッド・ジンネマン監督の二度目の監督賞受賞作です。作品賞含む6部門受賞。
背景の説明無しに突然始まるので、この時代の英国史とトマス・モアについての前提知識がないと、理解が追いつかなくてちょっと厳しいところがあるかもしれません(自分がそうでした)。会話劇がメインで、神の話や信仰の話が延々と続くのですが、それもまた人によっては退屈に感じられる要素かもしれません(自分がそうでした)。ハリウッドの低迷期で不作だったというのもあると思いますが。
♦︎オススメ度:☆
○第40回受賞作『夜の大捜査線』(1967年)
ある田舎町で、老人の死体が発見されるところから物語は始まります。巡回中の警部は、駅舎で電車を待つ一人の黒人に殺人の嫌疑をかけ、署まで連行するものの、奇しくも彼はフィラデルフィア市警殺人課の敏腕の刑事であった。そこで、署長と彼は一時共同で捜査線を組むことに・・・というお話。街を照らす夜のネオンが美しい一作です。
地味ではあるものの、中々骨太な一本で、安易な友情物語でないのがいいですね。お酒を飲みながら1対1で語らい合うシーンでも、二人の間には常に緊張感が漂っています。音楽監督はジャズ・ミュージシャンとしても有名なクインシー・ジョーンズ、主題歌はレイ・チャールズと、音楽面が豪華な顔ぶれです。オープニングとエンディングで、「In the heat of the night」がまた違う響きを持って耳に沁みます。
4月8日を予定していた授賞式は、マーティン・ルーサー・キング牧師の暗殺(4月4日)を受けて2日間延期されました(セレモニーの参加者が葬儀に参列するため)。そういう意味では、『招かれざる客』『夜の大捜査線』のような人種差別を扱った作品がこの年にノミネーションを受けたのも考えさせられるところがあります。
♦︎オススメ度:☆☆
○第41回受賞作『オリバー!』(1968年)
チャールズ・ディケンズ原作のミュージカル映画。劣悪な労働環境で働くことを余儀なくされる孤児のオリバー・ツイスト。そんな生活に耐えかねて逃げ出そうとすると、今度は売りに出されてしまいます。その後、スリの窃盗団を率いる老人に拾われたことで、彼の人生は動き出すものの、そこでもオリバーは大人たちに翻弄され・・・という筋書きです。
「オリバー・ツイスト」という有名なナンバーですが、やっぱりミュージカルが好きじゃないとそんなに面白くはないかなあと思います。正直、あまり映画であることの必然性が感じられない作品です。
有名なところで、この年にはスタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』があり、監督賞にノミネート、特殊視覚効果賞を受賞しています。
「ウンパッパ ウンパッパ みんな知ってるこの歌 ウンパッパ ウンパッパ」
オススメ度 :☆
○第42回受賞作『真夜中のカーボーイ』(1969年)
60年代、70年代に撮られた“アメリカン・ニューシネマ“と呼ばれる映画群のうちの一作品。テキサスからジゴロ(男娼)としてやってきたカウボーイのジョーが、同居人のラッツォ(ダスティン・ホフマ)とともに、大都会ニューヨークでもがきながら生にしがみつく映画です。オスカーとはズレますが、他に『イージー★ライダー』『明日に向かって撃て!』『ワイルドバンチ』などもこの年の製作です。
こういう頽廃的な映画がつくれるようになったのは、1966年にプロダクション・コード(映画倫理自主規制)が大幅に改定され、年齢を基準にしたレーティング・システムが導入されたから、というのが一番大きいです。ちなみに、『真夜中のカーボーイ』は、「成人映画」に該当しながら作品賞を受賞した唯一の作品でもあります(受賞後に成人指定は解除されました)。
印象的なのは「Everybody's Talkin' (うわさの男)」ですね。原曲は66年に米国で発売されたフレッド・ニールの楽曲で、68年にニルソンがカヴァーしてシングルとして発売されたものが、本作の主題歌として起用され、再び大ヒットとなりました。刹那を生きる二人の若者の、可笑しくも儚い友情の物語です。
ジョーを演じたジョン・ヴォイド、ラッツォ役のダスティン・ホフマンともに主演男優賞にノミネートされましたが、賞はデビュー40周年の大ベテラン、ジョン・ウェインに授けられました。
♦︎オススメ度:☆☆
1970年代〜

1970年代には、ベトナム戦争に対する反戦運動が高まり、60年代から続く国内の分裂状態がさらに深刻なものになりました。それを受けて、社会的なテーマや政治的な問題に焦点を当てた作品も増えていきます。また、ハリウッド再起の時代(ニュー・ハリウッド)でもあり、『ゴッドファーザー』(1972年)『ジョーズ』(1975年)『スター・ウォーズ』(1977年)といった大作が次々と生まれ、興行的な成功を収めました。社会不安を反映した、アンチ・ヒーロー映画やクライム映画、ホラー映画が人気を博するようになったのもこの時代のことです。
○第43回受賞作『パットン大戦車軍団』(1970年)
フランシス・フォード・コッポラとエドマンド・H・ノートンの共同脚本で制作された、ジョージ・パットン将軍の伝記映画。パットン及びパットン軍の攻勢を、リアリティ溢れる映像と、主演のジョージ・C・スコットの名演で描いた172分の長編です。
とはいいつつ、ドンパチの戦争映画というわけではなく、あくまで、戦場に生きたジョージ・パットンという一人の男の人生にスポットを当てた人間ドラマになっています。巨大な星条旗の前に立って将軍がスピーチをする冒頭のシーンが大変印象的です。
しかしこれといった盛り上がりや見所はなく、172分という上映時間に耐えうる内容であるかと考えると、興味のない人にとってはかなり退屈な映画だと言えるでしょう。
この回、パットンを演じたジョージ・C・スコットは、主演男優賞の受賞を拒否し、プロデューサーのフランク・マッカーシーがオスカーを受け取るという賛否両論の事態となりました。
「数千年の昔、戦いから帰ったローマの兵士たちは、熱狂的なパレードを繰り広げて彼らの勝利を称えた。行進には様々な楽器を打ち鳴らし、征服した国の珍しい動物を連れ、荷車には勝ち取った財宝と武器が山積みされた。兵士たちは意気揚々と戦車に乗り、鎖に繋がれた捕虜を引き回した。兵士の子供らは白衣に身を包み、父と戦車に乗るか馬に乗って行進した。兵士のあとに続く奴隷たちは、黄金の冠をささげ主人の耳にそっと警告した。栄光はいつか消え去ると」
♦︎オススメ度:☆
○第44回受賞作『フレンチ・コネクション』(1971年)
同名のノンフィクション小説の映像化作品。ニューヨーク市警察本部薬物対策課のドイル刑事(通称"ポパイ")とその相棒のルソーは、密売取引のルートを探りながら、麻薬カルテルの壊滅を狙います。
演出も音楽も抑制が効いた渋い映画。と思いきや、終盤では息を呑むようなド派手なカーチェイスで映画的な跳躍をみせてくれます。映画の尾行シーンというのは、何故こうも心踊るものなんでしょうか。敵対するマフィアのボスが地下鉄で刑事を巻くシーンがあって、それもまた格好いいんですよね。
本作で(31歳の若さで)監督賞を受賞したウィリアム・フリードキン監督は、その勢いに乗って、W・P・ブラッティのベストセラーである『エクソシスト』(1973年)の製作に取りかかります。相次ぐ不自然なトラブルによって完成まで2年を要したものの、こちらは製作費1200万ドルが費やされたホラーの大作です。
またこの回では、「映画を今世紀の芸術たらしめたはかりしれない功績」があるとして、72歳の老公チャールズ・チャップリンに名誉賞が送られました。赤狩りで追われるようにアメリカを去って以来、チャップリンがニューヨークに降り立ったのは20年ぶりのことです。
♦︎オススメ度:☆☆
○第45回受賞作『ゴッドファーザー』(1972年)
フランシス・フォード・コッポラ監督作品(マリオ・プーゾの同名小説原作)。ご存知のとおり、文句なしの傑作で、およそ「完璧」と呼ぶに相応しい映画だと思います。
舞台は1940年代のアメリカ、ニューヨーク。シチリア系マフィアのドン、ヴィト・コルレオーネ(マーロン・ブランド)とその家族を中心に話は展開していきます。また、第一作目は、ヴィトから息子のマイケル(アル・パチーノ)へ、という「継承の物語」でもあります。
人間ドラマとしても、犯罪映画としても、非常に高いクオリティを持った作品で、主演のマーロン・ブランドやアル・パチーノ、ジェームズ・カーンを始めとする、大物俳優人の個性的で迫力ある演技が光ります。
カメラワークや照明、セットデザインなどの映像美はもちろんのこと、ニーノ・ロータの音楽も素晴らしいもので、物語が醸し出す哀愁に深みを与えてくれます。後続の作品にも大きな影響を与えた、まさにマフィア映画の金字塔です。しかし意外にも、オスカーの受賞は3部門(作品賞、主演男優賞、脚色賞)に留まっています。また、マーロン・ブランドが代理人として若いインディアンの女性をセレモニーに出席させ、一騒動を起こしたのはこの年のことです。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第46回受賞作『スティング』(1973年)
どんでん返しもの(コンゲーム)の原点にして頂点のような作品。『明日に向かって撃て!』(1969年)のロバート・レッドフォード/ポール・ニューマン主演で、アカデミー賞7部門を受賞しています。
1930年代のシカゴ。スリや詐欺で日銭を稼ぐジョニー・フッカー(ロバート・レッドフォード)は、些細な事件をきっかけに、大物ギャングの恨みを買ってしまいます。相棒であるルーサーを殺され、復讐を誓うフッカーが、伝説の賭博師ヘンリー・ゴンドーフ(ポール・ニューマン)の元を訪ね、彼の協力のもと、ギャングから金を騙し取るための一大詐欺計画を企てる、というお話です。
緊張感のあるストーリーとは対照的に、スコット・ジョブリンの「The Entertainer」 をはじめとする軽快な音楽(ラグタイム)が、物語のテンポを引き上げ、 ワクワクを掻き立ててくれます。とにかく、事前情報なしで観てほしい作品です。章立てで進む幕間には、西部開拓時代を思わせる可愛らしいイラストが挟まれています。
オススメ度:☆☆☆
○第47回受賞作『ゴッドファーザーPARTⅡ』
ゴッドファーザーシリーズシリーズ3部作の第2部にあたる作品です。前作(『ゴッドファーザー』)の続編として、主人公マイケル・コルレオーネ(アル・パチーノ)が、ファミリーのボスとしての地位を確立しながらも、仲間の裏切りや腐敗に直面する姿を描きます。
また、フラッシュバックの形で、偉大な父であるヴィト・コルレオーネの若き日(ロバート・デ・二ーロ)のストーリーも描かれており、2つの時代が交差するような構成で物語が進んでいきます。栄光を極める父と、破滅に向かうマイケル。強くなればなるほど孤立していく彼の姿が哀愁を誘います。最後の晩餐のシーンなど、なんて悲しくてなんて美しいんでしょう。
アカデミー賞では、続編が前作を凌ぐことはないというジンクスを覆し、見事6部門受賞を果たしました。少し間が空いて、1990年に制作された『ゴッドファーザーPARTⅢ』は、マイケル・コルレオーネの最晩年の物語で、彼の苦悩や後悔を深掘りして描いた作品になります。監督によれば、そちらは最終作というより「後日譚」といった位置付けになるそうです。内容についてここで詳しくは書きませんが、興味のある方は続きとして追ってみてください。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第48回受賞作『カッコーの巣の上で』(1975年)
刑務所の労役から逃れるため、狂人を装い、精神病棟に入院する主人公マクマーフィーをジャック・ニコルソンが演じます。
カッコーの巣(精神病棟)に托卵された卵がマクマーフィーであり、擬態した彼は、同じ巣の雛に自由と解放を与えようとします。作品の中では、患者を厳しく縛り付け統制を図ろうとする冷酷なラチェッド看護婦の姿が描かれるものの、鉄仮面の彼女から本当のところは読み取れず、一概に悪として括ることは難しいです。
悪役ランキングの常連でもあるラチェッド看護婦長ですが、2020年には彼女を主人公としたドラマシリーズ『ラチェッド』(本作の前日譚)がNetflixで配信され、話題になりました。
あまり明るい終わり方ではないので、積極的には勧めづらいですが、やっぱりいい映画だと思います。『或る夜の出来事』以来の主要5部門(作品賞、監督賞、主演男優賞、主演男優賞、脚本賞)受賞で、アメリカン・ニューシネマの代表作としても評価されています。この年の候補作には他にキューブックの『バリー・リンドン』がありました。
オススメ度:☆☆☆
○第49回受賞作『ロッキー』(1976年)
賭けボクシングと高利貸しの取立てで日銭を稼ぐ無名のボクサー、ロッキー・バルボア(シルヴェスター・スタローン)。才能はありながらも、なかなか日の目を見ないロッキーであったが、ある時、とあるファイトとの誘いが舞い込む。それは、現アメリカチャンピオン、アポロ・クリードとの世紀の大試合で・・・といったストーリー。朝日をバックにお馴染みのあのテーマが流れた時の感動はひとしおです。
本作は製作費削減のために、スタローンの弟、父、妻らがカメオ出演していたり、試合の観客に老人ホームのおじいさんおばあさんを入れて撮影していたり、と面白いエピソードがたくさんあります。実は、製作に携わったロイド・カウフマン御大も出演しています。ロイド・カウフマンは「悪魔の〇〇」シリーズで知られるトロマ・エンターテインメントの代表ですね。宣伝のためのウソのエピソードも結構あるので、ぜひ調べてみてください。
また、スタローン自身が監督を務めたのは、2/3/4とfinalで、無印(『ロッキー』)と5は、『ベスト・キッド』(2010年)でも知られるジョン・G・アヴィルドセン監督によるものです。
この年、アカデミーは創設50周年を迎えました。
「アメリカはチャンスの国だ。誰にでも勝てるチャンスがある」
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第50回受賞作『アニー・ホール』(1977年)
ウディ・アレンのセンスが遺憾なく発揮された、アイロニーたっぷりのラブコメディです。作品賞含む5部門受賞。
途中にアニメーションを挟んだり、こちらに語りかけてみたり、前衛的で実験的な手法が多く、その手練手管で観客を飽きさせません。面白いんですが、個人的には、ウディ・アレン監督作はアレン本人が出ていない作品の方が好きかもしれません。色々ありましたしね。
彼はセレモニー欠席の常連で、この年には司会のボブ・ホープに「今日はウディ・アレンが来ていない。たぶんマーロン・ブランドと二人でポーカーでもやってるんだろう」と皮肉られたそうです。実際はマンハッタンのパブでクラリネットを吹いていたとかなんとか。
主演女優賞を受賞したダイアン・キートンのファッションは、男もののシャツにジャケット、スカートの下にパンツの重ね着というだぼだぼファッションで、アニー・ホールそのものの出で立ちでした。「アニー・ホール・ルック」と言って当時流行ったスタイルです。
この年の最有力候補であったジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』は、7部門をかっさらうトップ受賞だったものの、作品賞には一歩届きませんでした。SFはコメディより受賞のハードルが高いんですね。
オススメ度:☆☆
○第51回受賞作『ディア・ハンター』(1978年)
マイケル・チミノ監督作品。ヴェトナム戦争に出征した3人の若者たちの過酷な体験と、彼らが背負った精神的な傷を描いた映画です。
故郷ペンジルバニアで友人と過ごす第一部、ヴェトナム出征の第二部、帰還後の第三部という形で、およそ三部構成になっています。戦争映画(反戦映画)とは言いつつも、主人公のマイケル(ロバート・デ・ニーロ)、ニック、スティーブン、この3人の友情が中心の軸としてあります。そういった点で、同じヴェトナム戦争を背景としながらも、『プラトーン』(1987年)とはまた少し毛色の違う作品です。
印象深いロシアン・ルーレットのシーンについては、一方的な解釈で戦争を歪曲しているという批判も多くありましたが、チミノ監督は「極端な描写は映画(ドラマ)を盛り上げるためのものであり、これはドキュメンタリーではない」と、あっけらかんとした姿勢を貫いています。また、この年の対抗馬には、同じくヴェトナム戦争の問題を扱ったハル・アシュビー監督の『帰郷』がありました。
♦︎オススメ度:☆☆
○第52回受賞作『クレイマー、クレイマー』(1979年)
ダスティン・ホフマン、メリル・ストリープ主演のファミリードラマで、離婚問題、夫子家庭、親権争いを扱った作品です。その背景には、70年代に入って(60年代の)2倍にふくれ上がった高い離婚率があります。
いい映画なんですが、かなり夫目線の映画というか、母親視点の描写が少ないので、(実態はそうではないのに)メリル・ストリープ演じる妻がちょっとイヤな女性に見えてしまって、それが勿体無いなあと感じます。
『gifted/ギフテッド』(2017年)や『マリッジ・ストーリー』(2019年)のようなヒューマンドラマの先駆けといっていいでしょう。
♦︎オススメ度 :☆☆
1980年代〜

1960年代、70年代にみられる価値観の多様化の揺り戻しで、80年代は再び保守的・伝統的な価値観が強調されるようになりました。レーガン政権が掲げる「強いアメリカ」は、20年代、50年代に対する懐古主義でもあります。
「レーガノミクス」によって経済的な自由主義が進んだ結果、映画産業では、メジャーによるチェーンの買収、配給と製作を兼ねる垂直統合型組織の勃興(復活)が相次ぎます。またこの頃には、ホームビデオと有料ビデオの普及によって、多ジャンルの映画(コンテンツ)の需要が高まっていきました。
○第53回受賞作『普通の人々』(1980年)
名優ロバート・レッドフォードの監督デビュー作。兄を偏愛する見栄っ張りの母、家族と向き合うことを恐れる弁護士の父、兄を失ったショックとその罪悪感から自殺未遂をする次男。長男の死をきっかけに、“普通”の家族の日常が崩れてゆく様子を丹念に描きます。
俳優が監督業に転身する場合は傾向として、その本人が出演も兼ねることが多い(そうすればネームバリューによってある程度の興行的成功が見込めるから)のですが、彼に至ってはカメオ出演もなく、初めから監督としての仕事に専心しています。
その後も『リバー・ランズ・スルー・イット』(1992年)『クイズ・ショウ』(1994年)といった骨太で硬派な作品を撮り続けるレッドフォードですが、やはり注目すべきは、処女作にしてオスカー受賞を果たした本作品でしょうか。予算の限られる中で撮られた本作は、「普通の家族」という一見地味なテーマでありながら、いや、地味なテーマであるからこそ、彼の真価が発揮され、今でも人々の心を掴んで離さない、普遍的な名作となり得ました。
普通の、どこにでもいるような家族に起きる、普通じゃない出来事。そんな彼ら家族が迎える結末は、どこか必然の帰結のようでもあり、観る者の胸を静かに締めつけます。前年の『クレイマー、クレイマー』に続いての受賞は、家族という社会の最小単位が抱える漠然とした不安を象徴するようです。
「誰の責任でもない。結果がこうなっただけだ」
♦︎オススメ度:☆
○第54回受賞作『炎のランナー』(1981年)
映画よりも、テーマ曲であるヴァンゲリスの「Chariots of Fire」の方が有名であろう本作。ケンブリッジ大学の学生であるハロルド(ユダヤ系)と、そのライバルであるキリスト教宣教師のエリック。ハロルドは人種差別という壁を越えて、またエリックは自身の信仰のあいだに揺れながら、彼らがオリンピックで優勝を果たすまでを、群像劇に近い形で荘厳な音楽と共に描きます。1924年のパリ・オリンピックで起きた実話を元に撮られた作品だそうです。
映画のヴィジュアル面が重要視される時代の中で、この年からオスカーにはメイクアップ(メイク・へアスタイリング)賞が導入されました。ちなみに第一回の受賞は『狼男アメリカン』です。
「負ける怖さは知ってた。だが今は勝つのが怖い」
♦︎オススメ度:☆
○第55回受賞作『ガンジー』(1982年)
誰もが知るインドの偉人、ガンジーの伝記映画。8部門受賞。『アラビアのロレンス』同様に、盛大な彼の葬儀から物語は始まり、時代は過去に遡ります。ベン・ギングズレー演じるガンジーがもはや本人にしか見えないレベルの再現度で、またインドの原風景がたいへん美しい映画です。
この『ガンジー』の8部門受賞について、ニューヨーク・タイムズ紙は「オスカーはノーベル平和賞と取り違えている」と揶揄したそう。オスカーを逃し続け、『E.T.』で作品賞、監督賞にノミネートされていたスピルバーグ監督も、その敗因について「面白い映画を作ってしまったためでしょう。ヒットしすぎたためでしょう」と皮肉っています。
でも何の縁か、『ジュラシックパーク』(1993年)で、ジョン・ハモンド(パークの創設者)を演じたのは『ガンジー』のリチャード・アッテンボロー監督でしたね。
「暴力は西洋の持つ不幸だ。それを輸入するのは進歩ではない」
♦︎オススメ度:☆☆
○第56回受賞作『愛と追憶の日々』(1983年)
ラリー・マクマートリーの同名小説を、ジェームズ・L・ブルックス脚本・監督のもとで映画化した作品。少し変わった母と娘の、30年間に渡る歪な愛と絆の物語です。邦題は前年のヒット作『愛と青春の旅だち』に影響を受けているんでしょう
タフで個性的な母親オーロラ(シャーリー・マクレーン)と勝気な娘エマ。21歳になった彼女は、母親の反対を押し切って、大学教師のフラップとの結婚を決める。しかし、2人の結婚生活は順風満帆とは程遠く・・・というストーリー。
母と娘の話、夫婦の話、家族の話で、すごく地味なんですが、人間のかっこ悪いところをそのまま描いたようなその実直さに心打たれる作品です。95作品の中で同じような系統を言うと、『普通の人々』なんかが好きな人は気に入ると思います。なんだかんだ最後まで観ると、『愛と追憶の日々』という邦題にも感じ入るところがありますね。
母親役のシャーリー・マクレーンは、24歳の時に『走り来る人々』(1958年)で初ノミネートを受かてからおよそ25年、本作(5度目のノミネート)にて悲願の主演女優賞を獲得。50歳にして初の主演女優賞を勝ち取り、会場を大きく沸かせました。
ちなみに、ジェームズ・L・ブルックス監督は、アニメシリーズ「ザ・シンプソンズ」の脚本家としても有名です。
「色々あったけど 愛は変わらなかった」
♦︎オススメ度:☆☆
○第57回受賞作『アマデウス』(1984年)
『カッコーの巣の上で』で作品賞と監督賞を受賞したミロス・フォアマン監督作品。戯曲の映画化で、若くしてこの世を去った天才ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトと、同時代を生きた作曲家アントニオ・サリエリとの確執を描いたドラマです。
物語は、老いたサリエリが「自分がモーツァルトを殺した」と告白するところから始まります。モーツァルトの謎多き生涯が、サリエリの口から語られるという構成です。いかにして彼の存在がサリエリのキャリアをおとしめたのか、そしていかにモーツァルトという人の才能が傑出したものであったのか、その愛憎入り交じる複雑な感情がこちらに伝わってきます。残酷なまでの圧倒的な「才能」を前にした時、凡人に残された道はどこにあるでしょうか。
しかし実際のサリエリはというと、こんなにしかめつらの悲観家ではなく、温厚で優しい人物であったそう。モーツァルトの才能を認め、妬ましいと感じていたのは事実のようですが、彼(モーツァルト)の晩年には、裏表のない、良好で健全な関係を築いていたそうです。
本作では、サリエリ役のF・マーリー・エイブラハムと、モーツァルトを演じたトム・ハルスが共に主演男優賞にノミネートされ話題になりました(受賞はエイブラハム)。
またこの年から、中国、ポーランド、デンマークが中継先として新たに加わり、セレモニーは世界77ヵ国でテレビ放送されるようになりました。
「私は凡庸なるものの頂点に立つ守り神だ」
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第58回受賞作『愛と哀しみの果て』(1985年)
デンマークを代表する女性作家カレン・ブリクセン(=アイザック・ディネン)の半生を、自伝的エッセイ『アフリカの日々』に基づき再構成した作品。主演はオスカー常連のメリル・ストリープとロバート・レッドフォードで、監督は俳優としても知られるシドニー・ポラックです。
映画はサバンナに響き渡るモーツァルトの「クラリネット協奏曲 第二楽章」から始まります。友人であるブロア・ブリクセン男爵と擬似結婚し、アフリカはケニアに渡った一人の女性の生きざまと、そこで出会った冒険家デニス(ロバート・レッドフォード)との交流を描きます。
正直言って、アフリカの美しい野山以外は注目すべき点がほとんどありません。でもそれも、アフリカ(撮影地ケニア)の雄大な自然を映しているだけで、アフリカという国を“撮っている“わけではないのが残念です。原作はそうではないのでしょうが、この作品から窺えるのはエキゾチシズムとしか呼べない何かで、いまみるとすごく不遜な感じがするというか、あくまでアメリカによる「アメリカの映画」だなあという感想になってしまいます。
この年に、黒澤明の『乱』 が監督賞、撮影賞、美術賞、衣装デザイン賞の全4部門でノミネートを受けたのは知っておきたいです(受賞が叶ったのは衣装デザイン賞のみ)。
♦︎オススメ度:☆
○第59回受賞作『プラトーン』(1986年)
オリバー・ストーンの実際の従軍経験が基となった製作された作品。『ディア・ハンター』とは少し異なり、こちらはおよそ全編に渡って戦場のショッキングな描写が続きます。
両親の反対を押し切って大学を中退したクリス・テイラー(チャーリー・シーン)。アメリカ陸軍に志願した彼は、カンボジア国境付近に駐屯する第25歩兵師団の小隊(「プラトーン」は小隊の意)に配属されます。軍内部の対立に巻き込まれる中で、自分自身に信念やモラルを問いかけながら彼は戦争の苛酷な現実に直面してゆきます。荒野に虚しく響く「弦楽のためのアダージョ」がとても印象的です。
本作は、ベトナム戦争というアメリカが抱える病理を、センチメンタリズムに陥らず、自己批判的な視点で描いた誠実な作品ですが、実は、ベトナム戦争映画というある種の禁忌に踏み込むことをためらってアメリカのメジャーが映画化しなかったものを、ヘムデイル社というイギリスの小プロダクションが支援して作られたものなんですね。同じく、ベトナム戦争を題材にした『ディア・ハンター』もイギリス系のEMI FILMから資金提供を受けていました。
演技派としても名高く、世間の人気もあるポール・ニューマンは、6度もノミニーに選手されていながら(『明日に向かって撃て!』、『スティング』に至ってはノミネートすらなし)、この年初めて『ハスラー2』で主演男優賞を受賞しました。しかし、ポール・ニューマン自身は「授賞式に出席すると受賞を逃す」と自虐的に述べて、式を欠席しています(前年に名誉賞を受けた時も撮影中で欠席でした)。また、“償い“のしるしとして、スピルバーグ監督にタールバーグ賞が送られたのもこの回のことです。
「今から思うと───僕たちは自分自身と戦ったんだ。敵は自分の中にいた。僕の戦争は終わった。だけど思い出は一生残るだろう」
♦︎オススメ度:☆☆
○第60回受賞作『ラストエンペラー』(1987年)
ベルナルド・ベルトルッチ監督作。最後の中国皇帝溥儀(愛新覚羅溥儀)、その幼少期から晩年に至るまでの数奇な人生を大スケールで描きます。映像美と壮大な音楽に気圧されるような、圧倒的な映画体験です。物語は、中ソ国境地帯ハルビンにある溥儀(1950年)が、過去を回顧する形で展開されていきます。
配給会社がアメリカ、イタリア監督、ロケは中国、音楽はアメリカ人と中国人と日本人と、国際色豊かな映画で、実際の紫禁城で撮影が行われたというのが驚きです。作品賞他、オスカー9部門を受賞しています。ノミネートされた全ての部門で受賞を果たしたのは、1958年の『恋の手ほどき』以来のことでした。
本作で日本人として初めて(デイヴィッド・バーン、ソン・スーとともに)アカデミー賞作曲賞を受賞した坂本龍一氏ですが、彼がベルトルッチ監督から音楽提供のオファーを受けたのは撮影終了から半年もあとのことだったそうです。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第61回受賞作『レインマン』(1988年)
トム・クルーズとダスティン・ホフマンが兄弟を演じるロードムービー。父の遺産が、存在も知らない自閉症の兄レイモンド(ダスティン・ホフマン)に信託されることを知ったチャーリー(トム・クルーズ)は、その遺産を手に入れようと、施設から彼を強引に連れ出します。そんな2人がメインマン(親友)になるまでの物語です。
レイモンドは、自閉症というよりサヴァン症候群っぽいですね。感覚器官が異常に過敏で、生活や日常会話がままならないものの、記憶力が抜群によくて、3×3、4×4の掛け算が瞬時にできるという、そういう感じの天才です。作品賞受賞作の中で、「ロードムービー」と呼べるものはこれと『グリーンブック』『ノマドランド』くらいかなあと思います。
この年、プレゼンターのアナウンスが「アンド・ザ・ウィナー・イズ・・・」から、「アンド・ジ・オスカー・ゴーズ・トゥ・・・」に変更されました。
「自分の世界で生きてる」「それの何が悪いの?」
♦︎オススメ度:☆☆
○第62回受賞作『ドライビング Miss デイジー』(1989年)
舞台は1948年アトランタ。身支度をする老女デイジーを、真正面から捉えたショットで映画は始まります。彼女が家の敷地内で事故を起こしたことをきっかけに、息子は新しく黒人の使用人(運転手ホーク)を雇うことに。はじめは、ホーク(モーガン・フリーマン)の運転する車への乗車を拒んでいたデイジーも、だんだんと彼の人柄に惹かれてゆき・・・というお話。
ユダヤ系の白人女性(未亡人)と黒人の使用人(ホーク:モーガン・フリーマン)が徐々に打ち解けていくというストーリーは後の受賞作『グリーンブック』を彷彿とさせますね。御歳80歳で主演女優賞を受賞したジェシカ・タンディの最高齢記録(同賞において)は、今でも破られていません。また、上映時間は99分とかなり短めですが、しっとりとした締め方で味のある良作です。
♦︎オススメ度:☆☆
1990年代〜

冷戦が終結し、米ソ対立の構図が崩れた90年代。経済全体としては好景気が続くものの、国内の貧富の格差は拡大し、政治不信や社会不安が増長します。「病んだアメリカ」という言葉も囁かれるようになり、保守派の掲げる「50年代のアメリカ」への回帰というシナリオが、もはや有効に機能しないことが誰の目にも明らかになりました。
映画産業における変化には、共産圏の崩壊によるハリウッドのグローバル化(肥大化)、独立プロの台頭と空前のインディーズ・ブームがなどが挙げられます。
1990年代のアカデミー賞受賞作は、まず『ダンス・ウィズ。ウルブズ』や『許されざる者』のようなこれまでのハリウッド映画に内省的な作品があり、血なまぐさいスリラーである『羊たちの沈黙』の主要5部門受賞の快挙があり、一方では大作の『タイタニック』があり、古風な仕立ての『恋に落ちたシェイクスピア』のような作品もありと、非常にバラエティに富んだ10年でした。
○第63回受賞作『ダンス・ウィル・ウルブズ』(1990年)
ケビン・コスナーが自ら製作、監督、主演を兼ねた野心作。西部劇での作品賞受賞は『シマロン』以来の快挙です。
南北戦争時代、19世紀のアメリカ西部。争いの最中、右足に重症を負ったダンバー中尉は、足を切断されるならと、決死の覚悟で自軍の囮となる。しかし、銃弾の中を駆け抜け、奇しくも生還した彼は、北軍の英雄として崇められることに。勤務地の自由を与えられたダンバーは、フロンティア(開拓前線)に身を置き、ネイティブ・アメリカンとの交流の中でその実態を知ろうとする・・・というストーリー。
スー族(ネイティブ・アメリカン)の社会に一時同化したダンバー中尉の視点から、白人至上主義を再検討するという真摯なつくりの映画で、その点において、ネイティブ・アメリカンを"蛮族"として描く従来の西部劇とは一線を画す作品です。変に誇張するところなく、彼らの生活がこまやかに再現されており、90年代以降の「修正主義西部劇」と呼ばれる映画の先がけと言ってもいいでしょう。
上映時間は181分と少し長めで、寡黙な主人公だけにモノローグが多めです。大スケールの原野をバッハァローが駆け抜ける映像には、なんとも変え難い映画的な高揚があります。ちなみに、ダンス・ウィズ・ウルブズ(狼と躍る男)というのは、スー族に名付けられた主人公ダンバーのネイティブ・アメリカン名のことです。
エンドクレジットの最後の最後に、「撮影中、動物には一切危害が加えられず、終始専門の調教師が訓練と指導を行った」と表示されるのが、この映画に臨むケビン・コスナーの誠実さを表しているようで印象的でした。
西部劇全盛期は悪役にネイティブ・アメリカンがいてのことだった。一九七〇年代にネイティブ・アメリカンやエスニック・マイノリティの研究が進み、ベトナム戦争の挫折が加わると、以前のようなストーリー展開は無理になり、西部劇は衰退したのである。
♦︎オススメ度:☆☆
○第64回受賞作『羊たちの沈黙』(1991年)
アカデミー賞主要5部門受賞のサイコスリラー。映画史に名を残す魅力的な悪役「ハンニバル・レクター」を、アンソニー・ホプキンスが演じます。製作会社のオライオンの経営が立ちいかなくなり、倒産が決まった中でのオスカー受賞でした。
FBI訓練生のクラリス・スターリング(ジョディ・フォスター)が、シリアルキラーで元精神科医のハンニバル・レクター博士の協力のもと、連続殺人鬼「バッファロー・ビル」の捜査を進めていくというお話で、緊張感のある展開が見事に描かれています。
「キャラクター映画」としての側面も強い本作ですが、その強烈な印象に反して、レクター博士の登場時間は計16分と短いのが驚きです。同じ年には、クラリスを演じたジョディ・フォスターの初監督作にあたる『リトルマン・テイト』も公開されています。
第64回の注目点の一つは、ディズニーの『美女と野獣』がアニメ映画として初めての作品賞ノミネートされたことでしょうか。また初の黒人、かつ最年少(24歳)の監督賞候補として、ジョン・シングルトン(『ボーイズ‘ン・ザ・フッド』)の名も話題になりました。
クラリス役と監督は変わってしまうのですが、2001年には続編として『ハンニバル』(監督:リドリー・スコット)、その翌年には『羊たちの沈黙』の前日譚にあたる『レッド・ドラゴン』(監督:ブレッド・ラトナー)が製作されています。
♦︎オススメ度:☆☆☆
(ホラーやスリラーが苦手な人には☆☆)
○第65回受賞作『許されざる者』(1992年)
クリント・イーストウッドが監督・主演を務め、彼の師であるセルジオ・レオーネ監督とドン・シーゲル監督に捧げた映画。 もうずっと前に脚本を買い取っていたイーストウッドが、原作の主人公と同じ歳(62歳)になるまで製作を待ったという話が有名です。
舞台は19世紀後半のアメリカ西部。妻に先立たれ、二人の子供と質素に暮らす男マニー(イーストウッド)のもとに、一人の若いガンマンが訪れる。話をもちかけてきたキッドと、同じく農夫として暮らす元相棒ネッド(モーガン・フリーマン)ともに、マニーは賞金首を追って南へと移る・・・。
西部劇に魅せられ、またその中で輝きを放ったイーストウッド自身の決別を示した作品(「最後の西部劇」)でもあります。老いたカウボーイは脆弱なアメリカを、彼の抱える苦悩や葛藤はこの時代の「アメリカ批判」を象徴しているようにも見えます。「許されざる者」とは、一体誰のことでなんでしょうか。
「連中は自業自得さ」「おれたちも同じだぞ」
♦︎オススメ度:☆☆
○第66回受賞作『シンドラーのリスト』(1993年)
スティーブン・スピルバーグ監督による伝記映画。ナチス・ドイツのホロコーストと、その大虐殺から多くの民衆を救った実業家オスカー・シンドラーの軌跡を描きます。パートカラーを除いてほぼ全編にわたるモノクロ映像と、手持ちカメラを使用したドキュメンタリー風の映像が特徴的です。
本作以降、監督は娯楽作と並行して、戦争と難民といったテーマを扱った映画を製作していくことになります。そういった点では、スピルバーグ監督のフィルグラフィの契機ともなるとても重要な作品です。
この年の授賞式は、『ジュラシック・パーク』で3部門(音響効果編集賞、視覚効果賞他)、『シンドラーのリスト』で作品賞、監督賞含む7部門受賞と、これまでオスカーで冷遇されてきたスピルバーグのためのセレモニーであったといっても過言ではないでしょう。ホロコーストの生還者であり共同製作者のブランコ・ラスティグは、「アウシュヴィッツからこの舞台まで長い道のりだった」と、感慨深く語っています。
しかし一方で、この映画に向けられた否定的な意見もあり、同じホロコーストを題材にドキュメンタリー映画『SHOAH ショア』(1985年)を監督したクロード・ランズマンは、「ホロコーストは表象不可能な出来事であり、それを俳優の演技によって再現するとは何事だ」「出来事を伝説化している」として、スピルバーグ監督を強く批判しました。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第67回受賞作『フォレスト・ガンプ / 一期一会』(1994年)
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズで知られるロバート・ゼメキス監督作品。激動の50年代〜80年代を駆け抜けたフォレスト・ガンプの生涯を描いたヒューマンドラマです。フォレストを演じたトム・ハンクスは、前年の『フィラデルフィア』に次いで、2年連続で主演男優賞を受賞しました。
物語は、ベンチに座る彼がバスを待つ人々にこれまでの自分の人生を語る、という形をとり、そのままの意味で、アメリカという国の自己言及的な映画でもあると言えます。大きな傷を抱え、落ち込んだ時代に、成功物語として再びアメリカン・ドリームを見せてくれたのが、大ヒットの要因でしょうか。歴史の一面的な切り取り方に色々と言いたいことはありますが、一つの映画としては大変面白く完成された作品だと思います。
映像にマッチングした音楽が特に素晴らしく、この作品のサウンドトラックは1800万枚を売り上げるという大ヒットを記録したそうです。
「人生はチョコレートの箱、開けてみるまで分からない」
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第68回受賞作『ブレイブハート』(1995年)
メル・ギブソン監督・主演の歴史スペクタクル超大作。自由を求めて戦った実在の英雄ウィリアム・ウォレスの物語を大スケールで描きます。
舞台は13世紀のスコットランド。イングランド兵に家族と恋人を殺され、復讐を決意したウォレスが、民衆を率いて、エドワード1世打倒のために立ち上がるというお話です。神話的な叙事詩で、肉体的にも精神的にもかなりマッチョな作品なので、そういうのが苦手な人はあんまり合わないかもしれません。あと結構長い(177分)です。
また主人公ウィリアム・ウォレスの逸話自体が確証のない半分フィクションのようなもので、更にそこに映画的な脚色が加わっているため、これを「史実」として受け取るのはちょっと無理があるかなあと思います。とはいえ、CGなしで撮られた合戦のシーンなんかは圧巻ですから、あくまでひとつのドラマとして大雑把に楽しむのがいいんではないでしょうか。13世紀の設定なのに、参加したエキストラがサングラスや腕時計を身につけていたため、再撮影が必要になったというエピソードが可笑しいです。
♦︎オススメ度:☆☆
○第69回受賞作『イングリッシュ・ペイシェント』(1996年)
ブッカー賞を受賞した『イギリス人の患者』の映像化作品。舞台は第二次世界大戦中の北アフリカ。砂漠に撃ち落とされた一人の男は、全身に火傷を負って記憶喪失に。自分の名前も忘れたその「イギリス人の患者」を熱心に看護するハナ(ジュエリット・ビノシュ)は、だんだんと彼に惹かれてゆき・・・というお話。
患者である彼の過去回想と、現在の描写がシームレスに映されるので、すぐには呑み込みにくい構成になっています。しかもその「悲劇」の真相というのが、浮かれた男女が不倫関係に陥り、嘘と情事で周りを巻き込んで破滅したという、大変身勝手でバカバカしいものなので、なかなか感情移入もできません。背景にある戦争のおかげでなんだか大袈裟な話に思えますが、彼らの不倫愛は戦争とはほとんど関係がなく、不貞によって勝手に自滅しただけであると言って違いないでしょう。登場人物たちがなんかずっとカッコつけてるのもイヤですね。不倫がイヤというよりは、それを変な感傷とナルシシズムで美化しているのが気持ち悪いです。本当にそんな感じの映画なので、気になる人はちょっと見てみてください。
本作を初めとして、この回は「海辺のサンダンス映画祭」と揶揄されたほど、独立系プロの作品が多い年でした(事実、作品賞候補5作品のうちでメジャーの製作によるものは、トム・クルーズ主演の『ザ・エージェント』の一本のみ)。
また、『カッコーの巣の上で』『アマデウス』を世に送り出した名プロデューサーのソウル・ゼインツは、その業績を讃えられ、3度目の作品賞と合わせてタールバーグ賞を受賞しています。
♦︎オススメ度:☆
○第70回受賞作『タイタニック』(1997年)
ハリウッド史上最大の製作費約2億ドルをかけてつくられた、アカデミー賞最多11部門受賞(14部門のノミネートも最多タイ)の超大作。ちょうどついこのあいだ(2023年2月)、本作の特別版である『タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター』が公開され話題になりましたね。
ラブロマンスを交え、豪華客船タイタニック号の沈没までを描いた作品。おそらく、観たことない人の方が少ないであろう不朽の名作というやつです。物語後半はパニック・スリラーとしても大変上質な出来となっています。実際の事故をこういった形で消費するのはどうかという思いも少しはあるんですが、かなりの部分が史実に忠実につくられており、そこにキャメロン監督のこだわりと製作にかける意志の強さを感じさせます(監督料も返上し、自宅を抵当に入れていたというエピソードも有名です)。
一つ残念なのは、これだけ存在感を放つレオナルド・ディカプリオが主演男優賞にノミネートすらされていないことでしょうか。その他の俳優賞も、実は全て他作品が受賞しています。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第71回受賞作『恋に落ちたシェイクスピア』(1998年)
強力な対抗馬であるスピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』を押さえ、見事作品賞受賞に輝いたロマンチックコメディ。
舞台は16世紀ロンドン。テムズ川を挟み、「カーテン座」と「ローズ座」という2つの劇場が、芝居好きの女王陛下のために演目を競い合っています(いわゆる“エリザベス朝演劇“の時代)。資金難にあるローズ座の劇場主は、シェイクスピアの新作喜劇、「ロミオと海賊の娘エセル(改題:ロミオとジュリエット)」にその命運をかけることに。そんな中、シェイクスピアは令嬢のヴァイオラと身分違いの恋に落ちるも、彼女には貴族の婚約者がいて・・・というお話。
シェイクスピア≒ロミオ、ヴァイオラ(ウィグネス・パドルロー)≒ジュリエットという対応関係で、この映画自体が『ロミオとジュリエット』『十二夜』の恋物語と重なる構図となっています。史実にフィクションを織り交ぜた脚色作ですが、シェイクスピアの作品世界のカジュアルな紹介としてみれば中々いい仕上がりです。アカデミー賞では、時代考証に基づいた衣装デザイン、舞台芸術にも注目が集まりました。
また、ハーヴェイ・ワインスタインの名で知られる本作の配給会社ミラマックスのキャンペーンが功を奏したのか、エリザべス女王を演じたジュディ・デンチは、出演時間約8分にも関わらず助演女優賞を獲得しています。
「君は僕の中で決して年をとらず死ぬこともない」
♦︎オススメ度:☆☆
○第72回受賞作『アメリカン・ビューティー』(1999年)
イギリスの舞台畑出身のサム・メンデス監督による怪作(快作)。とある平凡な家族の崩壊を、強烈な皮肉を交えてコミカルに描きます。あらゆる虚構をひっぺがし、アメリカン・ドリームの失墜を象徴するような奥の深い作品で、20世紀末、つまりは「アメリカの世紀」の終わりにこれが撮られたというのがとても感慨深いです。
アメリカはシカゴ郊外。これといった大きな不満はないものの、広告代理店に務めるレスター・バーナム(ケヴィン・スペイシー)は、自分の人生に行き詰まりを感じている。見栄っ張りの妻と、反抗期真っ只中の娘。つまらない仕事にも、家庭にも嫌気の差した彼は、「誰か」の理想を降りて、自分なりの「幸せ」を求めて歩み出すことを決心する・・・。
父権制とマッチョイズム、資本主義と成功崇拝、同性愛とホモフォビア。アメリカの栄光の裏にある影と、それがもたらす悲劇を映し出した秀逸な一本です。不快感を示す人が多いのも納得な内容ですが、作品賞受賞作全95作品の中では、最も高い完成度の脚本ではないでしょうか。
「あたし平凡な女になるのが一番イヤなの」
♦︎オススメ度:☆☆
2000年代〜

21世紀のアメリカの歴史は、世界を震撼させた9/11同時多発テロに始まります。「テロとの戦い」とイラク戦争の大義、それによる監視社会の到来と警察権力の不当な行使に、国民は不信感を募らせてゆきます。そこに経済的な不満も重なり、悪い予感はいよいよ金融危機という最悪の形で噴出することになりました。
ハリウッドでは、このような政治的・社会的な変化を背景に、イラク戦争をテーマにした映画や、国家安全保障の問題を扱った作品が数多く製作されました。
インターネットとデジタルカメラの普及によって、「ドキュメンタリー」というジャンルが再び脚光を浴びるようになったのも00年代の特徴の一つです。
○第73回受賞作『グラディエーター』(2000年)
オールド・ハリウッドを思い起こさせる史劇の大作。リドリー・スコット監督が、シンプルで分かりやすいストーリーラインと迫力ある映像で、帝政ローマ時代を描きます。
ローマ皇帝マルクス・アウレリウスはその後継者について頭を悩ませていた。実子コモドゥス(ホアキン・フェニックス)が王の器に値しないと判断したアウレリウス公は、心を許した将軍マキシマス(ラッセル・クロウ)に次期皇帝の地位を約束する。しかし、マキシマスはそれを知った皇子コモドゥスに反逆の罪を負わされ、ついには奴隷として売られてしまう。そこから、彼はコロッセウムのグラディエーター(剣闘士)として再び立ち上がる……という話。
『ブレイブハート』に続いて、また屈強で勇猛な男たちの映画です。脚本が大味なのはさることながら、こういう男性性が強調された大胆な映画はもうちょっと食傷気味かなあという感じです。くだらない権威とマチズモに振り回される女性の姿を描いた『最後の決闘裁判』(2021年)に至るまで、監督の中でなにか心境の変化があったんでしょうか。脚本家が違うのでなんとも言えませんが、そのあたりがすごく気になります。
ちなみに、本作で使われた小道具やセットは、全て使い回しなしの特注品であったそうです。お金がかかってますね。
♦︎オススメ度:☆
○第74回受賞作『ビューティフル・マインド』(2001年)
ロン・ハワード監督によるヒューマンドラマ。ノーベル経済学賞を受賞した天才数学者ジョン・ナッシュの半生を描いた伝記的な映画でもあります。少しでも経済学を勉強したことがある人は、「ナッシュ均衡(ゲーム理論)」などで名前を聞いたことがあるかと思います。
プリンストン大学院の数学科に入学したナッシュ(ラッセル・クロウ)。輝かしい功績によってMITの研究所に採用された彼は、仕事の傍ら、政府の要請でソ連の暗号解読を進める。教え子と結婚し、私生活も順風満帆に思えたナッシュだったが、ある時から”敵“にその身を狙われるように。しかしそこには驚くべき真相が隠されていて・・・というストーリー。
少しサスペンス風味なのが作品の面白さを際立たせています。『博士と彼女のセオリー』(2014年)『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』(同年)など、数学あるいは数学者を取り上げた映画は傑作が多いですが、多分にもれず、『ビューティフル・マインド』もオスカーの誉れにふさわしい名作です。
この年は、主演男優賞をデンゼル・ワシントン(『トレーニング・デイ』)、主演女優賞をハリー・ベリー(『チョコレート』)が受賞するという形で、黒人俳優によるダブル受賞であったのが印象的です。名誉賞も、黒人初の主演男優賞を獲得したシドニー・ポワチエに贈られています。
また、「長編アニメ部門(長編アニメ賞)」が新設され、ドリームワークス製作の『シュレック』がその第一号を飾りました。
♦︎オススメ度:☆☆
○第75回受賞作『シカゴ』(2002年)
後に、エミリー・ブラント主演の『メリーポピンズ リターンズ』(2018年)を監督したロブ・マーシャルによるリッチなミュージカル。彼が魅力的なミュージカル映画を撮れるのは、元振付師という異色の経歴があるからなんですね。
舞台は1920年代のシカゴ。スターダムを夢見るロキシー(レニー・ゼルウィガー)であったが、発砲事件で警察沙汰を起こし、刑務所に収容されてしまう。そこで歌手のヴェルマ(キャサリン・ゼダ=ジョーンズ)と出会った彼女は、ある敏腕弁護士に事件の担当を依頼することに。欲望と陰謀渦巻く世界で、彼女はスターになれるのか・・・。
ピカレスクロマンならぬピカレスクミュージカルです。登場人物もれなく全員頭のネジが飛んでいるんですが、舞台仕立て(元舞台原作)なのもあって不快感はあまりなく、次第に「シカゴ」の蠱惑的な世界観に惹かれていきます。ミュージカル映画が作品賞を受賞するのは、イギリス映画の『オリバー!』以来の快挙でした。対抗馬には、『戦場のピアニスト』があります。
この年に、宮崎駿監督は『千と千尋の神隠し』で長編アニメ賞を受賞しました。
♦︎オススメ度:☆☆
○第76回受賞作『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』(2003年)
「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズ三部作の完結編。『ベン・ハー』『タイタニック』に並ぶ最多11部門(11部門ノミネートのうち)を受賞したファンタジー映画の大作です。
中つ国で繰り広げられる大きな戦いの果て。フロドとサムは指輪を消滅させるため、ゴラムを案内に滅びの山を目指す。一方、メリー、ピピンと合流したアラゴルンは、サウロンの軍勢との最終決戦に向けて準備を整える・・・。
すごく面白いんですが、全三部作の三つ目なので前二作を観る必要があるのが興味のない人にはちょっとキツかもしれません。しかも一作一作が結構長いので。2001年に公開された一作目(『ロード・オブ・ザ・リング』も、その翌年の二作目(『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』)も、作品賞候補として一応ノミネートされていたんですが、これは同時製作のシリーズだったので、「待った」の意識が働いて、この完結作での大量受賞という結果になりました。
第76回では、山田洋次監督の『たそがれ清兵衛』が日本映画として22年ぶりに外国語映画正直の候補に、『ラスト サムライ』で渡辺謙が日本人初の助演男優賞候補に上がり、大いに話題になりました。ソファア・コッポラ(『ロスト・イン・トランスレーション』)がアメリカ女性初の監督賞候補にノミネートされ、父フランシス・フォード・コッポラをはじめとする彼女の家族がセレモニーに詰めかけたのもこの年のことです。
♦︎オススメ度:☆☆
(シリーズもののため)
○第77回受賞作『ミリオンダラー・ベイビー』(2004年)
クリント・イーストウッド監督が『許されざれる者』に続いて2度目の作品賞・監督賞を受賞。ボクシングという賞レースに強いスポコン的なテーマに、尊厳死という現代的なテーマを絡めた重厚な一作です。
ある日、ボクシングジムを経営する老トレーナー・フランキー(クリント・イーストウッド)のもとに、一人の女性が訪れる。初めは彼女(マギー)のトレーナーになることを拒んだ彼だったが、旧友エディ(モーガン・フリーマン)の助けもあり、やがて二人の間には親子を超えた強い絆が芽生えていく。しかし、次々と勝ち上がる彼女の栄光は試合中のある事故によって途切れることに・・・というお話。
モーガン・フリーマンによるモノローグが、誰に向けられたものであるか最後まで分からない、というのが秀逸です。ヒラリー・スワンクは本作で二度目の主演女優賞を、モーガン・フリーマンは自身初の助演男優賞を受賞しました。キネマ旬報の外国映画ベスト・テンでは、『ミスティック・リバー』(2003年)、父親たちの星条旗』(2006年)と並んで、3年連続でイーストウッドの作品が1位を獲得しており、どの作品の完成度をみても、この頃が彼のフィルモグラフィの全盛期といって差し支えないでしょう。
「何もせずに身を引き 全てを神にお任せするのだ」
「彼女は神でなく俺に助けを求めてる」
♦︎オススメ度:☆☆
○第78回受賞作『クラッシュ』(2005年)
前年の『ミリオンダラー・ベイビー』の脚本を担当したロバート・ハギス監督による社会派映画。冬のロサンゼルスで起きたある衝突事故と、そこに至るまでの36時間を、群像劇という形で描きます。
2001年の同時多発テロを皮切りに、アメリカ国内で溢れ出した社会不安や人種差別が一つの作品となって結実したような映画です。ロサンゼルスという大都市は、ニューヨークやロンドンと比べると広いですよね。だから、普段はそれぞれの人種コミニュティで棲み分けがされている。それが、ある時ふとしたことで「クラッシュ」を引き起こす。でも、心の奥深い部分で通じ合うためにはある種の「クラッシュ」が必要で、痛みを伴いながらも、不寛容と寛容のあいだを傷つきながら行ったり来たりしなくてはなりません。それが社会で暮らすということの意味だからです。
この年の本命にはクィアのカウボーイを描いた『ブロークバック・マウンテン』がありましたが、脚本賞他三部門での受賞に留まり、作品賞の受賞は叶いませんでした。アン・リー監督は、台湾出身のアジア系監督、つまりはアメリカにおける人種的マイノリティであることにも注目されたいです。
当然のことながら、ゲイ・カウボーイに暗示されるのは、ナルシスティックな自我イメージへの固執であり、言い様のない閉塞感だろう。ニューシネマが描いた逆接的「カウボーイ」は、アメリカへのジレンマを悲痛なカタチで表出する。そして、その後裔が『ブロークバック・マウンテン』なのだ。
「お前は俺だけじゃなく お前自身も貶めてるんだ」
♦︎オススメ度:☆☆
○第79回受賞作『ディパーテッド』(2006年)
豪華キャストによる「インファナル・アフェア」シリーズのリメイク作品。マーティン・スコセッシ監督悲願の宿願の監督賞受賞作でもあります。外国映画(香港映画)のリメイク作品としては史上初の受賞です。
アイルランド系マフィアのボスであるコステロは、警察組織に内偵としてコリン(マッド・デイモン)を送り込んでいる。一方でその警察側も、学校を卒業したばかりのビリー(レオナルド・ディカプリオ)をマフィアの組織に潜入させ・・・というストーリー。
ローリング・ストーンズの「gimme shetler」をバックに、フランク・コステロ扮するジャック・ニコルソンが街を闊歩する鮮烈なシーンから物語は始まります。全然つまらなくはないんですけど、三部作をギュッとしたリメイクなので、やっぱり元の方が面白いかもしれません。話はバッド・エンドと言えばバッド・エンドで、結構しんどい終わり方をします。
また、主演男優賞候補としてノミネートされていながら、ディカプリオはまたしても受賞を逃してしまいました。他にも、トム・クルーズ、ブラッド・ピッド、ジョニー・デップのような、いわゆる「ドル箱俳優」は、なぜかオスカーの受賞が難しいことが知られています。ディカプリオの初受賞も、第88回の『レヴェナント:蘇えりし者』(2015年)まで待つ必要があります。
♦︎オススメ度:☆☆
○第80回受賞作『ノーカントリー』(2007年)
『バートン・フィンク』(1991年)と『ファーゴ』(1996年)で監督賞を受賞し、カンヌ国際映画祭での評価も高いコーエン兄弟によるスリラー。めちゃくちゃ怖いんですけど、めちゃくちゃ面白いです。
麻薬取引による大金200万ドルを持ち逃げしたヴェトナム帰還兵のモス、彼を追う殺人鬼アントン・シガー、またその事件を捜査する保安官(トミー・リー・ジョーンズ)の三つ巴の追走劇を、圧倒的な暴力とユーモアで描きます。
ガッツリ賞を狙いにいった作品ではなく、ただ撮りたい映画を好きなように撮って、純粋にその面白さで作品賞受賞というのがカッコイイですね。ちなみに、この映画の中で殺人鬼アントン・シガーが使ってるのは正式名称を「キャトルガン」といって、ふつうは牛の屠殺に使われる道具(高圧ボンベ付きエアガン)です。彼を演じたスペイン出身のハビエル・バルデムは、その異様に不気味な風体と怪演で、見事助演男優賞を獲得しました。
♦︎オススメ度:☆☆
(怖いのが苦手な人には☆)
○第81回受賞作『スラムドッグ$ミリオネア』(2008年)
ダニー・ボイル監督によるイギリス製インド映画。小説『ぼくと1ルピーの神様』の映像化作品です。「コウン・バネーガー・カロールパティ」(日本で言うところの「クイズ$ミリオネア」)に出場した一人の青年(ジャマール)が、高額な賞金を獲得するまでのドラマです。
貧民街で育ったジャマールの過去の経験が、まさかまさかミリオネアの問題と合致して、どんどんクイズを勝ち進めていくというストーリー。クイズ番組の問題に答えながら、彼の人生に起きた事件を回想するという構成で、映画話法としては面白いけど、筋書きとしては少しよく出来すぎているかなあという感じがします。でもこういうわかりやすい作品もたまにはいいですよね。音楽も相まって、ノッてきたら面白いので、結構万人が楽しめる映画かもしれません。
この回では、『ダークナイト』でジョーカーを演じるも、28歳の若さで夭逝したヒース・レジャーに助演男優賞が贈られました。故人の受賞は、俳優では『ネットワーク』(1977年)のピーター・フィンチ以来二人目のことです。また、外国語映画賞には滝田洋二郎監督の『おくりびと』が選ばれました。
♦︎オススメ度:☆☆
○第82回受賞作『ハート・ロッカー』(2009年)
『ゼロ・ダーク・サーティ』(2012年)『デトロイト』で(2017年)で知られるキャスリン・ビグロー監督作品。彼女は本作で、女性として初の監督賞を受賞しています。主演を務めるのは「ホークアイ」のジェレミー・レナーです。
舞台はイラク戦争中のバグダッド。死も恐れずに最前線で爆弾の処理任務を引き受けるジェームズは、ある時から、極限の緊張感に一種の中毒症状を覚えはじめる・・・。
1500万ドルという低予算で作られた映画で、カメラには16ミリフィルムが使われています。手に汗握る演出と撮影で、終始ストレス(負荷)のかかる映像体験です。戦争の大局的な話というよりは、兵士の個人的な話として描かれているのが印象深く、もはや日常には戻る場所もないという帰結にペーソスを感じます。
第82回からは、作品賞の候補作が一気に10本まで増え、ヒット作や娯楽作、コメディやSF作品などもノミネートを受けるようになりました。この年の対抗馬にはジェームズ・キャメロン監督の『アバター』があります。
小話ですが、本作の製作者の一人であるニコラ・シャルティエは、協会員に投票を促すような電子メールを送ったことで、式への出席が禁止されてしまいました。アカデミー賞にも一応選挙法みたいな決まりがあるんですね。
「イラクに来たってことは、死ぬってことだ」
♦︎オススメ度:☆
2010年代〜

2009年、バラク・オバマ氏の大統領の就任は、「人種」にまつわる暗い過去を持つアメリカにとって、時代の変化を物語る象徴的な出来事でした。しかし、続くテロとの戦い、不法移民問題、広がる経済格差、人種間の軋轢と、オバマ大統領が背負うことなった“負の遺産“は、簡単に解決できるものではありませんでした。2016年には、民主党政権のバックラッシュ、ネットやSNSの普及によるポピュリズムの台頭を受けて、「Make America Great Again」を掲げる共和党候補のドナルド・トランプ氏が大統領に当選しましたが、その後も、国内の政治的な分断は進むばかりです。
アカデミー賞では、第82回(2009年)以降、作品賞の候補作がこれまでの5本から10本以内に増え、ノミネート作品、受賞作品ともに、バラエティに富んだラインナップが確認されるようになりました。また、2013年から17年まで映画芸術科学アカデミー(AMPAS)の会長を務めた黒人女性シェリル・ブーン・アイザックスによって、女性や非白人の会員数が飛躍的に増加したことも、受賞傾向に多大な影響を与えています。
人口動態の変化や、マイノリティの権利意識の先鋭化を受け、ハリウッドやオスカーを取り巻く環境は、今この時も大きく変わりつつあります。
○第83回受賞作『英国王のスピーチ』(2010年)
トム・フーパー監督による伝記映画。英国王ジョージ6世とその妻との絆、言語聴覚士ライオネルとの不思議な友情を描いた実話です。こうやってみると、アカデミー賞はやっぱり伝記が強いですね。でもそうした題材の強さだけでなく、彼の発する人間臭さ、誰しもが持つ弱みのようなものが、今作では観客を惹きつけるヒットの要因となったのではないでしょうか。
吃音に悩むジョージ6世は、妻のはらからいで、オーストリアの言語聴覚士(療法士)ライオネル・ローグのもとを訪れる。ライオネルは医師が誰も直せなかった彼の吃りを、心理的なアプローチから解きほぐしていく。大戦を目前に動揺する国民に、国王として立派なスピーチを届けることができるのか・・・。
スピーチは、単に技巧的であればいいというものではありません。最後のラジオ放送で、彼の言葉に魂が宿るその瞬間の美しさ。あまり字幕/吹替にこだわりはないですが、この作品に関しては字幕での視聴をお勧めします。セラピーの中で、Fワードを連発するコリン・ファースの姿が愛おしいです。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第84回受賞作『アーティスト』(2011年)
ハリウッドの黄金期を舞台に、あるスターの凋落から再生までを、モノクロ&サイレントで描いた挑戦的かつ実験的な作品。スクリーン比も当時の1.33:1という比率が採用されており、監督の映画愛とリスペクトが窺えます。白黒映画としては1993年の『シンドラーのリスト』以来、無声映画としてはなんと第1回の『つばさ』以来の(作品賞)受賞です。
映画の本流がサイレントからトーキー(有声)へと移り変わる時代。それでもサイレント映画の形式にこだわり続けるジョージと、時代の波に乗ってスターとしての地位を確立していくペピー。対照的な2人の出会いがもたらす運命の結末は・・・と言うお話。
この年の作品賞候補には他に、マーティン・スコセッシ監督が手がける3D映画『ヒューゴの不思議な発明』があったんですが、その作品内で、SF映画の創始者ジョルジュ・メリエスの撮った『月世界旅行』(1902年)やシネマトグラフの発明で知られるリュミエール兄弟のフィルムが使用されたことが話題になりました。「映画とは何か」と言う原点に立ち返った二つの作品が受賞を争ったというのが印象的ですね。
(ちなみに、日本の富士フィルムが映画用フィルムの生産中止を発表したのは翌年2012年のことでした。)
♦︎オススメ度:☆☆
○第85回受賞作『アルゴ』(2012年)
ベン・アフレックが製作、監督、主演を務めるサスペンスドラマ。「イランアメリカ大使館人質事件」を題材に、緊迫の救出作戦をます。本命であるスピルバーグ監督の『リンカーン』を下し、ダークホースとしての受賞でした。
1979年2月、革命によってイランのアメリカ大使館がイスラム過激派によって占拠される。からくも脱出に成功した六人を救い出すため、CIAのトニー・メンデス(ベン・アフレック)はとある作戦を立てる。しかしそれは、架空の映画『アルゴ』の製作によって救出を図るという奇想天外なものだった・・・。
半分実話の“娯楽サスペンス“、つまり一本の映画としてはよくできているんですが、アメリカによるプロパガンダの色を強く感じる作品です。欧米がイランの主権を侵害したことに対する省察はなく、イラン側から反撥の声が上がったのも納得です。中東が抱える諸問題の根っこを辿れば、そこにあるのは列強による植民地支配、帝国主義というエゴですから。また、この年には作品賞のプレゼンターとして大統領夫人が中継で出演しており、そういう意味でも、オスカーと政治の結びつきが強調された年でした。
♦︎オススメ度:☆
○第86回受賞作『それでも夜は明ける』(2013年)
奴隷廃止運動の活動家として知られるソロモン・ノーサップの伝記(奴隷体験記)『12(トウェルブ)イヤーズ・ア・スレイブ』に基づいて製作された作品。ソロモンを演じたキウェテル・イジョフォーをはじめ、ベネディクト・カンバーバッチ、ブラッド・ピット、ポール・ダノなど、錚々たる名優が脇を固める良質な一本です。
妻子を持ち、ニューヨーク州サラトガに住む"自由黒人"であったソロモンが、当時奴隷合法のワシントンで誘拐され、「奴隷」として過ごした12年間を痛切に描きます。リンカーンによる奴隷解放宣言(1862年)のほぼ20年前の出来事です。
アメリカの恥部である“奴隷制度“にスポットを当てた映画。彼らが受けた非人道的な扱いとその惨たらしさ、また権力の側にいる時の人の残酷さというものをまざまざと見せつけられ、観客である我々も息の詰まるような苦しさに晒されます。映像ですらこうなんですから、ソロモンの味わった心理的苦痛と辛酸は、想像を遥かに絶するものであったでしょう。アメリカにおける黒人差別の歴史や制度の推移に興味がある人は、併せてNetflixドキュメンタリー『13th 憲法修正第13条』(2016年)の視聴をお勧めします。
「これは病気さ この国に巣食う恐ろしい病気だよ」
♦︎オススメ度:☆☆
○第87回受賞作『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(2014年)
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督作。現実と妄想を行き来するよな一風変わったテイストで、カムバックに賭けるかつての人気俳優リーガン(マイケル・キートン)の日々を描きます。役者としてだけでなく、父親としての再生の映画でもあります。
スパーヒーロー映画『バードマン』で一世を風靡したリーガン・トムソン。落ち目にある自信のキャリアの復活を図るため、一つの挑戦として、彼はブロードウェイ進出という決断をする。家族関係の不和、共演者やスタッフとの衝突に頭を悩ませながら、リーガンが新たな人生の一歩を踏み出す、というストーリー。
全編ワンカットに見える特殊な編集で目が結構疲れるので、酔いやすい人は注意です。どこをどう切って繋いんでるんだろうというのを考えながら観ても面白いかもしれません。ドラムオンリーの劇伴もなかなか乙です。1989年に、実際にバットマン(『バットマン』)を演じたマイケル・キートンが、「バードマン」を演じるアイロニーもいいですね。
撮影監督のエマニュエル・ルツベキは、前年の『ゼロ・グラビティ』と本作で撮影賞を受賞、またその翌年の『レヴェナント:蘇りし者』(2015年)でも受賞を重ね、(同賞において)史上初の3年連続受賞を果たしました。
♦︎オススメ度☆☆
(三半規管が弱い人には☆)
○第88回受賞作『スポットライト 世紀のスクープ』(2015年)
2001年に実際に起きた事件、報道を基につくられたドラマ映画。カトリック司祭による性的虐待事件の報道に至るまでの顛末を映します。センセーショナルな話題だけに誇張や脚色はほとんどなく、記者の行動様式、服装、セリフなどが忠実に再現されているそう。
ボストン・グローブ紙の「スポットライト」と名付けられた4人組の記者チームが、協会の神父による児童への性的虐待という組織ぐるみの巨悪に迫る。それは世間を揺るがす、まさに世紀のスクープであった・・・。
神父の聖職者免責といった法の壁、社会的な信用にメスを入れた作品。定期購読者の53%がカトリックという中で、臆せずに教会の権力に立ち向かう記者たちの勇ましい姿がドキュメンタリータッチで活写されています。それにしても胸糞悪い話ですね。
NYタイムズによる、ハリウッドの絶対的権力者ハーヴェイ・ワインスタインの告発は、翌年2017年10月のことでした。それを皮切りとして、映画業界全体に飛び火した「#MeToo」運動。そこに本作が与えた影響というのも少なからずあるんじゃないでしょうか。
「この記録が記事に使われた場合、編集責任は誰がとる?」
「じゃあ、これを記事にしなかった場合の責任は誰が?」
♦︎オススメ度:☆☆
○第89回受賞作『ムーンライト』(2016年)
アカデミー賞13部門ノミネートの『ラ・ラランド』やドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『メッセージ』、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』といった強力な候補作をよそに、番狂せの受賞に輝いた自伝的映画。少年期/青年期/壮年期と、大きく3つに別れた主人公シャロンの成長譚です。
性自認への葛藤。いじめ、差別。麻薬中毒の母親。ポートレートのように一人称の目線で、あくまで彼の主観から物語は流れていきます。アメリカの様々な社会問題を扱ってはいるものの、それよりもずっと内的世界にフォーカスした、パーソナルで静的な、個人的にはすごく好きな映画です。
大統領に就任したトランプ大統領の差別発言が問題になる中で、その対極にあるような人間理解の難しさと奥深さを描いた作品が受賞に輝いたというのは、なんだか少し思うところがあります。
その一方、2015年2016年と2年連続、俳優部門にノミネートされた俳優が白人のみだったことを受け、アカデミー賞を主催するAMPASが「白すぎるオスカー(OscarSoWhite)」と非難される事態も起こりました。
♦︎オススメ度:☆
○第90回受賞作『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017年)
スペイン出身のギルレモ・デル・トロ監督によるロマンチックなラブストーリー。監督は押井守の大ファンで、日本のアニメ・マンガ・特撮マニアとしても知られていますよね。ここまでずっと受賞作を観てきて、昔だったら考えられないような作品の受賞なので感慨深いです。
舞台は1960年の米ソ冷戦下。航空宇宙研究センターで清掃員として働く聾唖の女性イライザ(サリー・ホーキンス)は、そこに捕えられた謎の水棲生物(半魚人)に恋をしてしまう・・・という突飛なお話。
笑ってしまうくらい監督の趣味丸出しというか、いい意味で作家の変態性・オタク性が発揮されたこだわりの強いSFですが、マイノリティに焦点を当て、息苦しさを感じる人々に手を差し伸べてくれるような温かい映画でもあります。ユーモアのセンスも結構良くて飽きません。ほんの少しですが、ミュージカル的な要素も入っています。アカデミー賞の投票開始直後に、盗作問題で一騒動あったのも記憶に新しいです。
投票といえば、2016年以降、会員の投票資格はそれまでの終身制から期限つきの10年までに変更されています。認められたら更新も可能なようで、3回更新すると終身投票権が与えられるそうです。
♦︎オススメ度:☆☆
(流血描写、グロテスクな描写アリ)
○第91回受賞作『グリーンブック』(2018年)
コメディ映画が得意なピーター・ファレリー監督によるロードムービー。天才ピアニストのドクター・シャーリーと、その運転手トニーとの友情を描いた実話です。
舞台は1962年アメリカ。黒人天才ピアニストのシャーリー(マハーシャラ・アリ)は、イタリア系アメリカ人のトニー・リップ(ヴィゴ・モーテンセン)とともに、南部都市を演奏旅行で回ることに。差別と偏見にまみれた旅の中で、徐々に二人の間には強い絆と信頼関係が結ばれてゆく・・・。
ユーモラスで心温まる作品で、誇り高きシャーリーの姿と彼のピアノ演奏に心打たれます。酒場で弾かれた「木枯らしのエチュード」(ショパン)は特に素晴らしいです。表題の「グリーン・ブック」というのは、黒人が利用可能な施設の情報が細かく記載されたガイドブックのことで、ジム・クロウ法下の人種差別の厳しいアメリカ、特に南部で重宝されたもののようです。
この年の作品賞には、Netflix配給のモノクロ映画『ROMA/ローマ』が有力視されていましたが、 TVでしか観られない、あるいは一部の映画館でしか上映されない作品はアカデミー賞にはふさわしくないという辛辣な意見もあがり、最終的には監督賞、国際長編映画賞に落ち着きました。これは未だに賛否が分かれる問題ですね。
また、MARVELシリーズの『ブラックパンサー』が作品賞候補にノミネートされたことも印象的で、作品賞は逃しましたが、衣装デザイン賞他2部門を受賞し、マーベル・スタジオ製作の映画としては初めてのオスカーを獲得しました。
日本からは、是枝裕和監督の『万引き家族』が国際長編映画賞に、細田守監督の『未来のミライ』が長編アニメ賞にノミネートされています。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第92回受賞作『パラサイト 半地下の家族』(2019年)
ポン・ジュノ監督によるコメディスリラー映画。一貫して、階層社会の格差や貧困というテーマを扱ってきた監督の渾身の一作です。非英語の外国語映画としての作品賞受賞は歴史上初の快挙で、国際長編映画賞と作品賞の受賞を兼ねるのも、同賞の創設以以来初めてのことでした。
全員が失業中の貧しいキム一家は、裕福なパク一家に潜り込み、寄生(パラサイト)する計画を思いつく。父ギテク(ソン・ガンホ)は社長お抱えの運転手として、長男のギウは家庭教師、妹のギジョンは美術教師として、また母チュンスクは新しい家政婦として、パク家への就職を成功させる。しかし、ある衝撃的な真実が明らかになり、物語は思わぬ方向へと暗転してゆく・・・。
わかりやすいストーリーにあっと驚く意外性、ミステリーやサスペンスとしての味つけ、話にユーモアや緩急もあり、まず一本の映画としてとても面白いです。ポン・ジュノ監督の作品ってそういうバランス感覚がすごくいいんですよね。
韓国では97年にバブル崩壊が、その後IMFの介入による経済構造改革がありました。「頑張ればその分だけ報われる」という努力神話(コリアン・ドリーム)が砕け散り、格差の是正も遠い夢となったあとの韓国で、「半地下」から這いあがろうとするキム一家を誰が笑えるでしょうか。
カンヌ国際映画祭の最高賞との同時受賞も果たした本作ですが、2016年にパルム・ドールを受賞したケン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・ブレイク』も、2018年受賞の『万引き家族』(是枝裕和監督)も、行き過ぎた資本主義や格差社会への問題意識を同じくしています。そして注目すべきは、そのどれもが「家族」を描いた作品だということです。
♦︎オススメ度:☆☆☆
2020年〜
※2020年代はまだ何も総括できる段階にないので、時代解説は割愛します。
○第93回受賞作『ノマドランド』(2020年)
ジャーナリストのシカ・ブルーダーが記したノンフィクション本『ノマド:漂流する高齢労働者たち』を、中国出身のクロエ・シャオ監督が映像化した作品。実際に、この本の中で登場するノマドたちが、映画の中でも本人として登場しています。
本作で彼女は、非白人女性として初の監督賞を獲得し、主演のフランシス・マクドーマンドは、『ファーゴ』『スリー・ビルボード』に続いて3度目の主演女優賞に輝きました。
リーマンショック後の住宅バブルの崩壊によって街を追われ、家を失ったファーン(フランシス・マクドーマント)。トレーラーハウス(バン)を生活の拠点に、季節労働を渡り歩く彼女と、“ノマド“生活者たちとの交流を、アメリカの広大な風景をバックに捉えます。
ノマドの暮らしは開拓時代からのアメリカの伝統、と言った劇中のセリフが頭印象的。経済恐慌によってもたらされた悲劇を描く点では『パラサイト』と同じ問題系ですが、(映画内では)格差や貧困を強調して描くことはなく、どちらかといえば、人の孤独や寂しさをよく映した作品です。マジックアワーでの撮影を始めとして、ある視点からは「美化している」と指摘されるような、この詩的な作風が評価の分かれるところかもしれません。
「本当のさよならを言うことはない。いつも『またそのうちどこかで』って言うだけ。で、本当にその通りになるんだ」
♦︎オススメ度:☆
○第94回受賞作『コーダ あいのうた』(2021年)
エリック・ラルティゴ監督のフランス映画『エール!』(2014年)のリメイク作。いわゆる「カミング・オブ・エイジ・ムービー」と言われる、ティーンが大人になるまでを描いた物語で、振り返ってみると、作品賞には今までそういった作品の受賞がなかったのが意外です。
ろう者である両親と兄をもつルビー(エミリア・ジョーンズ)。家族の中で一人だけ耳の聞こえる彼女は、心密かに音楽への熱い情熱を持っている。家業である漁場を手伝いながらも、自分の夢を諦められずにいるルビーは・・・というお話。
「Coda」というのは「Children of Deaf Adults(聴覚障害のある親に育てられた子ども)」の意味で、ここでは主人公ルビーのことを指しています。
映画館でこの作品を観たとき、彼女の歌声に感涙してしまって、別に泣けるからといって良い映画ということはないんですが、周りを見回してもみんな号泣していて、正直それが全てなのかなともと思いました。すごくバイタリティに満ちた作品で、真っ直ぐな姿勢に素直に勇気を貰えます。無音の演出によるインパクトも大きいものでした。
今回は、作品賞候補に『ベルファスト』『パワー・オブ・ザ・ドッグ』『ドント・ルック・アップ』『ドライブ・マイ・カー』『ウエスト・サイド・ストーリー』『DUNE/デューン 砂の惑星』他 と、良作揃いの年でしたね(濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は国際長編映画賞を受賞)。
またこの年、受賞式の視聴率の低下を受け、放送時間短縮のために、一部の賞の発表(ドキュメンタリー短編映画、編集、メイクアップ&ヘアスタイリング、作曲、美術、音響など8部門)が事前収録によるものとなりました。
ちなみに、監督賞にノミネートされず作品賞だけを受賞したのは、第1回の『つばさ』、第5回の『グランド・ホテル』、第62回『ドライビング Miss デイジー』、第85回『アルゴ』、第91回『グリーンブック』と本作のみです。
♦︎オススメ度:☆☆☆
○第95回受賞作『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022年)
『スイス・アーミー・マン』(2016年)の奇才ダニエル・クワン監督によるSFコメディ。前哨戦とされるPGA(製作者組合賞)、DGA(監督協会賞)、SGA(俳優組合賞)、WGA(脚本家組合賞)の4賞全てを総なめにしたそのままの勢いで見事アカデミー賞作品賞も受賞しました。
家庭や仕事のトラブルに毎日頭を抱える中国系アメリカ人のエヴリン(ミシェル・ヨー)。突如マルチバースの存在を知らされた彼女は、宇宙の命運をかけた戦いに巻き込まれてしまう。しかし、脅威の敵ジョブ・トゥパキは娘のジョイにそっくりで・・・というストーリー。
いま流行りのマルチバースを題材に、アメリカで暮らすマイノリティの苦悩や葛藤、家族間の軋轢を描いた作品です。アイデアとしてすごく面白い部分もあるんですが、色々な要素を詰め込みすぎた結果、いびつなパッチワークのような形になり、全体としてはとっ散らかった印象を受けます。「家族セカイ系」というのも、多くのアニメで慣れ親しんだテーマなので、日本人にとってはそれほど新鮮味がないのかもしれません。「カオス」と居直る割に、説教臭いところがあり、案外普通の着地をみせるのも少し残念でした。
色々と書きましたが、結局は好みの問題で、ハマる人にはかなりハマると思うので、まずは自分の目で確認してみてください。それと、「エブエブ」の配給会社である「A24」は、設立が2012年と新しいのですが、10年台後半から急激に存在感を示すようになった注目のスタジオなので、名前だけでも覚えておくとこれから面白いと思います。
♦︎オススメ度:☆
おわりに
オスカーをめぐって繰り広げられるドラマは時に映画よりも劇的で、それゆえに、今やこうして多くの映画人(ハリウッド人)や映画ファンを魅了する一大イベントになりました。それは、たとえそこに対立や不和が、闘いや不調和があろうともです。
そして、アカデミー賞はその時の世相を反映した政治性の強い賞でもあります。だから、全ての作品を追っていくと、映画という表象を通して、また「観る」という行為を通じて、“アメリカ“という国の輪郭がぼんやりと浮かび上がってくる。もちろん、95作品だけでは不十分ですが、全作品を見通すというのは、そんなところに大きな魅力があると思います。
大変長くなりましたが、最後までお付き合いありがとうございました。この記事がどうか、皆さんがオスカー受賞作品を見る時のガイドラインとなれば幸いです。それでは、よき映画ライフを。
フリーターでいるうちにやりたかったことがひとつあって、それがアカデミー賞の歴代作品賞受賞作を(既視聴分も含めて)全部観ることだったんですが、半年弱かけてやっと達成できました。全94本と少なすぎずも多すぎもせず、自分は何も関わっていないのに観終わった後は感慨深くなれるのでオススメです pic.twitter.com/C5xU3j9Df8
— Suzuki (@finto__) July 30, 2022
<参考資料>
・川本三郎『アカデミー賞 オスカーをめぐる26のエピソード』,中央公論社,1990年
・筈見有弘/渡辺祥子監修『アカデミー賞記録辞典』,キネマ旬報社,2013年
・越智道雄監修『映画で読み解く現代アメリカ オバマの時代』,明石書店,2015年
・鈴木透『実験国家アメリカの履歴書: 社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡』,慶應義塾大学出版会,2016年
・村瀬広『アメリカが面白くなる映画50本』,新日本出版社,2019年
・メラニー『なぜオスカーはおもしろいのか? 受賞予想で100倍楽しむ「アカデミー賞」』,2020年
・町山智浩『それでも映画は「格差」を描く』,集英社,2021年
※イメージ画像 by #Midjourney
※リンクは全てポスタービジュアルの代わりに添付しているもので、アフィリエイトではございません。
最後までありがとうございます。
