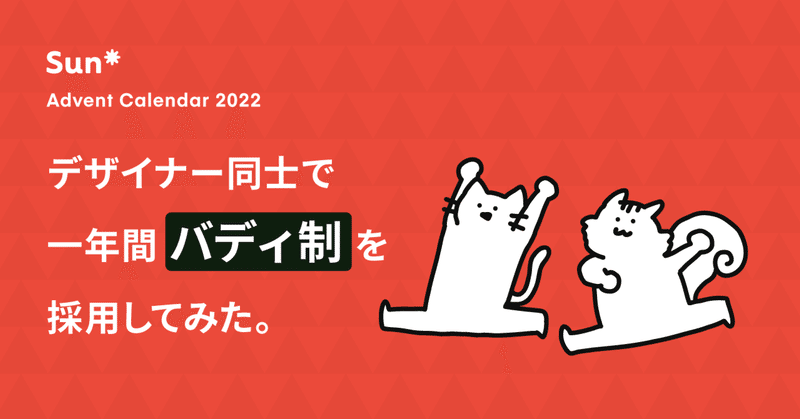
デザイナー同士で1年間バディ制を採用してみた
はじめまして。
Sun Asterisk UI/UXデザイナーのせーなです。
わたしがデザイナー同士でバディを組んでから、1年が経ちました。
その振り返りを通して見えた、バディを組む「良さ」「課題」「これから」について、Sun* Advent Calendar 2022 7日目の記事としてまとめます。
自己紹介
わたしはUI/UXデザイナーとして働いて6年目で、Sun*に入社してからは4年目です。
今は新規事業のUI/UXデザインの支援をしています。
バディの紹介
わたしのバディは、UI/UXデザイナーである、S氏です。
デザイナー歴はわたしより先輩の11年です。
事業会社や制作会社で経験を積んだあと、Sun*にはわたしより少し後に入社して2年目になります。
バディを組んだ背景
Sun*は自立自走できる人が多い環境で、それぞれが自分自身の信念に基づいて本質を追求できる環境ではあるのですが、プロジェクトチームの外と共有し合う文化は弱い、ということが課題としてありました。
今回のバディ制を始めたマネージャーはエンジニアでもあり、エンジニア同士バディを組んでお互いに成長していくことの良さを知っていて、デザイナーにも有効なのではないか?と考えたそうです。
他のデザイナーから刺激をもらえる環境は、わたしも求めていたことでした。
この制度の狙いとしては大きく分けて以下の4点です。
プロジェクトワークの中で発生する稼働量の波に、バディがサポートすることで稼働量を平準化する
ピアレビュー (※1)文化を作り、品質・スキルの向上を促進させる
サポートで入るプロジェクトが、経験できるプロジェクト数や量を増やす
レビュー文化の醸成
※1:ピアレビューとは、業務の成果物を別の人が詳細に評価・検証するレビューの類型の一つで、立場や職種が同じ(または近い)者同士の間で行うもの。
1年間のアサイン状況
クライアントワークでは、バディそれぞれが明確に工数を持ちます。
1ヶ月に出来る稼働量を1人月として、どのくらいの割合でどのプロジェクトに参加するかという目安になりますが、わたしたちは以下のような形でした。

どちらがメインデザイナーで、どちらがサポートなのかは工数量で明確になります。
メインデザイナーはプロジェクトを推進させ、悩んだり困った時は適宜バディに相談をします。
サポートは、ミーティングには参加して情報をインプットし、メインデザイナーから相談があれば一緒に考えるなどの形で動きます。
自分がメインデザイナーのプロジェクトに余裕があるときは、サポート側の作業も手伝いました。
バディを1年間組んでみての振り返り
1.タスク管理・工数管理のコントロールはできたのか?
<結論>
できた

自分に余裕があるとき、かつバディが忙しいときは、一部のタスクを代わりに対応するなどのサポートができます。
また、お互いの状況がわかるため、キャパオーバーしそうだったり、プロジェクトにトラブルが起きそうな時を客観的に感じ取ることができて、マネージャーに状況共有やアラートが出しやすく、リスクヘッジできるという点でもよかったです。
ただ、工数が少ないプロジェクトへのコミット感は希薄になりやすく、サポートとして参加しているプロジェクトでバリューを発揮できているかどうかも不安でした。
関わるプロジェクトのチームメンバーに、バディとしての取り組みを伝え、メインデザイナーとサポートの違いや関わり方を理解してもらうことが大事で、作業できない時はできない、などときちんと共有していく必要があるのだと感じました。
あとは、お互いが暇なときに無理にタスクを分けようとして逆にやりにくくなることなどもあったので、バディ間でも手助けが必要かどうかをしっかり伝えていくことは重要だと感じています。
今後、タスクや状況を共有する時間を定期的に持ち、タスクを把握している状況を作り、空いている工数で「何をするか」を雑談するなどで、「手伝う?」や「いる」「いらない」をより言いやすい関係性が作れるように試してみようと思います。
また、タスクのない期間は、方向性を決めて同じ勉強をし、共有しあうことで、成長につながる期間を作り出す取り組みも考えています。
2.品質・スキルの向上は実現できたのか?
<結論>
できた

一人で考える時には出なかった考えが出たり、デザインについて意見をもらうことでクオリティや仕事の精度が上がったと思います。
レビューをしてもらうと、考えられていない部分が出てきたり、視野が狭まっていた状態から客観的になれるようなアドバイスをもらえました。
加えて、他のデザイナーが気になるポイントをインプットできました。
S氏はわたしよりも経験値のあるデザイナーですが、わたしが役に立ったと思うシーンが何度かあります。
改めて、どんなベテランデザイナーでもレビューは必要なんだということを感じました。
デザイナー同士でデザインを揉むことで、クライアントやプロジェクトにとってより良いものが出せることは、わたしたちにとってもクライアントやプロダクトにとっても良いことだと思いました。
相談しあえるのはよいのですが、相談した結果、意見が別れ、かえって判断しかねるという状況になってしまう時がありました。
そのため、最終的な決断はメインデザイナーが行う、と責任を定めることにしました。
3.レビュー文化は醸成されたのか?
<結論>
できた

デザインに関して相談したい時、これまでであれば相談相手がプロジェクト外の方になるため、事前知識を理解をしてもらってから初めて相談できる、ということが多かったのですが、事前知識の共有はできている状態なのですぐ相談できました。
もちろん自分自身もバディの相談にも乗りやすかったです。
その結果、レビューをしてもらうためのフットワークが軽くなったように思います。
それで感じたのは、入社してすぐは社内のデザイナーがどの領域のどんなデザインに詳しいか分からないので、最初からバディがいれば、相談先が分からないといった課題もカバーできるのではないか、ということでした。
お互いが忙しい時期に入ってしまうと、そもそものコミュニケーションが少なくなってしまうということは避けられず、バディのメリットであるレビューの依頼のしやすさや、カバーし合える点などが感じられなくなってしまいました。
この点についてはまだ明確な改善方法が見えていません。
4.バディの関係性はどうだったか
<結論>
なかよし

コロナの影響もあり、密なコミュニケーションが希薄になる中、バディとはコミュニケーションが多くなるため、ちょっとした相談もすぐできるようになりました。
結果的に信頼感や安心感を持てるようになったと思います。
Sun*の所属期間は、S氏よりもわたしの方が長かったこともあり、他のデザイナーさんに共有したり繋げるなど、Hubにもなれた気がします。
まとめ(感想)
性格の相性
施策で組んだバディでしたが、性格の相性も良く、お互いのやっていることを尊重できていたと感じました。
尊重しあえるかはバディを組む上では大事な要素になりそうです。
保有知識のレベル感
UIが得意などスキルセットが似ていたことで、お互いのやりたいことの把握もしやすかったです。わからないことはお互い調べて共有し合うこともできました。
それゆえ師弟関係になりにくく、フラットに切磋琢磨できたのも良いポイントだと思います。
経験が浅い人が経験豊富な人と組むことで、意見をもらいやすい環境を得ることもできそうだと感じました。
バディを組んでみて、仕事の効率もクオリティも上がったと思います。
デザイナーに限らず、他の職種でも試してみる価値はあると思います。
すぐそばに助けてくれる人がいて、安心して仕事ができること。
技術の共有をし合えること。
うまくいかない時はお互いの愚痴を聞き、頑張っている様子を見て自分の励みにできること。
これが、わたしとS氏がバディを組んで感じたことです。
コロナ禍でオンラインコミュニケーションが増えた今、こういった仕組みで切磋琢磨できる環境を作っていくのはいかがでしょうか。
以上でわたしの記事はお終いになりますが、Sun* Advent Calendar 2022 はまだまだ続きます。
明日は、プロジェクトマネージャーのそらくんによる記事です。
新卒二人目の記事になります。
お楽しみに!
p.s.
バディってよくわからないな、、と思ったあなた。
アニメで例えるならTIGER & BUNNYの「タイガーとバーナビー」みたいなものです。
Confidence is a plant of slow growth.
(信頼という木は大きくなるのが遅い木である )
もしくはジョジョの「ジョセフとシーザー」でも良いです。
おしまい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
