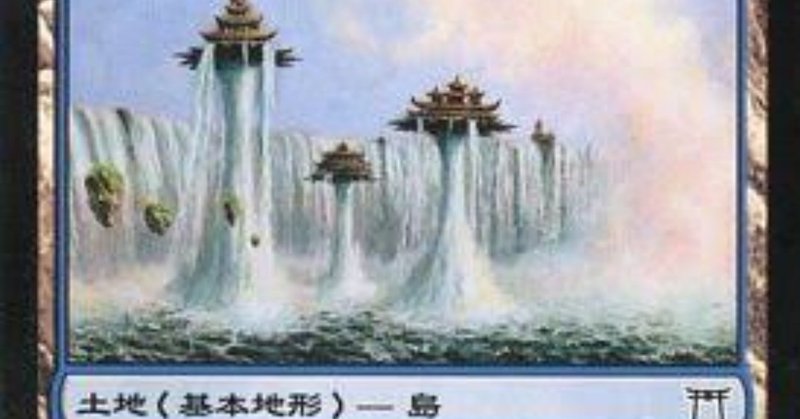
MTG-スタンダード-灯争大戦環境の青単アグロについて
はじめに
こんにちは。
最近青単アグロを使っていたので、今回は灯争大戦環境に於ける青単アグロの解説記事をガッツリ書いていきたいと思います。
(現実世界での)直近の成績は17-6で勝率73%、この前に出た晴れる屋トーナメントセンターの大会でで5-0して5000ポイントを貰ったりもしました。この結構勝てている青単アグロのこと、気になりませんか?
もちろんベストなデッキを探すことも大事ですが、好きなデッキを使うこともカードゲームの醍醐味。青単アグロスキーの方なら是非とも読んでください!
「今更、青単アグロの解説?」と思われるかもしれませんが、私自身、灯争大戦が来てからの青単アグロってどうなんだろう?と考えた際、参考に出来る記事が少なくて困った記憶があります。
ですから、《時を解す者、テフェリー》や《覆いを割く者、ナーセット》が跋扈する環境で、久しぶりに青単アグロを使いたい人には自信を持ってオススメ出来ます!
もちろん、「そもそも青単アグロって今使う意味あるの?」と疑問視している方の参考にもなれば幸いです。
デッキリスト

メイン(60)
土地(20)
20 島
クリーチャー(20)
4 プテラマンダー
4 霧まといの川守り
4 セイレーンの嵐鎮め
4 マーフォークのペテン師
4 大嵐のジン
スペル(20)
4 選択
4 呪文貫き
4 執着的探訪
1 一瞬
1 否認
1 本質の把握
4 魔術師の反騶
1 覆いを割く者、ナーセット
サイドカード(15)
1 否認
4 波濤牝馬
3 本質の把握
4 幻惑の旋律
1 排斥する魔道師
1 覆いを割く者、ナーセット
1 永遠神、ケフネト
1.青単アグロとは?
申し訳ないのですが、灯争大戦環境での青単アグロの話を始める前に、そもそも青単アグロってどんなデッキ?というところから整理させていただきます。
もちろん、デッキリストであるとか、基本的な戦い方に関してはご存知の方も多いと思うのですが、より具体的な話、つまりは『ゲームプラン』の確認ですね。
(『ゲームプラン』という言葉に関しては様々な解釈がありますが、ここでは『どうやって勝とうとしているのか?』という意味で使わせていただきます。)
さて、強いデッキというのはゲームプランが分かりやすいことが多いです。
例えば4色《戦慄衆の指揮》デッキのゲームプランはそのまんま『《戦慄衆の指揮》をぶっ放す!』、赤単アグロのゲームプランは『火力と生物でタコ殴り!』、グリクシスコントロールのゲームプランは『更地にボーラス様が君臨すれば勝ち!』でしょう。
その点、青単アグロのゲームプランは少し難解です。
土地(20)
20 島
クリーチャー(20)
4 プテラマンダー
4 霧まといの川守り
4 セイレーンの嵐鎮め
4 マーフォークのペテン師
4 大嵐のジン
スペル(20)
4 選択
4 呪文貫き
4 執着的探訪
1 一瞬
1 否認
1 本質の把握
4 魔術師の反騶
1 覆いを割く者、ナーセット
これは私が現在使用しているリストのメインボードですが、ライフを素早く削りたいならカウンターは必要ないし、コントロールがしたいなら1マナのクリーチャーをたくさん入れるべきではないはずですよね?
じゃあ、青単アグロのゲームプランって?
ズバリ、『相手に全力を出させない!』。
これこそ青単アグロの目指している勝ち方です。
赤単アグロが「軽量クリーチャー+火力呪文」で速度勝負を挑んでいるのに対して、青単アグロは「軽量クリーチャー+相手の妨害を妨害するカウンター」で速度勝負を挑むわけです。
一見すると赤単アグロのコンセプトの方が優れているように思えますが、《ケイヤの誓い》や《聖堂の鐘撞き》のような非常に強力な妨害に対しては、青単アグロのコンセプトの方が有効に働くこともあります。
つまり、同じアグロであっても、青単アグロは赤単アグロとはアプローチが異なるので、赤単アグロが苦手な相手に対して有利に戦えることがあるのです!(もちろん、「赤単アグロなら有利なのになあ」ってマッチアップもありますが…)
また、相手のキーカードをカウンターしてしまえば一発逆転を許さないのも、青単アグロの大きな特徴だと言えます。
現環境には《集団強制》や《戦慄衆の指揮》のような1枚で有利不利を入れ替える凄まじいカードがあるので、この点も魅力ですよね!
要するに青単アグロは、赤単アグロとは異なるデッキであり、差別化は充分出来ているんだよ!ってことをお伝えしたいわけです(笑)。
それでは青単アグロのゲームプランが『相手に全力を出させない!』だと分かったところで、いよいよ灯争大戦環境の話に移りたいと思います。
2.灯争大戦環境の青単 環境編
灯争大戦環境の特徴は、
エスパーコントロールやバントランプ、《戦慄衆の指揮》デッキのように重くて強いデッキ
と
赤単アグロやグルールミッドレンジのように早くて強いデッキ
の二極化です。
早速、青単アグロと両者の相性を各デッキが灯争大戦で強化された点を踏まえながら確認していきましょう。
まず、エスパーコントロールに関してですが、前環境の青単アグロにとってこのデッキは是非とも当たりたいデッキの筆頭でした。
コントロールだけあって重いカードばかりなので、全体除去だけカウンターしてあげれば、正におやつを食べる感覚で倒せるぐらいの相性差があったのです。
しかし、灯争大戦がリリースされ、皆さんご存知のバグレベルの強さを持つプレインズウォーカーがスタンダードに参戦します。

(5マナでも3マナでもテフェリーは強い。)
《時を解す者、テフェリー》は環境からカウンター呪文が消え去った元凶であり、青単アグロにとっては天敵ともいえるカードです。
具体的には、青単アグロに対して3ターン目に《時を解す者、テフェリー》をプレイ出来れば、それだけでゲームが終わるぐらいのインパクトがあります。(モダンのコンボでも基本的に2枚揃わないと勝たないのに!)
ただ、個人的な考えとしては、前環境でも《大嵐のジン》をコントロールしていないタイミングで《肉儀場の叫び》や《轟音のクラリオン》のような3マナソーサリーの全体除去が通れば負けていましたし、《時を解す者、テフェリー》を打ち消せず、プラス能力を起動されるようなシチュエーションならば、唱えられたカードが何であれ、厳しい勝負だったのではないかとも思います。

(同じく通ったら負け…。)
それでも3ターンでゲームが終わる可能性があることが驚異なのは間違いないため、先行3ターン目《時を解す者、テフェリー》に抗える《呪文貫き》は4枚採用したほうが良いでしょう。
《呪文貫き》が4枚あれば、《選択》や《執着的探訪》で探しにいけますし、そもそも先行を取れる可能性も50%あることを考慮すれば、この変更込みでまだ有利と言えそうです。

(日本語版使用率90%)
エスパーコントロールに新たに採用されたもう1枚のプレインズ・ウォーカーである《覆いを割く者、ナーセット》に関しては、《執着的探訪》の弱体化や《航路の作成》の採用にリスクが生じるようになったことはマイナスであるものの、やはりエスパーコントロールと青単アグロの相性差を逆転させるほどインパクトがあるカードではありません。
それどころか、青単アグロにも無理なく採用出来るアドバンテージ源であり、打ち消してもリソースを回復する《ハイドロイド混成体》などに強いことを考えれば、若干の強化だと言えます。
他にもエスパーコントロールのカードは何枚か変わりましたが、《古呪》や《灯の燼滅》などは青単アグロに対して有効なカードではなく、《ケイヤの誓い》も劇的なカードとまでは言えません。
結論から述べれば、前期と同じくエスパーコントロールvs青単アグロは、青単アグロ側が有利だと言えそうです。

(ナメクジ料理人おばさん)

(重くて強いカード代表)
《世界を揺るがす者、ニッサ》のリリースによって誕生したバントランプ、《戦慄衆の指揮》のリリースによって生まれた各種《戦慄衆の指揮》デッキに関しても、動きが非常に大振りなので青単アグロ側が有利なマッチアップです。
総じて、重くて強いデッキに対しては青単アグロは相変わらず有利であり、構築を少し変えるだけで充分戦えるというのが私の見解です。
問題は、早くて強いデッキです。

(ずっと強いゴブリン)
灯争大戦で得たカードは《炎の職工、チャンドラ》と《無頼な扇動者、ティボルト》の二種類のみですが、赤単アグロは青単アグロに滅法強いデッキです。
相手のデッキ構成も軽いためカウンター呪文は有効ではなく、《執着的探訪》は大量の火力呪文のせいで全く機能しません。タフネス1の生物が多いのも致命的です。
サイド後に至っては《溶岩コイル》で《大嵐のジン》が焼かれ、《軍勢の戦親分》や《再燃するフェニックス》が戦場を蹂躙します。

(環境の王者)
グルールミッドレンジに対しても同じく相性が悪く、先行《ラノワールのエルフ》からの《グルールの呪文砕き》は言わずもがな、新たに投入された《ボーラスの壊乱者、ドムリ》も《時を解す者、テフェリー》と同じぐらい厳しいカードです。
再び結論から述べますが、青単アグロは赤単アグロとグルールミッドレンジに対してかなり不利であり、サイド後もあまり相性改善出来ません。
特に赤単アグロが絶望的であり、対グルールミッドレンジが1ターン目に《ラノワールのエルフ》をプレイされないことを祈るゲームだとすれば、対赤単アグロは相手の手札が弱いことを祈るゲームです。
こう書くと「やっぱり青単アグロ使う意味ないじゃん!」と思われるかもしれません。
ただ、どんなデッキにも苦手な相手はいるものです。赤単アグロを使えばエスパーカラーのデッキに当たりたくありませんし、グルールミッドレンジはミラーを意識した構築にするとバントランプに無茶苦茶されます。
確かに赤単アグロやグルールミッドレンジしかいない世界で青単アグロを使えば、勝率30%も行かないでしょう。
しかし、バントランプや《戦慄衆の指揮》デッキと当たり続ければ、青単アグロはかつての王者の風格を取り戻してくれます。
環境に存在するどのデッキにも不利なデッキがあるとすれば、それは単なる75枚の紙束かもしれません。ですが、環境の何かしらのデッキに対して有利に戦えるとすれば、それはメタデッキです。
今の青単アグロの立ち位置は、重くて強いデッキを狩るデッキなんだと考えましょう!
3.灯争大戦環境の青単 構築編
青単アグロは重くて強いデッキを狩るデッキという認識を元に、早速構築していきます。
固定スロット
20 島
4 プテラマンダー
4 セイレーンの嵐沈め
4 マーフォークのペテン師
4 大嵐のジン
4 選択
4 呪文貫き
4 執着的探訪
4 魔術師の反騶
20 島
《大嵐のジン》を場に出しつつ1マナを構えたいことが多いので、4枚目までは是非とも引きたいカードです。
カウンター呪文を構えるコンセプト的にも、序盤に土地が置けないことは致命的なので、19枚にするべきではないと考えています。
4 セイレーンの嵐鎮め
飛行クロックでありながら、《プテラマンダー》や《大嵐のジン》を守ってくれるスーパークリーチャーです。
しかも、ウィザードなので《魔術師の反騶》のマナコストを下げてくれますし、海賊なので《焦熱の連続砲撃》で吹き飛びません。最強!
4 プテラマンダー
序盤のクロック兼フィニッシャー。このデッキでは4、5マナで順応することが多いです。
順応するタイミングが難しいカードですが、順応すれば勝てるタイミング以外、手札に《潜水》やカウンターがあれば構えながら順応出来るまで待ち、なければさっさと順応して殴ってしまうのがいいと思います。
4 マーフォークのペテン師
基本的な使い方は
①
2マナ2/2のクロック。
②
出した時の効果で相手のアタックを1回止め、ブロックで相手の攻撃をもう1回止める壁。
です。
①、②以外のプレイをしようとすればいくらでも出来るカードなのですが、狙いすぎるとプレイが歪むため、①、②以外の使い方をする時は、それは本当にする必要があるプレイかを脳内で確認してください。
4 大嵐のジン
《島》の分だけパワーが上がる攻撃性能もですが、タフネス4という防御性能も重要なカードです。ブロッカーに回れば環境にいる小粒なクリーチャーは全て一方的に打ち取れるので、安易な攻撃を許しません。
このカードを出す時は基本的にカウンターが構えられません。なので、手札にカウンターがある際は、返しに使われた際に最もやばいカードを考え、それを使われてもどうにかなるなら《大嵐のジン》を出し、どうにかならなければカウンターを構えるべきです。
4 選択
《プテラマンダー》との噛み合いや、後手2ターン目に《呪文貫き》を探しにいくケースを考えれば、4枚採用以外ありえません。
《選択》をデッキから抜くということは《選択》以上に採用価値があるカードが存在するということですが、現状存在しません。
4 呪文貫き
先述したように《時を解す者、テフェリー》対策のカードです。引けるか引けないかで勝率が変わるカードなので、最大値の採用が望ましいですね。
《ケイヤの怒り》や《ドミナリアの英雄、テフェリー》のような致命的なカードも展開次第では打ち消すことが出来ます。
4 執着的探訪
エンチャントし、1回殴れば1マナ1点1ドロー、2回殴れば1マナ2点2ドロー、3回殴ればゲームに勝利します。
青単アグロを使う理由とでも呼ぶべきカードですので、サイドアウトするマッチアップも赤単アグロのみです。
4 魔術師の反騶
現代版《対抗呪文》。
3マナで使っても別にゲームに敗北するわけではないため、このカードがあるからといって、目的もなく《マーフォークのペテン師》を出したりはしない方がいいです。
自由枠 優先度高
4 霧まといの川守り
青単アグロがエスパーコントロールやバントランプに敗北するパターンの中で最も頻繁に起きるのは、最序盤にクロックを出せなかったことによりゲームスピードが低下し、相手が強力なカードを連打し始めることです。
これを防ぐためには《霧まといの川守り》を入れてクロックを増やす他ありません。入れる理由が負け筋の防止なので、中途半端な枚数は意味がなく、採用するならば4枚がいいと思います。
1 一瞬
場に出てしまい、プラス能力を起動し始めた《時を解す者、テフェリー》に干渉出来るカードが1枚もないのは余りにも心もとないので採用しています。
バウンスし、場に十分なクロックが用意出来ていれば、出し直してプラス能力を起動するとライフが保たない展開に持ち込める可能性があります。
かなりサイドアウト率が高いのですが、メイン戦ではどのデッキに対しても50点ぐらいの良いカードです。
1 覆いを割く者、ナーセット
ランプデッキの《ハイドロイド混成体》は巨大な飛行生物であり、打ち消してもライフゲインしつつ、リソースを回復してくる非常に厄介なカードです。
《覆いを割く者、ナーセット》は打ち消しやバウンスを供給し、大量のマナからのハイドロイド連打を防いでくれるベストな対策カードだと言えます。
自由枠 優先度低
1 否認
1 本質の把握
追加のカウンターです。《呪文貫き》と《魔術師の反騶》以外にも何枚かカウンターが欲しいため、私はこの2種を1枚ずつ採用しています。
感想としては強い時もあれば、弱い時もあるという非常に頼りないものなので、お好きなカードに変えて問題ないかと思います。
採用しなかったカード
《潜水》
個人的にどうしても好きになれないカードであることを除いても、バントランプや《戦慄衆の指揮》デッキが単体除去をあまり採用していないことを考えれば、コンセプトから外れています。
エスパーコントロールに強いことは間違いないので、好みによって何枚か入れてもよいかと思います。
《火消し》
マナクリを大量に採用したデッキ(マナクリ型グルール 、バントランプなど)は《呪文貫き》や《火消し》のような条件付きカウンターを簡単にケア出来るので、《呪文貫き》4枚に加えて《火消し》まで入れるのはリスクが大きすぎます。
《航路の作成》
《覆いを割く者、ナーセット》によって採用にリスクが生じていますし、アドバンテージ源が欲しいのならば、自分の《覆いを割く者、ナーセット》の方が優秀です。どちらにせよ、過去のカードとなってしまった感があります。
《無神経な放逐》
《一瞬》との選択枠です。
グルールミッドレンジや白単アグロには1/1のトークンが有用ですが、《培養ドルイド》の順応に対応してバウンス出来ることや、キッカーコストで唱えられることを評価し、《一瞬》を優先してしまいす。
※サイドボードは次項で解説します。
4.灯争大戦環境の青単 実戦編
デッキが完成しました! いよいよ実戦編です!
現在最メジャーなデッキである
赤単アグロ
グルールミッドレンジ
エスパーコントロール
バントランプ
《戦慄衆の指揮》+《野茂み歩き》
との戦い方を解説していきます。
使用デッキリスト(再掲)

土地(20)
20 島
クリーチャー(20)
4 プテラマンダー
4 霧まといの川守り
4 セイレーンの嵐鎮め
4 マーフォークのペテン師
4 大嵐のジン
スペル(20)
4 選択
4 呪文貫き
4 執着的探訪
1 一瞬
1 否認
1 本質の把握
4 魔術師の反騶
1 覆いを割く者、ナーセット
サイドカード(15)
1 否認
4 波濤牝馬
3 本質の把握
4 幻惑の旋律
1 排斥する魔道師
1 覆いを割く者、ナーセット
1 永遠神、ケフネト
vs赤単アグロ
最悪の相手です…。
メイン戦
メインボードでは、順応した《プテラマンダー》か《大嵐のジン》で速やかにゲームを終わらせるぐらいしか勝ち筋がありません。
ここで重要になるテクニックとして、
①
すぐにドローしたい時や、タフネスを上げて《ゴブリンの鎖回し》をケアしたい時以外、《執着的探訪》は《大嵐のジン》にエンチャントする。
②
ブロックしなければ負ける時以外、絶対に《ゴブリンの鎖回し》を順応した《プテラマンダー》や《大嵐のジン》でブロックしない。
というのがあります
①に関して分かりやすいですね。
赤単アグロに対する《大嵐のジン》はメイン戦では非常に頼りになるカードで、火力を2枚打ち込まないと倒されません。ですから、《大嵐のジン》に《執着的探訪》をエンチャントし、カウンターを構えられるとかなり強力です。
除去されなければ巨大な飛行クロックとしてライフを速やかに削ってくれますし、相手がたまらず《大嵐のジン》に火力を打ち込んできた際、上手く2枚目をカウンターできれば勝利は目前です!
②に関しては、赤単アグロはメイン戦では《大嵐のジン》が中々除去出来ないことを理解すると分かりやすいですね。
例えば《ギトゥの溶岩走り》をブロックした《大嵐のジン》に《稲妻の一撃》を打ち込まれた場合、相手はカードを2枚失って《大嵐のジン》を倒しているので損しています。
しかし、《ゴブリンの鎖回し》をブロックしてしまうと先制攻撃+《稲妻の一撃》で《ゴブリンの鎖回し》が生き残り、《大嵐のジン》は倒されてしまいます。
そうなってしまえば、折角の《大嵐のジン》を実質的に火力呪文1枚で失ったことになるので、どれだけ《ゴブリンの鎖回し》が憎くてもブロックするのは我慢しましょう!
サイド後
対赤単アグロの最も苦しい点は、メイン戦の相性が悪いこと以上に、サイド後の赤単アグロが凄まじく強化されることです
まず、《溶岩コイル》が投入されるので、メイン戦では強かった《大嵐のジン》が1枚で除去されるようになります。
また、《軍勢の戦親分》、《再燃するフェニックス》という1枚で勝てるクリーチャーが追加されます。
尚且つ、相手は火力を顔に打ち込むアグロプランを取るか、火力をクリーチャーに打ち込むロングゲームプランを取るかの選択権まで保有しています。

サイドアウトするカードですが、まず鎖が回ると吹っ飛ぶ《霧まといの川守り》と何の役にも立たない《一瞬》、《覆いを割く者、ナーセット》を全部抜きます。
次にエンチャントしようとした際に火力が飛んでくると悶絶する《執着的探訪》も全部抜きます。
もちろん先に述べたように、ゲームが長引いてカウンターを構えながら《大嵐のジン》にエンチャント出来れば最高ですが、ゲーム序盤に引けば困ってしまいますからね。
同様の理由で、《プテラマンダー》も全部抜きます。順応出来れば強いとは、順応出来ないと弱いの同義語です。
はい、弱いカードを弱い順に抜くだけで14枚のカードがサイドアウトされてしまいました。

ところで、青はクリーチャーを除去出来ませんし、エンチャントを破壊出来ませんし、ライフゲインすることも出来ない色です。
つまり、《永遠神の投入》のような赤単アグロに分かりやすく有効なサイドカードが存在しません。
それでも赤単アグロに勝ちたいなら、サイドカードを最低14枚用意する必要があります。

そもそも対赤単アグロ用のサイドカードを14枚用意出来たとして、他のデッキと対戦した際、サイドチェンジはどうすればいいのでしょうか?

青単アグロの対赤単アグロがどれぐらいヤバイのかお分かりいただけたでしょうか?

それではサイドチェンジプランです。
アウト
4 プテラマンダー
4 霧まといの川守り
4 執着的探訪
1 一瞬
1 覆いを割く者、ナーセット
イン
1 否認
4 波濤雌馬
3 本質の把握
4 幻惑の旋律
1 排斥する魔道士
1 永遠神、ケフネト
地上を《本質の把握》と《波濤牝馬》で止めながら、島が5、6枚並ぶまで耐え、《幻惑の旋律》で相手の《軍勢の戦親分》か《ゴブリンの鎖回し》、《再燃するフェニックス》を奪って勝ちます。

これは悪い冗談でも、酔っ払って書かれた文章でもありません。色々と試しましたが、これが最も勝率が高いプラニングです。10回やったら3、4回ぐらいは勝てますので、是非試してみてください。
ちなみに私はこのサイドチェンジプランのことを“インパール作戦”と呼んでいます。誰か対赤単アグロで良いプランがある方がいたら教えてください。
vsグルールミッドレンジ
厳しい戦いが予想されます。
メイン戦
赤単アグロと同じく厳しい相手ですが、赤単アグロとは異なり、火力呪文が6枚程度しか採用されていないので《執着的探訪》が機能し、重いカードも多いことからカウンターが有効に働きます。
《ラノワールのエルフ》からのブン回りはどうにもなりませんが、相手の引き次第では充分に勝ち目があるので諦める必要はありません。
対グルールミッドレンジで気をつけることは、相手が暴動で速攻をつける派かカウンターを乗せる派かの判断です。
私は使ったことがないのでどちらが正解なのかよく分かりませんが、グルールミッドレンジ使用者には《グルールの呪文砕き》や《スガルガンのヘルカイト》の暴動で速攻を付与して殴ってくる派、カウンターを乗せる派がいます。
相手が速攻派の場合は、火力でライフを詰めてくる算段を立てているかもしれないので、早めにチャンプブロックをしたり、《マーフォークのペテン師》を出す必要があります。
対して相手がカウンターを乗せる派の場合、《大嵐のジン》がブロッカーとして信用出来なくなるので、急いでライフを詰めに行かなければなりません。
相手がどちら派なのかを早めに見極め、どうゲームを進めるかを決めるのが大事です。
サイド後
アウト
4 霧まといの川守り
1 一瞬
1 覆いを割く者、ナーセット
イン
4 波濤牝馬
2 本質の把握
対赤単アグロと同じく《波濤牝馬》で地上を止めるプランですが、《幻惑の旋律》で悠長するよりも飛行で殴り切った方が早いです。尚、《ボーラスの壊乱者、ドムリ》が非常に辛いので、《呪文貫き》は減らしません。
vsエスパーコントロール
有利なマッチアップです!
メイン戦
盤面にクリーチャーを並べ、相手が唱えてきたスペルをカウンターしていれば勝つことが出来ます。
考えるべきことはあまりなく、こちらのカウンターが尽きるのが先か、相手のライフが尽きるのが先かの勝負です。
勝てなさそうな盤面になってしまった場合、時間切れする可能性を考慮し、早めに投了することが望ましいですね。
サイド戦
アウト
1 本質の把握
1 大嵐のジン
イン
1 否認
1 覆いを割く者、ナーセット
相手がクリーチャーを採用していなかったりするとゲームが終わるまで使えないので、《本質の把握》をサイドアウトします。
もちろん、相手がメイン戦で《聖堂の鐘撞き》を出してきた場合や《黎明を齎す者、ライラ》をケアしたい場合は残すこともありますので、その場合は《一瞬》をサイドアウトします。
《大嵐のジン》に関しては、不要なカードというわけではないものの、このカードが手札に何枚も溜まってしまうと負け筋になるため、1枚だけ減らします。
元からかなり有利なように構築しているので、入れ替えは最低限だけで充分です。
vsバントランプ
有利なマッチアップ、その2!
メイン戦
有利ですが、常勝を目指せるほど有利なわけではありません。
何故なら相手はマナブーストさえ出来れば『《ハイドロイド混成体》から《ハイドロイド混成体》を繋げる』という明確な勝ちプランがあるからです。
ですから、ゲームスピードを速める追加のクロックである《マーフォークの霧まとい》や《ハイドロイド混成体》のドローを防げる《覆いを割く者、ナーセット》が大事になってきます。
サイド後
アウト
1 一瞬
2 大嵐のジン
イン
1 否認
1 本質の把握
1 覆いを割く者、ナーセット
《ハイドロイド混成体》が着地してしまうと非常に厳しいので、《大嵐のジン》を何枚か減らし、カウンターと入れ替えます。
相手が《クロールの銛撃ち》を採用している場合や、クリーチャーの量が多い場合、《本質の把握》を3枚ともサイドインします。
vs《戦慄衆の指揮》+《野茂み歩き》
様々な型がありますが概ね有利です!
メイン戦
カウンターがあっても《野茂み歩き》は通してもよいので(=手札にカウンターがあってもクロックを展開してよい)、後から出てくる探検クリーチャーを通さないようにするプレイを徹底しましょう!
《戦慄衆の指揮》が通るようなことはまずないので、《野茂み歩き》によるライフゲインさえ防げれば、飛行ビートしているだけで勝てます。
イメージとしては前環境のスゥルタイミッドレンジが勝手に弱体化してくれた感じなので、こちらとしては非常に楽ですね!
サイド後
アウト
1 一瞬
1 覆いを割く者、ナーセット
イン
1 否認
1 本質の把握
有利なので入れ替えもあまり必要ありません。相手は全体除去をサイドインしてくるので、それだけはケアし、カウンターがある際はきっちり構えておきましょう!
終わりに
長々と続きましたが、これでひとまず終わりです。最後に私が考える青単アグロのプレイのコツを書いておきます。
打ち消しがある時は相手にカードプレイされた際は打ち消さない理由-例えば「単体除去は通しても他で殴ればいいからカウンターは温存」など-を考えて、理由がなければ打ち消す。
打ち消しがない時は全体除去がないことに期待して生物を全部出す、打ち消しがある振りをしても全体除去は撃たれるので、リターンが大きい方を選ぶ。
対戦相手を不愉快にするだけなので打ち消しがないのに打ち消しがある振りをしない。同じく、打ち消すことに決めているのに、打ち消すか悩んだ振りをしない。(マジギャザはお遊戯会ではないため)
さて、青単アグロは派手なデッキではないし、一発逆転の手段があるわけでもありません。赤単アグロにも不利です。
しかし、灯争大戦がリリースされて以来、全然ダメなデッキになったわけではないと思います。
青単アグロスキーの方や、青単アグロを組んだけど家で埃をかぶっている方、どうせならローテーション落ちするまで、青単アグロを使い込んであげましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
