
玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする 式子内親王 百人一首 89 橋本治(1948.3.25-2019.1.29)『桃尻語訳百人一首』海竜社 2009年10月刊 117ページ 田渕句美子(1957- )『新古今集 後鳥羽院と定家の時代 角川選書』角川学芸出版 2010年12月刊 278ページ 『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』KADOKAWA(角川学芸出版) 2014年2月刊 258ページ 日記 2010年1月28日
日記
2010年1月28日
体重60.2kg BMI 22.4
ランニング10分
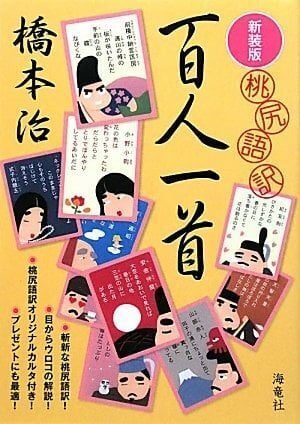

橋本治(1948.3.25-2019.1.29)
『桃尻語訳百人一首』
新装版
海竜社 2009年10月刊
117ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/4759310932
「『桃尻語訳 枕草子』などでも定評のある橋本治の桃尻語訳で、百人一首もぐっと身近に感じられます。百人一首の名歌の数々をわかりやすく親しみやすい訳をつけると同時に、美しい本歌にも触れて「古典の楽しさ」を味わってもらいたいという深い願いがこめられています。百人一首に関する解説も目からウロコの内容で大変面白く、中高生から大人まで楽しめる内容になっています。

初版 大型本 2003.111
https://www.amazon.co.jp/dp/4759307893
2010年1月28日読了
福岡市総合図書館蔵書
2003年11月に刊行された大型本
『桃尻語訳 百人一首』
を再編集した新装版
https://bmshop.jp/cgi_bin/bbs/shinbunka/read.cgi?no=9919
「海竜社が破産
日時: 2021/10/30 18:43:39
情報元: 日書連」
書影は、刊行時の
海竜社ホームページ
http://www.kairyusha.co.jp/ISBN/ISBN978-4-7593-1093-1.html
からダウンロードしていました。



最初に橋本治による簡単な解説、
「百人一首について」
「カルタになった百人一首」
「百人一首の現代語訳」
「百人一首の遊び方」
があり、
次に百首の桃尻語訳と鑑賞が続きます。
119ページ以降は、
切り取って遊べる
「桃尻語訳 百人一首 カルタ(塚原一郎:切り絵)」
になっています。
とても可愛い絵なので、図書館から借りた本
でなければ切り取ってカルタにしてしまいたいところです。
「89 式子内親王
玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする
桃尻語訳
ネックレス 切れてもいいのよ このままじゃ 心もそのうち はじけて消えそう
後白河天皇の皇女です。
「皇女」というと華やかに思えますが、
そうでもありません。
立場上「独身」が当たり前になってしまうからです。
式子内親王も十代の初めに賀茂神社の神に仕える斎院になって、
病気治療のためにそれをやめるまで、十年間そのままです。
藤原俊成に和歌を習って、平安時代の終わりから鎌倉時代にかけての
代表的な女性歌人になりましたが、
「どういう女性だったか」ということになるとぼんやりしています。
この歌は、そんな式子内親王の雰囲気をよく伝えています。
「玉の緒」は「美しい玉をつなぐ糸」ですが、
実は「命」のことでもあります。つまり、
「死んでもいいのよ。このままじゃ我慢することだって出来なくなるから」です。
式子内親王は恋とは無縁の女性ですから、恋はしません。
これは「忍ぶ恋」というテーマで詠んだだけの和歌です。
でも、「それをどう考えます?」と言われた途端、
この激しさを示す人です。」
p.106

読書メーター
百人一首の本棚
登録冊数15冊
https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091294
橋本治の本棚
登録冊数42冊
刊行年順
https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091217

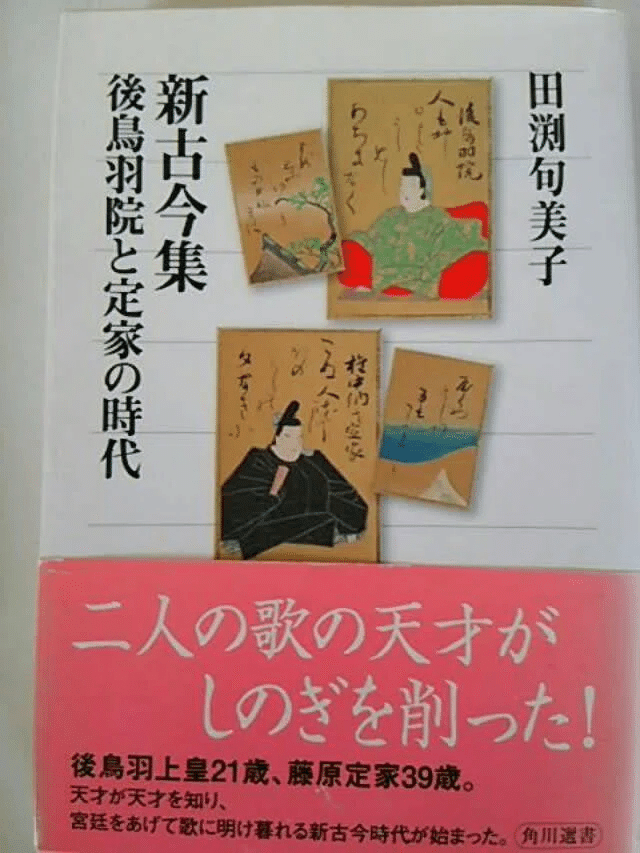
田渕句美子(1957- )
『新古今集 後鳥羽院と定家の時代
角川選書』
角川学芸出版 2010年12月刊
278ページ
2011年2月15日読了
https://note.com/fe1955/n/n8dfcbf3d6859
https://www.amazon.co.jp/dp/4047034819
「『正治初度百首』[1200年]の
式子内親王の百首からは、後にその四分の一にもあたる
二十五首もの歌が『新古今集』に採られたが、
最も良く知られているのは『新古今集』[1034]の
この歌であろう。
百首歌の中に、忍恋を
式子内親王
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする (恋 一)
自らの命を滅ぼそうとする、あまりにも有名な歌だが、
これは近代において長い間、女性の、あるいは式子自身の、
忍ぶ恋の歌であると解釈されてきた。
だが近年、「忍恋」という歌題は基本的に男性の立場に立つもので、
女性の体験詠ではあり得ず、虚構で描き出された恋歌であり、
例えば『源氏物語』の柏木のような立場に立ち、女三宮との密通の
露顕を恐れる恋歌かとの説が出され
(後藤祥子「女流による男歌」『平安文学論集』 風間書房 1992)、
きわめて説得力に富む。
式子の秘めた恋の歌であるというイメージは、払拭すべきなのである。
式子内親王は、皇女という高貴な身分にありながら、歌道家の
藤原俊成に指導を受け、定家とも交流し、多くの和歌を詠んだ。
とりわけ晩年の建久期に、九条家[藤原兼実・良経]で花開いた
新風歌人の和歌をいち早く学び、時代の先端をゆく表現世界を
捉えながら、独自の歌境を獲得した。
『千載集』以前からいくつもの百首歌を詠み、専門家人に伍して
秀歌を詠出することに力を注ぐという立場を、自ら選び取ったのである。
このような道を選んだ内親王や女院は、この前には全く見られないし、
後も南北朝期の永福門院まで見い出せない。」
p.64
「第三章 女性歌人たちの活躍
四 異端の皇女 式子内親王を把え直す」

田渕句美子
『異端の皇女と女房歌人
式子内親王たちの新古今集』
KADOKAWA(角川学芸出版)
2014年2月刊
258ページ
2014年3月29日読了
https://note.com/fe1955/n/n8dfcbf3d6859
https://www.amazon.co.jp/dp/404703536X
「式子の歌のうち、よく知られている歌の一つは、
『新古今集』のこの一首であろう。
百首歌の中に、忍恋(しのぶるこひ)を
式子内親王
玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば忍ぶることの弱りもぞする
[巻第十一]恋一 1034
(私の命よ、絶えるなら絶えてしまえ。長らえると、私の恋を
自分の中に秘めておくことが、玉をつなぐ糸が弱るように
抑制が弱って、思いが外にあらわれてしまうかもしれないから。)
はりつめた烈しい恋歌である。自らの死を願って緊迫する上句、
「長らへば」で一呼吸おいた後、流れ落ちるように収束する
哀艶な下句。この歌では、「絶え」「長らへ」「弱り」がすべて
「玉の緒」の縁語である。縁語とは、歌の中に散乱する詞を、
一つのイメージに統合するものである。巧緻なレトリックが
歌全体を覆っていて、技巧的に、巧みに構成された歌である。
歌にあふれる情念の強さが、詠歌主体が作者自身であるかのような
錯覚を生み、式子自身の恋をそこに読み取ることが度々行われてきた。
しかしこの歌については、大きな読みの変更があった。和歌の表現史を
検証し、十一世紀以降、題詠が急に増え、さらに『堀河百首』以後は
女房歌人による男性恋歌(男歌。詠歌主体を男性とする恋歌)が詠まれる
ようになったこと、俊成は『千載集』に女性歌人の男歌を多数入れ、
式子の歌もその中にあること、「忍恋(しのぶるこひ)」という歌題は、
恋の初期段階において、男性が恋する女性に自分の思いを秘めて
明かさないことであって、男性恋歌の歌題であること、つまり
「玉の緒よ…」は男歌の題詠であること、式子には『源氏物語』の
光源氏や薫の立場で詠んだ歌も多く、「玉の緒よ…」は内容的には、
相手に恋を明かしてはならない禁忌の恋であり、『源氏物語』の
柏木のような状況の恋歌であることが、鮮やかに論証されたのである
(後藤祥子[「女流による男歌 式子内親王歌への一視点」1992])。」p.70
第二章 「式子内親王 後鳥羽院が敬愛した皇女 二
和歌への情熱と精進 式子の百首歌と贈答歌」
「『古今集』以来の勅撰集では、例外もあるが殆どの勅撰集の恋部は、
恋一~恋五の五巻構成で、恋一は恋の初めの「初恋(はしめのこひ)」
から始まり、恋が進行していき、恋五で恋が終わる。
恋一は多くが男歌である。「忍恋」は「初恋」の次に位置する男歌の
歌題であり、恋一にある。そして「玉の緒よ…」は、『新古今集』の
恋一に「忍恋」の歌として入っている。後藤祥子の論証の通り、
「玉の緒よ…」が男歌であることは、抗(あらが)いようのない事実
であろう。」
p.70
「同じ新古今歌人の藤原定家や良経の題詠の恋歌が、どれほど切実な
情念をあらわしていても、それが彼らの現実の恋を直接にあらわす歌
であるとは解釈されないのが普通である。男性歌人にくらべて、
なぜか女性歌人の恋歌は現実の恋と結びつけられてしまうことが多いが、
題詠歌の世界ではそれは誤りである。式子内親王の題詠の恋歌も、
式子の現実の恋とは切り離して見るのが当然なのである。」
p.71
「「玉の緒よ……」は今は散佚した百首のうちの一首であり、
成立年代はわからない。……
式子の恋歌は、男歌も女歌もあり、強く屈折した調べもあれば、
やわらかく静かに流れる声調もある。自らの死を思う恋死の歌も
いくつもある。そのいずれかだけを、あるいは「玉の緒よ……」の
一首を、式子の実人生に当てはめて推測することは、題詠である
ゆえに自由に詠むことができた恋歌の世界とかけ離れてしまう。
題詠歌の中で、百首歌は、宮廷という空間の内にある和歌会・歌合
よりもさらに自由に自分の想念を羽ばたかせることができる場であった。
皇女という最も不自由な立場にいた式子が、百首歌の自由さを愛した
ゆえに、観念の中で自由にふるまえる百首歌をわがものとして、
百首歌を自分の舞台としたのではなかったか。」
p.79
「玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば忍ぶることの弱りもぞする
藤原定家は『百人一首』に、式子のこの歌を採入した。
正確には『百人一首』の原型とされる『百人秀歌』だが、
九十七首まで同じなので、ここでは『百人一首』としておく。
内親王(皇女)は百人中ただ一人である。女性歌人二十一人のうち、
ほとんどは女房であり、天皇家の女性は万葉時代の持統天皇と、
式子内親王だけであるから、式子内親王がここまでの長い和歌史を
代表する皇女歌人として、いかに際立った存在であったかがわかる。
『百人一首』では、百首のうち、[勅撰集の]部立から言うと、
恋歌は半分近くの四十三首を占める。定家は恋歌にかなり比重を置いて
撰歌した。しかも女性歌人に限って言えば、二十一首のうち十六首が
恋歌である。
けれども、題詠歌であってもはっきり男の立場で詠んでいる歌は、
式子の歌のほかにはない。定家は「玉の緒よ…」の歌が男歌である
ことを深く理解していたであろうが、あえてこの歌を入れた。
女性歌人による、恋する女を歌の主体とした嫋嫋とした恋歌が
並ぶなかで、この歌だけが異質な鋭さ、強さをもって屹立している。
定家は若い頃から仕えた式子内親王が、これほど激しい表現を選ぶような
精神を内包していることを深く感じ取っていて、畏敬の念を抱いていた
のではないか。」
p.120
https://note.com/fe1955/n/n8dfcbf3d6859
式子内親王(1149-1201)
田渕句美子(1957- )
『新古今集 後鳥羽院と定家の時代(角川選書)』
角川学芸出版 2010.12
『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』
KADOKAWA(角川学芸出版) 2014.2
平井啓子(1947- )
『式子内親王(コレクション日本歌人選 010)』
笠間書院 2011.4
馬場あき子(1928.1.28- )
『式子内親王(ちくま学芸文庫)』
筑摩書房 1992.8
https://www.facebook.com/tetsujiro.yamamoto/posts/676055679135741
昨日読み終わった本。橋本治 『古典を読んでみましょう (ちくまプリマー新書)』 http://bit.ly/1psnefs #bookmeter 筑摩書房...
Posted by 山本 鉄二郎 on Sunday, August 17, 2014
https://note.com/fe1955/n/n9cc4d3928d2c
https://note.com/fe1955/n/ne0e6e04a9227
『芸術新潮』2019年5月号
追悼 橋本治はなにを見たか。
大島弓子「橋本さんが我が家に!?」
山岸凉子「感性の鋭さと優しさと」
https://note.com/fe1955/n/nd68febc9004e
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
