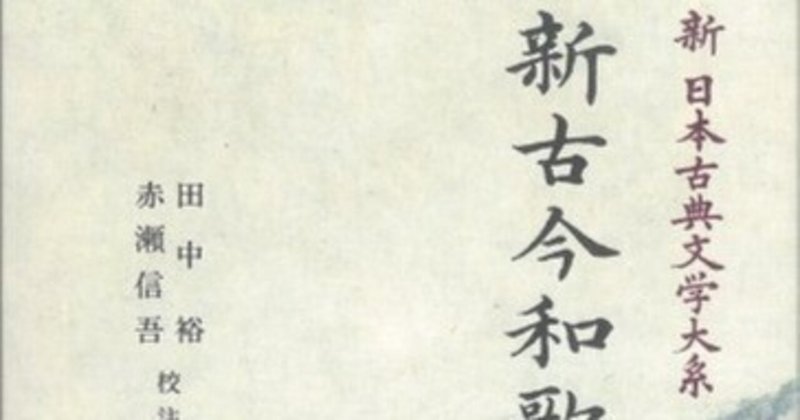
後鳥羽院宮内卿(ごとばのいんくないきょう、生没年不詳)『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』田中裕・赤瀬信吾校注 岩波書店 1992.1

田渕句美子『新古今集 後鳥羽院と定家の時代(角川選書)』
角川学芸出版 2010.12
https://note.com/fe1955/n/n8dfcbf3d6859
「『新古今集』に入集(にっしゅう)した歌数を見ると、
当代女性歌人は、
式子内親王が突出して多い四十九首、
俊成卿女が二十九首、
二条院讃岐が十六首、
宮内卿が十五首、
殷富門院大輔が十首、
[以下略]」
田渕句美子(1957- )
『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』
KADOKAWA(角川学芸出版) 2014.2
p.146「第三章 女性歌人たち 新古今歌壇とその後 二
後鳥羽院の革新 女房の専門歌人の育成」
https://yatanavi.org/rhizome/新古今和歌集
西行 94
慈円 92
藤原良経 79
藤原俊成 72
式子内親王 49
藤原定家 46
藤原家隆 43
寂蓮 35
後鳥羽院 35
俊成卿女 29
藤原雅経 22
藤原有家 19
源通具 17
藤原秀能 17
二条院讃岐 16
宮内卿 15
源通光 14
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『新々百人一首』新潮社 1999.6
「宮内卿 片枝さすをふの浦梨初秋になりもならずも風ぞ身にしむ
…
勅撰集の巻一のはじめの配列はすこぶる儀式的なものだが、
『新古今和歌集』巻第一春歌上は、
摂政太政大臣良経、
後鳥羽院、
式子内親王、
宮内卿とつづく。
その意味では、
彼女は後鳥羽院の歌道の師、
藤原俊成よりも重要な歌人だったのである。」
p.193「夏・宮内卿」
『草月』1978年6月号

田中裕・赤瀬信吾
『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』
岩波書店 1992.1
https://www.amazon.co.jp/dp/4002400115
後鳥羽院宮内卿(ごとばのいんくないきょう、生没年不詳)
鎌倉時代初期の歌人。
二十歳前後で夭折。
源具親(みなもとのともちか 生没年未詳 鎌倉時代初期の官人・歌人。和歌所寄人)の同母妹。
隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では和泉式部と番えられている。
新古今集初出(十五首)。
勅撰入集四十三首。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kunaikyo.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/後鳥羽院宮内卿
かきくらしなをふる里の雪のうちに跡こそ見えね春はきにけり
宮内卿
五十首歌たてまつりし時
新古今和歌集 巻第一 春歌上 4
「あたりを暗くして今日も降りつづく古京の雪中に、足跡は見えないが春は来たことだ。」
『新日本古典文学大系 11』p.21
建仁元年(1201)二月、老若五十首歌合。
なをふる里 旧年と変わらず「降る」意に「古里」を掛ける。古里は吉野の古京か。
跡こそ見えね 「春無跡至、争(いかでか)尋得」(藤原篤茂 新撰朗詠集「立春」)ともいうが、ここは降る雪に消されて春の足跡は認めにくい意。「跡」は人跡に擬したもの。
参考「雪深き岩のかけ道跡たゆる吉野の里も春は来にけり」(待賢門院堀河 千載 春上)。
立春の歌。
うすくこき野辺のみどりの若草に跡までみゆる雪のむらぎえ
宮内卿
千五百番歌合に、春歌
新古今和歌集 巻第一 春歌上 76
「あるいは薄くあるいは濃い野辺の緑の若草の上に雪の斑に消えた痕跡までが見えることだ。」
『新日本古典文学大系 11』p.39
建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 春二。
むらぎえ 消えた跡が斑に残っていること。残雪の「跡」ばかりか、消えた遅速も若草の色に反映している面白さ。
「若草」の歌。
花さそふ比良(ひら)の山風ふきにけりこぎゆく舟の跡みゆるまで
宮内卿
五十首歌たてまつりし中に、湖上花を
新古今和歌集 巻第二 春歌下 128
「花を誘って散らす比良の山風が吹いたのだな。漕ぎゆく舟の航跡がくっきりと見えるまでに。」
『新日本古典文学大系 11』p.54
建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首。
本歌「世の中を何に譬へむ朝ぼらけこぎゆく舟の跡の白波」(沙弥満誓 拾遺 哀傷)。
比良の山風 「比良山」は近江国の歌枕。陰暦二月にその山上より湖面に吹きおろす寒風。比良八講[毎年3月26日に行われる天台宗の行事「比良八講」の前後に吹く]。
忽ち消え失せるはかない譬えの航跡がまぎれず残るほどに湖上に花の散り敷いた大観。
参考「桜さく比良の山風ふくままに花になりゆく志賀の浦波」(藤原良経 千載 春下)。
名所に寄せた「山下の落花」の歌。
逢坂(あふさか)やこずゑの花をふくからにあらしぞかすむ関の杉村
宮内卿
関路花を
新古今和歌集 巻第二 春歌下 129
「逢坂山を見れば、木末の花を吹くと同時に山風は霞となって立ちわたるよ。関の杉群を覆い隠して。」
『新日本古典文学大系 11』p.54
建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首。
逢坂 近江国の歌枕。
こずゑの花 木の先端の花。高い杉群を覆うことを言うための趣向。
あらしぞかすむ 122「山ふかみ杉のむらだち見えぬまでをのへの風に花のちるかな」のように山上から吹きおろすのではなく、杉群に立交わる桜を水平に吹くのである。霞むはずのない嵐が霞むという気持ち。
詠歌一体[えいがいつてい 鎌倉初期の歌論書。1巻。藤原為家[定家の子]著。弘長3年(1263)または文永7年(1270)ころの成立か。]は制詞[せいのことば 歌学用語 歌を作るときに使用を許されない詞(ことば)]とする。
関の杉村 この関路の知られた景物。
花の嵐の白と杉群の青の対照も趣向であるが、嵐につれて空間を埋め尽す豪華な落花の趣を情緒に頼らず知巧的に構成しようとする手法に、
前歌121 藤原良経「花さそふ比良の山風ふきにけりこぎゆく舟の跡みゆるまで」と同様特色がある。
名所に寄せた「山下の落花」の歌。
柴の戸をさすや日かげのなごりなく春くれかかる山のはの雲
宮内卿
山家暮春といへる心を
新古今和歌集 巻第二 春歌下 173
「柴の戸を鎖すと今まで射していた光はあとかたもなく、同時に春もすっかり暮れようとする、あの山の端の雲よ。」
『新日本古典文学大系 11』p.66
建仁元年(1201)三月十六日、土御門内大臣家影供歌合。内大臣は源通親。
暮春 春の末。季春と同じく三月の異称にも。
柴の戸を 戸を「鎖す」と日が「射す」と掛けるべきところ。柴の戸 雑木の枝折戸で庵のさま。さすや 「や」は詠嘆。山のはの雲 最後の日のあり所を見せている山の端の夕焼雲。三月尽(さんがつじん・やよいのはて・やよいつくる 三月末日)の日暮れはまた春の暮でもあるが、両意を重ねたのが第三・四句。それで「なごりなくくれかかる」の主語として「日かげ」に「春」を添加した形。参考「入日さす山の端さへぞ恨めしき暮れずは春のかへらましやは」(源雅通 千載 春下)。
「三月尽」の歌。
片枝さすをふの浦なし初秋になりもならずも風ぞ身にしむ
宮内卿
千五百番歌合に
新古今和歌集 巻第三 夏歌 281
「片枝を伸ばしているおうの浦の梨の片影は、初秋になったともならぬとも分からないが、風はまさしく身にしみることだ。」
『新日本古典文学大系 11』p.95
建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 夏三。
本歌「をふの浦に片枝さし覆ひなる梨のなりもならずも寝て語らはむ」(古今 東歌 伊勢歌)。
をふの浦 志摩国の歌枕。
なりもならずも その片陰は涼しく、すでに初秋の気配であるが、他の片側は依然夏なので、思い惑うさま。「梨がなる」と「秋になる」を掛ける。
「晩夏の涼」の歌。
新古今 秋上の巻 356-368 は、良経・慈円・寂蓮・西行・定家・宮内卿・式子内親王と続く、新古今和歌集オールスターズとでも呼びたい豪華メンバーです(俊成・俊成女・後鳥羽院がいませんけど)。
思ふことさしてそれとはなきものを秋のゆふべを心にぞとふ
宮内卿
秋の歌とてよみ侍(はべり)ける
新古今和歌集 巻第四 秋歌上 365
「物思いは特にこれといってないのに秋の夕のこの寂しさは何故かとわが心に問いただすことだ。」
『新日本古典文学大系 11』p.118
理由のないこの悲しみを怪しんで、改めて自問するのである。
「秋夕」の歌。
心ある雄島(をじま)の海人(あま)のたもとかな月やどれとはぬれぬものから
宮内卿
八月十五夜和歌所歌合に、海辺秋月といふことを
新古今和歌集 巻第四 秋歌上 399
「ああ、雄島の海人の情趣を知る袂よ。海人は月が映るようにとことさら潮に濡れているわけではないのに。」
『新日本古典文学大系 11』p.126
建仁元年(1201)八月十五夜撰歌合「海辺秋月」。
本歌「松島や雄島の磯にあさりせし海人の袖こそかくはぬれしか」(源重之 後拾遺 恋四)。
雄島 陸奥国の歌枕。宮城県松島湾。和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書]「まつしま」の条に「をじまなどつづく」とある。
たもと 「そで」との区別は明らかでなく、当時は「同じ事」(顕昭・古今集注四)とされている。
心なき海人の袂に月の映る美しさに堪えかね、袂を有情化して讃嘆したもの。
「海辺の秋月」の歌。
まどろまでながめよとてのすさびかな麻のさ衣月にうつ声
宮内卿
和歌所歌合に、月のもとに衣うつといふことを
新古今和歌集 巻第五 秋歌下 479
「「まんじりともせずに月を眺めるがよい」と告げるすさびなのだな。麻の衣を月下に打つ音よ。」
『新日本古典文学大系 11』p.148
建仁元年(1201)八月十五夜撰歌合。
すさび 興にまかせてするわざ。
麻のさ衣 麻衣。里人の常の着用。
「すさび」は作者自身の折節の感興を心なき里人の上に移し入れたもの。
「擣衣」の歌。
月をなほ待つらんものか村雨のはれゆく雲の末のさと人
宮内卿
雨後月
新古今和歌集 巻第四 秋歌上 423
「月を今も待っていることであろうか。村雨が晴れるにつれて晴れてゆく雲がまだかかっている彼方の里人は。」
『新日本古典文学大系 11』p.132
建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首。
村雨 激しい俄か雨。季節を問わない。
こちらでは雲がはれて名月を仰いでいるのである。
「秋月に末を結んで月前の遠望」の歌。
霜をまつまがきの菊のよひの間におきまよふ色は山のはの月
宮内卿
五十首歌たてまつりし時、菊籬月といへる心を
新古今和歌集 巻第五 秋歌下 507
「霜の来るのを待っている籬の白菊が、宵の間に、もう霜が置いたかと見まちがうばかり見せている色は山の端に出た月が映るのである。」
『新日本古典文学大系 11』p.155
建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首。
霜をまつ 霜に逢って色変りしようと待ちうけている残菊。
「菊のうつろふはまづ赤くなり、後に紫になるなり。のちまた紫の色も朽ちぬれば三度うつろふとなり」(拾遺愚草抄出聞書[室町後期、東常縁による定家家集の注釈書])。
「まつ」「よひの間」は縁語で、宵の間に男を待つ女に見立てる気持ちがある。
まがき 竹木で粗く編んだ垣。
おきまよふ 白々と冷やかに射す月光。
参考「心あてに折らばや折らむ初霜のおきまどはせる白菊の花」(凡河内躬恒 古今 秋下)、
「さえわたる光を霜にまがへてや月にうつろふ白菊の花」(藤原家隆 千載 秋下)。
「ま」音を重ねたのも技巧で、快い。
「菊」の歌。
立田山あらしや峰によわるらんわたらぬ水も錦たえけり
宮内卿
百首歌たてまつりし時
新古今和歌集 巻第五 秋歌下 530
「立田山は、峰に吹く風が弱まったのであろうか。人の渡らない流れも途中で錦が切れているよ。」
『新日本古典文学大系 11』p.161
正治二年(1200)[後鳥羽]院後度百首「紅葉」、三句「かよふらむ」。
本歌(一)「立田川もみぢ乱れて流るめり渡らば錦中や絶えなむ」(古今 秋下 読人しらず)、
(二)「嵐ふくみむろの山のもみぢ葉は立田の川の錦なりけり」(能因 後拾遺 秋下)。
立田山 大和国の歌枕。竜田本宮の西方の山地で大和・河内・難波を結ぶ竜田道が通っていた。
よわるらん 嵐の弱まっている間は紅葉が散り止んでいたという趣向。
わたらぬ水も 詠歌一体[えいがいつてい 鎌倉初期の歌論書。1巻。藤原為家[定家の子]著。弘長3年(1263)または文永7年(1270)ころの成立か。]は制詞[せいのことば 歌学用語 歌を作るときに使用を許されない詞(ことば)]とする。
本歌(一)の「渡らば」、(二)の「嵐ふく」の逆をゆく趣向の興。
「山の紅葉」の歌。
唐錦秋のかたみやたつた山ちりあへぬ枝に嵐吹くなり
宮内卿
五十首歌たてまつりし時
新古今和歌集 巻第六 冬歌 566
「唐錦、この美しい秋の形見を裁とうというのか、立田山ではまだ[紅葉が]散りきらずに残っている枝に嵐の音がするよ。」
『新日本古典文学大系 11』p.172
建仁元年(1201)二月、老若五十首歌合。
本歌「唐錦枝に一むら残れるは秋のかたみをたたぬなりけり」
(遍昭 拾遺 冬)。
唐錦 中国渡来の高価な錦。紅葉の譬喩(ひゆ)で、下の「裁つ」の縁語。
たつた山 大和国の歌枕。裁断する意の「裁つ」、絶えるの意「絶つ」に掛ける。
ちりあへぬ枝 紅葉が散りきらない枝。
本歌を裏返した趣向。
「落葉を山に結ぶ」歌。
聞くやいかにうはの空(そら)なる風だにも松に音(おと)するならひありとは
宮内卿
寄風恋
新古今和歌集 巻第十三 恋歌三 1199
「お聞きですか、いかがです。上空を吹く気まぐれな風さえも松には訪れて音を立てる習性があるということを。」
『新日本古典文学大系 11』p.354
建仁二年(1202)九月十三日、水無瀬恋十五首歌合 七十一番左勝。
同年、若宮撰歌合。
聞く 「風」「音する」と縁語。
うはの空 上空とあてにならない意とを掛ける。
松に音する 「松」に「待つ」を掛け、「音する」は「おとづる」と同じで、音を立てる意と訪れる意とを兼ねる。
待てど訪れない男をなじる歌。
「風に寄せて待つ恋」。
竹の葉に風ふきよわる夕暮(ゆふぐれ)のものの哀(あはれ)は秋としもなし
宮内卿
題しらず
新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 1805
「竹の葉に吹く風が弱まってきた夕暮時のこのあわれさは、秋だからというのではない。」
『新日本古典文学大系 11』p.525
建仁元年(1201)二月、「老若五十首歌合」二百七番右負。
参考「わが宿のいささ群竹ふく風の音のかそけきこのゆふべかも」(大伴家持 万葉集十九)。
「秋は夕暮」といわれる定論を否定するのではなく、秋よりも上句の情景――日も暮れて来、竹の葉のそよぎもようやく静まってきた、そのあわれさを強調しようとするのが眼目。
「秋風」に寄せる雑歌。
後鳥羽院宮内卿(ごとばのいんくないきょう、生没年不詳)
鎌倉時代初期の歌人。二十歳前後で夭折。
源具親(みなもとのともちか 生没年未詳 鎌倉時代初期の官人・歌人。和歌所寄人)の同母妹。
隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では
和泉式部と番えられている。
新古今集初出(十五首)。
勅撰入集四十三首。
読書メーター 和歌の本棚(登録冊数57冊)
https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091215

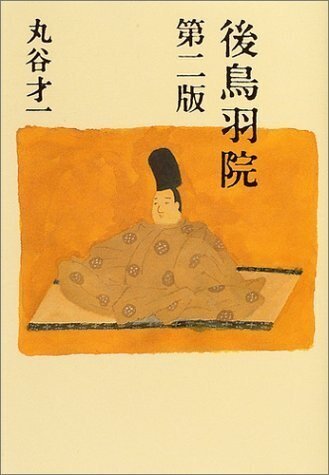
https://note.com/fe1955/n/nce8e9a0c3675
後鳥羽院(1180.8.6-1239.3.28)
『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』
田中裕・赤瀬信吾校注
岩波書店 1992.1
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9
『後鳥羽院 第二版』ちくま学芸文庫 2013.3
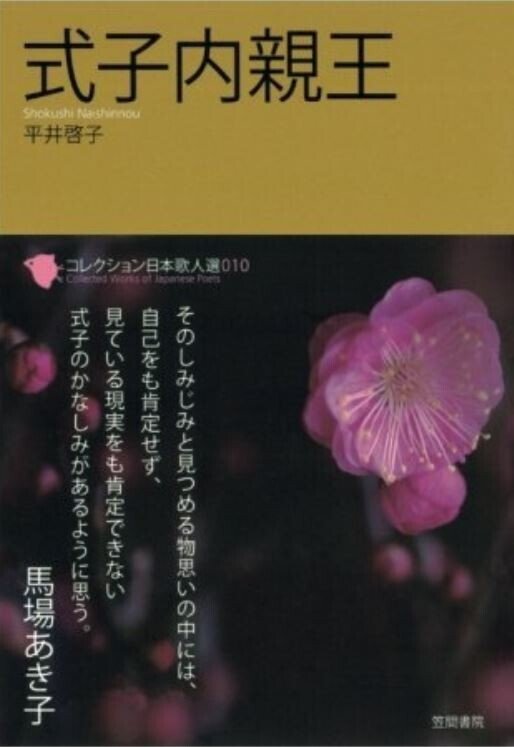
https://note.com/fe1955/n/n8dfcbf3d6859
式子内親王(1149-1201)
田渕句美子(1957- )
『新古今集 後鳥羽院と定家の時代(角川選書)』角川学芸出版 2010.12
『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』KADOKAWA(角川学芸出版) 2014.2
平井啓子(1947- )
『式子内親王(コレクション日本歌人選 010)』笠間書院 2011.4
馬場あき子(1928.1.28- )
『式子内親王(ちくま学芸文庫)』筑摩書房 1992.8

https://note.com/fe1955/n/n56fdad7f55bb
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『樹液そして果実』集英社 2011.7
『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9
『恋と女の日本文学』講談社 1996.8
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
