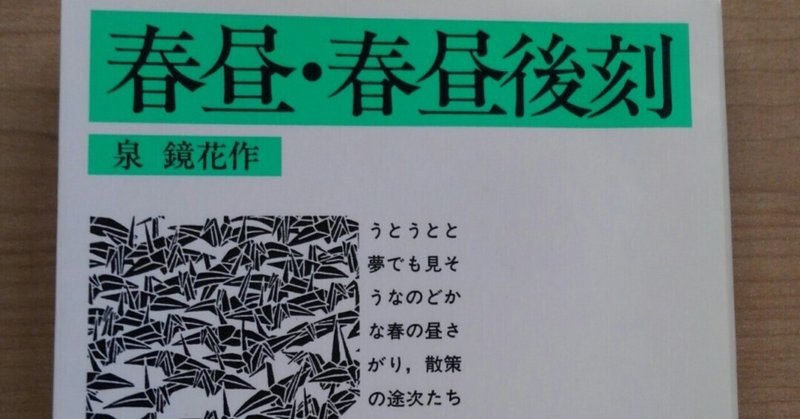
風の吹くまま、気の向くまま に 5 (泉鏡花『春昼・春昼後刻』から)
現実なのか、夢幻なのか、泉鏡花の美しい情景描写の中で物語は展開します。のどかな春の昼下がり、主人公の散策士が聞きかじり、垣間見た世にも妖しい、この世じゃ結ばれぬ男女の恋の話です。
この小説を読んでみて、話の内容もさることながら、文章力と言おうか、物語全体が一枚の絵になったように美的に表現されていると感じました。文字で描いた絵と言おうか、微細なところまで作者は丹念に描き上げます。
余りにも平穏な、うとうとしそうな春の陽気だからこそ、それと裏腹にどこかに妖しの気配が出番を待っているのではと不安に思うこともあるのです。寂しいと思う人もいるのです。その予兆は、青大将の出現です。
主な作中人物は、「散策士」、「畑の親仁」、「出家」、「庵室の客だった若い男」、「玉脇みを」、「玉脇斉之助」それに旅芸人の「二人の子供」となっています。
物語は、久能谷の観音堂仮庵室に宿泊していた青年が、有夫の美しい女性「玉脇みを」に恋い焦れ、海に投身するというものです。後編では、海辺の遊びで溺れた角兵衛獅子の下の子と共に、みをの亡骸が一年前の青年が上がった海岸の同じ岩の上に打ち上げられたというのです。
海に飛び込む前に、庵室の青年が見た夜の幻影があります。庵室の向こうの山の中から祭囃子が聞こえます。青年はそれにひかれ、山中に分け入ります。窪地にうずくまる者が拍子木をたたき、横穴の幕が開き、そこにはさらに小さな横穴が三十五十とあり、なかに婦人が頬から血をたらしたり、縛られたり、立ったり、座ったり、緋の長襦袢ばかりの者とか色々おります。
ぞっとしても逃げられずにいると、拍子木が鳴り、玉脇斉之助の美しい御新姐が舞台に上がりました。そして青年の後ろから舞台に上がり、御新姐と背中合わせに座った者がおります。何と自分だったのです。その自分が、後ろ向きに惚々と御新姐の後ろ姿を見ていると、指先で、薄色の寝衣の上に△、▢、○と書いたのです。それやこれやでそこから夢中で駆け戻ります。
みをの境涯は、物語の中では明らかにされていません。庵室の青年の幻影の中で暗示されているように見受けられます。これは青年の一方的な思い込みだったのでしょうか。青年は二、三日引籠っていましたが、あの晩のような芝居をまた見たくなったのかいなくなり、あの場所、蛇の矢倉で木樵が見かけたとの知らせがあったものの、戻っては来ませんでした。
この青年の話を出家から聞いた後、帰路に就いた散策士は、往路で蛇が近くの二階家に入るとの伝言を頼んだ老農夫に、御新姐が土手でお礼を言いたくて待っていると告げられます。
道はそこしかないし、知らんふりで通り過ぎようとすると、声をかけられお礼を言われました。散策士は及び腰で応対しますが、美しい御新姐に平静ではいられません。そこからの二人のやり取りは絶妙ですが、話はどうどう巡りでかみ合いません。
御新姐は、散策士が恋しい、愛しい人に似ているといい、後を追って死ぬか生きるか悩みの心情を婉曲的に切々と訴えます。いつの間にか散策士の心にもその妖艶、華美な御新姐の全体に共振し、心情が移ってしまいます。
その間、御新姐は、散策士の求めに応じ、手に持っていたノオトブックの中身を見せます。それには、○と▢と△が乱雑にびっしりと書き込まれています。散策士は見るなり蒼くなります。丸が海、三角が山、四角が田圃、または、丸い顔、四角い胴で三画に座っている、あるいは、今戸焼の姉様でも袴をはいた殿様でも思いようでどれでもよいといいます。
ちょうどその場に来合わせた旅芸人、二人の子供との因縁も語られますが、後刻、散策士は、海辺で遊ぶ二人の子供を見つけ、下の子が裸で海に入り遊び、波にのまれるのを目撃します。
だいぶ端折りましたが、この物語のどうにもならない男女の恋情の軌道、懊悩、深淵、そして異界にも踏み込む妖しの景色などの雰囲気の一端を感じ取っていただけたでしょうか。前編の散策士は、もっぱら出家の語りの聞き役ですが、後編では、物語の中に立ち入り、美しく妖艶な御新姐と相対します。まかり間違えば、恋の深淵に落ち込みかねないのですが、出家の話で備えがあったため、危ういところで踏みとどまったと感じました。いずれにしても、男女の恋情は、古今東西永遠の課題だし、人の世には、形は変えても常在するものと思いました。
参考文献:泉鏡花著『春昼・春昼後刻』岩波書店1991年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
