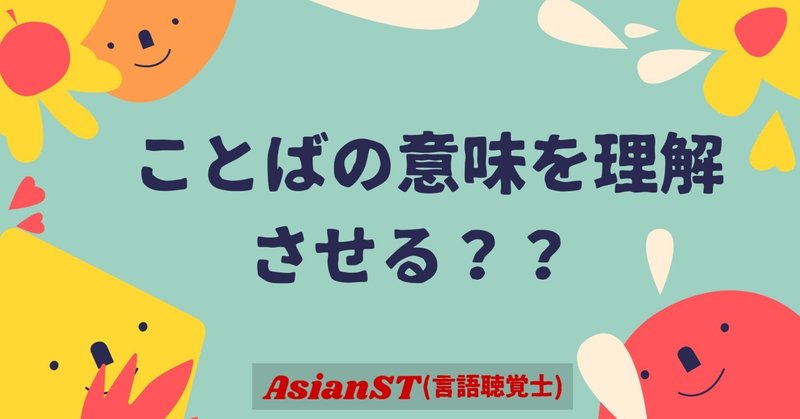
ことばの意味を理解させる??
こんにちは、AsianSTです!😊
今週は、台風6号の影響で仕事が休みになったり、停電が続いたりで
ネットもなかなか使えず困りました😓 *AsianST=沖縄県在住

ようやく台風も去ったかと思ったら、また引き返してきて
昨日金曜日の夕方から暴風警報発動…、雨も凄いです。

今のところ電気だけはつながっているのが救いです(❁´◡`❁)。
それはさておき、今回は『ことばの意味を理解させる??②』
をテーマにお届けします!
6月に行われた、日本言語聴覚学会では
8年振りに発表させてもらったのですが、
特別講演で、慶応義塾大学の今井むつみ先生が発表されていた
「思考力と学力の基盤となることばの力」の中で、
共感し勉強させてもらった内容がありましたので、
今回は、そこを抜粋しながら紹介させてもらいます。
「大人はこどもにことばを教えることができるか」
という重要な問いかけから始まります。
そして
”うさぎ”という単語を例に、目の前にいる動物がうさぎであることを
こどもに伝えることができるか? について説明されていきます。
この白い生き物がうさぎである、ということは伝えらるかもしれない。
しかし、本当はケージの中にいる生き物ととらえているかもしれないし、
白い生き物のことと、とらえている可能性もある。
うさぎ、という言葉をこどもが使うことができるためには
目の前にいるケージに入ったうさぎが分かっただけでは不十分…。
うさぎに似た動物や、耳が垂れ下がった状態のうさぎも
含めて、どの範囲までがうさぎなのか、
また、どこでうさぎと、うさぎでないものの境界が
引かれるのかまではこどもに教えることができない。
どこまでがうさぎなのかは、こどもが自分で考えて、
みつけていくしかない。
つまり、そのことばをとりまく他のことばとの区別を
こども自身がみつけていく。
たとえ大人がこどもに
辞書の意味を暗記させたとしても、
また単語と絵を結び付けたとしても、
使えることば、語彙は生まれない。
こどもは自分でことばの意味を考え、他のことばと関連づけながら
考え、ことばの意味をつかんでいく。
私は、去年の12月に『ことばの意味を理解させる??』
という内容のブログを書きました。
その時は、知り合いから
「こどもにことばを教えるには、どうしたらいいでしょうか?」
と質問を受けました。
私は ”言葉の意味を理解させる”
というのは教える側がそう思っているだけで、
実際は、こどもが自らの意思で能動的に理解している
ことを書きました。
こどもは周囲の大人から教えてもらいながら
自分でもさまざまな経験をしていきながら
能動的に、ことばの意味理解をより深めていきます。
それは、もちろんそのことばをとりまく
他のことばとの区別ができることや
どこが共通し、どの部分が異なるのかが、分かっていくことも含みます。
「教えたから、こどもは分かった筈、理解したはず」
というのは大人側がそう思っているだけで、
実際にそのことばについてどこまでわかっているのか、
こどもに話してもらったり、そのことばを使っている様々な場面を
みないことには、こどもがどう感じていて
どこまで本当に理解しているのかは分かりません。
「こどもが言葉の意味を理解するためには
どういった支援をすればよいのか?」
といった考え方で、適切な支援を追求していくことが大切ですし、
私自身、そこは意識して取り組んでいることでもあります。
それでは
今回も最後までお読みいただきありがとうございましたm( _ _ )m
それではまた次回お会いしましょう(*^▽^*)!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
