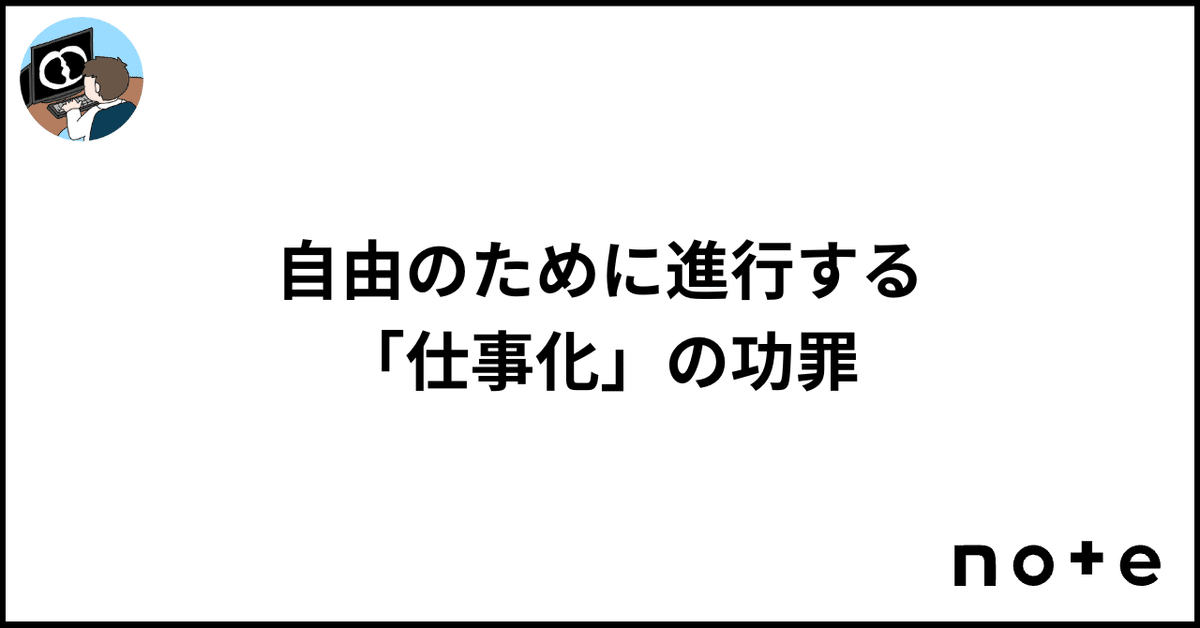
自由のために進行する「仕事化」の功罪
続きの続きを行きますよ。
前2回はこちら。
自由とは「理由や目的を問われないこと」という側面があり、自由を人々が求める自由主義社会では理由や目的を問われない効果を持つ「お金」というツールに人気が集まるよねという話までしました。
今回は、人々が理由の説明責任を逃れようとした結果起きているもう一つの現象について見ていきます。
それが何かと言うと「仕事化」です。
お金を払えばそもそも理由や目的を問われないという自由が得られるわけですが、もう一つの戦略としてあるのが、理由を聞かれるのは受け入れつつも、とりあえず最強の理由を提示してさらっとかわしてしまおうというものです。それが「仕事」なんですね。
別にそんな珍しい話をしようとしてるわけではありません。
私たちが何か気が進まないアポイントをせがまれた時に「あー、申し訳ない。その日は仕事が入っていて」と言ったら相手は「仕事なら仕方ないかあ」と引き下がるしかありません。しかし、これが「あー、その日はゲームの発売日で」と言ったら、「じゃあその時間を私に割いてよ」と相手はムッとしてしまうでしょう。(これは初回にとりあげた有給休暇の理由の格付け差異の話とも近いですね)
あるいは飲み会に行くのをパートナーに咎められた時に「これも仕事の付き合いのうちなんだよ」と言って「仕事」を理由に強行するのは定番です。
「プロとして学会に行くのは仕事のうち」と言えば、勤務先から出張費等々を出してもらいながら、学会参加のついでに、日本各地域に年変わりで旅行に行けて、美味しいものを宴会で食べることも可能です。
このように「仕事」というのは他人に説明する理由として非常に強力かつ定番で、ある種ジョーカー的な強さがあります。
仕事に勝てるのは急病や身内の不幸ぐらいですが、事前に分かるものではないという性質や、非日常的イベントであるために多用してると嘘がバレバレというのもありますし、そもそもそういう嘘は自他ともに倫理的に傷つけるので、理由としての便利さや正当性はありません。
だから、日常的に用意できる理由としては「仕事」が最強なんですね。
とはいえ、流石に仕事の内容と違いすぎたり豪華すぎると建前としても成り立ちにくくなります。
視察という名目でエッフェル塔前で記念撮影をしていた政治家が、それは仕事の範疇なのかを問われて批判の的になったことも最近ありましたね。
学会についてもコロナ禍が(政治的に)落ち着く前に豪華な懇親会を催していた外科学会が炎上する騒ぎもありました。
だから、決して「仕事だから」という理由が万能というわけではありません。しかしながら「仕事だから」が有力な理由であるが故に、なんとかして「これは仕事の範疇だ」と言い張ろうと皆が努力し始める現象、それが「仕事化」です。
イメージとしては経費を認めてもらうのに近いですね。「これは仕事で必要な物品だから経費で落としました」と言うのと同じで、「この活動は仕事で必要な活動なので」と、仕事として認めてもらう範囲をできる限り増やそうとする力学です。
ここで問題になるのが、どういう職業のどういう仕事を担当しているかというところです。先ほど仕事の内容と違いすぎる活動では仕事として認めてもらえないという話をしましたが、つまりそれは仕事の内容によって仕事として認められやすい範囲が変わると言うことでもあります。
たとえば、吉野家で牛丼販売を担当している者が仕事中にSNSを眺めていたら「仕事をサボって何やってんだ」と叱られますね。牛丼販売業務でSNSを眺める合理的な理由が乏しいからです。
ところが、これがオフィス勤務のマーケティング担当者であれば、SNSを眺めているのをとがめられても「SNSの最新トレンドをチェックしてたんです」と言えば、(もちろん限度はあるものの)言い分としては成り立ちます。
つまり、仕事として認められる範囲が、職業や職種によって異なってくると言うわけです。
さて、ここでは、人々が自分の自由を求めるために「仕事」という理由を活用しようとしているという前提でした。となると必然的に起きるのは、仕事として認められる範囲が広い、すなわち自己裁量権が大きい仕事を人々が求めるという現象です。もっと言えば、それまでは仕事とみなされてなかった活動までも仕事にしてしまうことも起きています。
実際、プロセスや生産性を逐一管理監視され仕事の内容が固定化される現場スタッフよりも、(比較すれば)自由度が高いマネジメント層やクリエイティブワークの方が人気が高まってるのは否定できない現象でしょう。
書籍『タイムバインド』の中でも、仕事の範疇で各地に出張し高級ホテルに泊まり美味しいものを食べる生活をしているエグゼグティブたちが「私は仕事が大好きだ」と嬉しそうに語ってる姿が、「そりゃ面倒ごとを秘書や家族に任せてそれだけ自由にできたらそうでしょうね」という皮肉的な目線をもって描かれています。
また、YouTuberやゲーム配信者なんて、まさに今までは仕事でなかったものが(狭き門ではあるものの)仕事として成り立つようになった象徴的な存在でしょう。ここまで来ると、極論何をしようとも仕事として言い張れてしまうかもしれません。そういう何でも仕事と言えそうなところが、自由の象徴として子どもたちの憧れの職業となってる大きな一因であるでしょう。
従って、総じて見ると「仕事」とみなされる範囲が社会全体としても広がってると言えます。
NHK『欲望の資本主義2022』での斎藤幸平とセドラチェクとの対談でも、現代では仕事の内容が「娯楽」となってきていることの指摘がされています。
斎藤 そのとおりです。私たちは、かつては週6日働いていましたが、今では、週休2日は当たり前になりました。それは規制したからです。でもなぜ、もっと進歩しないのでしょう。なぜ、労働時間を週30時間や20時間に短縮しないのでしょう。ましてや、デヴィッド・グレーバーは意味のない「ブルシット・ジョブ」が増えていると述べるくらいなのに。
セドラチェク それは、仕事自体が進歩しているからではないでしょうか。私もあなたも、今、働いていますね。ですが、一方で、暖かい部屋の中で、何の危険もなく、我々は議論を楽しんでもいます。思うに、これが仕事自体に起きていることです。大半の仕事が、中世の視点から見れば「娯楽」になっています。
セドラチェクは「仕事が娯楽化している」という表現ですが、これは「娯楽が仕事化している」と見ることもできるでしょう。繰り返しているように、仕事とみなされる方がつべこべ言われない自由を得ることができるからです。私たちは自由のために仕事を作る。
だから、次々と人間の活動が仕事と化しています。これが江草が「仕事化」と読んでる現象のゆえんです。
似た名称で医療社会学ではよく知られた概念として「医療化; medicalization」というものがあります。
雑に一言で言えば、それまで医療の対象とみなされてなかった様々な行動や嗜好に病名が付き治療対象としてみなされる現象のことを言います。ゲーム依存症とか発達障害とかはそういうところがありますね。「医療化」には様々に功罪の指摘がされていて議論があるところですが、とにかくも全般着実に進んでいるところがあります(なお、同性愛は逆に「脱医療化」を果たしています)。
江草的には「仕事化」も「医療化」と同様に様々な功罪があるだろうと考えています。何でも仕事として言いやすくなったことで、ある意味人々の自由は拡張したと言えます。クリエイティブな発想で仕事そのものをうまい具合に創り出しさえすれば、各人思い思いの自由を得ることができるのですから。
ただ、それは、逆に新しく作り出された仕事は良くても、古くからあって役割が固定的となってしまってる仕事では自由が得られ難いことの裏返しでもあります。現場スタッフ的なエッセンシャルワークは歴史も古く、往々にしてそういう「仕事だから」メソッドが使いにくいんですね。だから、不自由で窮屈な閉塞感が慢性化しています。
そして、「仕事化」はどうしても残り続ける家事労働などの「仕事以外の活動」の立場がどんどん弱くなると言うことでもあります。出張旅行や宴会が「仕事だから」とその自由が担保される一方で「仕事じゃないんだから我慢しろ」と劣位の立場に押し留められるからです。(もっとも、家事労働の外注化もどんどん進んでおり「仕事化」の波は着実に訪れていますが)
そうなると、こと自由主義社会においては、いかに不自由な家庭を脱して、裁量権のある仕事の名目を得るかが、人々の自由の追求の勝負所になってしまい、古い仕事や仕事外の活動が打ち捨てられていくことになります。
「医療化」が必ずしもいいことばかりではないように、そんな「仕事化」も本当に皆が幸せな道なのかどうかは今一度考えられるべきところでしょう。
というわけで、以上、「自由とは理由や目的を問われないこと」シリーズの「仕事」編でした。まだまだ話は広げられそうですが、今シリーズはとりあえずこの全3回で一旦〆ることにいたしましょう。
しかし、「仕事化」って検索しても意外と出てこないですね。英語だとworkizationとでも呼ぶのかと思ったけれど、なんか引っ掛かりません。
絶対、江草以外にも誰か言ってる気がするんですけどねえ。
江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。
