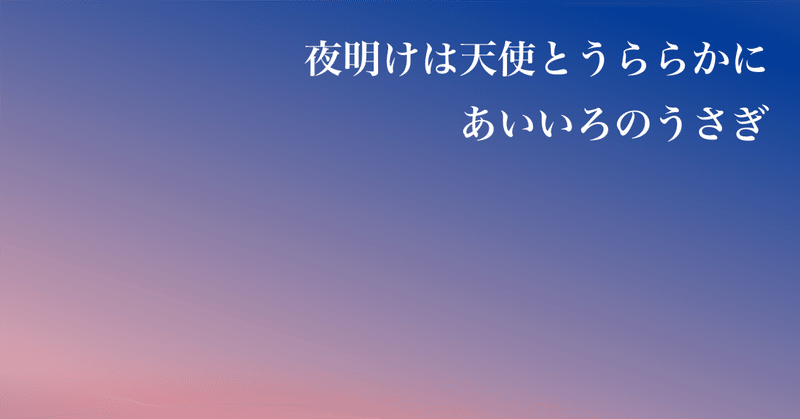
夜明けは天使とうららかに 3-1
第三章
春休みが終わって、最初の登校日になった。今日は始業式があるくらいで、午前中で帰れる。
僕は通学路をリセと二人で歩いていた。
学校に行く時はいつもそうだけど、通学中にリセと話せないのは少し不便だった。話しながら学校に行ければ少しは気が紛れるんだけど。
けれど、リセが隣にいてくれることで、僕が抱える緊張が何パーセントか減っているのも確かだった。
学校に辿り着いて、僕は自分のクラスを確認する。と言っても僕は事前に三組だって聞いてたけど、一応。
自分の名前が四年三組の表の中に入っている事と、そこに江藤君の名前が無い事、担任の先生が去年と同じであることを確認する。
息を吐いて、吸って、また深く吐く。
結局、僕は教室に戻ることにした。
正直、まだ見ぬクラスメイトたちのことも、クラスの雰囲気も、どうなっているのか分からなくてすごく怖い。でも、今日は始業式しかないようなものだから、それだけ教室で参加してみよう、と思ったのだ。ダメだったらまた別室登校すればいい。リセやお父さん、お母さんとそう約束した。
教室は三階の端っこで、ドアは開きっぱなしだった。もう何人か固まって喋っているのが見える。
前に進む勇気が出なくて教室を少し遠い所から見ていたら、リセが手を握ってくれた。リセの顔を見ると、いつも通りふわりと笑っている。僕はまた深く呼吸をして教室の中へ踏み出した。
自分の席を探さないといけない。黒板に書かれている座席表から名前を見つける。真ん中の列の前から二番目。
席に移動しようとして後ろを振り向いた時、ヒソヒソ話されているのに気づいた。
「あれ榊じゃない?」
「わ、ほんとだ。不登校になったんじゃなかったの?」
「なんかそうじゃないらしいよ。他の教室にいたらしい」
「えーそれって授業受けてないのに学校来てたってこと?」
「私はよく知らないよ。本人に聞いてみれば?」
「それはないわ」
笑いあっている女の子二人は、去年同じクラスだった子たち。僕は、あの子たちが悲鳴をあげたのを覚えている。僕に触れた江藤君が彼女たちに近づいた時のこと。
直接的に悪口を言われているわけじゃないけれど、好奇の目で見られていることは感じた。
席に着くと、あの子たちの周りに女の子が集まってきて話が更に広がっていく。
「ねぇねぇ、あの子不登校だったの?」
「不登校ではないらしいよ。学校は来てたけど教室には来てなかった」
「なんで?」
「さぁ? 江藤に遊ばれてたから逃げたんじゃない?」
「ゆーて一日とかだったけどね。普通そんなすぐ先生に言うかな?」
「チクリ魔だったりして」
笑い声が耳に刺さる。なんだか上手く呼吸ができない。わざと僕に聞こえるように話している気さえする。
「菖太さん、無理に教室にいる必要はありません。先生方は事情を分かってくれます」
リセがそう言ってくれたけど、頭の中にはさっきの女の子達の言葉がこだまする。
『逃げたんじゃない?』
それは、その通りのことで、僕はあの教室から、江藤君から逃げた。でもあの言い方は事実を言っただけじゃない。僕のことを馬鹿にしているんだってすぐ分かった。
ここで僕が教室を出て行ったら?
あの子たちはまた僕の話題を持ち出すだろう。あんな風に、笑って馬鹿にするんだろう。
……僕はこのままずっと、逃げ続けるんだろうか。僕はこのままずっと、教室に通えないままで、通ったとしても後ろ指をさされるのだろうか。
リセの声すら遠ざかっていった、その時だった。
「なぁ、話してること全部聞こえてるぞ」
大きな声が響いた。
「そんなデケェ声でつまんねぇ話するなよ。性格悪いぞ」
教室がシンと静まり返る。
声の主は僕の後ろで陰口を言っていた女の子達の方を真っ直ぐに見ている。女の子達はばつが悪そうに立ちすくんでいる。
女の子達の様子を見ていた声の主は僕の方を振り返って急に問いかけてきた。
「お前、榊? 今の全部聞こえてたよな」
何と言えば良いか分からなかった。その子は初めてクラスが一緒になった男の子で、面識もなくて、でも圧がすごい。
「ここで嘘つく必要ねぇから正直に答えろよ。あいつらの声聞こえてたよな?」
本当に聞こえていたから慌てて頷いたけど、聞こえてなかったとしても頷いてしまいそうなくらいの語気の強さだった。
彼はまた女の子達の方を向いて言う。
「お前ら、謝れよ」
女の子達が今度は聞こえない声でヒソヒソ話している。突然のことに戸惑っているみたいだ。
だけど。
「聞こえてんだろ。さっきのお前らの話、俺まで嫌な気分になった。本人だったら尚更だろ。それとも何、わかんねぇの?」
彼は強く言いつける。
「……ごめん」
女の子達はぽつりぽつりと謝ってそそくさと教室を出て行った。
男の子は大きくため息をついて僕の方を見る。
「……悪いな、あんな謝らせ方しかできなくて」
僕は必死に首を横に振る。まだ今は驚きの方が強くて状況をよく飲み込めない。
「お前、榊、だったよな。名前は?」
「しょ、菖太」
「そっか。俺の名前はあれ。右の列の上から二番目」
言われて黒板を見てみると、そこには『朝宮隆聖』と書いてある。
「あさみや りゅうせい。なあ、お前のこと菖太って呼んでいい?」
唐突な提案に頷くしかできないけど、朝宮くんは安心したように頬を緩ませた。
「ありがと。俺のことも隆聖でいいから。なぁ、菖太、お前の話聞かせてもらっていいか?」
問いかけてくる隆聖君に何の話をすれば良いのか分からない。
「……話って、何の?」
「ああ、悪い。言葉が足りなかったな。もしお前が良ければでいいんだけど、さっきあいつらが話してたみたいなやつの、本当のことが知りたい」
「……僕がどうして別室登校してたかって話?」
「ああ、別室登校って言うのか。うん。それとか、その時どうだったかとか」
隆聖君の纏う雰囲気は、優しい。さっきとはまるで別人みたいだ。好奇心で聞いているのではないことが分かるし、語気の強さも圧も感じない。本当に僕が話したければ話してほしいというスタンスなのだと伝わって来た。
だけど、どうして別室登校の話なんて聞きたがるんだろう。
僕はチラリとリセの方を見てみたけど、彼女も突然のことに驚き、戸惑っているみたいだった。
僕が隆聖君から目を逸らしたからだろう。彼は慌てて僕に言う。
「あ、ごめん。急にこんな話されても困るよな」
「ううん!」
『そうじゃないんだ』と続けそうになって慌てて口を噤む。ここで『そうじゃないって、どういうこと?』と問われてしまったらそれこそ何も言えなくなってしまう。
「まあ、今すぐじゃなくてもいいからさ……あー、でもこれからも教室に通うってわけでもない、のか?」
隆聖君はどこか心配そうに聞いてくる。
「……まだ分からない、かな」
僕は正直な事を答えてみた。さっきみたいな目がある中で教室に通い続けるかと聞かれると、今すぐ決めるのは難しい。
「そうか……。じゃあ、話す気になったら俺に声かけてくれよ。今話したい気分じゃないなら諦めるから」
じゃあな、と言って隆聖君は自分の席に座った。
隆聖君は、悪い人じゃなさそうだけど、でも僕の話を聞いてどうしたいんだろう。
「菖太さん、ノートを出していただけますか? 自由帳でも構いません」
状況を飲み込んだらしいリセにそう言われて、僕は指示通りにノートを出した。
「菖太さんの思っていることをそこに書き出してください。お話ししましょう。菖太さんはどうしたいですか?」
確かにこれならリセと話ができる。僕は自分が今どう考えているかをまとめながらノートにこう書いた。
『話をすること自体は別に大丈夫だと思う。ただ、その原因まで話さないといけないのかもしれないって思うと、ちょっと嫌だな』
リセはそれを読んで、少し間をおいて答える。
「先ほどの話しぶりからしても、菖太さんが話したくないことを無理に聞くような方ではないと思います。そこについては『こうなった理由については話したくないんだ』と付け加えれば良いかと」
それなら、隆聖君に話ができる。でも、分からないことがあった。ノートに鉛筆を走らせる。
『リセはりゅうせい君が話を聞きたがるのはなんでだと思う?』
「……分かりません。悪意からではないようです、としか。お話をする前に聞いてみても良いかもしれませんね」
リセにしては歯切れの悪い回答だったけれど、確かにそれもそうだな、と思った。隆聖君は質問された時にそれを無視するような人じゃない、と思う。出会って数分しか経っていないけれど、そんな気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
