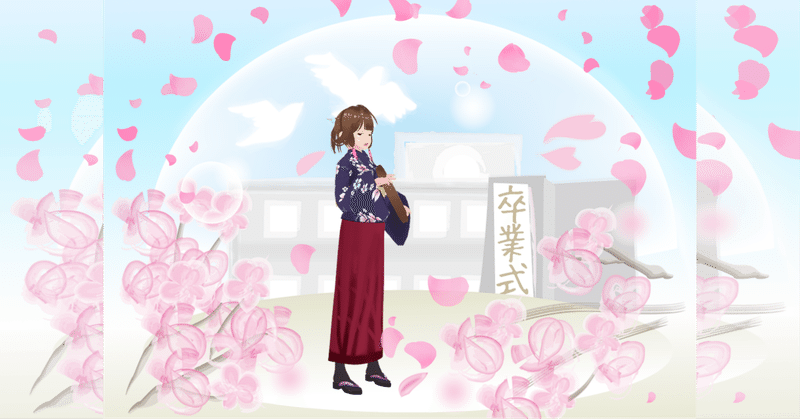
6年間の幻影
6年間の幻影
むぎすけ
中学1年。幼馴染の礼音と竹下通りを歩いている時、彼は名刺を持った男性に声をかけられた。大手アイドル事務所A社の社員だと告げられた時、まず「嬉しい」以前に
「キャッチセールスの人間か?」
と思うのがまともだと信じたい。事実、私たちもそうだったのだ。もっとも、どの道私は眼中になく事務所が求めていたのは礼音の方だ。彼がアイドルを目指せる顔立ちなのは私もよく知っていた。隣町の学校と一緒の行事になると向こうの先生もたじろいだ程なのだから。それから数日後、彼のお母さんと礼音がいそいそと出かける事が増えた。どうやらホンモノの名刺だったらしい。私が高校に進学して桜の花吹雪を浴びる頃、彼はスポットライトを浴びていた。TVは盛んに「アイドルになる為に生まれてきた少年」や「事務所始まって50年に1人の逸材」と彼を持てはやした。
彼の人気を肌で感じるようになったのは、休日に事務所の公式グッズ店に必ず行くファンの同級生と行動するようになってからだ。事務所に入ってからも礼音とは気の置けない友人だった。マメに電話したり、たまにあの日行くはずだった仄暗い喫茶店で待ち合わせしてそれぞれ近況報告がてら話し込んだりして逢っているのもトップシークレットだ。一歩大きな町に二人で出ようものなら友達ですらいられなくなるのだから。それを、少女たちでごった返した2階建てのグッズ店で身を以て理解した。私はひたすら友人の百合がアイドルに限らず他のグループのファンの事など噂するのに相槌を打っていた。聞いていてあまり退屈はしないがその実
(家に帰って昨日手に入れた古本、読みたいなぁ…)
とぼんやり感じていた。そんな事をつゆ知らず彼女は
「ねぇ、ここの最寄りの反対出口に余りバえない喫茶店あるよね」
とあの場所の事を言い出した。
(バえなくて悪かったな、ミーハー)
…と可愛げのない軽口を心の中で叩く余裕はあった。そう、この時までは。
「そこね、礼音の行きつけだって。お店に迷惑が掛かるからテレビや雑誌でも紹介されてないのだけど」
「へえ、何処でそんな情報を?」
「インスタ。一応名前はイニシャルだけだったけれど、礼音だってすぐにわかっちゃうよね」
少し意地の悪い笑みを浮かべスマホの画面を突き付けられる。今思えば百合からの静かな宣戦布告だったのだ。
「茉莉、次のライブに来てくれるって…?」
「友達に誘われたの。私を見かけても余り反応しないで頂戴ね」
ここまでは事務連絡に近い。ここ最近はあの場所も件の記事のおかげで繁盛してしまい私と礼音を繋ぐ手段が電話かメールのみになってしまった。
「じゃあ、変装してない茉莉が久々に見られるのか」
「…まあ、そうなるわね。変装に見慣れて気付かない事を祈るけど」
「とびきりおしゃれしてきても、気付くよ。だって幼馴染だぜ」
ステージ上の彼ならここで「女の子の努力はすぐに気付くよ」…なんてクサイ台詞を言うのだろう。電話を切っても、暫くスマホに耳を当てたままだった。「幼馴染」と言われた事に一先ず安堵するのと同時に、何故か百合の事が頭をよぎった。
(百合には一生振り向かない。甘ったるい口説き文句を言わない礼音。知らないままだろうな…私が流行りの香水をふったファンレターを送る必要のない事を)
机の上、傍らにコスメポーチを置いた鏡に映った私は嘲るような微笑みを浮かべていた。再び耳元で着信音が鳴り響き、我に返る。運悪く百合からだったので鏡から目を離すよりなかった。
(何考えているの、私……! 魔性の女なんてバラエティ番組だけの話だろ)
百合からの電話の応対をしつつ、彼女とお揃いでお迎えしたテディベアのマスコットとリボンのついたトートバッグをウォールフックからひったくる。
「明日学校終わりにA事務所のショップのあと、キディパークに行こうー?」
と言われたので、ファンシーグッズ好きの私はいそいそと準備するよりなかった。
話はライブ数日前、午前中で学校が終わったこの日の事だ。
「まーりっ」
校門前、初代学長がスロープ越しに街を見つめる像の前で待つ事30分、薄いピンクのメッシュが入った黒髪を靡かせ百合が現れたのは。
「ごめーん、髪の毛やら化粧やら…気付いたら30分か!」
「百合、前髪だけで14分近くかかるものね…髪や顔のセットの為に毎朝5時起きはプロよ」
えへへ、とはにかんだ後百合は私の手を取り
「30分間待ってくれた友達は茉莉だけ」
スロープを降り、少し歩くと摩天楼が駅を取り巻く街へ。雑踏が得意なら古本漁りになんて目を向けなかっただろうが、今は談笑しながら歩く友達がいた。それは百合も変わらないらしく……
「学校にも推し活仲間が出来るなんて思わなかった」
この日、コーヒーショップでバニラのフラッペを啜りながら呟いていた。
「今まで、友達ってネットで作るものだと思っていたの。コンサートの現場にいけば話す人はいたけれど、学校では一人が当たり前だった」
私は専ら聞き役だ。頼んだアールグレイのラテは私の好物でもある。
「でも、茉莉がA事務所を余り知らなくてもショップでお買い物に付き合ってくれて、友達と一緒にスタバでお茶するのも…こういうの、憧れだったの」
深く頷いた。もちろん紅茶の香りに浸っているわけではない。私は幼馴染こそいたが、クラスが離れていた年は図書室にいる子供だった。だから、気持ちは分かるのだ。
「二人で、飲み物持った写真撮ってインスタにあげるね! 茉莉の顔は隠すから」
「お、おぅ! あと混んできたしそろそろ出ますか」
カップ片手に出口へと向かう。
話はファンシーグッズ店まで歩を進める。やけに店内がざわついていた。礼音のストラップを提げた女の子たちが一か所を指さしそのコーナーを見守っていた為に私は一瞬で何事かを察した。SNSの漫画発のキャラクターの棚。アイツは八割れの猫のキャラクターを好いていた…
「あれ、絶対礼音だよね」
耳打ちする百合の目は輝いていた。誰ひとり声をかけなかった辺り、マナーがなっている界隈だったのだろう。
「ねぇ茉莉、話さなくてよかったの」
キディパークの出口、購入したものをエコバックに詰めていると普段と変わらない調子で百合がそう尋ねてきた。
「あれはお忍びです…って顔に書いてあるもん、ムリだよ」
あくまで一介のファンを装うよりない。大げさに照れてぬいぐるみで顔を隠した。
「幼馴染なのに、気にするのね」
普段と変わらない声音で言われた為に、「うん」と返し…その後ぬいぐるみを落として茫然とする。この状況をなんと表現しようか。ただひとつ、目を見開いた私は心の中で一言
(これは、詰んだ……!!)
と視線を泳がせていた。それにしてもトップシークレットだったはずだ。どこから割れてしまったのだろうか?
「前に…5月くらいに茉莉の家に遊びに行った事があるでしょう」
知られた時、かなり怒られるかと思ったが構わず袋に荷物を詰めている。
「トイレを借りた時、リビングを通ったらさ……写真立てに茉莉の中学の入学式の写真があったでしょう。中学の時の礼音が隣にいたの。茉莉と手を繋いでいたでしょ」
「なんで、隣の中学生が礼音だって……」
「ネットに中学の卒アルが出回っていたから。おばさんもその写真の前通る時ね、明らかに挙動不審だったから察しちゃった」
「………」
退路は断たれた。踏切を通り切った後遮断桿が降り、特急列車が横切る。
「黙っていた事は謝る。でも私も向こうも疚しい事がないから言わなかっただけだよ」
「信じているよ、その言葉」
その後はライブ当日の待ち合わせの話になり、その日はいつもと変わらない帰り路を踏む。だがその日の夜、百合が信じた私の言葉が全て嘘偽りと悟った。ついに礼音への恋慕を自覚したのだ。
ライブが始まる前、百合と待っているとメールが来た。
「やばい、緊張してきた……」
差出人を見ると礼音の名前。いつもの事と飲み込むのに時間はかからなかった。ドームで単独ライブをやるようなアイドルの弱点を。
「昨日買ったぬいぐるみでも握ればー?」
と、敢えて軽口で返してやる。彼は極度のあがり症なのでライブ開始前は毎回私にメールを送り付けてくるのだ。もっとも、今回は無事取り越し苦労に終わったようだ。終了後、ドームの裏側にある関係者出口の階段に百合と座って待っていた。他のファンも一カ所、関係者用の扉を凝視しながら階段に固まっていた。
「来た」
一人がそっと放った一言を聞き逃さなかった。(本当はダメだが)プレゼントを押し付けようとするファンに、警備員は
「入口のポスト以外のファンレター、プレゼントはお渡しできないです! すいません!」
といなして礼音の通る通路を作った。(友達に付き合わされたとはいえ)流石にここで手を振れないのか私ではなく百合にファンサービスで握手していた。
(そりゃそうだよな、アイドルだし仕方ないか)
大喜びで電車に乗り、呆けて乗り過ごしかねない百合に
「よかったじゃん」
と声をかける。全くもって心がこもってなかっただろう。だが。百合の最寄りまであと1駅に差し掛かった時にまたメールが来て…
「今帰り?」
案の定礼音だった。せめて百合が降りてからにしてほしいが。だがこの時、彼女は恐ろしい形相で私を見ていた事をあとになって知る。
「じゃ、私帰るねー」
「お疲れ。また明日学校で」
百合はにっと笑って駅へと降り、「ばいばい」と手を振っていた。どうも、最近百合と話していると疲れてくる。
最寄り駅から家路に帰る途中、自販機のベンチに彼は腰かけていた。
「久しぶりだね。綺麗になったね」
言われた私は赤面する。12月の寒さのせいにできればいいが…辛うじて
「あれ…もしかして、まだステージ酔いが醒めてないの? アイドルさん」
いつも通りである。そう呼ばれた礼音は不機嫌な顔をして
「オフの日ぐらい、忘れちゃダメか?」
と苦笑した。何も言わず、ベンチに二人腰かけていた。ずっとこの時間が続けばいい、とふと思うが彼は制服より煌びやかな衣装を選んだのだ、と我に返る。
(百合と礼音と、彼が制服を着て三人肩を並べて歩く未来もあったのかもしれない…)
静寂の中、降り始めた雪が入学式の桜吹雪の幻を見せた。ぼんやりしていた私は、右肩にある礼音の手に気付かなかった。
「ちょ、久々に幼馴染に会って泣くヤツがいる…?」
「ゴメン…迷惑するよな。幼馴染でいるだけでも大変だろうに」
「ちょっと、何を言っているか」
この態度を崩さず済んだのが、今となっては不思議だ。寒い夜の抱擁ほど暖かなものはない。余りに静かで雪が地に降る音ですらも耳に響いてきそうだ。
「事務所の人とも話しているけど、来年3月で退所する」
「後悔しないの? 大きい会場を押さえても一杯に出来るほどのアイドルになれたのに」
「オレがステージに立つのに、実は特に理由はなかった。事務所に声をかけられた時…どちらかというとマネージャーに根負けしただけで。テレビでは見てくれる人の為、なんてのたまったけどその実3か月もしたら周りの同級生が羨ましくなる程に日常に帰りたかったし」
「……贅沢な悩みってヤツよ、それ」
「じゃあ、聞くけど。アイドルだからって理由でこれからもコソコソ電話でしか話せないのと、これからは普通の恋人として白昼堂々一緒に歩くのとどっちがいい?」
「まさか、アンタその為に退所届書いたっていうワケ……?」
どうやら図星のようだ。
「バカじゃないの、アンタ……!」
私もあらぬ方向に目をそらす。電信柱の影……ちょうどそこに電灯があり、ビジューの付いた厚底靴を見出した。
「ゆ、百合……」
スマホを構えた百合が私たちに一歩ずつ近づいてくる。見開いた目には涙すらなかったが手は震えている。寒さのせいではないようだ。
「礼音くん、あたし達を騙したのね。ステージを見ているコの光になりたいって? ボクの生きる意味になってくれてありがとうって?……とんだ詐欺師じゃない」
礼音は彼女を見つめる。百合は何かをこらえて見つめ返す。
「その目で見ないで! あたし普通の男の子になり下がった礼音君になんて興味ない。茉莉も忘れないで頂戴。沢山のファンがいるステージから王子様を攫ったの。魔女みたいにファンに化けて、友達のフリをしやがって! もう仕返しする気にもならないけど、あたし達を裏切った事は忘れないで。言いたい事はそれだけ」
どうやらスマホをかざしているのは威嚇に近いようだ。厚底靴を履いているとは思えない速度で走り去る。
その後すぐ百合も私もそれぞれ別の学校に転校し、礼音は定時制の高校に通い始めた。気兼ねなく会えるようになったはいいが…時々傍らに百合もいれば、とは思う。晴れた竹下通りを歩く時、半年前には当たり前にあったはずの青春が頭をよぎる。……それは向こうも同じようだ。
「何、感傷に浸っているの?」
出会い頭に頬を軽くつねられた。ピンクのメッシュこそ取っていたが百合だった。
「アンタこそ、もう此処には来ないと思っていた。……詐欺師にはウンザリした?」
「一回、見破ったからもう簡単には騙されないよ」
互いに大声で笑う。思えばこんな事は初めてだ。いつになく、この街の空は高い。
【完】
執筆 むぎすけ様
挿絵 kyura様
投稿 顯
©DIGITAL butter/EUREKA project
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
