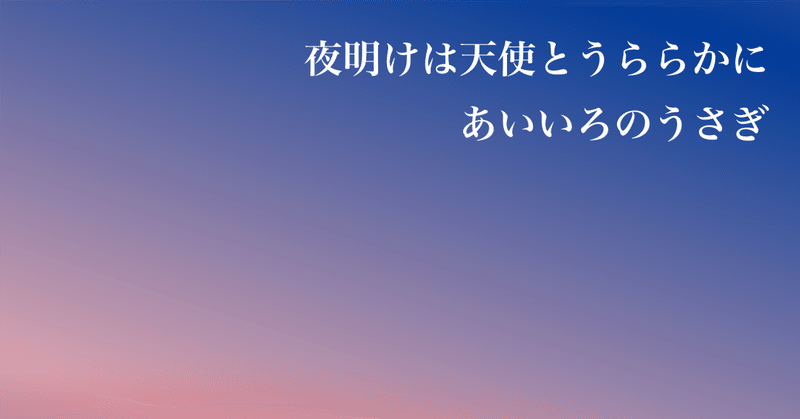
夜明けは天使とうららかに 2-4
〇 〇 〇
あれからも別室登校は続いた。続いた、と言っても、あの日はもう二月の最後の週で、もう学校に行く日自体がそんなになかった。
それくらいの短い期間なら教室に戻れるんじゃないかって考えてみたこともあったけど、やっぱり江藤君やクラスメイトのことが怖かったから、行くのはやめておいた。あんな風に意見できたのは、あの時の感情のおかげで、今の自分が同じように意見できるとは思わなかったから。
空き教室で勉強を見てもらったり、図書室や保健室で読書している時は、なんだかゆったりした時間が流れている気がして心地良かった。別室登校になってから気づいたことだけど、僕は勉強が好きな方らしい。今まではクラスの中で空気になるのが億劫で、勉強の楽しさまで見えていなかったみたいだ。
先生の出すプリントを解いていると、正解の数が最初の頃より増えているらしくて、リセが「すごいです、菖太さん!」と褒めてくれた。でも、それを言われると答え合わせの前に全部合っていることが分かってしまって、僕としてはちょっと微妙な気分だったんだけど、本当に嬉しそうなリセの顔を見ていたら『まぁ、いっか』と思えた。
先生たちがいない隙にリセとこっそり話をするのも楽しかった。と言っても、話している内容は「さっきの問題が難しかった」とか「この言葉がなんでか全然覚えられないんだよね」とか「今読んでる本、面白いね」とか、そんな他愛ないことだった。でも、リセはその全部にちゃんと答えてくれる。「先生そろそろ来るかな」と黙ってみたりして、でも全然来なくて笑ってたらドアが開いて慌てて口を閉じる、なんてこともあった。そういう時、リセの方は先生に見えていないから、リセまで口を閉じなくていいのに、慌てているところがおかしくて少し笑ってしまったりした。
学校で楽しく過ごして家に帰ってくると、お母さんも嬉しそうだった。というか、僕が別室登校になってから、お母さんは少し元気になった気がする。たまに不調な時もあって、ボーッとしちゃっている時もあるけど、寝込むほど体調が悪いことは僕の知る限りない。
そのことが不思議で、お父さんに聞いてみたら、なんだか色んなことを考えているみたいな、複雑な表情をしていた。
けれど、こう答えてくれた。
「お母さんも菖太みたいに学校で嫌なことがあったから、ちょっと前までは自分と菖太を重ねていたんじゃないかな。今は菖太が元気に帰ってくるから嬉しいんだよ」
お母さんも学校で嫌なことがあった、というのは初耳だった。でも、今の僕が元気でいることでお母さんも元気になってくれるなら、そんなに良いことってないな、と思った。
修了式が終わって春休みに入った。僕は自分から先生に頼んでプリントを貰っていた。別室登校で周りの子たちに完全に追いつけない分を春休みの間にやろうと思ったのだ。
部屋で勉強している時、リセはずっと見ていてくれる。分からない所も質問できて、僕はすごく助かっていた。
「菖太さん、そろそろ三時になりますから、休憩しましょう」
それに、僕の勉強のペースまで管理してくれる。僕は勉強していると夢中になって疲れるまでやっちゃうから、こうして休憩のタイミングを教えてくれるのはありがたかった。
おやつでも食べようかと思って一階に降りたらお母さんが電話をしていた。話をよく聞いてみると、担任の先生と話しているらしい。でも、電話がかかってくるなんてどうしてだろう。そう思ったけど、その答えはすぐに分かった。
電話が終わったお母さんが、心配そうな、不安そうな顔で、僕に話しかける。
「菖太、あのね、今先生から電話があったんだけど」
「うん」
「四月から教室に通う事はできないかって」
その言葉を聞いた途端、心がズシッと重くなるのを感じた。
「もちろん、無理はしなくていいのよ。でも先生が言うには、来年も菖太は先生のクラスに入れて、菖太にその……悪い事した子と別のクラスなんですって。だから帰ってこれないかって話だったんだけど……」
お母さんは悩ましげに僕を見ている。
江藤君と別のクラスで、担任の先生も同じ。確かに、戻るには悪くない状態かもしれない。
……けど。
「ちょっと自分の部屋で考えてもいい?」
「……わかった。でも無理はしないでね。今日中に答えを出さなくても大丈夫だから」
「うん」
僕はリビングを出て自分の部屋に戻った。
「菖太さん、随分早いですね。もう少し休んでいても良いと思いますよ?」
リセが驚いたように言う。
「いや、ちょっと、話したいことができて」
僕がそう言うと、リセは「わかりました」と答えて、こう続けてくれた。
「ゆっくりで構いません。菖太さんの様子を見るに、これは急な話のようですから、考えをぽつりぽつりと話していきましょう」
そう言ってふわりと笑う。
僕はすっかりリセの笑顔を見ると落ち着くようになっていた。呼吸を深くして、何を話したくてどう考えているのかまとめていく。
「……実は、さっき電話があったんだ。担任の先生が同じで、江藤君も違うクラスだから、教室に戻ってこれないかって」
リセは目を見開いた。僕は俯いたまま話を続ける。
「……正直、授業を受けたいって気持ちは、ある。やっぱり別室登校だと追いつけてないみたいだし、プリントをやるより先生の授業の方がずっと分かりやすいから」
それは本心だった。……けれど。
「でも、江藤君がいなかったところで、またあんな目に遭わないっていう保証はどこにもない。……先生がいてくれるのは、ちょっと安心だけど、でも、僕は元々クラスの子と話したりするの苦手だし……」
そればかりが不安だった。
リセはちょっとの間、僕の言葉に続きがないか待って、
「菖太さんは、本心では教室に戻りたいんですね」
と言った。
「けれどそれを恐怖心が遮っている。それは、当たり前のことだと思います。誰だって恐ろしいところには行きたくありません」
どこか遠くを見つめるようだったリセがスッとこちらに視線を戻す。
「けれど、そこが恐ろしい場所かどうかは、まだ分からない」
今までに見たことがないくらい真剣な顔だった。リセは、そう、今ふっと笑ったように笑顔を見せることが多かったから。
「もし恐ろしい場所だったなら、また別室登校にしてしまいましょう。一度教室に戻ったからといって、そこからずっと通い続けなければならない、というものではないでしょうから。それに、勉強の仕方は色々あります。学校に通う、ということだけでしか勉強ができないわけではないですから」
聞きながら納得していた。確かに、もう絶対に逃げられないわけじゃない。それに、勉強の方法は一つじゃない。
笑顔を見せていたリセが少し俯いて、
「それに、これは菖太さんのお役に立つか分かりませんが」
意を決したように僕の手を取って言う。
「私も教室について行きます。私は、ただ側にいることしかできませんが、それでも、菖太さんを決して一人にしないとお約束します」
僕を見つめるリセの瞳は真っ直ぐで、その誠実さに射抜かれそうだった。でも、リセはやっぱり最後にはふわりと笑う。
「最後は菖太さんの意思一つです。菖太さんはどうしたいですか?」
リセの手に包まれている僕の手を見ながら、考える。
僕は、どうしたい?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
